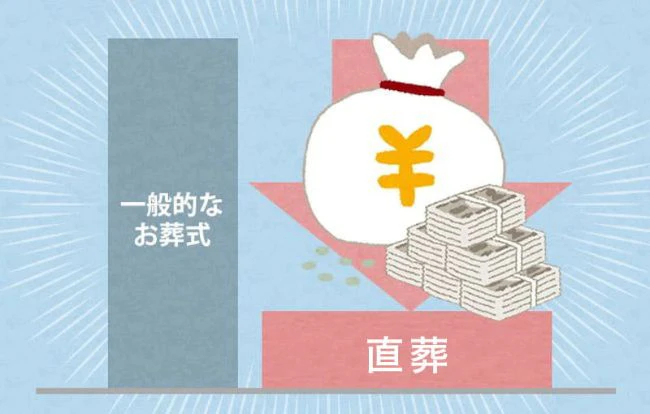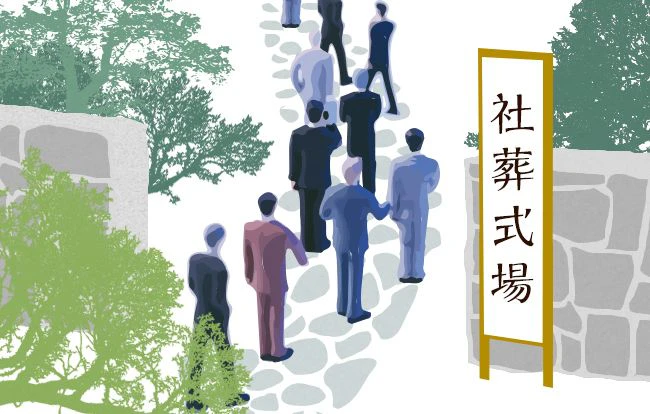華厳宗は中国から伝えられた、奈良仏教の宗派のひとつです。仏教の歴史は長く、宗派によって異なる点もあります。
この記事では「華厳宗とは何か」「奈良の大仏との関係性はあるのか」「葬儀やお墓の決まりはあるのか」などを知りたい方に、華厳宗の歴史や特徴を紹介します。
<この記事の要点>
・華厳宗は奈良時代に道璿によって日本に伝えられ、審祥によって確立された奈良仏教の一派である
・教えは華厳経に基づき、「四法界」という世界観を持つ
・葬儀やお墓の儀礼は他の宗派に倣うことが多く、独自の儀礼はほとんど行われない
こんな人におすすめ
華厳宗を信仰している人
華厳宗の教えについて知りたい人
華厳宗の歴史
華厳宗は中国発祥の仏教宗派です。ここでは華厳宗の始まりと、日本でどのように確立されたのかを簡単に説明します。
中国での始まりと開祖
華厳宗は、中国の僧侶「杜順(とじゅん)」が開きました。「地論宗(じろんしゅう)」の影響を受けている華厳宗ですが、他にも天台宗や法相宗(ほっそうしゅう)の教えも参考にしつつ、独自性を確立していきました。
【天台宗】
・すべての生命や現象を、10種類に分類(十界)して法理を学ぶ
・十界の例:恐怖にさいなまれる「地獄」、平常心や疑心暗鬼の「人間」、悟りを開いた「仏」
【法相宗】
・インドの思想が中国に伝わり生まれた宗派
・この世のすべては心が作り出していると考える「唯識論(ゆいしきろん)」が代表的
日本での確立と「南都六宗」について
日本で認知されるようになったのは、奈良時代736年の頃です。唐の僧侶「道璿(どうせん)」が日本に伝えたとされています。その後、審祥(しんじょう)という僧侶が日本で華厳宗を確立させました。
日本の歴史では、奈良・平安・鎌倉の3時代に仏教が盛んでした。奈良時代に中心的だった仏教は華厳宗を含めて6つあり、「南都六宗」と呼ばれています。南都六宗は儀式や布教活動よりも、教理の研究や学びに力を入れていました。
【南都六宗】
・華厳宗
・三論宗
・成実宗
・法相宗
・倶舎宗
・律宗
華厳宗の総本山・ご本尊
華厳宗の総本山とご本尊は、以下のとおりです。
| 総本山 | 奈良県の東大寺 |
| ご本尊 | 奈良の大仏「毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)」 |
東大寺は、奈良時代に聖武天皇が建てたお寺です。お寺にある巨大な大仏は、毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)と呼び、足元には蓮の花弁が見えるでしょう。花弁に毛彫りで描かれているのは、釈迦如来や菩提といった仏様です。
華厳宗の教え「四法界(しほっかい)」とは
華厳宗の教えは、華厳経に基づいています。教えのひとつに四法界があり、この世の現象について「縁起」や「因果関係」といった観点により世界を表す教えです。
華厳宗の教えは仏語で語られており、一般的な表現での解説が難しい面もあります。本項目では、華厳宗の中心である四法界(しほっかい)の世界観を理解するために、かみ砕いて説明しています。あくまでもイメージするための情報として読んでみてください。
事法界(じほっかい)
事法界は「人間界」を示しており、天地に数限りなく存在する「もの」のとらえ方です。そして因果応報の考えをもとに、すべての現象には「原因」と「結果」があると考えるようです。この教えを「因果の道理」または「縁起説」と呼びます。
理法界(りほっかい)
理法界とは、自我を捨てた世界、この世に存在するすべては空虚であるととらえます。「本質」に焦点をあてる理法界ですが、事法界とも関連性があるようです。
理事無礙法界(りじむげほっかい)
理事無礙法界の「理事」は、理法界と事法界を意味しています。無礙=障害のない自由な状態で、理法界と事法界がお互いに融合して存在しているのが「理事無礙法界」です。
事事無礙法界(じじむげほっかい)
事事無礙法界とは、空虚な現象や存在さえも消滅し、事象のみの世界を差します。すべてのものごとが相互に関連・融合しており、影響し合っているのです。四法界では、互いに影響し合っているという観点から、「自我や偏見を捨てる」「ありのままに物事をみる」といった教えについて伝えています。
<関連記事>
華厳宗のお経とは?宗派の歴史や修行・葬儀の有無などを解説
華厳宗の修行
修行の目的は、華厳宗の教えを理解し、悟りを開くことです。華厳宗の修行は難しいとされていますが、実際はどうなのでしょうか。ここではその概要を紹介します。
修行内容と修業期間
肉体的な鍛錬よりは、精神的な修行を重視していたようです。思想を体得した場合、「入法界(にゅうほっかい)」と呼ばれる境地に至ります。また空虚な事象さえもない「空」を体得すると、「煩悩即菩提」または「生死即涅槃(しょうじそくねはん)」に達すると教えられています。
修行の期間は、悟りを開くまで続きます。難しい修行を繰り返して、3回生まれ変わることで仏になれると教えられています。ただし体得できるかどうか、また修行の期間は、その人の才能や努力によって異なります。
【仏語解説】
| 煩悩即菩提 | 言葉で表現できない究極の幸せ |
| 生死即涅槃(しょうじそくねはん) | 生死(=迷い)と涅槃は対となっている |
| 涅槃(ねはん) | 修行により煩悩や執着を断ち切った境地 |
修行の難しさについて
華厳宗の修行は、高名な僧侶でも簡単には体得できなかったとされています。例えば有名なのは、当時、修行に励んでいた明恵という僧侶の話です。食への執着を断ち切るため、おいしい雑炊に埃を混ぜて食べたといわれています。
熱心に修行していた明恵ですが、ある日念珠を落としそうになります。地面に落ちる直前に拾い上げた時に、「あぁ、よかった」と安堵します。その途端に積み上げてきた悟りが崩れ去りました。このエピソードから、悟りを開く難しさが伝わってくるでしょう。
華厳宗|葬儀やお墓の考え方
華厳宗では、独自の宗教儀礼をほとんど行いません。そのため華厳宗の葬儀をする場合、他の宗派の作法に倣うことになるでしょう。これはお墓に埋葬する際も同様です。ただしお寺によっては、別の宗派を断るケースもあるため、事前に確認しておく必要があります。
<関連記事>
仏教宗派13宗の一覧を紹介!開祖・教え・葬儀の特徴などを解説
日本には宗教・宗派がたくさん!宗派の種類ごとの違いとは
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
華厳宗の特徴は修行の難しさや、学び・研究を重視している点です。
「小さなお葬式」では、24時間365日、通話料無料で葬儀や法要に関する疑問にお答えする「お客さまサポートダイヤル」を設けております。
またご要望に合わせて、葬儀プランや仏壇・仏具のご案内、遺品整理のサポートも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



お彼岸の時期は年に2回で、春分の日、秋分の日の頃だと覚えておくとよいでしょう。ホゥ。