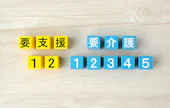家族が高齢になったなどの理由によって介護が必要になると、訪問介護の利用を検討するものです。しかし、訪問介護とは具体的にどのようなものを指しているのか理解できていない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、訪問介護の内容について詳しくご紹介します。訪問介護を受けるために必要な手続きや、コストについてもチェックしていきましょう。訪問介護について詳しく知っておけば、いざ必要になった時に迷わずに済みます。介護にかかる負担を減らすためにも、訪問介護を積極的に活用するのがおすすめです。
家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・訪問介護とは、被介護者の自宅で必要な介助を行うサービスのことを指す
・訪問介護で受けられるサービスには「身体介護」と「生活援助」がある
・訪問介護の自己負担額は「サービスの種類別料金×利用時間+その他料金」で算出する
こんな人におすすめ
訪問介護とはなにか知りたい方
訪問介護を受けるまでの手続き・流れを知りたい方
訪問介護の費用の目安を知りたい方
訪問介護とは
介護にはさまざまな形態がありますが、その中のひとつである訪問介護にはどのような特徴があるのかを見ていきましょう。似たような言葉に「居宅介護」があるので、この2つの違いについてもご紹介します。
在宅での介護を検討しているなら、訪問介護について詳しく知っておく必要があるでしょう。ここでご紹介するポイントをきちんとチェックすることをおすすめします。
ケアワーカーやホームヘルパーによる自宅での介護
訪問介護とは、被介護者の自宅で必要な介助を行うサービスのことを指すものです。したがって、被介護者は普段通り自宅で生活しながら、身体介護や生活援助などの必要な介護サービスを受けます。
ケアワーカーやホームヘルパーが被介護者の自宅を訪問し、入浴や食事の介護を行う仕組みです。ケアワーカーやホームヘルパーは介護福祉士などの資格を持っているため、安心して任せることができます。
訪問介護を利用する場合、被介護者が介護施設に出向く必要がないことが大きなメリットのひとつといえるでしょう。
居宅介護との違いは?
訪問介護と似た言葉に「居宅介護」があります。この2つはどのように異なるのだろうかと疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
訪問介護は、要介護認定を受けた高齢者を対象として提供される介護サービスです。一方の居宅介護は、障害支援区分1以上に認定された障害者を対象にした障害福祉サービスを指しています。介護の対象となる人が異なると覚えておきましょう。
訪問介護の対象となる人
訪問介護の対象になる人は、要介護1~5の認定を受けた65歳以上の人です。したがって、訪問介護を利用するためには、事前に居住地の区市町村から要介護の認定を受けておかなければなりません。
例外として、特定疾病を原因として介護を必要とするようになった場合は、40歳から訪問介護の対象になります。訪問介護を利用すれば自宅で生活しやすくなるため、条件を満たしているのであれば積極的に利用すると良いでしょう。
訪問介護で受けられるサービス
訪問介護を利用するとさまざまな介護サービスを受けられます。介護サービスは「身体介護」と「生活援助」に分けられるため、それぞれに何が含まれるのかをチェックしておきましょう。
訪問介護を利用しても受けられないサービスも存在しているので、こちらについてもご紹介します。利用する段階になって迷わないためにも、訪問介護に何が含まれているのかを覚えておく必要があるでしょう。
食事・入浴などの介助を行う「身体介護」
身体介護とは、食事・入浴・排泄・歩行などの介護をまとめた名称です。被介護者の身体に直接触れるものや被介護者と共に行うもの、専門技術を必要とするものが含まれています。自力で食事や入浴などができない人にとって、大きな助けになるでしょう。
必要に応じて服薬介助や着替えの介助、通院・外出の介助も行われますが、これらも身体介護に含まれるものです。ケアワーカーやホームヘルパーが、都道府県が行う研修を修了して認定を受けている場合は、経管栄養を始めとした一部の医療行為も認められます。
他にも、糖尿病の療養食などの特別な配慮が必要な食事を準備する作業も身体介護に含まれるサービスです。どのような介助が必要になるかは被介護者によって異なるため、状況に応じて必要なものを利用しましょう。
掃除・洗濯などを行う「生活援助」
生活援助とは、被介護者が行えない日常生活上の家事を代行するものです。生活スペースの清掃や買い物、選択などが生活援助の範囲に含まれます。日常生活に必要であるものの、被介護者の身体に触れずに行える作業や、専門知識が不要な家事などが含まれます。
被介護者が日常生活を円滑に送るために提供される介護サービスで、生活に必要不可欠な家事のうち、被介護者自身ができないものを行うものと覚えておきましょう。
訪問介護で受けられないサービスは?
訪問介護で受けられないサービスもいくつか存在しています。円滑に訪問介護を利用するためにも、どのようなものが対象外になっているのかをチェックしておきましょう。具体的な例は以下のとおりです。
・庭の手入れ
・家具や家電の移動
・被介護者以外の家族が生活するスペースの掃除
・ペットの散歩
被介護者の生活維持に必要なもの以外は、訪問介護サービスの対象にはなりません。事業者によってはこれらのサービスが必要な人向けに、介護保険適用外のサービスとして提供していることがあります。介護保険適用外のサービスが必要な場合は、事前に利用予定の事業者に確認しましょう。
訪問介護の費用の目安
訪問介護サービスを利用するためには、定められた費用を支払わなければなりません。介護保険が適用されるため全額を支払う必要はありませんが、所得に応じて1割~3割を支払う必要があります。
訪問介護を利用する場合に支払わなければならない費用についてもあらかじめチェックし、利用する段階になって迷わないようにしましょう。
自己負担額の計算式
訪問介護を利用した場合の自己負担額を計算する場合は、以下の計算式を利用します。シンプルな計算式なので、迷うことは少ないでしょう。
サービスの種類別料金×利用時間+その他料金
自己負担額は1日ごとに計算します。その他料金には緊急時加算や特定事業所加算などがあるため、利用したサービスの内容に応じて計算しましょう。
訪問介護サービスには2時間ルールと呼ばれるものがあります。2時間ルールとは、同日に2回の訪問介護サービスを受けた場合、サービス同士の間隔が2時間未満の場合は1回のサービスとして計算するものです。こちらも併せて覚えておきましょう。
自己負担額の目安
具体的な自己負担額は都道府県や利用事業者によって異なります。ここでは目安として自己負担額の一例をご紹介するので、参考にしてみてください。
| 種類 | 時間 | 利用額 | 自己負担額 (1割負担の場合) |
| 生活援助 | 20分~45分 | 2,086円 | 209円 |
| 生活援助 | 45分以上 | 2,565円 | 257円 |
| 身体介護 | 30分未満 | 2,793円 | 280円 |
| 身体介護 | 30分~1時間 | 4,423円 | 443円 |
自己負担割合が2割や3割の場合は金額が異なるため、必要に応じて計算しましょう。生活援助と身体介護の双方を利用する場合は、それぞれの金額を合算して算出します。
介護保険適用外のサービスを利用した場合は、その分を自費で全額支払わなければなりません。
訪問介護を受けるまでの流れ
訪問介護は必要になってすぐに利用できるものではなく、一定の手続きをする必要があります。ここからは訪問介護を利用するために必要な手続きと実際に受けるまでの流れを見ていきましょう。
迷わずに訪問介護を利用するためにも、どのような流れになっているのかを理解することは重要です。
1.要介護認定の申請を行う
訪問介護は要介護1~5の認定を受けなければ利用できません。したがって、最初に居住地の区市町村に要介護認定の申請を行いましょう。
要介護認定の申請を行う時は、「要介護認定申請書」を区市町村の介護保険を取り扱っている窓口や高齢者相談センターに提出します。書類を送付してもらう必要がある時や、記入方法がわからない時は区役所などに問い合わせると教えてもらえるでしょう。円滑に訪問介護を利用するためにも、速やかに申請することが大切です。
2.介護認定
区市町村が要介護認定申請書を受領すると、申請日から30日以内に郵送で結果が通知されます。通知には非該当・要支援1~2・要介護1~5のいずれかが記載されているでしょう。ここで要介護1~5に認定された場合に訪問介護を利用可能です。
申請から認定までの間には、介護支援専門員の訪問や主治医が作成した意見書の確認を始めとした調査が行われます。調査内容を基に審査を行い、要介護状態区分を判断する仕組みです。
3.ケアマネジャー決定
要介護1~5に認定された場合、被介護者は居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼しなければなりません。この際に利用する居宅介護支援事業者は、被介護者が任意に選択可能です。ケアマネジャーが決定した後でも、必要があれば変更できます。
どのような居宅介護支援事業所があるのか分からない場合は、区市町村が公開している情報を参考にして選ぶと良いでしょう。介護事業者情報検索システムを利用して探すのもおすすめの方法です。
4.ケアプラン作成
ケアマネジャーが決定すると、選任されたケアマネジャーが被介護者の自宅を訪問して面談を実施します。面談は被介護者の状態や生活の様子、どのような支援が必要かを聴取するものです。
面談の結果得られたさまざまな情報に基づいて必要な介護サービスを決定し、ケアプランを作成します。ケアプランは訪問介護のベースになるものなので、伝えておきたいことは面談時に漏れなく伝えましょう。
5.利用する業者を決める
ケアプランを作成したら、実際に訪問介護サービスを行っている訪問介護事業所と利用契約を締結します。利用契約を締結して初めて訪問介護を受けられるようになるため、区市町村が公開している資料などを参考にして適切な業者を選択しましょう。
訪問介護事業所ごとの特徴や、所属しているケアワーカー・ホームヘルパーの質が訪問介護のクオリティに直結します。被介護者の要望にきちんと答えてくれる業者を選ぶことが大切です。
介護保険外のサービスを利用したい場合は、利用したいサービスを提供しているかも確認しておきたいポイントといえるでしょう。
家族信託という選択肢もある
訪問介護の利用を検討している際に、認知症についても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。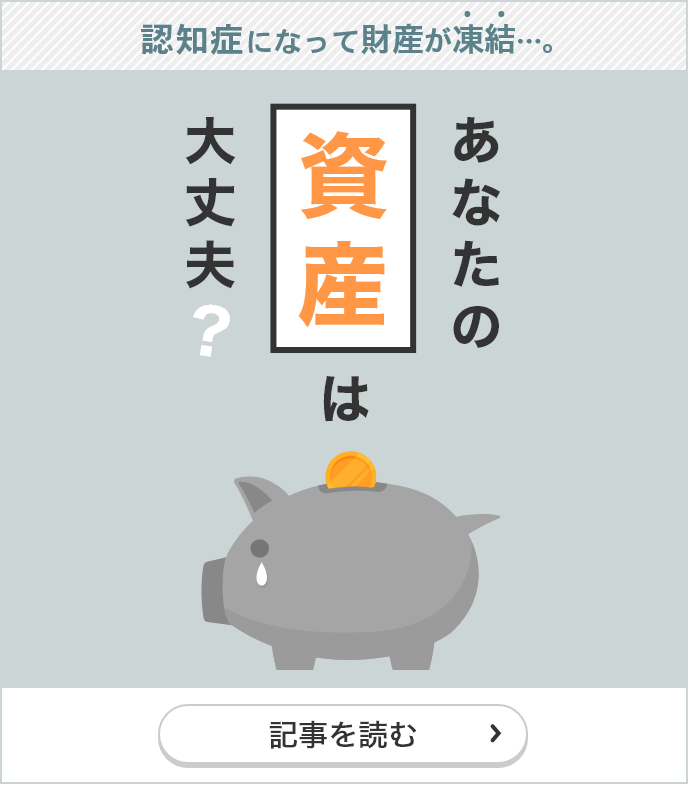
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2021年4月 自社調べ)
まとめ
家族が高齢になって介護が必要になった場合、訪問介護を利用すれば住み慣れた自宅で生活を続けられます。訪問介護を利用するためには要介護1~5の認定を受けなければならず、認定を受けるまでに一定の時間がかかるでしょう。
認定を受けた後も、ケアマネジャーを選定したり利用する訪問介護事業所と契約を締結したりするなど、さまざまな手続きが必要です。必要な時に訪問介護を受けられるようにするためにも、必要な手続きを速やかに行うことをおすすめします。
訪問介護は被介護者の生活を豊かにするだけでなく、家族の負担を軽減するためにも役立つものです。介護保険適用でコストも抑えられるため、積極的に活用すると良いでしょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
訪問介護とは?
訪問介護の対象となる人は?
訪問介護で受けられるサービスは?
訪問介護の費用の目安は?
お付き合いのあるお寺がない場合、寺院手配サービスを利用する方法もあります。ホゥ。