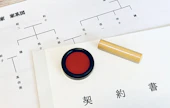不動産を所有している方や所有者から贈与を受ける方は、生前贈与でかかる贈与税が気になっているかもしれません。
贈与税対策まで検討している場合、課税されるケースや控除、特例の要件について確認しておく必要があります。この記事では、贈与税について詳しく解説します。
<この記事の要点>
・個人から個人へ不動産の生前贈与があった場合は、贈与税が課税される
・土地にかかる贈与税の場合の計算式は「基礎控除後の課税価格 × 税率 − 控除額 」となる
・所有権のトラブル防止のために、贈与契約書の作成や贈与登記により、所有権を証明する必要がある
こんな人におすすめ
不動産に対する贈与税について知りたい人
不動産の贈与税対策について知りたい人
不動産に対する贈与税の計算方法について知りたい人
不動産関連で贈与税が課税されるケース
不動産の贈与をする場合、課税対象か把握しておく必要があります。ここでは、課税されるケース3つについて解説します。自身のケースと照らし合わせて確認してみましょう。
個人から不動産の生前贈与があった場合
亡くなる前に個人から個人へ贈与する場合は、贈与税が発生します。なお、両親や祖父母からの贈与といった血縁関係の要件はありません。
もし、会社や法人から贈与すると、贈与税ではなく所得税がかかる仕組みです。また、個人から会社・法人への贈与には、法人税が課税されます。
本来の価値よりも安く不動産を譲り受けた場合
本来の価値より安く不動産を譲ると、「見なし贈与」として課税されます。見なし贈与とは、本来と異なる手段で財産を譲ることです。
もし、1,200万円相当の不動産を300万円で譲った場合は、差額の900万円に贈与税が発生する可能性もあります。また見なし贈与は、税金逃れ防止の仕組みなので、税率が高くなることを覚えておきましょう。
不動産購入にかかった借金が免除された場合
不動産購入時の支払いを免除してもらった場合にも、贈与税が課せられます。例えば、資金を両親から借りて、あとから「返済しなくてもよい」となったケースが挙げられるでしょう。その場合も、未返済分の金額が贈与税の対象です。
ただし、収入不足や預貯金不足により返済できない状況の方は、贈与税の対象外となるケースもあります。
不動産の贈与税を計算する方法
贈与税を算出する際に「暦年課税制度」が適用されます。暦年課税制度は、1月1日~12月31日までが課税期間です。ここでは、同制度に基づく「土地」と「建物」にかかる相続税の計算方法を解説します。
土地にかかる贈与税の場合
基本の計算式は、下記のとおりです。
贈与税額=(贈与財産総額-基礎控除110万円)×税率-控除額
土地の贈与財産総額を算出する方法は、2パターンあります。
1:路線価方式
・道路に面する宅地の価格を1平方メートル単位で算出
・計算方法は「正面路線価 × 奥行価格補正率 × 面積」
2:倍率方式
・土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかける計算方法
・路線価のない地域は倍率方式で求める
建物にかかる贈与税の場合
建物の場合は、「固定資産税評価額」に基づいて贈与税を計算します。固定資産税評価額は、固定資産税の「納税通知書」に記載されています。「評価額」または「当該年度価格」の名称で記入されているため、課税明細書のページを確認しましょう。
不動産の生前贈与でできる贈与税対策
「非課税で受け取る分を増やしたい」と考えて、贈与税対策を検討する方がいるかもしれません。ここでは、贈与税対策として、不動産の生前贈与や相続時精算課税制度の利用について解説します。
不動産のまま生前贈与する
現金に変えるよりも、不動産のまま生前贈与するほうが相続税対策になります。金額全体に課税される現金に比べて、不動産は評価額に基づいて税額を計算するためです。
例えば、1億円のマンションを贈与する場合の差額は下記のとおりです。
・現金で贈与すると、税額は約4,799万円
・マンションを贈与すると、税額は約2,775万円
つまり、現金とマンションのまま贈与する場合の差額は2,024万円となります。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度とは、贈与税において2,500万円までの特別控除を受けられる制度です。ただし、相続時には相続財産と贈与財産を合計して相続税額を計算しなければなりません。つまり、税金の支払いを先送りにしているとも考えられるでしょう。
「非課税でまとまった贈与財産を受け取っておきたい」という方に、適した制度だといえます。
<対象者>
・60歳以上の父母または祖父母から18歳(注)以上の子や孫にへの生前贈与
(参考:『相続時精算課税制度の選択|国税庁』)
不動産の贈与税対策として利用できる特例
不動産の贈与税対策には、配偶者控除や住宅等取得資金の非課税制度を受けるのも方法の1つです。それぞれの特例の要件や控除額について解説します。特例の利用時には、要件を満たせるかチェックしておきましょう。
配偶者控除
夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、基礎控除110万円のほかに配偶者控除として2,000万円まで非課税になります。
配偶者控除の特例を受ける要件は以下のとおりです。
・婚姻期間が20年以上の夫婦
・対象が国内にある居住用不動産、もしくは、それを取得するための金銭
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに対象の不動産に住んでいる、もしくは引き続き住む見込みがある
住宅等取得資金の非課税制度
住宅等取得資金の非課税制度とは、子や孫が新たに住宅を取得する場合の資金援助において、一定の金額は非課税になる制度です。
住宅等取得資金の非課税制度の要件は以下のとおりです。
・直系の親や祖父母からの贈与
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築を取得している
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに対象の不動産に住んでいるか、もしくは、住む見込みがある
非課税の金額は、下記のとおりです。
【住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合】
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
| 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万 | 2,500万 |
| 令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万 | 1,000万 |
【上記に当てはまらない場合】
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
| ~平成27年12月31日 | 1,500万 | 1,000万 |
| 平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万 | 700万 |
| 令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,000万 | 500万 |
(引用:『No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁』)
不動産の生前贈与で贈与税以外にかかる税金は?
生前贈与の場合は、贈与税のほかに「不動産取得税」や「登録免許税」が発生します。
| 不動産取得税 | ・都道府県税の1つで、税率は4% ・軽減特例:土地3%、住宅用の家屋3%、住宅用以外の家屋4% (令和6年3月31日まで) |
| 登録免許税 | ・所有権移転登記等で発生 ・税率:贈与2%、相続0.4% |
不動産の生前贈与をする際の注意点
生前贈与を進めるうえで、注意するべき事項があります。所有権をめぐるトラブル防止のために、証明の手続きが必要です。また、贈与税の税金対策は、場合によって損をすることもあります。各制度の概要を深く理解して、判断しましょう。
所有権を証明する必要がある
親族間でのトラブルを防ぐために、「贈与契約書」の作成や「贈与登記」により、所有権を証明しましょう。贈与契約書の書き方にルールはありませんが、贈与者の指名や受贈者の指名、契約日、実行日、贈与する不動産の情報や贈与の方法について記載します。
贈与登記は、対象の不動産を管轄している法務局に申請します。「固定資産評価証明書」や「印鑑証明書」などの必要書類を確認しておきましょう。
相続時精算課税制度にはデメリットがある
相続時精算課税制度は、2,500万円まで非課税になる制度です。ただし、相続時に贈与分を相続税として加算されるため、注意しなければなりません。
また、相続時精算課税制度は、「小規模宅地等の特例」制度との併用はできません。そのため、小規模宅地等の特例の対象となる小規模な住宅や店舗でも、評価額最大80%の減額を受けられません。
相続開始前3年以内の贈与は相続財産となる
不当な相続税逃れを防ぐために、3年以内(※)の贈与は相続財産に加算されます。これを「生前贈与加算」と呼びます。
<生前贈与加算の対象者>
・死亡前3年以内の贈与
・相続や遺贈(遺言による相続)を受ける方
・生命保険金の相続
・贈与税の基礎控除に満たない110万円以下の贈与
ただし、配偶者控除の適用や住宅取得資金の非課税額といった、生前贈与加算の対象外となるものも存在します。事前に確認しておきましょう。
※被相続人の相続開始日が令和8年12月31日までの場合
(参考:『No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)』)
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
贈与税は、個人から個人への生前贈与に対して課される税金のことです。不動産を贈与すると、土地と建物に対して贈与税が発生します。贈与税の対策としては、相続時精算課税制度」や特例の利用を検討するとよいでしょう。
ただし、贈与税を正しく理解しなければ、かえって納税額を増やしてしまう恐れもあります。小さなお葬式では、葬儀に精通したスタッフが24時間365日、無料通話で対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。