養子に遺産の相続が認められているのかどうか、気になっている方は多いでしょう。実の子ではなく養子でも問題なく相続できるのでしょうか。養子縁組によって発生した親子関係があると、養子への遺産相続がどうなるのか不安に思うものです。
そこで今回は、養子も実の子と変わらない条件で遺産相続ができるのかや、相続する際の注意点をご紹介します。遺産を相続する予定がある養子の方や、養子に自分の財産を贈りたい方は、ぜひチェックしてみてください。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・特別養子縁組の場合、養親の遺した財産のみ相続することができる
・養子には遺留分の制度についても正式に認められている
・孫を養子にした場合、相続税が2割加算になることもあるので注意が必要
こんな人におすすめ
養子は遺産を相続可能かを知りたい方
養子が相続するためのポイントを知りたい方
専門家に依頼するメリット・デメリットを知りたい方
養子は遺産を相続できる?
養子でも故人が遺した遺産を問題なく相続できるのか心配になるでしょう。実の子と同様に愛情をかけて育てていたのであれば、その子に故人が遺した財産を受け取ってもらいたいと考えるものです。
しかし、相続に関しては養子の形式によって大きく異なります。まずは自身と養子の関係がどの縁組に合致しているのか、以下で整理してみましょう。
普通養子縁組
古くから採用されている仕組みで、生みの親との親子関係は変わらず、新しく育ての親と親子関係を結ぶというものです。この制度を利用すると、子供は2つの親子関係を同時に保有することになります。
この場合、実の両親と育ての親の両方の故人が遺した財産の相続する権利を得るという、特殊な状況になることがわかります。15歳以上であれば本人の意思で、15歳以下であれば法定代理人との話し合いで決定されます。また、未成年者の場合、家庭裁判所の許可が必要です。普通養子縁組の場合であれば、生みの親、育ての親の両方における両親の遺産が相続できます。
特別養子縁組
昭和60年代に誕生した比較的新しい仕組みです。産みの親が、子供を産んだものの経済的に困窮し大人になるまで育て上げられない場合の救済措置として、新しく育ての親として志願した方の元で実の子と同様に育てるという制度です。
普通養子縁組とは異なり、特別養子縁組では産みの親との関係は完全に消滅します。そして子供は、新しい両親との親子関係のみを有します。養子の保護を目的とした新制度なので、話し合いで決定することが多い普通養子縁組とは大きく異なることがわかるでしょう。
養子になる人は15歳未満に限られており、養親候補の方は6ヶ月間の試験養育期間を経て、晴れて育ての親になることができます。育ての親になりたいと思っていてもすぐになれるわけではありません。
また、産みの親との関係は完全に消滅するため、相続する権利は養親の遺した財産のみになります。普通養子縁組とは大きく異なる点といえるため、事前に把握しておかなければなりません。
養子の人数上限は?
人数については上限が設けられていません。しかし税法上のルールとしては以下のようなものが定められています。
・育ての親に実の子がいる場合、相続する権利がある人数として数えられるのは1人のみ
・育ての親に実の子がいない場合、相続する権利がある人数として数えられるのは2人のみ
上記のルールが設けられているので、相続する権利がある人数は最大で2人までになります。しかし、実の両親との親子関係が完全に消滅している特別養子縁組制度を利用している場合、上記のルールは適用されません。
相続税には基礎控除が設けられており、相続する人数が多ければ多いほど、納税する金額は安く済みます。養子をたくさん取ることで税金を抑える行為を未然に防ぐためのルールです。養子に故人が遺した財産を相続させたいと考えている場合は、覚えておくとよいでしょう。
養子が相続するためのポイント
ここからは、養子が故人の遺した財産をスムーズに受け取るためのポイントをご紹介します。養子が故人に遺した財産を受け取るための重要な注意点になるので、しっかり押さえておいてください。
養子も遺産をもらうことができる
法律上、養子は相続する権利を保持していると定められています。養子は、養親の嫡出子という立ち位置になるため、育ての親が亡くなった際には財産を相続することが当然の権利として発生します。実の子とほぼ同じという認識で問題ないでしょう。
法定相続に関しては実の子と変わらない
養子縁組で後から親子関係を結んだ場合でも、実の子と変わらずに相続する権利を持つことができます。戸籍上は実の子として扱われているので、当然相続する権利に関しても同じ条件になります。
また、養子には遺留分という制度の利用権も正式に認められています。遺留分とは、相続が発生した際に故人との関係性に応じて、最低限の遺産を受け取ることが認められる権利のことです。
控除算出でも対象になる
養子でも相続する権利を持てるので、他の方と同じ様に控除の対象としてカウントされます。しかし、普通養子縁組の場合、人数制限が設けられているので注意が必要です。実の子の場合、相続する権利を持つ人数に上限はありません。何人いても問題なく控除額はプラスされるでしょう。
上述の通り、養子の場合は少し制限があります。実の子がいる場合は1人まで、実の子がいない場合は2人までしか計上できません。節税対策として、養子縁組をするというのを避けるためのルールになります。
ただし、特別養子縁組は実の子と同じ扱いになるので人数制限はありません。どの制度を利用しているかで状況が異なるので、事前に確認が必要です。
死亡退職金や生命保険の控除も含まれる
基礎控除額の算出方法と同様に、死亡退職金や生命保険に関しても、相続する権利を持つ人数に応じた控除が養子でも認定されています。しかし、カウント可能な人数には上限があるため気をつける必要があるでしょう。
養子を取ることで相続人が減る場合がある
養子を取ることで相続人が減ってしまう可能性があります。相続人が減るということは、1人当たりが受け取れる金額が増えるからよいのではと考える方もいるかもしれません。しかし、控除額が減ってしまうので、その分支払う相続税が高額になります。
基礎控除の計算は、「3,000万円+600万円×相続する権利を持つ人数」になるので、人数が多ければ多いほど控除額が大きくなります。控除額が大きくなれば支払う税金はその分安く済みますので、税制面で得をするでしょう。養子が多ければ多いほど、相続のときに得をするわけではないということは理解しておかなければなりません。
争いの原因になる可能性がある
養子は他の親族からすれば自分や故人とは血縁がない他人と認識するかもしれません。血縁者ではない人物が相続者となり、故人が遺した財産を相続することに不満を覚える方が出てくることもあるでしょう。
自分が知らないうちに故人が養子を取っていて、相続額を減らされていたとなれば、気分を害する方もいるでしょう。養子を取った結果受け取れる遺産が少なくなってしまい、大きなトラブルに発展するというケースも考えられます。
特に大人になってから養子縁組を行う場合は、他の方に説明してから実行するのが賢明といえます。
孫を養子にすると相続税が加算されるケースも
養子は一般的に実の子と同じ関係値と認識されるので、余計な加算はありません。しかし、孫を養子にした場合、配偶者や父母ではないその他という扱いになるので、相続税が2割加算となります。通常よりも多く税金を支払う必要があるため、あまり得策とはいえません。孫を養子にする場合には、本当によいのかを慎重に確認する必要があります。
相続に関する問題は専門家を頼ろう
相続に関する問題はかなり複雑で、ルールも多岐に渡ります。専門知識のない素人が独学でこなせるようなものではないでしょう。スムーズに進まなくなった結果、親族間で不信感が募ってしまい、大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。
そうなる前に、相続に関する知識を持つ専門家への依頼を検討してみてください。ここでは専門家に依頼するメリットとデメリットをご紹介しますので、参考にしてください。
専門家に依頼するメリット
専門家に依頼するメリットは、時間や手間がかからないという点が一番に挙げられるでしょう。手続きには書類の用意や申請など細かな作業が必要になるので、慣れない人がやろうとするとかなり時間がかかってしまいます。
また、一生懸命時間をかけて作成した書類だとしても、内容に不備が見つかると、受理されずに突き返されてしまいます。用意すべきものや書類が正しく書けるまで、当然相続作業は進みません。
専門知識を持つ方であれば、作業に慣れているため戻りなくスムーズな作業が可能です。また、相続税といった専門的な問題を依頼するときは、必ず相続を専門として扱っている方に依頼することが重要になります。相続は税理士試験で必修科目として認定されていないため、税理士であっても知識量に偏りがあります。相続を専門として扱っている税理士や弁護士の方に依頼するのがおすすめです。
専門家に依頼するデメリット
専門家に依頼するデメリットとしては費用がかかることが挙げられます。相続の専門家として、税理士や弁護士へ依頼する場合が多いですが、当然報酬を支払わなければなりません。作業量に応じて報酬は変動するものの、数万円〜数十万円程度になる場合がほとんどといえます。
親族間で相続に関して揉めてしまった場合のように、話がややこしくなるとかかる時間が長くなるので、費用もその分かさんでしまいます。少しでも費用を抑えるために、問題がややこしくなる前の早い段階で依頼したいものです。相続に関する問題や疑問が浮上したら、専門家に依頼するための費用を準備しておくと安心でしょう。
家族信託という選択肢もある
養子への相続について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。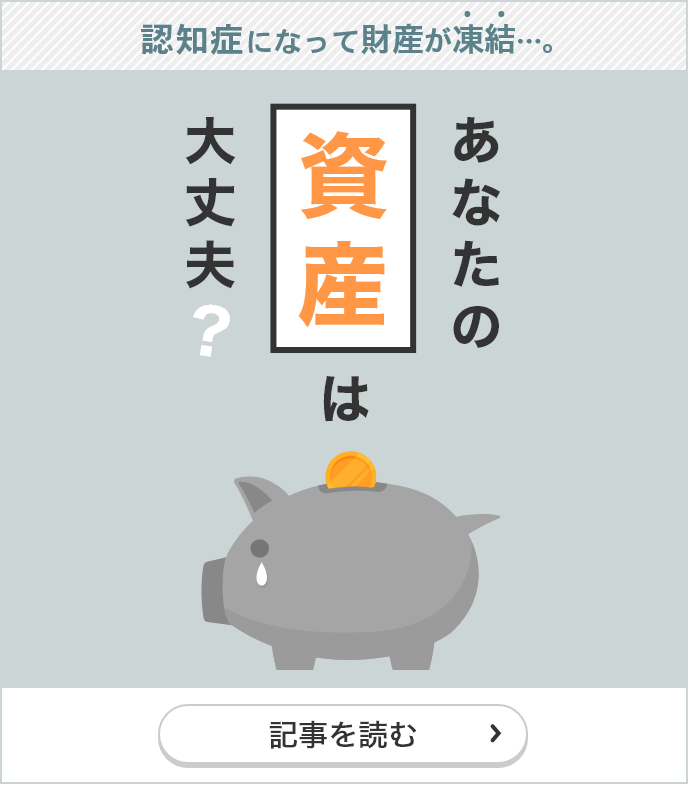
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
養子でも問題なく遺産を相続できます。実の子と同じ扱いになるので、基本的には問題ありません。実の子と唯一異なる点は、人数に上限が設けられている場合があるということです。養子縁組の形式によって異なるので、事前に確認しておく方がよいでしょう。
また、相続税に関する手続きや申し立ては内容が複雑なので専門家にお任せするのがおすすめです。問題がややこしくなる前に、専門家への相談を検討してみてください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
養子は遺産を相続できる?
相続できる養子の人数上限は?
養子が相続する際の注意点は?
相続の問題を専門家に依頼するメリット・デメリットは?
お通夜とは、家族や友人たちが集まり、故人と最後の夜を過ごす儀式のことです。ホゥ。






























