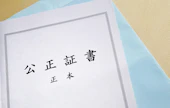最近は、夫婦水入らずの暮らしを楽しむケースや独身を貫くことも増えており、子供なしの相続に関する悩みを抱える方も少なくはありません。さまざまな生き方が浸透している中で、相続の問題をスムーズに解決するためには、遺言書の存在が非常に重要となります。
親族同士のトラブルが起こらないように、子供なしのケースにおける相続についてご紹介します。万が一のときに備えて、参考にしていただける内容でしょう。
<この記事の要点>
・子供なしの場合の法定相続人は、配偶者が最優先となる
・子供なしの夫婦における相続対策として、生前贈与を行う方法がある
・遺留分侵害額請求権を念頭において遺言書を作成する必要がある
こんな人におすすめ
子供なしのケースにおける相続について知りたい方
子供なしの夫婦における相続の注意点を知りたい方
子供なしの夫婦における遺言書作成の注意点を知りたい方
子供なしのケースにおける相続
子供がいない夫婦の場合、相続を決める際には遺言書が大切になります。しかし、故人が遺言書を遺していないケースも少なくはありません。この場合、重要となるのが法定相続人と相続割合についてです。まず、子供なしの場合の法定相続人は、配偶者が最優先となります。続いて、故人の親、兄弟と続くのが通例です。
また、親や兄弟が亡くなっている場合に続く法定相続人は、姪や甥となります。ただし、兄弟における代襲相続は一代限りと定められているため、姪や甥の子供は相続人にはなりません。法定相続人が配偶者しかいない場合は、必然的に全ての遺産を配偶者が相続することになります。
子供なしの夫婦における相続の注意点
子供なしの夫婦の場合、相続を行う際にさまざまなトラブルが起こることが考えられます。特に、配偶者以外にも相続人がいる場合は要注意です。問題なくスムーズに相続を行うためにも、相続の際に考えられるトラブルを前もって把握しておくと、いざというときに対処しやすくなるでしょう。
血族相続人との関係が悪い
子供なしの夫婦の場合、配偶者と血族相続人の関係が悪くなっているパターンがよく見られます。しかし、相続人として優先される立場である配偶者は、義理の両親や兄弟たちと遺産分割協議をすることは避けられません。万が一、話合いのないままに遺産相続を進めてしまうと、より関係が悪化することも考えられるでしょう。
長らく関係を損ねており、疎遠だった場合は相続の話合いが決裂するケースも少なくはありません。また、遠方に暮らしている場合は、連絡することすらできないという可能性もあります。
分割が難しい遺産の場合
たとえば、遺産が現金や銀行預金のみだった場合、綺麗に分割することができるでしょう。しかし、残された遺産が不動産だけだったというケースも少なくはありません。不動産の場合、現金のように綺麗に分けることが難しく、場合によっては現金よりも価値が下がることも考えられます。
こういった場合は、不動産を相続する人が、他の相続人に対して相続分の土地が持つ価値に見合った代償金を支払うケースが多いでしょう。しかし、代償金が高額になる場合は、支払えないことも考えられます。それが原因となってトラブルになるケースも少なくありません。
子供なしの夫婦における相続対策
子供なしの夫婦が相続でトラブルに巻き込まれないためには、きちんと相続対策をしておくことが大切です。その際に大切なのは、誰もが納得できる形で行うことと、法律に沿って対策を行うことでしょう。いざとなったときに慌てないためにも、元気なうちに対策をすることをおすすめします。
あらかじめ夫婦で話し合っておく
残された配属者が困らないように、あらかじめ夫婦間で話して認識を一致させておくことが何よりも大切でしょう。どちらかが亡くなったときのことを想定した上で、相続をどうするのか、その後の予定はどうしたらよいのかを話し合っておくと、万が一のときにも安心です。
生前贈与を行う
すでに、配偶者と他の相続人の関係が悪い場合は、生前贈与を行うのもひとつの手段です。亡くなる前に、配偶者に財産贈与をすることで、遺産から外すことができます。例えば、自宅を配偶者のものにするために、生前に贈与するケースはよくある話です。
平成30年に法律が改正された際に、結婚から20年以上が経過した後、居住用不動産を生前贈与するケースにおいては、遺産分割の際に居住用不動産は考慮されないという決まりができました。
また、結婚後20年以上経過した夫婦の間で、不動産を生前贈与する場合には、基礎控除に加えて贈与税の配偶者控除も適用されます。場合によっては、贈与税が全くかからないケースもあるので、一度税理士に相談してから贈与を行うと損をすることなくおこなえるでしょう。
遺言書の作成
子供なしの夫婦に限らず、さまざまなケースにおける相続に効力を発揮するのが正しい形で作られた遺言書です。遺言書は、財産を引き継ぐ相手を明確に決定することができます。相続人が多数いた場合でも、配偶者に全ての財産を相続させることも可能です。
また、相続人以外の関係が深い人物に財産を引き継いでもらうケースもあるでしょう。さらには、個人ではなく団体に対して相続することもできます。これらもすべて正しい遺言書があったうえでできる相続のかたちといえるでしょう。
保険を活用する
配偶者以外にも相続人がいる場合に活用できるのが、保険です。生命保険に加入して受取人を配偶者にしておくと、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。さらに受け取ったお金は配偶者の財産となるため、相続財産には当てはまりません。そのため、相続税もかからないという結果になります。
また、遺言書を書く手間も省け、受取人である配偶者も保険会社に請求を出すだけなので非常に便利な手段といえるでしょう。
遺言書の注意点
子供なしの夫婦において、遺言書の作成はスムーズな相続に欠かせません。特に、親族が多いケースではできるだけ遺言書を用意しておいたほうが、親族間のトラブルが起こりにくいと考えてもよいでしょう。ここからは、遺言書を作成するときの注意点についてひとつずつ解説します。
遺留分について
遺言書を作った場合に注意しておかなければならないのが、遺留分についてです。遺留分とは、兄弟以外の相続人に対して認められている最低限の遺産取得分を指しています。これは、法律によって定められているので把握しておく必要があるポイントです。
例えば、配偶者と親が相続人だったケースを見ていきましょう。配偶者に財産をすべて相続させるという遺言書を残していたとしても、親には遺留分侵害額請求権があるため配偶者に対して遺産の1/6に相当する金額を請求できます。遺留分侵害額請求権とは、遺留分の遺産を請求する権利です。この権利を念頭において遺言書を作るように心がけましょう。
ただし、兄弟には遺留分侵害額請求権がないため、すでに親が亡くなっている場合は気にする必要がありません。そのため、配偶者と兄弟のみが相続に該当する場合は、遺言書を作っておくと非常に有効だといえるでしょう。
予備的遺言を残す
遺言書には起こり得る事態を踏まえた上で書くことも大切です。例えば、配偶者へすべての財産を相続する旨を遺言書に書いたとしても、配偶者も亡くなってしまうケースも考えられます。そのため、もしもの場合の相続先も遺言書に書いておくことをおすすめします。その場合は、次のように書くと有効でしょう。
「自分より先に配偶者が亡くなった場合は、〇〇にすべての財産を相続させる」
このように明記しておくことで、万が一の事態にも対処することができ、希望通りの相手に財産を相続することができます。また、相続人が遺産分割協議をする必要もなくなるでしょう。
公正証書遺言にする
公証役場に出向いて、公証人に遺言書を作成してもらう方法です。正しい形式に則った上で作成してもらうため、ミスがない上に紛失する危険性も極めて低いのが特徴でしょう。また、法律的にも最も有効とされる遺言書となるため、他の相続人に納得してもらえる遺言書を用意することができます。
さらに、公正証書遺言の場合は自分で書く必要がなく、口頭で公証人に説明するだけで作成可能な点もメリットでしょう。病気や高齢により自書できない場合にも役立つ方法です。
不安があるときはプロに依頼
子供なしの相続については、親族や子供に相談することもできないため不安に思うことも多いでしょう。そんなときに頼りになるのが法律のプロである弁護士です。第三者の専門的な立場から手続きを行ってくれるため、スムーズな遺産相続が可能です。弁護士に相談した場合のメリットを把握しておきましょう。
相続トラブルを防止する
遺言書を残して相続のトラブルを防ごうと思っても、専門的な知識がなければさらなるトラブルを発生させる可能性も否めません。万が一、遺言書の内容が間違っていれば無効となるケースも考えられます。そのため、弁護士が入ってくれることで、法律的にも有効であり、親族にとっても納得できる遺言書を制作することができるでしょう。
遺言書がなかった場合もスムーズ
万が一遺言書がなく、遺産分割協議をしなければならなくなった場合も、弁護士が入っていると非常にスムーズに手続きを進めることができます。特に、義理の家族との折り合いが悪くなっている場合は、直接の話合いを行うとトラブルになる可能性も否めません。その場合はできるだけ弁護士に依頼をして、直接の話合いを避けたほうが無難でしょう。
ややこしい手続きを頼める
相続問題や遺言書については、すべての財産を確認することも必要です。特に高齢になっている夫婦の場合、自分たちで手続きを進めるのは非常に困難でしょう。とはいえ、しっかりと財産の調査を行わなければ、後になって漏れていた財産が発覚し、トラブルになることも考えられます。
弁護士に依頼しておくと、すべての煩わしい業務を代行してくれるため、非常に便利です。また、相続における親族間の問題に対してもアドバイスをしてくれるでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
子供なしの夫婦の場合、相続について相談できるところが少ないため、準備は慎重に行う必要があります。特に遺言書は自分で書くこともできますが、どちらかが亡くなってしまったあとに配偶者が困らないように、プロの視点も取り入れながら正しく遺すことが大切です。義理の家族との関係が良好であればスムーズにいく相続も、関係性によっては問題に発展することも否めません。
まだ元気だからといって相続についての話を放置してしまわずに、元気だからこそしっかりとした話合いを夫婦間で行うことをおすすめします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
子供なしの相続はどうなる?
子供なしの夫婦の相続の注意点は?
子供なしの夫婦が事前にできる相続対策は?
遺言書を作成するときの注意点は?
初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。