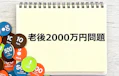老後にはいくらくらいの資金が必要なのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。人によって収入も支出も異なるため、自身の状況に合わせたシミュレーションをしてみる必要があります。そこでこの記事では、老後資金のシミュレーションや必要な金額について詳しく解説します。
<この記事の要点>
・老後資金のシミュレーションをするには、世帯の収支情報が必要
・老後の生活にかかる費用の項目は食費、住居費、水道光熱費、医療費、税、社会保険料などがある
・60歳~69歳の二人以上世帯の消費支出額は306,476円、70歳以上の世帯の月額平均は249,177円
こんな人におすすめ
老後資金の目安が気になっている方
老後資金の貯め方で悩んでいる方
今から老後資金の対策をしていきたい方
老後資金のシミュレーションをする必要性は?
2019年に金融庁の金融審議会によって発表されたのが、「夫婦の老後30年間で約2,000万円の老後資金が不足する」という試算です。これが「老後2,000万円問題」と呼ばれているものですが、あくまでも平均値をもとに算出した数字であることに注意が必要です。
老後資金がどれくらい必要になるのかは世帯によって異なるため、まずはシミュレーションをしてみましょう。自分の場合、あるいは自分の家庭ではどれくらいの金額が必要なのかを知ったうえで、資金を確保しておくことをおすすめします。
老後資金のシミュレーションをする際に必要な情報
老後資金のシミュレーションをするにあたっては、前提となる情報が必要です。必要な情報として、世帯の収入と支出に関するものがあることを解説します。
世帯の収入に関する情報
老後資金のシミュレーションには、世帯の収入に関する情報が必要です。具体的には、以下のような項目を反映させます。
| 退職金 | 退職金のない企業に勤めている人、自営業者にはない項目です。 |
| 公的年金 | すでに年金を受給している人は現在の金額、まだ受給していない人は受給金額を試算してみましょう。 |
| 賃金 | 定年後も働いている人は現在の収入を、働く予定の年数分反映させます。 |
| 資産運用による収益 | 投資信託、iDeCo、個人年金保険などによる収入です。 |
世帯の支出に関する情報
老後資金のシミュレーションには世帯の支出に関する情報も必要です。具体的には、以下のような項目を反映させます。
| 生活費 | 食費、住居費、水道光熱費、保健医療費、教養娯楽費などです。 |
| ローンの返済 | 住宅ローンなどの返済が残っている場合には、完済までの分を反映させましょう。 |
| 特別な支出 | 住宅リフォームや旅行、子どもへのお祝い金など、具体的に予定されている項目があれば反映させます。 |
老後資金のシミュレーションをする方法
実際に老後資金のシミュレーションをする場合には、どのような方法で行えばいいのでしょうか。自分で計算する方法と、プロに相談して計算してもらう方法の2つについて解説します。
自分で計算する
老後資金のシミュレーション方法の1つ目は、自分で計算する方法です。まず、毎月の生活費から毎月の収入を引いて、毎月の家計収支の不足額を計算しましょう。
次に老後の生活期間を計算して、毎月の家計収支の不足額にかければ、必要な老後資金がシミュレーションできます。
老後の生活にかかる費用の項目には下記のようなものがあります。
・食費
・住居費
・水道光熱費
・家具、家事用品費
・被服及び履物費
・保健医療費
・交通、通信費
・教養、娯楽費
・税、社会保険料
・その他(諸雑費、交際費、仕送り金など)
プロに相談して計算してもらう
老後資金のシミュレーション方法の2つ目は、ファイナンシャルプランナーや金融機関の無料保険相談窓口で相談をし、必要な老後資金を計算してもらう方法です。
金融の専門家としてより正確なシミュレーションをしてもらえるでしょう。また、老後資金対策についてのアドバイスも行ってもらえます。
老後資金のシミュレーションで注意すべきこと
老後資金のシミュレーションには注意すべきことがあります。当たり前のことですが、シミュレーションはあくまでもシミュレーションであることです。わかっていても、つい結果にばかり集中してしまって、焦ったりすることがあります。
シミュレーションを行う上で注意すべきことについて解説します。
シミュレーションが正確とは限らない
シミュレーションをしても、あくまで予測であるため、実際に必要な老後資金がシミュレーション通りになるとは限りません。シミュレーションで出た結果に対して、不安を感じすぎてもいけませんし、逆に安心してもいけません。
投資がうまくいって収入が増えることもありますし、予想していなかった支出が発生する事態も起こり得ることを認識しておきましょう。
働き方や暮らし方をイメージする
何歳まで働くのかによっても、必要となる老後資金は異なります。自分の働く期間を設定して、シミュレーションしてみましょう。もちろん、健康であることが前提となりますので、健康維持、体力維持には配慮して過ごすことが大切です。
また、どこで暮らすのか、どのような暮らしをしたいのかもイメージしておきましょう。ゆとりある生活を送るのと、最低限の生活を送るのとでは、必要な老後資金はかなり変わってきます。
定期的なシミュレーションをする必要がある
家庭の状況や収支の状況が変わることで必要な老後資金が変わる可能性があります。そのため、1回行ったシミュレーションをもとに行動し続けるのではなく、定期的にシミュレーションをして軌道修正を続けていくほうがよいでしょう。
さまざまなケースを想定する
老後資金のシミュレーションを行う際には、前提条件によって結果は大きく異なります。収入や支出について、最善のケースだけではなく最悪のケースも想定しながらシミュレーションをすることによって、より具体的に資金の目安が確認できるでしょう。
老後の生活資金の平均的な目安は?
老後の生活資金は結局いくら必要なのか、具体的な数字を把握しておきましょう。高齢夫婦と、高齢の独身それぞれの場合について、平均的な老後資金の目安を紹介します。
二人以上の世帯
総務省が発表した「2023年(令和5年)家計の概要」によると、世帯主が60歳~69歳の世帯の消費支出は月額平均306,476円、70歳以上の世帯の月額平均は249,177円です。また65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は月額平均244,580円、消費支出の月額平均は250,959円となっています。
単身世帯
総務省が発表した「2023年(令和5年)家計の概要」によると、単身世帯(平均年齢58.2歳)の消費支出額は167,620円です。また65歳以上の単身無職世帯の実収入は月額平均126,905円、消費支出の月額平均は145,430円となっています。
(参考:『2023年(令和5年) 家計の概要』総務省統計局)※2024年11月時点
老後資金を蓄えるには?準備する方法
老後資金の目安が分かったら、次にどのように蓄えるのかを考えなければなりません。定期預金をする、NISAやiDeCoを運用する、保険に加入するという、老後資金を準備するための3つの方法について解説します。
定期預金をする
定期預金をして貯蓄をするのは、最も安全な方法です。預け入れ期間を決めて満期日になると引き出しができます。
普通預金と比べると金利は高いものの、現在の金利は低いため大きな利益を得ることはできないでしょう。ただし手軽に引き出せないため、無駄遣いは防げます。
NISAやiDeCoを運用する
NISA
NISAは「少額投資非課税制度」のことで、運用益や分配金が非課税となる仕組みです。限られた金融商品が対象となっており、比較的リスクが低いのが特徴です。
iDeCo
iDeCoは「個人型確定拠出年金」のことで、投資信託などで運用して老後資金を作る私的年金です。掛け金全額が所得控除の対象となりますが、原則として60歳になるまで引き出せないという特徴があります。どちらも老後の備えとして有効的な手段であるといえます。
保険に加入する
保険も種類を選べば老後の備えとなるため、加入を検討してみましょう。以下のようなものが老後資金の準備に適しています。
個人年金保険
個人年金保険は私的年金であり、生命保険会社の商品です。堅実に運用できるものと、積極的に投資するものなどがあります。また、一定期間に年金が受け取れるタイプと、生涯受け取れるタイプがあります。ただし掛金全額は控除所得になりません。
終身保険
終身保険は、被保険者が死亡したとき、高度障害状態になったときへの補償が一生継続する保険です。中途解約した場合に「解約返戻金」が受け取れるので、老後資金の確保としても利用できます。
養老保険
養老保険は、満期になると「満期保険金」が受け取れます。満期を選べる商品が多いため、定年に合わせて満期保険金を受け取ることもできます。また、年金受け取りに変更できる場合もあります。
老後に備えて今から対策できること
老後に備えて今から対策できることについて知り、できるだけ早く準備を始めることが重要です。収入を増やしたり支出を減らしたりするための5つの対策について解説します。
収入額を増やす
老後の備えになる対策として、収入額を増やすことは有効的な方法です。昇進を目指すことが可能であれば、できるだけ昇進して年収をあげましょう。また、昇進が難しい状況であれば、夫婦で共働きをする方法を検討しましょう。
長く働く
長く働き続けることによって、生涯の総収入を増やせます。かつては60歳定年が主流でしたが、最近では65歳まで定年が引き上げられたり、定年が廃止されたりしています。長く働こうと思えば働ける環境が整いつつあるため、できるだけ長く働くことによって、老後資金を確保できるでしょう。
公的年金の受給額を増やす
受給できる公的年金を増やすことによって、老後資金の確保につながります。例えば、本人の申し出によって65歳まで国民年金保険料を納付することによって受給額を増やせる「任意加入制度」、上乗せの保険料を納めることによって受給額を増やせる「付加年金」、受給開始を遅らせることによって受給額を増やせる「繰り下げ受給」などを活用しましょう。
支出の見直しをする
支出の見直しをすることも、老後資金の確保につながる有効的な方法です。固定費の削減や無駄な出費を抑えることによって、毎月の家計を黒字に保っていけば、老後資金は貯まっていきます。スマホの契約、電気会社の契約、住宅ローン、生命保険などを見直してみましょう。特に子どもが独立した後は、支出を減らすチャンスです。
生活習慣の見直しをする
生活習慣の見直しをして健康的な生活を送れれば、老後に増える傾向にある医療費や介護費を抑えられるでしょう。また健康であれば、定年後も働き、継続して収入を得られるため、老後資金の減少を緩和できます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
老後資金のシミュレーションを行えば、自分の老後資金の目安がわかります。そのうえで、自分に合った方法で老後資金の準備を始めて、安心して老後の生活を送れるようにしましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。老後資金のシミュレーションについて知りたい方や、葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。