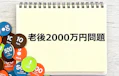老後資金の準備をしなければならないといわれますが、実際のところ、他の方はいくら貯めているのか、疑問を持つ方もいるでしょう。そこでこの記事では、 老後資金は平均でいくら貯めているのか、いくら必要なのかについて詳しく解説します。また、老後資金の貯め方についても紹介します。
<この記事の要点>
・二人世帯以上の60代の金融資産保有額の平均値は2,427万円、中央値は810万円
・夫婦の老後資金は、介護費用を含めて約2,000万円必要
・老後資金はiDeCoやNISA、個人年金保険を活用して貯めることができる
こんな人におすすめ
老後資金を周りがいくら貯めているのか知りたい人
老後資金の貯め方について知りたい人
老後資金は平均でいくら貯めているのか?
実際に老後資金の貯蓄額は、平均でどのくらいなのでしょうか。夫婦の場合、独身の場合それぞれについて紹介します。参考にしてみてください。
夫婦の平均貯蓄額
金融広報中央委員会が発表している「家計の金融行動に関する世論調査2021年」(二人以上世帯調査)によると、60代の金融資産保有額の平均値は2,427万円、中央値は810万円です。
実際の金額の目安を知るためには、金融資産保有額の高い方やない方に影響を受けにくい中央値を見たほうがよいでしょう。70歳代になると金融資産保有額の平均値は2,209万円、中央値は1,000万円となります。
独身者の平均貯蓄額
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査2021年」(単身世帯調査)によると、60代の金融資産保有額の平均値は1,860万円、中央値は460万円です。70歳代になると金融資産保有額の平均値は1,786万円、中央値は800万円となります。
老後資金はいくら必要なのか
老後の平均貯蓄額は分かりましたが、実際の老後資金がいくら必要なのかを把握しておく必要があります。老後の収入、支出、介護費用について紹介し、老後資金の必要額を解説します。
老後の収入
総務省「家計調査」(2021年)によると、高齢夫婦無職世帯の実収入の平均額は23万6,576円です。このうち、年金などの社会保障給付は21万6,519円です。高齢者の主な収入源が年金であることがわかります。
老後の支出
総務省「家計調査」(2021年)によると、高齢夫婦無職世帯の実支出は25万5,100円です。このうち、食費、住居費、水道光熱費、保険医療費、教養娯楽費などの消費支出が22万4,436円であり、税金や社会保険料などの非消費支出が3万664円です。
介護費用
総務省「家計調査」の支出には介護費用が含まれていないことに注意が必要です。生命保険文化センターが発表した「生命保険に関する全国実態調査(2021年度)」によると、介護にかかる月額の平均費用は、83,000円です。介護に必要な期間は、平均で61.1か月でした。つまり、8万3,000円×61.1か月=507万1,300円となります。
また、住宅改修や介護用ベッド購入など、介護にかかる一時費用の合計額は平均で74万円であるため、合計で1人あたり約580万円、夫婦であれば約1,160万円の介護費用が必要となります。
老後資金の必要額
老後を65歳からの30年間であるとすると、実収入と実支出から導き出される老後資金の不足額は、(実支出25万5,100円−実収入23万6,576円)×12か月×30年=666万8,640円です。
ここに夫婦の介護費用1,160万円を加えると、約1,830万円の老後資金が必要であることがわかります。
<関連記事>
老後資金はいくら必要か?平均額・計算方法・貯め方を解説
老後資金を準備するポイント
平均の貯蓄額や必要な老後資金について解説してきましたが、老後資金はどのように準備すればよいのでしょうか。ここからは、老後資金を準備する4つのポイントについて解説します。
老後資金を準備する時期
老後資金は、基本的に年金支給が開始される65歳までに貯めておきましょう。ただし、65歳以降も働く場合には、全ての老後資金を準備しておかなくてもかまいません。
また、老後資金を貯め始める時期はできるだけ早いほうがよいでしょう。特に投資をする場合には、複利のため運用期間が長いほど資金を増やせる可能性が高まります。
働き方や暮らし方をイメージする
何歳まで働くのかによっても、必要となる老後資金は異なります。自分の働く期間を設定し、シミュレーションしてみましょう。もちろん、健康であることが前提となりますので、健康維持、体力維持には配慮して過ごしましょう。
また、どこで暮らすのか、どのような暮らしをしたいのかもイメージしておきましょう。ゆとりある生活を送るのと最低限の生活を送るのとでは、必要な老後資金はかなり変わってきます。
年金の試算・繰り下げ受給の検討
まずは自分が受給できる年金額を試算してみましょう。加入状況、働き方、現役時代の給料によって大きく異なりますので、「ねんきんネット」や「公的年金シミュレーター」を活用して算出します。
また、年金の「繰り下げ受給」を行うと、受給のスタートを1か月遅らせるごとに年金額は0.7%ずつ増加しますので、「繰り下げ受給」制度の利用も検討してみましょう。
定期的にライフプランをチェック
ライフプランは1度決めたら固定されるものでないため、暮らし方に対する考えや健康状態など、さまざまな要因の変化に応じて見直していくことが必要です。
定期的にライフプランをチェックすることによって、その後の老後資金の修正もしやすくなるでしょう。
老後資金の貯め方
老後資金の貯め方には、いくつもの種類があります。それぞれの方法に特徴があるため、自分に合ったものを選ぶ必要があります。iDeCo・つみたてNISA、個人年金保険、固定費の見直しについて解説します。
iDeCo・つみたてNISA
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を作るための私的年金です。掛け金の全額が所得控除の対象となり、運用益は非課税で再投資されるというメリットがあります。ただし、原則として60歳になるまで引き出せないため注意が必要です。
つみたてNISA(少額投資非課税制度)は、毎月一定額を積立投資することができる仕組みです。20年間は運用益・分配金が非課税となり、いつでも売却できるというメリットがあります。ただし、金融商品は限られているのでしっかり確認することをおすすめします。
<関連記事>
iDeCoは不向きな方も。おすすめしない9つのケースを解説
個人年金保険
個人年金保険は、一定の年齢まで毎月保険料を積み立てていく保険会社の商品です。死亡時の保障が得られる、個人年金保険料控除を受けられるといったメリットがあります。ただし、途中で解約してしまうと元本割れしてしまう可能性があります。
固定費の見直し
毎月の支出のうち、固定費を見直すことも老後資金の形成に役立ちます。例えば、スマホを格安SIMに乗り換えて通信費を削減したり、住宅ローンを繰上げ返済しておいたり、生命保険料を見直したりすることによって、支出を減らせるでしょう。
<関連記事>
50代からでも始められる老後の資金の貯め方
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
老後資金は平均でいくら貯めているのか、老後資金にはいくらいるのかなどを把握した上で、自分の老後資金の準備に取り組む必要があります。効率的な貯め方を選び、安心して老後生活を送りましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが24時間365日、通話料無料でご連絡をお待ちしております。他の方が老後資金をいくら貯めているのか知りたい方や葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


墓じまいとは、先祖供養の続け方を考えた際の選択肢の一つです。ホゥ。