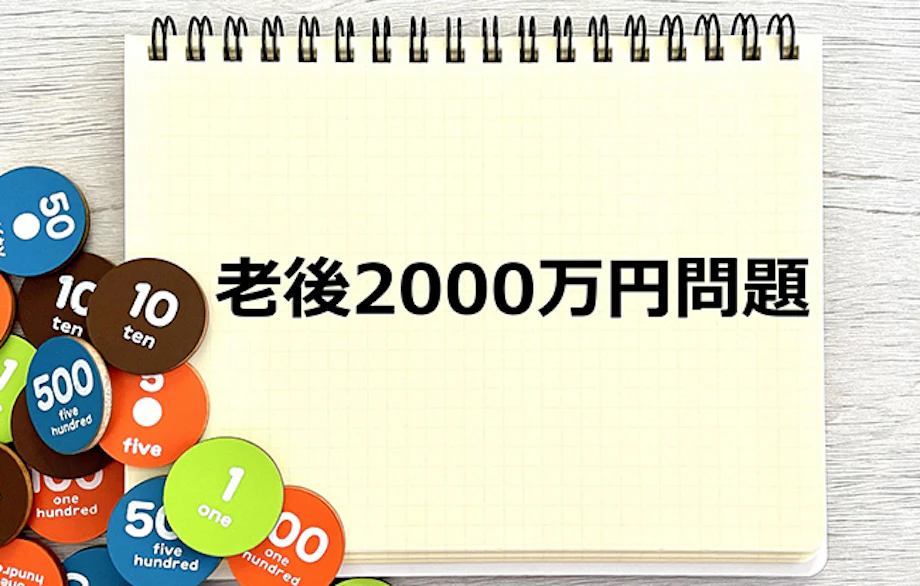夫婦の老後30年間で、約2,000万円の老後資金が不足するという試算が、2019年に金融庁の金融審議会によって発表されました。はたして、実際に2,000万円貯めておけば、老後の生活は安心なのでしょうか。
そこでこの記事では、2,000万円問題とは何かについて根拠や背景とともに解説します。また、夫婦の老後の収支や老後資金対策についても説明します。
<この記事の要点>
・「老後2,000万円問題」とは「老後の30年間で約2,000万円が不足する」という問題のこと
・65歳以上の夫婦のみの無職世帯の消費支出は、1か月に約22万4,000円(持ち家を含む)となっている
・長く働いたりNISAやiDeCoを活用することで、老後資金の対策ができる
こんな人におすすめ
夫婦の老後資金における2,000万円問題について知りたい人
老後にかかる費用を具体的に知りたい人
老後資金対策としてできることを知りたい人
夫婦の老後資金における2,000万円問題とは何か
「老後2,000万円問題」とは「老後の30年間で約2,000万円が不足する」という問題のことです。具体的には、夫が65歳以上、妻が60歳以上の無職世帯において、毎月の収入が20万9,000円、支出が26万4,000円であるため、毎月5万5,000円が赤字になるとされています。これが30年間続くと約2,000万円の不足になるというわけです。
夫婦の老後資金における2,000万円問題の背景
2,000万円問題には背景となる社会情勢があります。背景を考慮に入れると、将来、不足額がさらに高額になる可能も見えてくるので注意が必要です。平均寿命、退職金、多様な働き方に関する情勢について解説します。
平均寿命が伸びている
寿命が伸びれば、その分生活費が必要になります。厚生労働省発表の「令和3年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は81.47歳、女性は87.57歳です。今後もさらに平均寿命が伸びていくことが想定されています。長い老後期間への資金対策が必要だといえるでしょう。
退職金は減る傾向
平均寿命が伸びているのにも関わらず、退職金は減少傾向にあります。退職給付制度がない企業の比率が高まっているとともに、平均退職給付額も減少し、すでに2,000万円以下となっています。今後もこの傾向は続くと見られていますので、老後資金の不足分を退職金でまかなえるかどうかも考えなければなりません。
多様な働き方の広がり
終身雇用制度が当たり前だった時代は終わり、多様な働き方が広がってきました。転職者が増えて、勤続年数が短かったり、雇用形態が正職員とは異なったりして、年金受給額が少なくなる場合も珍しくありません。
また、フリーランスや自営業の人には退職金はありませんし、年金も国民年金のみとなります。
老後にかかる費用
実際に老後にかかる費用の内訳を見てみましょう。生活費に加えて、介護費用、入院・手術費、葬儀費用など高齢者に特有の費用があることに注意が必要です。
生活費
総務省が発表した「家計調査報告2021年」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の消費支出は1か月に約22万4,000円です。食費、水道光熱費、保健医療費、交通・通信費、教養娯楽費などが含まれています。
ただし、このうち住居費は約1万4,500円となっており、持ち家がある人を含んだ数字になっていることに注意が必要です。また、この他に税金や社会保険料などの非消費支出が約3万1,000円あります。
介護費用
家計調査報告の消費支出には、介護費用が含まれていません。生命保険文化センターによる「生命保険に関する全国実態調査 2021年度」によると、介護保険制度を利用した場合の介護費用の平均自己負担額は、月平均で8万3,000円です。
また、住宅改造や介護用ベッド購入などにかかる一時的な費用もあります。また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に夫婦で入居する場合には、2,000万円~4,000万円ほどの費用が発生します。
入院・手術費
消費支出には保健医療費が含まれていますが、入院・手術費までは含まれていません。特に、高齢になると医療機関にかかる機会も増え、入院や手術の可能性も高まります。公的医療制度を利用するだけではなく、民間の医療保険に加入しておくと安心です。
葬儀費用
最近では、家族に頼らずに自分で葬儀費用を準備しておく人が増えてきています。葬儀の規模や形式によってかかる費用は異なります。
小さなお葬式が調査した結果では、全国における平均葬儀費用は127万円※でした。葬儀形式別では、一般葬が平均191万円※、家族葬が平均110万円※、直葬が平均36万円※となりました。自分の葬儀の希望に応じて費用を用意しましょう。
(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)
<関連記事>
【第1回調査】家族葬にかかる費用相場(全国編)
【第1回調査】直葬にかかる費用相場(全国編)
【第1回調査】一般葬にかかる費用相場(全国編)
夫婦の老後の収支を考えるポイント
2,000万円問題は、あくまでも平均の老後資金の話なので、実際にはそれぞれの夫婦の場合に応じて考えていかなければなりません。夫婦の老後の支出と収入について、収支を考えるポイントを解説します。
夫婦の老後の支出
支出についてまずチェックしておきたいのが住居費です。持ち家の場合は住宅ローンが完済しているかどうか、リフォーム費用が必要かどうかという2点が大きなポイントになります。特に住宅ローンは可能な限り、老後期間に入るまでに繰上げ返済しておきましょう。
また、医療費は後期高齢者医療制度において1割負担ですが、現役並みの所得者は3割負担であることに注意が必要です。
夫婦の老後の収入
一般的な老後の収入源は公的年金です。夫婦の年金受給額を、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」によって確認しておきましょう。仕事を続ける場合や、他の収入源がある場合には、収入見込み額を計算して世帯支出と比べ、過不足を把握しておかなければなりません。
老後資金対策としてできること
具体的には、どのような老後資金対策ができるのでしょうか。ライフプランを立てる、生活費を見直す、長く働く、つみたてNISAやiDeCoを利用、年金の繰り下げ受給、個人年金保険の6つの対策について説明します。
自分に沿ったライフプランを立てる
かつては、終身雇用制度に支えられた標準的なライフプランに沿っていけば、安定的な人生を送ることができました。ただし、今後はそれぞれの働き方や、収支状況などに応じた、独自のライフプランを立てる必要があります。まずは、現時点から将来に向けての家計状況をシミュレーションすることから始めてみましょう。
生活費を見直す
毎月の生活費を見直すことも、老後資金対策の1つになります。無駄な支出がないか、削減できる項目がないかをチェックしてみましょう。特に、固定費の削減は効果的です。例えば、スマホの格安SIMへの乗り換え、電力会社の変更、生命保険の見直しなどに目をむけてみてはいかがでしょうか。
長く働く
健康であれば、できるだけ長く働いて収入を得るということも、効果のある老後資金対策になります。厚生年金の「在職老齢年金」制度を利用すれば、60歳以降に会社で働きながら年金を受け取れます。
また働くことによって、気分転換になったり、人との関わりが持てたりするなど、収入以外のメリットもあるでしょう。
つみたてNISAやiDeCoを利用
つみたてNISAは「少額投資非課税制度」であり、毎月一定額を積立投資できる仕組みです。利益は一定額まで非課税となり、いつでも売却できるという特徴があります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を作るための私的年金の仕組みです。掛け金の全額が所得控除の対象となり、運用益は非課税なので、効率的に老後資金を形成できます。
<関連記事>
iDeCoは不向きな方も。おすすめしない9つのケースを解説
年金の繰り下げ受給
「繰り下げ受給」という制度により、公的年金の受給を先延ばしにすると、年金給付額が上乗せされます。少しでも年金受給額を増やしたい人は、ぜひ活用しましょう。ただし、受給開始までの生活費のやりくりをしなければなりません。
個人年金保険
個人年金保険とは、民間の保険会社によるサービスで、一定の年齢まで毎月保険料を積み立てていきます。満期後に年金を受け取れる仕組みであり、公的年金に加えて収入を確保できるので安心です。
生命保険料控除の対象となる契約であれば、積み立て期間に控除を受けられ、節税効果があります。
<関連記事>
老後の資金を増やすための運用方法とは?投資との違いや注意点について徹底解説
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
老後資金は平均の試算では2,000万円必要であるとされていますが、それぞれの場合によって必要な資金は異なります。安心して老後の生活を送れるように、ライフプランを立て、老後資金対策を行いましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。夫婦の老後資金に2,000万円が必要なのかどうかを知りたい方や、葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


「お悔やみ申し上げます」は通夜や葬儀の定型句なので、宗派を気にせず使えます。ホゥ。