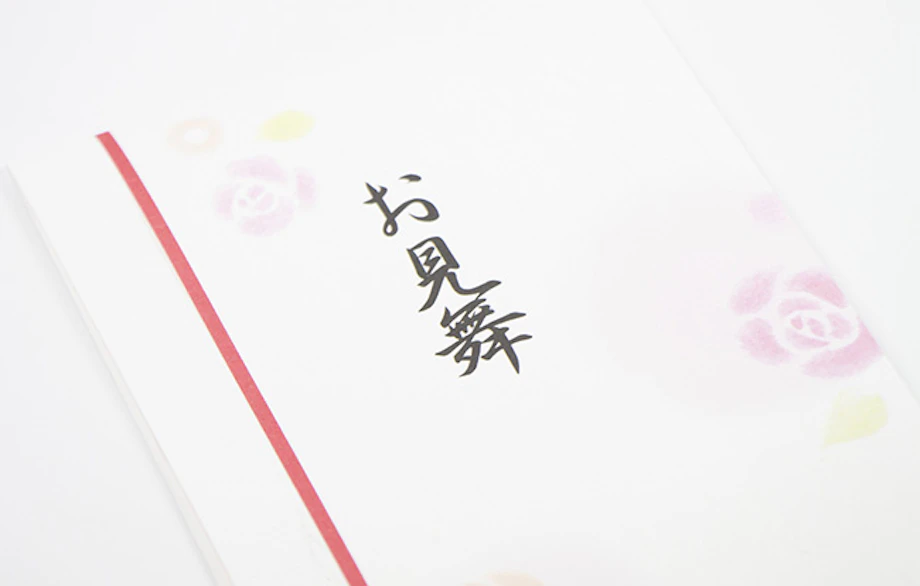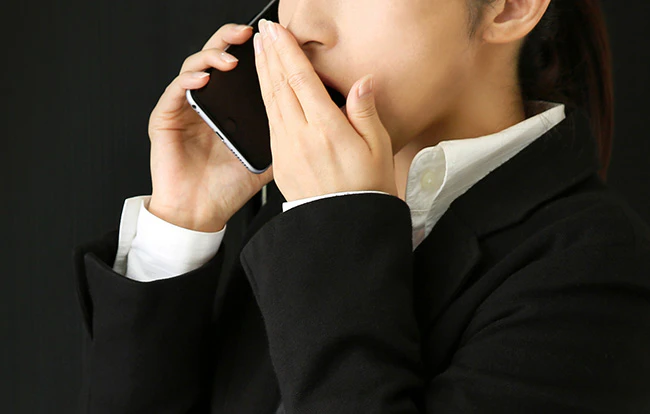友人や親戚、職場の人が入院した際にお見舞金を渡すケースもあるでしょう。しかしお見舞金の包み方や渡し方など、細かいマナーがあることを知らない人は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、お見舞金を包む封筒の選び方や包み方、渡し方のマナーについて解説します。
<この記事の要点>
・お見舞金の封筒はのしがついていない、結び切りの水引がついたものが適している
・お見舞金は新札を使わず、紙幣の肖像画が表側になるように入れるのがマナー
・お見舞金は入院や手術から数日後の14時以降に渡すのが最適
こんな人におすすめ
お見舞金を初めて包む人
お見舞金の封筒の書き方が知りたい人
お見舞金の渡し方のマナーが知りたい人
お見舞金を包むのに適している封筒は?
お見舞金を包む封筒は何でもよいわけではありません。お見舞金に適した封筒を選び、渡す相手に失礼のないようにしましょう。ここでは、お見舞金を包むのに適している封筒とは何か解説します。
紅白のご祝儀袋が基本
お金を包む封筒にはさまざまな種類がありますが、お見舞金を包む場合は紅白のご祝儀袋が適しています。そして贈る相手の全快を祈りつつ、病気やケガを繰り返さないという願いを込めて、結び切りの水引を選ぶようにしましょう。
中袋を用意するのが正式
お見舞金を包む際には中袋を用意するのがマナーです。簡易的なご祝儀袋には中袋がついていないケースがあるため、中袋の有無をきちんと確認して選びましょう。中袋にお見舞金を包み、表包みで中袋を包むのが基本です。
熨斗がついていないもの
お見舞い金は熨斗がついていないものを選ぶのが一般的です。ただし、熨斗はもともと長寿や繁栄を象徴する縁起物とされています。地域や風習によっては、贈る相手の幸せと健康を願うものとして熨斗をつけて贈る場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
水引がないほうがいいケースも
基本的にご祝儀袋の水引には、結び切りや鮑結び(あわじ結び)のタイプを選びます。しかし重篤なケガや病気、事故、流産といった深刻な状況で入院している場合は、水引がついていないもの(赤い帯だけがついているもの)を選ぶとよいでしょう。
お見舞金を包むのは避けたほうがいい封筒は?
お見舞金を包む際は色に注意しましょう。お見舞金を包むのは紅白のご祝儀袋が基本です。黒白や黄色、銀の水引が用いられた封筒は不幸ごとに使用するものであるため、お見舞金を包むのには適していません。
また水引の結び方も、結び切りや鮑結びを選びましょう。花結びは「何度繰り返してもよい贈り物」に用いられるため避けてください。
お見舞金を入れる封筒の書き方
お見舞金を入れる封筒には書き方のマナーがあります。書き方を誤ると相手に悪い印象を与えかねないため、ここで紹介する表袋と中袋の書き方を押さえておきましょう。
表書きの書き方
お見舞金を入れた封筒の表書きは、上段中央に「御見舞」もしくは「お見舞」と記載するのが一般的です。しかし病気や事故の場合は「お慰め」と記載しても問題ありません。
注意すべきは、表書きを4文字にしないことです。「お見舞い」のように4文字にすると、「4」という数字から「死」を連想する人もいるため、注意しましょう。
下段中央には指名を記載しますが、連名で記入する場合は右から順番に目上の人から記入します。送り主が4名以上の場合は代表者の名前を記載し、「外一同」と代表者の隣に小さく記載してください。連名者の名前は別紙に記載して同封しましょう。
中袋の書き方
中袋の表面中央には、縦書きでお見舞金の額を記載します。金額は算用数字ではなく、「壱」「弐」「伍」「仟」のように大字を使用しましょう。
お見舞金が5,000円であれば、「伍仟圓」のように記載します。中袋の裏面左下には、送り主の氏名と住所を記載してください。
お見舞金を封筒に包むには?入れ方のマナー
お見舞金を封筒に包む際にも、「新札を使わない」「縁起の悪い金額を避ける」などの細かなマナーがあります。ここで紹介するマナー3つを押さえておきましょう。
新札ではないきれいなお札を使う
弔事と共通していますが、新札は使わないように気をつけましょう。折り目のついていない新札は「最初から用意していた」「病気や不運を予測していた」と思われることから、避けるべきとされています。
とはいえ汚れや破損のあるお札を使うのではなく、できる限りきれいなお札を用いましょう。手元に新札しかない場合は、折り目をつけてから入れるのがマナーです。
正しい向きで入れる
お見舞金は紙幣の肖像画が表側になるように入れるのがマナーです。上下の向きに決まりはありませんが、「千円札を5枚」といったように複数枚入れる場合は、前後だけでなく上下の向きも揃えましょう。向きがバラバラだと相手に不快な印象を与えかねません。
縁起の悪い金額は避ける
「4」「9」といった数字は「死」「苦」を連想させることから忌み数とされています。そのためお見舞金の額は「4,000円」「9,000円」といった数字を避けるようにしましょう。お見舞金の金額は贈る相手との関係性によって決めるとよいでしょう。
お見舞金を入れた封筒を用意したら!渡し方のマナー
お見舞金を贈る際には、渡すタイミングや渡す際にかける言葉にも配慮する必要があります。ここで紹介するお見舞金を渡す際のマナー2つを押さえておきましょう。
お見舞金を渡すタイミング
お見舞金を渡すタイミングは、入院や手術から数日後の14時以降が最適です。入院直後や手術直後は本人の調子が優れない恐れもあるうえに、バタバタと忙しい可能性もあります。また昼食があることも考慮し、時間帯はお昼過ぎがよいでしょう。
面会したら相手の体調を配慮しつつ、長居せずに速やかに渡してください。
渡す際にかける言葉
お見舞金を渡す際は「お気持ちばかりですが、お役に立てれば」といった言葉を添えるとよいでしょう。相手に負担をかけたくない場合は、お返しはいらない旨を伝えるようにしてください。
また、お見舞い金はお見舞いの品の代わりとして渡すものであるため、「お見舞いの品の代わりですが」といった言葉を加えるのもよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
お見舞いで渡すお見舞金は、中袋のある紅白のご祝儀袋を使用するのが一般的です。渡す際には相手の体調や様子に配慮して、入院や手術から数日経った14時以降に渡すようにしましょう。渡す際には、相手の心情に寄り添うような言葉を選んで声をかけましょう。
小さなお葬式では、香典袋の渡し方など葬儀に関するマナーのご相談も受け付けています。葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。