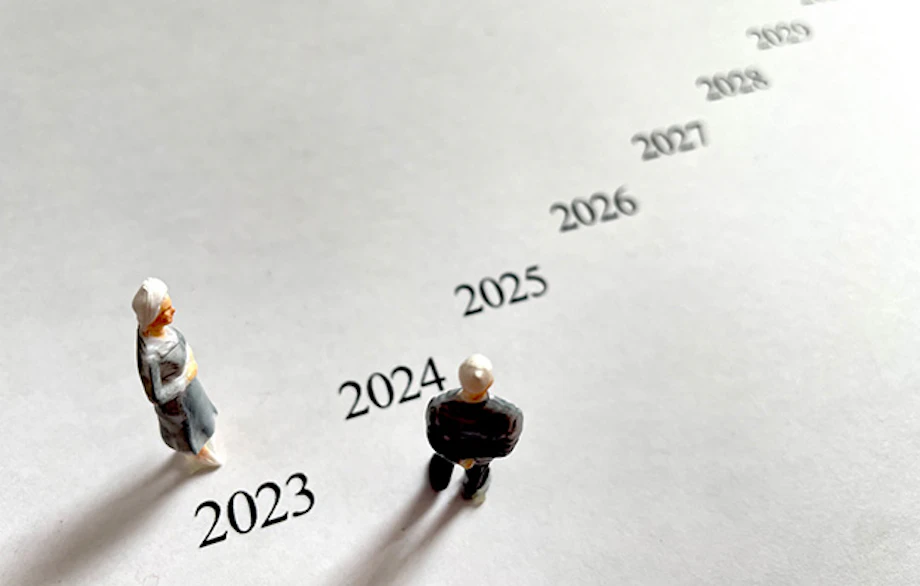長期間納める年金に対して、「一体いつまで払うんだろう」と考える方は少なくないでしょう。毎月の出費にもなっているため、「払った分を受け取れる?」と不安を感じている方もいるかもしれません。
本記事では、年金の納付期間と受給額の関係、早め・遅めに受給する方法、受給額を増やす方法について解説しました。また支払いが難しい方への免除・猶予制度についても触れているので、ぜひご覧ください。
<この記事の要点>
・繰り上げ受給は60歳~65歳の間に、繰り下げ受給は66歳~75歳の間に年金を受取れる方法
・年金は基本的に60歳まで支払うが、任意加入や付加保険料により受給額を増やすことができる
・支払いが難しい場合には免除や猶予制度を検討するとよい
こんな人におすすめ
年金に不安を感じている人
年金の納付期間について知りたい人
もらえる年金の金額について知りたい人
年金いつまで払う?開始から終了まで
年金保険には、国民年金と厚生年金があります。どちらも年金を受け取るための納付期間と、満額受給するための納付期間は同じです。
【国民年金・厚生年金の納付期間】
・年金を受け取るための納付期間:10年
・年金を満額受給するための納付期間:40年(20~60歳まで)
ただし厚生年金は、公務員や会社員の加入する保険です。保険料は会社と折半し、給与から天引きされます。そのため定年後も働き続ける場合、最長で70歳まで支払い続けることになるでしょう。
(参考:『厚生労働省』https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html)
年金いつまで払う?支払い期間と受給額の関係
納付期間が長いと、その分多くの年金が支給されます。下記では国民年金と厚生年金の受給額についてまとめました。
【国民年金の受給額(自営業の方)】
・40年間納付/77万7,800円(年間)
・30年間納付/58万3,350円(年間)
・20年間納付/38万8,900円(年間)
・10年間納付/19万4,450円(年間)
※令和4年4月分からの年金額
【厚生年金の受給額(公務員・会社員)】
・40年間納付/93万6,000円(年間)
・30年間納付/69万6,000円(年間)
・20年間納付/46万8,000円(年間)
・10年間納付/22万8,000円(年間)
※年収400万円で計算したケース
※平成15年改正以降の「平均標準月額×5.769/1,000×加入月数」で算出
(参考:『日本年金機構』)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/040103.html)
年金いつまで払う?繰り上げ受給と繰り下げ受給について
原則65歳から年金を受け取れますが、「繰上げ受給」もしくは「繰り下げ受給」により金額は増減します。それぞれ何歳から受け取れるのか、早め・遅めの受給による増減率についてまとめました。
繰り上げ受給による影響
繰上げ受給は、本来よりも早い60歳~65歳の間に年金を受け取ります。「定年退職をしたから早めに受け取りたい」「収入を増やしたい」という理由から、選択する方もいるでしょう。
ただし早めの受給は、減額されます。減額率は、以下の式を確認してください。
減額率(最大24%)=0.4%×繰上げ受給の月から65歳になる日
(※昭和37年4月1日以前生まれの方は減額率0.5%、最大30%)
【減額率の具体例】
・60歳から受給開始
・年間360万円を受給する予定だった場合
・減額率:0.4%×5年×12か月=年間24%減
・受給額:360万円×(1-0.24)=273万6,000円(年間)
(参考:『日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html)
繰り下げ受給による影響
繰上げ受給は、本来よりも遅い66歳~75歳の間に年金を受け取ります。「多めに年金を受け取りたい」という理由から、選択する方もいるでしょう。
遅めの受給は、増額されるのが特徴です。増額率は、下記の式をご覧ください。
増額率=0.7%×(65歳になった月から繰下げ受給する月の前月までの月数)
【増額率の具体例】
・70歳から受給開始
・年間360万円を受給する予定だった場合
・増額率:0.7%×5年×12か月=年間42%増
・受給額:360万円×(1+0.42)=511万2,000円(年間)
(参考:『日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html)
年金いつまで払う?受給額を増やす「任意加入」「付加保険料」
納付期間が長ければ、それだけ多くの年金を受け取れます。受給額を増やしたい方向けに、「任意加入制度」があるので要チェックです。ほかにも定額に上乗せする「付加保険料」についても確認してみましょう。
任意加入制度とは
60歳になった方でも「受給額をもっと増やしたい」という目的で、「任意加入制度」に加入できます。通常は60歳~65歳まで加入できますが、受給資格の10年に満たない方は最長70歳まで納付可能です。
ただし任意加入制度を利用できるのは、下記のケースになります。
・繰上げ受給をしていない
・厚生年金に加入していない
・納付期間が40年未満
(参考:『日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html)
付加保険料とは
付加保険料では、定額保険料(月額1万6,590円)とは別に任意で月額400円納めることが可能です。納めた分は、「200円×付加保険料納付月数」で計算し老齢基礎年金に上乗せされます。
【付加保険料を納めた場合の計算例】
・付加保険料の納付期間20年を想定
・付加保険料分:200×240月(20年)=4万8,000円
・老齢基礎年金77万7,800円+4万8,000円=82万5,800円(年間)
年金いつまで払う?支払いが難しい方の免除・納付猶予制度
収入面から保険料を払うのが難しい場合、免除・猶予制度を検討するのも方法の一つです。「本人や世帯主、配偶者の所得が一定より低い」「失業により納付できない状況」といったケースが対象になります。
免除制度は名称のとおり納付を免除され、全額・4分の3・半額・4分の1といった4つの割合があります。納付猶予制度は、納付の猶予期間を設けられるのが特徴です。
申請方法は、住所の登録をしている役場の「国民年金担当窓口」より申請書を提出します。なお申請書は、日本年金機構の「国民年金関係届書・申請書一覧」ページからダウンロードが可能です。
年金の支払い期間を確認する方法
現状、どのくらい納付したのか知りたいという方は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で納付状況を確認できます。いつまで払い続けようか、将来いくら受給したいのか、検討するために納付状況を見てみるとよいでしょう。
ねんきん定期便をチェック
日本年金機構は、毎年ねんきん定期便を発行しています。これは保険料納付額・年金加入期間・加入実績に応じた年金額に加えて、月別の納付状況も確認できるハガキです。また50歳以上だと、老齢年金の種類と見込み額も確認できます。
35歳・45歳・59歳の節目年齢では、全期間の年金加入履歴や納付状況がまとめられているため要チェックです。
(参考:『日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/teikibin.html)
ねんきんネットをチェック
日本年金機構では、「ねんきんネット」というサイトを運営しています。こちらのサイトでは、年金記録や年金見込み額、保険料に関する通知書を含むいくつかの情報が閲覧可能です。
また年金の免除・納付猶予の申請書や追納申込書といった書類を作成したり印刷したりできる便利なサイトです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
年金を満額で受け取るには、20歳~40歳(40年間)払わなければなりません。より多く受給するには、60歳~65歳までの任意加入制度の利用も検討するとよいでしょう。反対に収入面から納付が厳しい場合、免除・納付猶予制度の利用も考えてみてください。
将来に対して収入や健康だけでなく、漠然とした不安を覚える方が少なくないでしょう。事前に調べて準備しておくと、不安の軽減にもつながります。
「小さなお葬式」では、ご予算やご意向に合わせた葬儀プランを提案しています。終活の一環として、葬儀の規模や参列者について検討したい方は、お気軽にお問合せください。24時間365日つながるお客さまサポートダイヤルを設置しており、お急ぎの方には最優先する「専用ダイヤル」で対応させていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


香典の郵送は、現金を不祝儀袋に入れ、現金書留用の封筒でなるべく早く送ります。ホゥ。