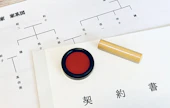贈与税は、一定額以上の財産を他人から譲り受けた際に発生する税金です。財産の贈与を検討中の方の中には、「贈与税の申告義務はあるのか」「どのような場合で申告が必要なのか」について気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、贈与税で申告が必要・不要になる条件や、申告手続きの流れを紹介します。申告時の注意点や無申告のリスクに関することも併せて解説するため、財産を贈与する予定のある方には必見の内容です。
<この記事の要点>
・受け取った財産が110万円以下の場合、贈与税は発生せず申告不要である
・贈与税申告には贈与税申告書やマイナンバーなどの書類を揃えて、住所地管轄の税務署に申告する
・一定額以下の贈与財産が非課税になる特例制度を使用する際は、適用条件の確認が必要
こんな人におすすめ
贈与税の申告方法について知りたい人
贈与税が申告不要になる条件を知りたい人
贈与税が申告不要になる条件は?
贈与税には110万円の基礎控除があります。1月1日から12月31日までに受け取った財産が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。そのため、非課税枠内での贈与なら、贈与税申告も不要とされています。
例えば、1年間に父親から50万円、母親から20万円の合計70万円を受け取ったとしましょう。この場合は、贈与税は課されず贈与税申告も不要です。
贈与税の申告が必要となる条件は?
贈与税の申告が必要になるのは「基礎控除を超える金額を受け取るとき」と「特例制度を利用するとき」の2種類に大別されます。以下の条件に当てはまる方は、贈与税を申告しましょう。
年間110万円を超える生前贈与
贈与税の基礎控除である「年間110万円」を超える金額の贈与を受けた際は、贈与税の申告が必要です。なお、贈与税の申告義務が発生するのは受贈者です。贈与した方に贈与税がかかることはありません。
例えば、父親から娘へ1年間に210万円贈与したとしましょう。この場合は、110万円を超えた「100万円」に贈与税がかかり、受贈者である娘に対し贈与税申告の義務が発生します。一方、父親は贈与税の支払い義務も申告義務も発生しません。
特例を利用する生前贈与
特例制度を利用する場合にも贈与税申告が必要です。贈与税には「贈与財産が一定額以下であれば贈与税がかからなくなる」という非課税制度がいくつかあります。中でも、以下の制度を利用する際は贈与税申告が必要です。
・相続時精算課税制度
・配偶者控除の特例
・住宅取得等資金の非課税制度
上記の特例を利用する際には、たとえ贈与税が0円であったとしても、税務署に申告書を提出する必要があります。
非課税枠内の生前贈与でも税金がかかる場合がある
非課税枠内で贈与した際にも税金が発生することがあるため、注意が必要です。ここでは、気を付けておきたい2つのケースを紹介します。
定期贈与とみなされた場合
定期贈与とは、毎年決められた金額を計画的に贈与する方法です。定期贈与では、贈与を受けた合計金額に対して贈与税が発生します。
ただし、基礎控除の110万円以下に抑えて暦年贈与をしていた場合でも、「定期贈与」と見なされることがあるため注意が必要です。例えば、毎年100万円ずつ10年間贈与を受けたことが定期贈与と見なされると、「1,000万円-110万円=890万円」に対して贈与税が発生します。
相続開始前3年以内の贈与だった場合
相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象です。死亡前3年間の贈与は無効となり、相続財産に加算されます。贈与税の基礎控除以下の財産も対象です。
例えば、2019年に父親が息子に80万円を贈与し、その後2020年に亡くなり5,000万円を相続したと仮定しましょう。この場合、「80万円+5,000万円=5,080万円」が相続税の対象となります。なお、受贈時に贈与税を納めていれば、相続税から贈与税額を控除可能です。
贈与税を申告しないと起こるリスク
贈与税の申告義務があるにもかかわらず申告をしなかったときは、税務署からペナルティーが与えられます。ペナルティーの内容は、以下の通りです。
・延滞税
・重加算税
・過少申告税
・無申告加算税
その時の状況に合わせて、上記のうちのいずれか、あるいは複数の税が課されます。申告や納税までの期間が長くなればなるほど税額が上がることもあるため注意しましょう。
贈与税の申告手続きの流れ
贈与税が発生する際は、税務署に申告書を提出します。スムーズに手続きを進めるためには、事前に申告手続きの方法を確認しておくことが大切です。ここでは、申告手続きの方法を手順に沿って詳しく解説します。
1.必要書類を用意する
贈与税の申告に必要な書類を用意しましょう。贈与税申告の必須書類は「贈与税申告書」と「マイナンバー」です。また、他にも以下のような書類の提出が求められます。
・受贈者の戸籍謄本
・受贈者の戸籍の附票の写し
・受贈者の所得の分かる書類
・相続時精算課税選択届出書 など
適用する特例や、財産の種類によって必要とされる書類が異なるため注意しましょう。なお、贈与税の申告書は、国税庁のホームページから取得できます。
(参考: 『国税庁 令和3年分贈与税の申告書等の様式一覧』)
2.贈与税申告書を作成する
贈与税申告書を入手したら、住所や氏名などの基本情報と、贈与財産の金額、贈与税額などを記載します。贈与税額を出す際は、以下の手順で計算しましょう。
【計算方法】
1.贈与財産-基礎控除110万円=課税価格
2.課税価格×税率-控除額=贈与税額
【一般贈与税率】
| 課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3000万以下 | 3,000万円超 |
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | - | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与税率】
| 課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万以下 | 4,500万円超 |
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | - | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
例えば、1年の間に夫から妻に500万円の贈与があったとすると、税額は「500万円-110万円×20%-25万円=53万円」です。特例贈与税率は18歳以上の方が直系尊属から贈与を受ける際に適用し、それ以外の場合は一般贈与税率を適用します。
(参考: 『国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)』)
3.期限までに申告と納付をする
贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。受贈者の住所地管轄の税務署に、申告書の提出と納付を済ませる必要があります。贈与者ではなく受贈者が対象となるため注意しましょう。なお、申告書の提出や納税方法は以下の通りです。
| 申告書の提出 | ・税務署の窓口に提出する ・税務署宛に郵送する ・e-Taxで申告する |
| 贈与税の納付 | ・税務署や金融機関の窓口で納付する ・電子納税を利用する ・クレジットカードで支払いする ・コンビニ納付を利用する |
贈与税の申告をする際の注意点
贈与税の特例制度を使用する際は、適用条件に合致しているかを事前に確認しましょう。特例制度とは、一定額以下の贈与財産が非課税になる制度です。特例制度の一例には、以下のようなものがあります。
| 特例制度 | 適用条件 | 非課税限度額 |
| 偶者控除の特例 | ・夫婦の婚姻期間が20年を超えていること ・贈与財産が、 居住用不動産または居住用不動産を取得するための費用であること ・翌年3月15日までに、対象の不動産に住んでおり、その後も引き続き住む予定であること ・贈与税の申告をすること |
最高2,000万円 |
| 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 | ・受贈者が30歳未満の子または孫であること ・直系尊属からの一括贈与であること ・受贈者の前年度所得が1,000万円を超えていないこと ・国税庁の指定する方法で、贈与すること |
最高1,500万円 |
贈与財産を非課税枠以下に抑えれば、贈与税がかかりません。そのため、大きな節税効果を期待できます。
ただし、その分特例制度には細かい適用条件が設定されているため注意が必要です。適用条件をしっかりと確認してから利用を検討しましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
贈与金額が110万円の基礎控除以下であれば贈与税は発生せず、贈与税申告をする必要もありません。一方、基礎控除や非課税限度額を超える金額を贈与する際や、特定の特例制度を利用する際には、贈与税申告の義務が発生します。
申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日です。期限内に申告や納税ができなければペナルティーが発生する恐れがあります。申告や納税の手続きは余裕を持って進めましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


四十九日法要は、故人が亡くなってから48日目に執り行います。ホゥ。