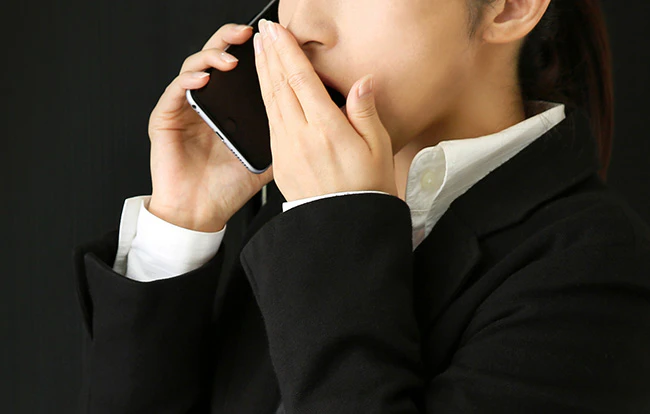日頃親しくしていた人が病気やけがで入院した場合、回復して退院した後にお見舞いを渡したいと考えることもあるでしょう。その際は、どのようなことに気をつけて贈ればよいのでしょうか。
この記事では、お見舞いを贈るタイミング、のしなどのマナー、贈る品物、お見舞いにふさわしくないものについて詳しく解説します。
<この記事の要点>
・退院後に贈るお見舞いは「退院祝い」と呼ばれる
・退院祝いを贈るタイミングは退院後1週間~1か月が目安
・退院祝いには「消えもの」と呼ばれる洗剤や石鹸、タオルなどの消耗品がおすすめ
こんな人におすすめ
退院後のお見舞いを渡したい人
退院後のお見舞いをいつ渡すべきか悩んでいる人
退院後のお見舞いの品選びに悩んでいる人
退院後のお見舞いは「退院祝い」
退院後に贈るお見舞いのことを「退院祝い」といいます。退院祝いには、どのような意味があるのでしょうか。また、よく似た言葉に「快気祝い」があります。退院祝いと快気祝いはどう違うのでしょうか。
退院祝いの意味
退院祝いには2つの意味があります。1つは、入院していた人が退院した際に無事に回復したことを祝って、知人、友人、親族などが贈るものです。
もう1つは、入院中にお見舞いに行けなかった場合に、お見舞いの代わりとして贈るという意味もあります。どちらの意味であっても回復を祝うことは同じです。
快気祝いとの違い
「退院祝い」は病気になった人に対して周りの人が贈るものですが、「快気祝い」は病気になった人が周りの人に贈るものです。
お見舞いに来てくれたことやお世話になったことに対して感謝の気持ちを表し、病気やけがから回復して退院したことを報告するために贈ります。
なお、通院や療養が不要となりすっかり元気になった場合には「全快祝い」ということもあります。
退院後のお見舞いを贈るタイミングは?
退院後のお見舞いを贈るタイミングの目安は、退院後1週間~1か月くらいまでです。退院直後は、自宅に戻ってまだ落ち着かない時期ですので避けましょう。また、あまり時間が経ってからだと退院後のお見舞いとしてふさわしくありません。
自宅を訪問して直接お見舞いを渡したい場合は、あらかじめ連絡をして、相手の都合や体調を確認しましょう。
<関連記事>
【例文あり】お見舞いをするタイミングやマナーは?注意点も解説
お見舞いの言葉かけのマナーとは?危篤の場合は特に注意
退院後のお見舞いのマナー
退院後のお見舞いを贈る際には、のしをどのようにかけるのがマナーなのでしょうか。失礼にならないように、のしと表書きのマナーについて押さえておきましょう。
のしのマナー
退院祝いには、のしの飾りのついていないかけ紙を選びましょう。のし紙の右上についている飾りは「のしあわび」というものです。かつて、伸ばして干したあわびを縁起物として贈っていたことに由来しており、「伸ばす」ということが「病気やけがの療養を長引かせる」ことを連想させるため、お見舞いではつけないのがマナーとされます。
また、水引は紅白の結び切りのものを選びましょう。紅白は「お祝い」を、一度結ぶとほどけない結び切りは「2度と繰り返さない」を意味します。病気やけがは繰り返したくないので、結び切りを使うのがマナーです。
表書きのマナー
表書きには「祝 御退院」と書くのが一般的です。相手の状況を把握している場合には次のように使い分けましょう。すでに完治しており通院や療養の必要がなくなっている場合には、「祝 御全快」と書きます。また、退院後にも療養や通院が必要な場合には、「祈 御全快」と書くこともあります。のしの下には、贈り主のフルネームか苗字のみを書きましょう。
<関連記事>
お見舞金を包む封筒はどれにすべき?包み方や渡し方のマナーを解説!
退院後のお見舞いに何を贈るか
退院後のお見舞いとして、何を贈るのがよいのか迷ってしまうかもしれません。お見舞いの相場について説明した上で、ふさわしいものを実例を挙げて紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
退院後のお見舞いの相場
退院後のお見舞いの相場は、相手との関係性によって異なります。友人、知人、職場関係者であれば3,000円~5,000円、家族や親族であれば5,000円~10,000円程度が目安です。
相場よりも高いものを選んでしまうと、かえって相手に負担をかけてしまうので、高価になりすぎないように気をつけましょう。
洗剤・石鹸・タオル
退院後のお見舞いにふさわしいものとして、使うとなくなる「消え物」があります。その中でも特に、「病気やけがを洗い流す」ことに通じる洗剤・石鹸・タオルなどが、縁起のよいものであるとされています。誰でも使う生活必需品であることからも、贈り物に適している品物です。
食品
お菓子、果物、ゼリー、ジュースなどの食品も、食べるとなくなる「消え物」として「病気やけがが消える」ことに通じることから、退院後のお見舞いにふさわしいとされています。
ただし、退院直後の人に食事制限がないかはあらかじめ確認しておいたほうがよいでしょう。また、家族で分けられる詰め合わせのお菓子などであれば、家族の苦労をねぎらうことにもなります。
花
退院後のお見舞いに明るい色の花を贈ると、気持ちも晴れやかになり喜ばれます。また、花が枯れていくことが「病を枯らす」ことにつながるとされているので、退院後のお見舞いとしてふさわしいものです。
特に、花瓶の準備などがいらないフラワーアレンジメントであれば、相手に負担をかけることなく飾ることができるので喜ばれるでしょう。
カタログギフト
相手の体調や好み、家族構成などがわからず、何を贈ればよいのかわからない場合には、カタログギフトという選択肢もあります。相手に好きなものを自由に選んでもらえるため、選ぶ楽しみも感じてもらえるでしょう。
退院後のお見舞いにふさわしくないもの
退院後のお見舞いにふさわしくないものがありますので覚えておきましょう。
【鉢植えの花・シクラメン・菊】
鉢植えの花は「根付く」ことが「寝付く」ことを連想させることから、お見舞いにはふさわしくありません。シクラメンは「死」や「苦」を連想させ、菊は弔事でよく使われることから避けましょう。
【枕・パジャマ・シーツ】
ベッドに寝ることを連想させる寝具類は、入院を連想させてしまうため、退院後のお見舞いにはふさわしくありません。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
退院後のお見舞いは、相手が病気やけがから回復したことをお祝いして贈るものです。お見舞いの贈り物のマナーや相場を押さえて、相手の負担にならないように配慮しつつ、喜ばれるものを選びましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。