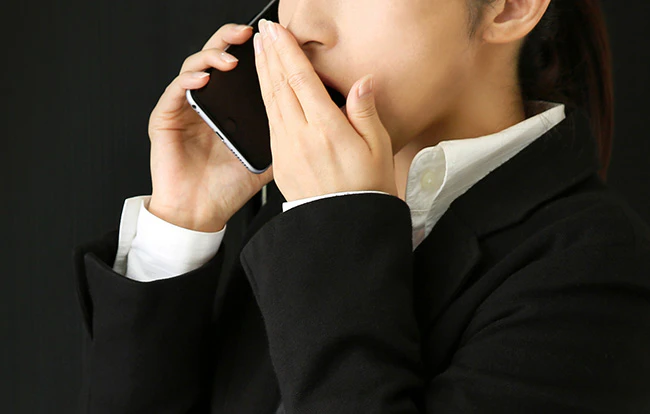親族が危篤になったら、付きっきりで看病をしてあげたいものです。しかし、それぞれの生活がある以上勝手に振舞うわけにもいかず、看病するには手続きが必要となります。しかし、会社の休みの取り方がわからず不安という人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、親族が危篤になった場合の休みの取り方についてご紹介します。休みを取る際に、会社へ送る文例も盛り込まれています。適切な形で休みを申請すれば、心置きなく看病に専念できるでしょう。
<この記事の要点>
・親族が危篤になった場合は慶弔休暇は使えない
・危篤で休みを取る場合は、休暇日数を決めてから上司に相談する
・危篤後に慌てないために、普段から周囲の人に闘病している人がいることを伝えておく
こんな人におすすめ
親族が危篤になった際の対応について調べている方
危篤時の休暇の取り方について知りたい方
親族が危篤になった場合の休みの取り方
身近な人に危篤者が出てしまったら、会社へ連絡を取って休暇を申請しましょう。誰にコンタクトをとればよいのか、看病のための休みはどのような扱いになるのか、何日くらい休めるのかなど気になることは多いのではないでしょうか。ここでは、適切な休みの取り方について解説します。
慶弔休暇を使えないので有給を使う
危篤による休暇は「慶弔休暇」として認められません。そのため、有給休暇を使うのが一般的です。危篤は人命にかかわる重大な理由ですが、存命であるうちは慶弔休暇が適用されないのが決まりになっています。葬儀という形になった場合でも、一般的には慶弔休暇は3親等以内の親族の葬儀にのみ適用されます。
有給が使えない場合は、欠勤扱いです。会社によっては考慮してもらえる場合もあるので、就業規則は事前に確認しておきましょう。
何日の休みを申請するか決める
危篤になってから臨終までの期間は人それぞれなので、申請する休みの期間は事前に決めにくい面があります。また、危篤者との関係性によっても休む長さも変わります。
休む日数はおおよそ1~3日程度を目安と考えて、定期的に状況を報告しながら延長していくか、まとまった日数を取得しておくのが一般的です。まずは休みの取り方にどのような選択肢があるのか、上長に相談してみる必要があります。
危篤で休みを取る場合は事前に上長へ相談する
危篤で休むときは、まずは直接、上長へ相談しましょう。会社によっては休暇申請の提出先が決められている場合もありますが、自分から上長にも話を通しておいたほうが職場での関係性を良好に保てます。
相談の内容としては、どのような形で休みを取るか、どのくらい休暇を取るかを決めます。休んでいる間の代理は誰か、業務の分担などについても話し合っておくと、業務上の混乱を抑えてスムーズに復帰しやすくなります。
親族が危篤になった場合の連絡の仕方
業務時間内であれば口頭で伝えるのが原則ですが、直接伝えられない場合は電話で連絡を取りましょう。深夜や早朝といった電話をするのがはばかられる時間帯であれば、メールでも問題ありません。
メールで連絡した場合は、差し当たりの連絡であることを記載して、のちほど電話でフォローを入れます。その際に状況の報告や、今後の相談などもしておきましょう。
親族危篤で休みを取るときのメール例文
親族が危篤になって、会社を休むときに送るメールの文例をご紹介します。「父母が危篤になったとき」と「祖父母が危篤になったとき」「身内が危篤になり取引先との打ち合わせを延期する場合」とそれぞれ場面に合わせて用意しました。シチュエーションに合わせて、活用していきましょう。
父母が危篤になった場合の休みを申し出る文面
(所属)部 ○○部長様
(所属)部 (自分の名前)
深夜につき、差し当たってメールで失礼します。
私事で恐縮ですが、長期にわたって入院していた父(母)が、危篤になったと連絡がありました。
これから病院へ向かいます。
このため、看病のために本日は休みをいただきたく存じます。
詳細は状況を確認次第ご報告させていただきます
(所属)部 ○○部長様
(所属)部 (自分の名前)
いつもお世話になっております。
先ほど、父(母)が倒れ危篤状態となりました。
突然で大変恐縮ですが、2日間の休みをいただきたく存じます。
状況によっては延びることも考えられますが、よろしくお願いいたします
祖父母が危篤になった場合の休みを申し出る文面
(所属)部 ○○部長様
(所属)部 (自分の名前)
私事ながら、同居している祖父(祖母)が倒れ危篤状態となりました。
つきましては、付き添いのため明日は休みを行きただきたく思います。
よろしくお願いいたします
(所属)部 ○○部長様
(所属)部 (自分の名前)
お疲れ様です。
祖父(祖母)の危篤に伴い、明日休みをお願いしたく連絡させていただきました。
場合によっては日数が増えることも考えられますので、状況が変わり次第、その都度報告させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします
身内が危篤になり取引先との打ち合わせを延期する文面
株式会社(先方の会社名) 〇〇部 ~~様
平素より大変お世話になっております。
(所属)の(自分の名前)です。
私事で申し訳ございませんが、先ほど親族が危篤状態となりました。
ご迷惑をお掛けして大変心苦しいのですが、本日予定していた打ち合わせの延期をお願いできないでしょうか。
急なことで誠に申し訳ございません。
休暇明けに改めて日程の調整についてご連絡させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします
株式会社(先方の会社名) 〇〇部 ~~様
いつもお世話になっております。
(所属)の(自分の名前)です。
明日、XX月XX日に打ち合わせをお願いしておりました件でご連絡差し上げました。
私事で大変申し訳ありませんが、身内に危篤状態となったため、X日まで休暇をいただく運びとなりました。
つきましては、打ち合わせの日程を変更していただきたく連絡させていただきました。
新たな日程につきましては、後ほど~~よりご相談させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします
社外の人に連絡するときは、会社の人に対するときよりも丁寧な対応が求められます。自分の代わりの人選が決まっている場合は、その件もあわせて連絡しましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
危篤になってから慌てないために普段からできること
危篤で休みを取るときは、周囲の理解も大事です。実際に危篤になってからでは手が回らないことも多く、普段からの行動や周囲への気遣いも重要になります。いざというときにスムーズに休めるように、前もって気をつけておきたいことをご紹介します。
闘病している人がいることを周囲に伝えておく
身内に体調がよくない人がいるときは、その事実を周囲に伝えておくと、休むときに理解されやすくなります。突然「危篤の人がいるので休みます」と告げると、本当に危篤者がいるのか疑われてしまうケースもあります。闘病している人がいることを周囲に周知しておくことは、信用を得るために大事です。
実際に親族の危篤はズル休みの言い訳として使われることもあるため、誤解されやすい面もあります。普段から疑われるような紛らわしい行動をとらないことも、難なく休暇を取るポイントです。
普段の社会生活で助け合いをしておく
自分が困ったときに快く助けてもらうためには、日ごろから助け合う関係を築いておくことも大切です。危篤で休む際には長引くこともあり、周囲の人たちに手助けしてもらう場面も数多く出てくるでしょう。
社会生活を営むには、さまざまな人間関係が影響してきます。快く協力を得るには、周りの人の心証を良好に保つことも重要です。普段から好印象を持たれていたほうが大変なときに共感を得られやすく、休みも取りやすい環境になるでしょう。
元気なうちから「もしものとき」のことを相談しておく
元気なときから何かあったときのことを話し合っておくと、そのときが来たときに迷わずに行動しやすくなります。倒れてしまってからでは、本人の意向は確認できません。本人の希望を尊重したい場合は、十全に話ができるうちにきちんと相談しておきましょう。
相談しておくべき内容としては、葬儀や遺産関係があげられます。どのような形態の葬儀を行いたいのか、誰を呼んでほしいのかといったことは確認しておきましょう。遺産についても生前からはっきりとした意思表示があれば、後々の遺産に起因する争いを避けやすくなります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
この記事では、親族が危篤になった場合の休みの取り方について解説しました。身内が危篤で会社を休むときは、まずは上長へ連絡を取って有給をとります。何日休むかは、状況を見ながら相談して決めましょう。長引きそうな場合は、その旨を相談して理解を得られるように話し合うことも大切です。
元気なときから後のことを相談しておくと話を進めやすく、土壇場で迷わずに行動できます。特に生前から葬儀のことについて金額や規模、葬儀の形態などを葬儀のプロに相談しておけば、計画的な葬儀が可能です。
小さなお葬式でも、生前からの葬儀のご相談を受け付けております。しっかりと段取りされた葬儀をお望みの方は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
身内が危篤で休みを取るのは非常識なのか?
ほかの予定と身内の危篤が重なってしまったときどうしたらよいか?
危篤の身内にどのような言葉をかけたらよいのか?
身内以外が危篤の人のお見舞いに行くのはNGか?
身内が危篤で休みを取るとずる休みと勘違いされる?
危篤のお見舞いに行く場合、お見舞金が必要?

葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。