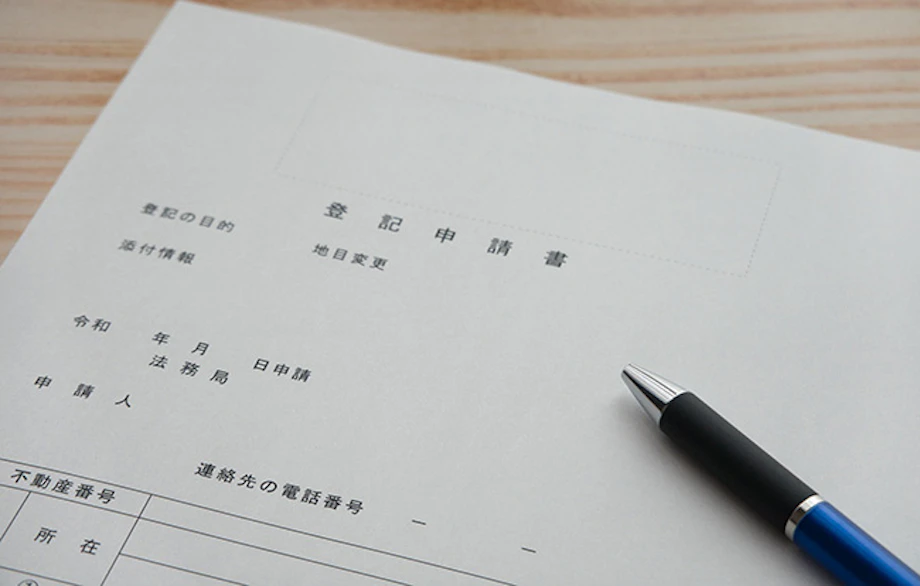相続登記をするには、どのような書類が必要なのでしょうか。この記事では、相続登記の必要書類の請求先窓口や取得費用、郵送で取り寄せる方法などについて詳しく解説します。
<この記事の要点>
・相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する
・相続登記をするには、不動産の全部事項証明書や相続人全員の印鑑証明書などが必要
・相続登記に必要な書類は約3,000円程度で取得することができる
こんな人におすすめ
相続登記とは何かを知りたい方
相続登記の必要書類の請求先・費用を知りたい方
相続登記の必要書類を郵送で取り寄せる方法を知りたい方
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の名義となっている不動産を相続人などの名義へと変える手続きです。相続手続きをしないことには、その不動産を売却したり担保に入れたりすることができません。また、相続登記はその不動産を取得した人の権利を守ることにもつながります。
そのため、その不動産を取得する人が決まったら、すみやかに相続登記をしておきましょう。
まずは、相続登記の種類と期限について解説します。
相続登記には3パターンがある
相続登記には、3つのパターンが存在します。それぞれ見ていきましょう。
遺言で登記をする
亡くなった方の遺言で不動産を取得する人が定められていた場合には、遺言で登記を行います。相続人が遺言で不動産を取得した場合は、原則として他の相続人の協力は必要ありません。
なお、遺言で財産を渡す相手が相続人のみであれば、相続人全員が合意をすることで遺言書とは異なる遺産分割を行うことも可能です。
遺産分割で登記をする
遺産分割での登記は、最も一般的な相続登記のパターンです。不動産を取得する人を定めた遺言書がない場合には、この方法で登記を行います。
遺産分割での登記は、相続人のうち誰が不動産を取得するのかについて相続人全員で話し合い、相続人全員が合意をしなければなりません。この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
相続人全員が合意をしていることの証拠として、相続人全員が実印で押印をした遺産分割協議書の添付が必要です。
法定相続で登記をする
法定相続での登記とは、法定相続分どおりに登記をする方法です。例えば、相続人が亡くなった方の配偶者と長男、次男なのであれば、「配偶者2分の1、長男4分の1、次男4分の1」の共有として登記をすることになります。
法定相続での登記は、一部の相続人が単独で申請をすることが可能です。
法定相続での登記は遺産分割協議が長期にわたってまとまらない場合などに行うことがあります。しかし登記識別情報が申請者にしか交付されないことや、その後遺産分割が確定した際に再度遺産分割での登記をし直す必要があることなどは注意が必要です。
相続登記はいつまでにすべき?
これまで、相続登記には特に期限はありませんでした。そのため、亡くなった方の名義のままで長期間放置をされる不動産が少なからず生まれてしまっているのが現状です。
亡くなった方の名義のまま放置をされると、その土地を活用しようにも誰に許可をとって良いのかわからず、使いようのない土地となってしまいます。
こうした所有者不明土地の問題を受け、2021年4月、相続登記に期限を設ける改正不動産登記法が成立しました。この改正は、2024年中に施行される予定です。
この改正により、相続登記に3年という期限が設けられました。
改正後は、正当な理由がなくこの期限内に登記をしないと10万円以下の過料に処される可能性があるため、より計画的に相続登記を進める必要が生じます。
相続登記の流れを解説
相続登記をするといっても、何をどこから進めて良いのか迷ってしまう人もいるのではないでしょうか。ここでは、相続登記の流れを解説します。
不動産を相続する人を決める
相続登記をするには、まず、その不動産を誰が取得するのかを決める必要があります。不動産を取得する人を決める方法には、主に次の3つがあります。
遺言で決める
亡くなった方の遺言書で不動産を取得する人を決める方法です。遺言書で不動産を相続する人が定められていた場合には、原則としてその遺言書で指定をされた人が不動産を取得します。
遺産分割協議で決める
相続人全員での話し合いである遺産分割協議で不動産を取得する人を決める方法です。遺言書がない場合には、この方法で不動産の取得者を決めます。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要です。
調停や審判で決める
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合には、調停や審判で不動産を取得する人を決めます。調停とは、調停委員を交えて家庭裁判所で行う話し合いのことです。
調停でも結論が出ない場合には、審判へと移行します。審判とは、遺産に属する物又は権利の種類などの事情を考慮して、裁判官が結論を下す手続きです。
参考:『遺産分割調停 裁判所』
相続登記の必要書類を集める
不動産を取得する人が決まったら、相続登記の必要書類を準備します。必要な書類や取得方法については後ほど解説します。
相続登記を申請する
必要書類の準備ができたら、相続登記を申請します。相続登記の申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。
相続登記の申請方法には、次の3つがあります。
・窓口に書類を持参して申請する
・郵送で申請する
・オンラインで申請する
相続登記に慣れていないのであれば、窓口へ持参する方法を選択すると良いでしょう。その場で不備が見つかれば、すぐに修正ができる可能性があるためです。
とはいえ、管轄の法務局が他県など遠方で出向くことが難しい場合には、郵送での申請が現実的です。
オンラインでの申請はシステムなどの準備も必要となるため、自分で登記をする場合にはおすすめできません。
相続登記の必要書類はどこで取得する?費用はいくら?
相続登記をするには、登記申請書だけを提出すれば良いわけではありません。
登記申請書に加えて、様々な添付書類が必要となります。遺産分割で登記をする場合の主な必要書類は、次のとおりです。
【相続登記の主な必要書類と取得先】
| 必要書類 | 取得先 |
| 登記申請書 | - |
| 遺産分割協議書 | - |
| 不動産の全部事項証明書 | 最寄りの法務局 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 |
| 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本 | それぞれその時点で本籍地のあった市区町村役場 |
| 被相続人の除票または戸籍の附票 | 除票:最後の住所地の市区町村役場 戸籍の附票:最後の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 |
| 不動産の評価証明書または評価通知書 | 不動産所在地の市区町村役場 |
状況によっては上記以外の書類が必要となる場合もあります。そのため、司法書士へ依頼せず自分で書類を準備する場合には、申請の前に法務局へ確認するとよいでしょう。
それぞれの書類について詳しく解説します。
不動産の全部事項証明書
不動産の全部事項証明書自体は、相続登記の添付書類ではありません。しかし、登記申請書や遺産分割協議書を正確に作成するためには、この全部事項証明書を取得する必要があります。
全部事項証明書とは、その不動産について登記されている情報が確認できる書類です。登記が電子化されたことで名称が変わりましたが、従来の登記簿謄本と基本的には同じものだと考えて差し支えありません。
全部事項証明書は、1通600円で全国どこの法務局からでも、誰でも取得することが可能です。例えば、大阪市内に存在する土地の全部事項証明書を名古屋市内の法務局で取得することもできます。
また、オンラインや郵送での取得も可能です。
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を記し、相続人全員が実印で捺印をした書類です。相続登記をしようとする不動産を誰が取得するのかが明確にわかるように作成します。
遺産分割協議書の記載例は、次のとおりです。
遺産分割協議書
被相続人 大阪太郎(昭和10年1月1日生、令和3年3月1日死亡、最後の住所は 愛知県名古屋市緑区○○1丁目1番地1)の財産につき、相続人 大阪花子、相続人 大阪一郎、相続人 大阪次郎 は分割協議を行った結果、次のとおり分割し、取得することを合意した。
第1条 次の財産は、相続人 大阪花子 が取得する。
1、土地
所在 名古屋市緑区○○1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 200平方メートル
2、建物
所在地 名古屋市緑区○○1丁目1番地
家屋番号 1番
種類 居宅
構造 木造瓦ぶき2階建
床面積 1階 100平方メートル 2階 80平方メートル
令和3年7月1日
住所 愛知県名古屋市緑区○○1丁目1番地1
相続人(配偶者) 大阪花子 印
住所 愛知県名古屋市中区〇〇1丁目1番地 〇〇マンション101号室
相続人(長男) 大阪一郎 印
住所 大阪府堺市〇〇2丁目2番地 コーポ〇〇202号室
相続人(二男) 大阪次郎 印
*押印は、実印で行います。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押した印が実印であることの証明のため、相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です。
印鑑証明書はそれぞれの相続人の住所地の市区町村役場で取得します。市区町村によってはマイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアなどで取得できることもありますので、お住まいの市区町村役場へ確認すると良いでしょう。
取得手数料は市区町村によって異なりますが、300円前後であることが一般的です。印鑑証明書の取得には印鑑カードが必要ですので、忘れずに持っていきましょう。
被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本等
相続人を確認するため、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。
現在も動いているものが戸籍謄本で、掲載されている人全員が転籍や死亡などで抜けたものを除籍謄本、戸籍の改製により閉鎖されたものを原戸謄本と言います。
1人の被相続人につき4通前後が必要となることが多いのですが、被相続人の転籍回数が多ければその分取得すべき通数も多くなります。
それぞれ、その時点で本籍を置いていた市区町村役場で取得します。取得費用は、戸籍謄本であれば1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本は1通750円です。
被相続人の除票または戸籍の附票
被相続人の最後の住所を証明するため、除票または戸籍の附票が必要です。
除票は被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得する一方、戸籍の附票は被相続人の最後の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。取得にかかる手数料は市区町村によって異なりますが、200円から400円程度であることが一般的です。
相続人全員の戸籍謄本
相続人の生存を確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、それぞれの相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。取得にかかる手数料は、全国一律で1通450円です。
不動産を相続する相続人の住民票
新しい所有者の情報を正確に登記するため、不動産を取得する相続人の住民票が必要です。住民票は、住所地の市区町村役場で取得します。
取得にかかる手数料は市区町村により異なりますが、1通200円から400円程度であることが一般的です。
不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書
登記をする不動産の固定資産税評価証明書または固定資産税評価通知書が必要です。
相続登記をする際には登録免許税という税金を支払う必要がありますが、登録免許税は固定資産税評価額の1,000分の4で計算されるため、この計算に必要な固定資産税評価額を証明する資料として添付します。
固定資産税評価証明書や固定資産税評価通知書は、その不動産の所在地である市区町村役場で取得します。
固定資産税評価証明書の取得費用は市区町村により異なり、300円前後です。固定資産税評価通知書であれば無料で取得できます。
地域によっては、毎年4月から6月ごろに市区町村役場から送付される固定資産税の納付書に同封されている固定資産税課税明細書でも受け付けてもらえる場合があります。
相続登記の必要書類を郵送で取り寄せる方法とは
相続登記の必要書類中には、郵送で取得できるものが多く存在します。
ここでは、次の書類を市区町村役場から郵送で取り寄せる方法を解説します。
・戸籍謄本
・除籍謄本
・原戸籍謄本
・住民票
・住民票の除票
・戸籍の附票
請求用紙を用意して必要事項を記入する
まずは書類の請求用紙を準備して、その必要事項を記載します。請求用紙は各市区町村役場まで取りに行かなくても、各市区町村役場のホームページに掲載されていますので、印刷をして利用しましょう。
必要事項さえもれなく記載があれば、必ずしも所定の様式ではなくとも受け付けてもらえる場合が大半です。
定額小為替を購入する
書類を取得するには、手数料がかかります。窓口へ向いて取得する場合にはその場で現金で支払えば良いのですが、普通郵便では現金を送ることができません。
そこで、郵送で書類を取り寄せる際に使うのが、定額小為替です。定額小為替であれば郵便へ同封できますので、これで手数料を精算します。
定額小為替には、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類が存在しますので、必要なものを購入しましょう。
定額小為替はその額面で購入することはできず、1枚の購入ごとに100円の手数料が別途必要です。つまり、450円の定額小為替を買うには550円を支払わなければなりません。
また、定額小為替はお釣りを出してもらえないことが大半です。
例えば、750円の除籍謄本1通を取るために1,000円の小為替を1枚送付した場合、250円分の小為替を返送してもらえることはほとんどありません。この場合には市区町村役場から電話がかかり、1,000円の小為替は返送するので、代わりに750円分の小為替を送り直して欲しいと言われます。
そうなれば、時間や手間が余分にかかってしまいますので、あらかじめ必要な額面の定額小為替を送るようにしましょう。
定額小為替は、ゆうちょ銀行で窓口が開いている時間内のみ購入できます。土日や夜間に開いているゆうゆう窓口では購入できません。
必要書類を同封して郵送する
準備ができたら、必要書類を同封して発送します。送り先についても各市区町村役場のホームページであらかじめ確認しましょう。
市区町村によってはどの庁舎宛に送っても良いわけではなく、郵送での請求先を別で設けている場合があるため、注意が必要です。また、送付先の部署名も「市民課」や「郵送事務処理センター」など市区町村によって異なります。
請求時に同封すべきものは、次のとおりです。
・請求用紙:記載済みの請求用紙を同封します。記載漏れがないか確認の上、封入しましょう。
・定額小為替:必要な分を同封します。
・本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードのコピーを同封します。
・返信用封筒:返送先の住所を明記し、切手を貼った返信用封筒を同封します。
相続登記の必要書類が追加される場合とは
相続登記の一般的な必要書類は上で解説したとおりですが、状況によっては他の書類が必要となります。
ここでは、他の書類が必要となるケースをいくつかご紹介します。
相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合
兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合には、次の書類が追加で必要となります。この場合には取り寄せに時間がかかることが予想されるので、早めから準備にとりかかることを特におすすめします。
・被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
・被相続人の兄弟姉妹で被相続人の死亡以前に死亡した人がいる場合には、その亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
遺言があった場合
被相続人が遺言書を残しており、その遺言書で登記をする場合には、その遺言書が追加で必要となります。
また、その遺言書が法務局での保管制度を使っていない自筆証書遺言であった場合には、先に家庭裁判所での検認手続きを済ませておくことが必要です。
遺言書で登記をする場合には、遺産分割協議書など一部の書類が不要となります。
相続放棄をした人がいる場合
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合には、相続放棄申述受理証明書も必要です。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした家庭裁判所で交付してもらうことができます。取得費用は、1通150円です。
書類の原本を返してほしい場合
相続登記の必要書類は数が多く、集めることも一苦労です。また、相続登記に必要となる書類の多くは預貯金の相続手続きでも使用できるため、できれば原本は返してもらいたいところでしょう。
そこで、次の書類のどちらかを一緒に提出すれば、原本を返してもらうことが可能です。
1.書類のコピー:原本還付を受けたい書類をコピーの上、「原本還付」と赤色のボールペンなどで記載します。原本に相違ない旨の付記や署名捺印、契印などのルールがあります。
2.相続関係説明図:相続に関係する部分のみを抜き出した家系図のような書類です。手書きでも構いませんが、必要な事項を正しく記載する必要があります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
相続登記の必要書類は数が多いため、集めるために時間がかかってしまう場合も少なくありません。相続登記を急ぐ場合には、早めから取得に取り掛かることをおすすめします。
また、自分で書類を取り寄せたり作成したりすることが難しい場合には、司法書士への依頼も検討すると良いでしょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
相続登記とは?
相続登記の必要書類は?
相続登記の流れは?
相続登記の必要書類が追加される場合は?
自筆証書遺言は押印がなければ無効だと判断されてしまうので注意しましょう。ホゥ。