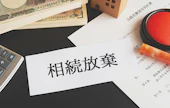相続手続きにおいて混乱しやすいのが相続放棄と代襲相続の関係です。このふたつは非常に複雑な仕組みになっていることから、どのような手続きを踏めばいいのか困る方もいるでしょう。しかし、きちんと理解して相続手続きを行わなければトラブルに発展する可能性もあります。
実は、相続放棄をしても代襲相続は発生しないのが通例です。今回は相続放棄と代襲相続について解説します。正しい相続をするために参考にしていただける内容でしょう。
<この記事の要点>
・相続放棄をした遺産が代襲相続されることはない
・相続放棄をした場合、相続権は「次順位の相続人」に変わる
・三代にわたる相続の場合、相続放棄は被相続人ごとに手続きが必要
こんな人におすすめ
代襲相続・相続放棄とは何かを知りたい方
相続放棄しても代襲相続にはならない理由を知りたい方
相続放棄における注意点を知りたい方
代襲相続とは
被相続人が死亡した段階で、本来相続すべき人がすでに死亡している場合、その下の代に当たる人が被相続人から直接相続することを代襲相続と言います。
例えば、被相続人の子供が被相続人より先に亡くなっていた場合は、孫が相続人になるといったケースが当てはまるでしょう。また、相続人として優先される配偶者が亡くなっていた場合は、子供が相続することになります。
相続放棄とは
相続放棄とは、裁判所で所定の手続きを通して、故人の遺産を一切相続しないことを表します。つまり、相続放棄を行うことで、相続人としてのすべての権利を手放すことができます。
例えば、相続する財産の中に借金やローンといった負債が多く、プラスの財産を負債が上回る場合には相続放棄を行うという事例が多いでしょう。相続放棄をする上での利点は、負の財産を負う必要がない点にあります。ただし、一度相続放棄をするとすべての財産を相続することができなくなるため注意が必要です。
プラスの財産が負債よりも多いというケースでは、限定承認という手段もあります。プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続するという方法です。
相続放棄しても代襲相続にはならない
相続放棄した後に心配になるのが、放棄した遺産が代襲相続されるのではないかという点でしょう。例えば、負の遺産が大きかった場合に自分の子供に代襲相続されてしまうと、大変なことになってしまいます。
実際のところ、正しい手続きを踏めば代襲相続を避けることができます。とはいえ、相続のケースはさまざまであり、内容によって流れも異なります。特に、相続放棄と代襲相続に関しては複雑な絡みがあるため、ケースごとの対処方法を把握しておきましょう。
一般的な相続放棄の例
例えば、祖父が多くの借金を残して亡くなった場合、その子である父親は相続放棄をすることができます。制度上、相続放棄をした父親は相続人から外れるため、おのずとその子供への相続も消滅し代襲相続も起こりません。
ただし、祖父の遺産を孫に相続させたいという考えを持っている際には、相続放棄をしてしまうと孫への権利も失うことになるため、注意が必要です。
相続権はどうなるのか
相続放棄をした場合に気になるのは、相続権が誰の元に移るのかという点です。相続するべき人物が相続放棄をした場合、相続権は「次順位の相続人」に変わります。
とはいえ、相続放棄によって次順位の相続人に権利が映る場合、役所が次順位の相続人に連絡してくれるわけではありません。そのため、本人が次順位の相続人にその旨を伝える必要があります。
この連絡を怠ると、遺産として残った借金の督促が、知らない間に次順位の相続人に届くこととなり、トラブルを招く可能性があるでしょう。トラブルを起こさないためにも、しっかりと話合いをおこなったうえで相続放棄するかどうかを決定することがポイントです。
相続人全員が相続放棄をした場合
「次順位の相続人」も次々と相続放棄していき、法定相続人が全員相続を放棄してしまった場合についても触れておきます。基本的に、被相続人のすべての財産を計算した上でプラスの財産となった場合、「特別縁故者」と呼ばれる人が現れない限りは国のものになるというルールがあります。
特別縁故者とは、相続において法定相続人がいない場合に、特別に相続の権利を受けた人のことをいいます。主に、被相続人と生計を同じにしていた場合や療養看護に努めた場合に特別縁故者として選ばれる可能性があります。
一方、残った財産がマイナスになった場合は、債務者が消滅したことになり借金自体も無くなるのが通例です。つまり、債権者が持つ権利も失われることになります。
相続欠格者となった場合
法律の定める重大な違法行為をした場合、相続欠格者となる可能性があります。例えば、推定相続人であった人物が被相続人を殺害すると相続権を失うでしょう。また、遺言書の偽造や書き換えも相続欠格者になる違法行為にあたります。しかし、相続欠格となった場合でも、代襲相続は起こるため、相続放棄とは流れが異なることを頭に入れておきましょう。
三代にわたる相続の決まり
代襲相続において混乱しやすいケースが、三代にわたる相続です。例えば、祖父より先に父親が亡くなり、そのあとに祖父が亡くなった場合は、どのような流れになるのかを考えていきましょう。こういったケースでも、相続放棄と代襲相続が大きく関わってきます。
片方の相続放棄も可能
三代にわたる相続の場合、孫は父と祖父の財産を両方とも放棄することは可能です。また、父親の財産は相続放棄をしたものの、祖父の遺産は相続するという選択も可能とされています。相続放棄は被相続人ごとに別物として判断されるというルールがあるためです。
先ほどの例に合わせて考えてみましょう。祖父より前に亡くなった父親の遺産を相続放棄していたとしても、祖父の遺産に関しては代襲相続人として判断されるため、祖父の遺産だけを相続することができるということです。
相続放棄をして亡くなった場合
例えば、祖父が亡くなり、相続人である父親も相次いで亡くなった場合を考えてみましょう。万が一、父親が祖父の財産を相続放棄しようとした矢先に亡くなった場合は要注意です。この流れで、子供が父親の相続放棄をしてしまうと祖父の財産も放棄したことになります。
その理由は、祖父の遺産を相続する権利は、父から引き継がれるというルールがあるためです。三代にわたる相続は非常に複雑で、場合によっては大きな損失を被る可能性があるため、十分に注意して対応することが大切です。
父の相続放棄後の祖父の借金
例えば、父親が祖父より先に亡くなり、多額の借金を残していたとしましょう。このケースだと、子供は相続放棄をすることが通例です。しかし、その後に祖父が亡くなり、こちらも借金を残していた場合はどうなるでしょうか。
この場合、孫にあたる人物は、祖父の借金を相続する流れになるため、改めて祖父の財産も相続放棄をする必要があります。どちらの相続放棄でも、亡くなってから3ヶ月以内に手続きをおこなわなければ相続放棄ができなくなるので、要注意です。
専門家に依頼するケース
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能です。しかし、代襲相続が関わってくると難しくなるケースも多いでしょう。難しい手続きをよく理解しないままに進めてしまうと、結果的にトラブルに発展することも少なくありません。その場合は、できるだけ専門家に依頼することをおすすめします。
特に、故人が多額の借金を残している場合は、相続人に債権者からの取り立てがおこなわれる可能性が否めません。専門家に手続きを依頼しておけば、取り立てを止めることもできます。相続を原因としてストレスを抱えるよりも、専門家に頼む方が安心できるでしょう。
相続放棄における注意点
特に問題のないケースでは、十分に個人で相続放棄を行うことができます。しかし、スムーズに手続きを行うためには、注意点もしっかり把握しておくことが大切です。注意点の中には、つい忘れがちなポイントもあるため、結果的に相続放棄が不可能にならないように、ひとつずつ確認しておきましょう。
相続放棄の期限
相続放棄は、いつでもできる手続きではありません。相続開始を知った段階から3か月以内に相続放棄することを決めなくてはなりません。万が一、3か月以内に相続放棄をしなかった場合は、たとえマイナスな財産であっても相続を承認することになります。
とはいえ、後になってマイナスの財産に気がつくこともあるでしょう。こうした場合は、家庭裁判所に申し立てることで、相続放棄ができる可能性があります。ただし、家庭裁判所が期間延長を認めた場合に限るため注意が必要です。
相続開始前の相続放棄はできない
相続が開始する前に、マイナスな遺産について把握していたとしても、相続放棄は相続が始まらなければ受け付けてもらえません。被相続人に対して相続をしない旨を伝えるケースはありますが、これは相続放棄には当てはまらないので注意が必要です。いくら口頭で伝えてあったとしても、相続開始後に正規の手続きをしなければなりません。
生命保険について
被相続人が生命保険に入っており、相続人に当たる人が受取人に指定されているケースもよくあります。この場合に支払われた保険金は、受取人に指定された人の固有財産となるのが通例です。そのため、相続財産には含まれません。このことから、たとえ相続放棄をしたとしても保険金に関しては受け取ることが可能です。ただし、保険金は課税対象となるので注意しましょう。
しかし、被相続人が保険金の受取人を自分にしている場合は話が変わってきます。保険金は被相続人の財産と認定されるため、相続の対象になるでしょう。この場合、相続放棄をすれば保険金についても失効することとなります。
積立保険の解約返戻金
被相続人が積立式の生命保険に入っていることもあります。この場合、亡くなった段階で保険契約が解約されることとなり、解約返戻金が発生するケースも考えられるでしょう。この場合、解約返戻金の性質上、契約当事者に支払われるというルールがあるため、相続財産となります。万が一、解約返戻金を相続人が私的に利用した場合は、相続放棄ができなくなるのが通例です。
被相続人が積立保険に入っている場合は、解約返戻金の扱いについて注意する必要があります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
相続におけるさまざまなルールは非常にややこしく、相続人としては頭を悩ませるものです。ましてや借金があったり他の相続人との関係が複雑であったりするとさらに難しくなるでしょう。
相続放棄や代襲相続には、相続にまつわる多くの問題が関係します。相続の手続きはひとつずつ紐解きながら丁寧におこなわなければ、後になって面倒なことにもなりかねません。わからないときは専門家の力を頼りながら、正しく手続きをおこなうことをおすすめします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
代襲相続とは?
相続放棄とは?
相続放棄をすると、その遺産は代襲相続される?
相続放棄をする際の注意点は?
訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。