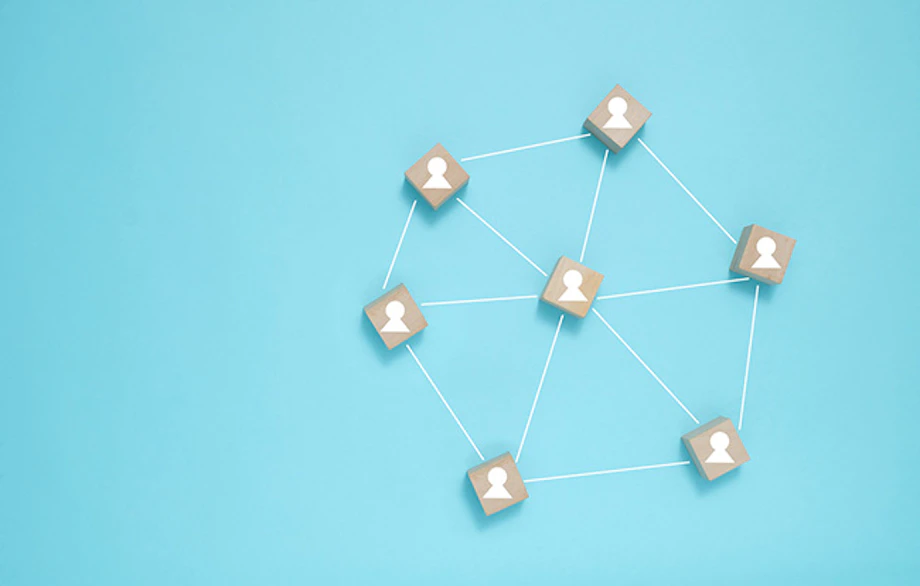親族が亡くなった場合に必要になるのが遺産の相続です。しかし、故人に多額の遺産がある場合などは、相続で揉めることもあります。いざ相続する立場になったときに備えて「遺産相続の具体的なルールを知りたい」という方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、基本的な遺産相続の順位やイレギュラーな場合のルールなどをご紹介します。遺産相続は民法に従って行われるため、関連する条文を理解することも大切です。今回ご紹介するルールを把握しておけば、遺産相続をするときに役立つでしょう。
<この記事の要点>
・基本的な遺産相続の順位は、配偶者と被相続人の子どもが第一順位の相続人となる
・子どもが生存している場合は代襲相続ができないため、孫の相続分はない
・遺言がある場合、法律に適合して有効なものであれば相続順位に影響する
こんな人におすすめ
基本的な遺産相続の順位について知りたい方
法定相続人がいない場合について知りたい方
相続順位に関する注意点について知りたい方
基本的な遺産相続の順位
実際に遺産相続が発生した場合に重要なのが相続順位です。遺産相続が発生した場合は、民法890条の規定により、どのようなケースでも配偶者は相続人になります。その他の親族については民法887条から889条が適用されるため、ここで詳しく確認しておきましょう。
【第一順位】被相続人の子ども
被相続人の子どもは民法887条第1項によって第一順位の相続人とされており、配偶者と共に遺産を相続します。子どもが実子か養子かは問われません。同様に嫡出子かどうか、同一の戸籍に入っているかどうかも関係なく遺産を相続できます。
したがって、離婚後に疎遠になっている場合や養子に出ている場合などでも遺産を相続できることを覚えておきましょう。相続分は配偶者が50%、子どもが50%になります。配偶者と子が2人いる場合は、配偶者が50%、子どもが1人あたり25%です。
被相続人に子どもが存在している場合は血族相続人として法定相続人となり、民法891条の欠格事由に該当しない限り全員が遺産を相続するのが基本です。相続が発生した時点で子が死亡している場合は、代襲相続人として孫やひ孫などの直系卑属が相続人になります。
【第二順位】被相続人の直系尊属
第一順位の相続人である子どもが存在していない場合は、民法889条第1項1によって第二順位の相続人として被相続人の直系尊属が相続する決まりです。この場合の相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
直系尊属の場合も実親、養親の別は問われません。ただし、過去の判例によると、直系尊属に姻族は含まれないので注意しましょう。
直系尊属が遺産を相続することになった場合、親等が近い方が優先されるというルールがあります。したがって、まずは1親等になる父母が相続人です。
父母がすでに死亡している場合は、代襲相続人として祖父母が相続します。法定相続人となる同親等の直系尊属が複数人存在している場合は、共同相続人として均等割で相続するのがルールです。
【第三順位】被相続人の兄弟姉妹
第一順位、第二順位の相続人が存在していない場合は、第三順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続するでしょう。第三順位の相続人に関しては民法899条第1項2で定められています。この場合の相続分は配偶者が75%で兄弟姉妹が25%です。
相続発生時に兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、代襲相続人として傍系卑属が相続人になります。傍系卑属が代襲相続する場合は甥または姪までとなり、それ以降の再代襲はできません。
遺言などで特別な指定がない限り、第一順位から第三順位までの相続人の中から優先度が高い人が遺産を相続します。家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、次の順位の相続人に相続権が移ることも覚えておきましょう。
【ケース別】遺産相続の順位
具体的な遺産相続のケースについても見ていきましょう。故人が遺言で相続人を指定していない場合は、法律で定められたルールに従って、それぞれの相続人が遺産を相続します。
相続は複雑なケースも多いので、いざというときに迷わないようにきちんと理解しておきましょう。複数の法定相続人がいる場合や相続人が行方不明の場合、相続欠格がある場合についても解説します。
妻と子どもの他に孫がいるケース
夫が死亡して妻と子どもが遺され、さらに孫がいるケースを見ていきましょう。この場合、妻は配偶者相続人として遺産の50%を相続します。被相続人の子どもは第1順位の相続人となるため、残りの50%が相続分です。
子どもが生存している場合は代襲相続ができないため、孫の相続分はありません。このケースで遺産を相続できるのは妻と子どもだけです。子どもが複数存在している場合は、子どもの相続分である50%を人数で均等割しましょう。
子どもが相続を放棄しているケース
子どもが相続放棄の手続きをした場合、相続放棄した子どもは存在しないものとして、他の相続人が相続します。妻と子ども2人がいて、そのうち子ども1人が相続放棄した場合の相続分は以下の通りです。
・妻(配偶者相続人): 50%
・子ども(法定相続人): 50%
相続放棄した子どもは存在しないものとするため、子どもは1人という扱いになります。したがって、子どもの相続分である50%を1人で相続することになるでしょう。子どもが1人しかいない場合でその子どもが相続放棄したら、第二順位の相続人である直系尊属に相続権が発生します。
内縁の妻と子どもがいるケース
内縁の妻とは、正式に結婚していない妻のことです。その妻との間に子どもができているケースがあります。この場合、結婚していないため妻は配偶者ではありません。配偶者ではないために配偶者相続人にならず、遺産を相続することは不可能です。
子どもは非嫡出子になりますが、法定相続人として相続権があります。したがって、遺産の全てを子どもが相続するのがルールです。子どもが複数人いる場合は人数で均等割して相続分が決まります。
相続人が行方不明者のケース
相続人が行方不明になっている場合でも相続権は発生します。行方不明になっている場合は適切な手続きをしなければ相続人から除外できないことを覚えておきましょう。相続順位も通常通りです。
行方不明の相続人を除外するためには、家庭裁判所で失踪宣告の手続きをしなければなりません。失踪宣告ができない場合は、家庭裁判所に不在者財産管財人を選定してもらって相続手続きを進めましょう。
相続欠格・相続人廃除の対象者がいるケース
法定相続人の中に相続欠格(民法891条)や相続人廃除(民法892条)の対象者がいる場合、対象者は法定相続人としては扱われません。この場合、相続欠格対象者は遺産を相続できませんが、その人に子どもがいる場合は代襲相続の条件を満たせば遺産を相続できます。
相続欠格対象者は存在しないものとして相続手続きが進められるため、他の相続人の相続分が増えることになるでしょう。
法定相続人がいない場合はどうなる?
法定相続人が非相続者より先に全員死亡している場合など、法定相続人が1人も存在しない場合があります。この場合は以下の手順で手続きがされますので覚えておきましょう。
1.家庭裁判所が相続財産の管理人を選任する(民法951条、952条)
2.相続財産の管理人を選定したことの公告を行う(民法952条)
3.2か月以内に相続人が現れなかったときは、清算手続きを始める(民法957条)
4.家庭裁判所が相続人を捜索するための公告を行う(民法958条)
5.相続人が現れなかった場合、遺産は国庫に帰属する(民法959条)
相続人がいない遺産は国のものということを覚えておきましょう。
遺言がある場合の相続順位への影響は?
被相続人が遺言を残している場合、その遺言が法律に適合して有効なものであれば相続順位に影響します。有効な遺言とは民法960条以降で定められている条件を満たしているものです。民法902条第1項では、被相続人が相続分を決められることを定めています。
法律にしたがって遺言を準備しておけば配分を変更できるため、特定の相続人に特定の遺産を相続させたい場合などに活用しましょう。遺産を相続させたくない法定相続人がいる場合も、遺言に明記しておけば除外することも可能です。
相続順位が異なる子・孫・兄弟がいる場合、法定相続では子しか相続できませんが、遺言で指定すれば全員に相続させることもできるでしょう。ただし、相続人は不服申立てをする権利を有するため、極端な配分を指定すると認められない可能性があります。
覚えておきたい!相続順位に関するポイント
相続順位に関して注意しておきたいポイントを見ていきましょう。相続には分かりにくいワードが多数登場するので、きちんと理解しておくことが大切です。ここでは法定相続人の確認方法や遺留分についてご紹介します。いずれも重要なポイントなので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
相続人と法定相続人は異なる
遺産を相続する権利がある人を示す用語には、相続人・法定相続人・推定相続人があります。それぞれが示す意味は以下の通りです。
・相続人:実際に遺産を相続する人。相続放棄をした人などは除かれる
・法定相続人:民法によって定められている遺産を相続する権利を有する人(配偶者相続人、第一順位~第三順位までの相続権を有する人)
・推定相続人:最優先順位の相続権を有する人
「相続人」とつく用語には上記のように細かな違いがあるため、迷わないためにも事前にチェックしておきましょう。推定相続人とは相続開始前にのみ使われる用語で、相続が開始すると法定相続人になります。
法定相続人の範囲は戸籍謄本で確認できる
場合によっては法定相続人の構成が複雑になったり、誰が法定相続人なのかがわからなくなったりすることがあるものです。そのようなときは、「被相続人の戸籍全部事項証明書および除籍全部事項証明書」を取得してチェックすると調べられます。
戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書は、最新のものだけでなく出生から死亡まで全てのものを取得しなければなりません。被相続人が分籍や転籍を行っている場合は、最新の戸籍全部事項証明書とこれまでに本籍を置いていた区市町村から除籍全部事項証明書を取得しましょう。
これらの証明書は本籍地の区市町村に請求する必要があり、時間がかかるので早めに準備することをおすすめします。全ての戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書がそろったら家族関係を調べ、誰が法定相続人になるのかを確認しましょう。子が多い場合などは手続きに手間がかかるかもしれません。
遺言があっても遺留分は受け取れる
遺言があれば民法の規定によらず相続分を指定できますが、民法1028条に規定されている遺留分は相続できます。
遺留分とは、民法によって保証されている相続できる財産の割合で、相続人の生活を保障したり、被相続人の利益と相続人の利益のバランスを取ったりするために定められたものです。2020年時点で遺留分に関する規定は以下の通りになっているため、あらかじめチェックしておきましょう。
・相続人が直系尊属のみの場合:遺産の3分の1
・上記に該当しない場合:遺産の2分の1
被相続人の配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属には遺留分侵害額請求権が認められています。遺言の内容が遺留分に関する民法の規定に従っていない場合は、忘れずに家庭裁判所に遺留分侵害額請求を行いましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
相続順位や相続分は民法によって定められています。配偶者はどのような場合でも相続人になることや、相続順位によって割合が異なっているのが特徴です。相続には複雑な決まりも存在しているため、いざ相続が発生してから慌てずに済むよう、事前に自分の相続順位や割合を確認しておくことをおすすめします。
代襲相続や相続放棄などが絡み合うとさらに複雑になるため、細かいルールを押さえておくことが大切です。遺言によってイレギュラーな相続が発生することもあるので、遺留分などのルールも理解しておくとよいでしょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
基本的な遺産相続の順位は?
遺言がある場合の相続順位への影響は?
法定相続人がいない場合はどうなる?
相続人と法定相続人の違いは?
直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。