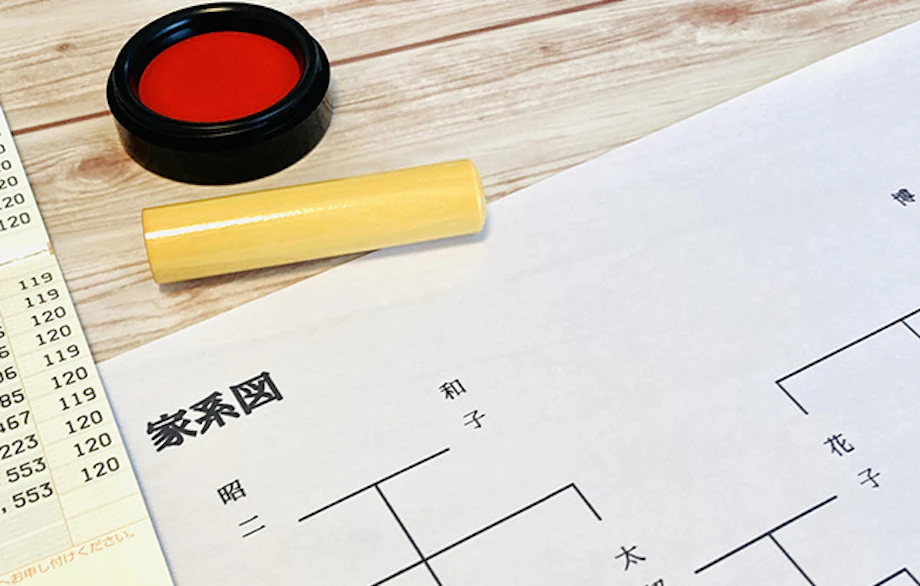口座の名義人が死亡すると、口座は凍結され、現金の引き出しや振り込みができなくなります。そのため凍結解除の必要がありますが、必要書類や手順が複雑です。
そこでこの記事では、口座凍結の解除方法について解説します。ケース別の必要書類や手続きのステップについても紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・相続税の支払いや遺産分割を適切に行うために、口座の名義人が死亡した場合、口座は凍結される
・銀行に凍結解除を依頼し、必要な書類を準備して提出すると口座の凍結は解除される
・生前に被相続人が利用している銀行を把握し、通帳や印鑑の保管場所を共有しておく
こんな人におすすめ
死亡後の銀行口座の取り扱いについて知りたい方
口座凍結の解除方法について調べている方
生前にしておくべき準備について知りたい方
名義人が死亡すると口座凍結される
金融機関は、名義人の死亡を知った時点で口座を凍結します。しかし、口座が凍結されるとどうなるのか、詳しく知らない方も多いでしょう。ここでは、名義人が亡くなった後の口座について解説します。
口座凍結とは?
口座凍結とは、銀行口座が完全に使えなくなることです。口座が凍結されると、遺族であってもお金を下ろせなくなります。また金融機関の窓口やキャッシュカードが使用できなくなるだけでなく、公共料金の引き落としもできません。
凍結されるタイミングは?
一般的に凍結されるのは、金融機関が名義人の死亡を確認した後です。基本的には、相続人の誰かが金融機関に申し出をして凍結されます。それ以外にも、新聞の訃報欄やほかの取引先からの情報で知るケースもあります。
なぜ口座凍結されるの?
口座が凍結されるのは、相続税の支払いや遺産分割を適切に行うためです。故人の銀行口座に残った預貯金は相続財産にあたります。相続財産を自由に引き出せてしまうと、相続人が自由にお金を引き出せてしまい、持ち逃げされる可能性も考えられるでしょう。
また相続財産は相続税の課税対象であるため、遺族が相続財産を引き出すと正確な課税額を計算できなくなるというのも理由のひとつです。
口座凍結を解除する3つのステップ
凍結された口座を再び使えるようにするためには、凍結の解除が必要です。ここからは、解除を行うための方法を3ステップで紹介します。
ステップ①:銀行に凍結解除を依頼する
まずは金融機関に凍結解除したいと連絡します。故人が複数口座を持っている場合は、すべての金融機関に連絡するのを忘れないようにしましょう。
なお、凍結解除を依頼できるのは「遺産の相続人」「遺言書執行者」「相続財産管理人」「相続人から依頼を受けた人」のいずれかです。
ステップ②:凍結解除に必要な書類を準備する
金融機関に凍結解除をしたい旨を伝えると、必要な書類を指示されます。金融機関や相続の状況によって必要な手続き書類が変わるため、書類は金融機関から指示されてから集めるほうがよいでしょう。具体的な必要書類は次章で紹介します。
ステップ③:銀行に書類を提出する
凍結解除に必要な書類を金融機関へ提出します。必要書類は状況によって変わる点に注意が必要です。
遺言書はあるものの遺言執行者がいないケース、遺言書がなく遺産分割協議書があるケース、遺言書・遺産分割協議書がない共同相続のケースなどさまざまな状況が考えられます。金融機関にきちんと相談してみましょう。
専門家に依頼する方法もある
弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼して凍結解除してもらうことも可能です。仕事や家の事情で金融機関にすぐに行けない方もいるでしょう。また慣れていない方が必要書類を準備するのは大変ですし、分からないことも多いものです。
専門家に依頼すれば、必要書類の作成や申請も代理・サポートしてくれるため、手続きがスムーズに進みます。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
【ケース別】口座凍結解除に必要な書類
前述したとおり、口座凍結解除に必要な書類はケースごとに異なります。ここでは、ケースごとに口座凍結解除に必要な書類を紹介します。
ケース①遺言書があり遺言執行者がいる場合
遺言書があり、遺言執行者がいる場合は以下の書類が必要です。
| 遺言書 | 資産や遺産分割について書かれた遺言書の原本 |
| 家庭裁判所の検認済証明書 | 遺言書を家庭裁判所が確認したことを証明する書類 |
| 戸籍謄本 | 口座名義人の戸籍謄本と法定相続人を確認できるもの |
| 印鑑証明書 | 銀行の資産を受け取る人の証明書 |
| 通帳 | 証書やキャッシュカード、貸金庫の鍵も含める |
ケース②遺言書はあるが遺言執行者がいない場合
遺言書はあるものの、遺言執行者がいない場合は以下の書類が必要です。
| 遺言書 | 資産や遺産分割について書かれた遺言書の原本 |
| 家庭裁判所の検認済証明書 | 遺言書を家庭裁判所が確認したことを証明する書類 |
| 戸籍謄本 | 口座名義人の戸籍謄本と法定相続人を確認できるもの |
| 印鑑証明書 | 遺言執行者と銀行の資産を受け取る人の証明書 |
| 通帳 | 証書やキャッシュカード、貸金庫の鍵も含める |
ケース③遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合は以下の書類が必要です。
| 遺産分割協議書 | 銀行の資産を誰が受け取るか記載された書類の原本 |
| 戸籍謄本 | 口座名義人の戸籍謄本と法定相続人を確認できるもの |
| 印鑑証明書 | 法定相続人全員の印鑑証明書 |
| 通帳 | 証書やキャッシュカード、貸金庫の鍵も含める |
ケース④遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の場合
遺言書・遺産分割協議書がなく、共同相続の場合は以下の書類が必要です。
| 戸籍謄本 | 口座名義人の戸籍謄本と法定相続人を確認できるもの |
| 印鑑証明書 | 法定相続人全員の印鑑証明書 |
| 通帳 | 証書やキャッシュカード、貸金庫の鍵も含める |
各銀行の必要書類について
以下がメガバンクごとの必要書類のリンクです。
・三菱東京UFJ銀行
・三井住友銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・ゆうちょ銀行
ネットバンクの場合も必要書類はさほど変わりません。しかし、細かい書類や手続きは異なる場合があります。
また、ネットバンクは店舗型と比べて何度かやり取りが生じることがあり、凍結解除まで時間がかかる恐れもあります。窓口がカスタマーサポートになるため、電話で聞いてみましょう。
生前にしておくべき準備
生前に以下3つの準備をしておくとよいでしょう。
- 被相続人が利用している銀行の把握
- 通帳や印鑑の保管場所を把握
- 被相続人と密にコミュニケーションを取る
銀行口座や通帳の保管場所は、家族であっても教えるのに抵抗がある方もいます。被相続人としっかり話し合い、亡くなった後の対応をどのように進めるのか確認しておくとよいでしょう。
<関連記事>
生前整理とは?今すぐできる生前整理のやり方・進め方
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
被相続人が利用していた口座は亡くなると凍結され、現金の引き出しや振り込みができなくなります。そのため、早めに凍結解除の手続きをしましょう。
「小さなお葬式」では葬儀に関するマナーや役立つ知識を発信しています。また24時間365日専門のスタッフがお客様の疑問にお答えしますので、気になることがあればぜひお気軽にお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
すぐに現金が必要な場合はどうしたらよい?
凍結解除・指定口座への振り込みにはどのくらい時間がかかるの?
凍結解除に期限はあるの?
口座凍結の解除を行わないほうがよい場合はある?

亡くなった方や仏に向けて、香を焚いて拝む行為を焼香(しょうこう)といいます。ホゥ。