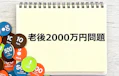「老後2,000万円問題」という言葉が話題になったのを覚えている方もいることでしょう。終身雇用制度の崩壊が危ぶまれている昨今、今までのように就職して働いてさえいれば退職金や公的年金の受け取りが確約されていて、老後の心配はなかったという時代は過去のものになったといえるかもしれません。
老後の資金がないことで不安を抱えている方が多いという現状もあり、早急な解決が求められます。本記事では、老後の資金がないと考えている方のために、個人が知っておくべきことや対策を紹介します。今は老後の資金がないという方も、本記事が老後のための行動のきっかけになれば幸いです。
<この記事の要点>
・定年後も働くことで老後資金を増やすことができる
・年金を繰り下げ受給することで受け取る年金の増額が期待できる
・老後の資金がないときは生活保護を受ける選択肢もある
こんな人におすすめ
老後資金の準備方法について知りたい方
終活をはじめた方
将来のライフプランについて不安を感じている方
老後に必要な資金は?
老後という言葉は人によって定義が違ってくるものですが、一般的には「経済的に公的年金や預貯金などを生活資金として使い始める時期」を指していうことが多いようです。つまり、定年を迎えて収入がなくなる60歳もしくは65歳以降を指し、期間としては寿命を迎えるまでのおよそ20~30年ほどとなるでしょう。
いわゆる「老後」にあたる期間は思いのほか長く、公的年金だけでは足りなくなってしまう可能性が高いといえます。老後の資金がない、もしくは足りないといったことがあるのは、そういった理由からです。
ゆとりある老後のために必要な資金とは?
生命保険文化センターの調査では生活に必要な費用と別に、ゆとりを持った老後生活を送るためには旅行やレジャー、趣味や教養などをはじめとした以下の用途にお金を使うと回答した方が約半数、またはそれ以上にのぼっています。
これらの目的をかなえるために必要な金額は、平均で月額14万8,000円です。この結果から、ゆとりを持った老後を送りたいならば、老後の最低日常生活費とあわせて月37万9,000円は必要ということになります。
(参考:『2022(令和4)年度 生活保障に関する調査』生命保険文化センター)
公的年金はいくらもらえるのか
公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。厚生年金は2階建ての建物に例えられます。1階部分は国民年金で、日本に住んでいる20歳以上から60歳未満の人は基本的に全員が加入するものになります。2階部分は厚生年金で、会社員や公務員が加入しており、国民年金に上乗せする形になっています。
こうした構造から2階建てに例えられる公的年金ですが、受け取りはいつから始まり、月々いくら支給されるのでしょうか。確認していきましょう。
いつから受け取れるのか?
年金は65歳から受け取ることができます。また、年金制度では繰り上げたり繰り下げたりすることで受け取る期間の調整を行うことができます。これを利用すれば、自分の希望したタイミングで公的年金の受け取りを開始できるようになります。
ただし、受け取り期間を調整できるのは前後5年までとなります。受け取り時期を調整することで受け取れる金額も変わりますので、あらかじめ金額がどのタイミングで切り替わるのか確認して検討を行いましょう。
公的年金の平均受給額
日本年金機構の令和6年4月分からの年金額によると、国民年金と厚生年金を受け取る場合、合計金額が298,483円(老齢基礎年金68,000円、老齢厚生年金230,483円)です。
あくまで上記の厚生年金の298,483円は、40年間就業した場合に受け取れる年金の給付水準となるので、この限りではありません。しかし、妻が働くことで老後の受給額にも大きな差が出ることは確かです。
(参考:『令和6年4月分からの年金額等について』日本年金機構)※2024年11月時点
老後の資金がないときの対象法
それでは老後の資金がないときはどうすればよいのでしょうか。おすすめの方法がいくつかありますので、こちらで紹介していきます。将来的に生活が困窮した場合は制度を頼ることも可能ですが、まずは「支出を減らす」「収入を増やす」「資産を運用する」といった方法で貯金することから始めましょう。
定年後も働く
2024年現在、65歳までは希望すれば企業で働くことができるようになっています。さらに、働く意欲がある高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法の改正で70歳まで働ける企業も増えてきています。
さらに、昨今の日本では深刻な少子高齢化が進んでおり、労働人口の減少が問題となっています。労働者が不足している傾向にありますので、高齢者でも比較的仕事を見つけやすくなっているようです。
年金の繰り下げ受給
通常であれば年金を受け取るのは65歳からとなっていますが、年金を繰り下げ受給するという選択肢もあります。この制度を利用するメリットは、年金の需給開始を1ヵ月遅らせるたびに、受け取れる年金が0.7%増額するという部分にあります。
繰り下げができるのは最大で5年間で、その場合最大42%増額することができるため、結果的に受け取る年金を増やすことができます。最近では70歳を過ぎても元気という人も増えてきていますので、長く働いて年金を受け取るタイミングを遅らせられるよう、今から健康に気を遣って生活してみるのもよいかもしれません。
また、先ほど紹介した「定年後も働く」ことと組み合わせることで、収入も年金も増えることがわかるでしょう。この2つの方法を利用するだけでも老後の資金がない問題が解消できるかもしれないため、有効な手段として覚えておくのをおすすめします。
支出を抑える
老後に限らず普段から気を付けたいことになりますが、無駄な支出がないかどうかを一度確認してみましょう。普段から些細な支出を抑えることで、老後の資金に回すことができるほか、老後の資金のための運用に回すことができるなど選択肢を広げることにもつながります。
具体的に、まずは保険料を見直してみましょう。保険はプランや商品が毎年変わっていきます。契約した当時はよいプランだったとしても、今は違うかもしれません。家族構成や自身の状況によっては大幅に変わることもありますので、一度相談してみるとよいでしょう。
次に挙げられるのは通信費です。最近では大手キャリアのほかに、格安SIMを売りにしているところもありますので、一度確認してみるのもよいでしょう。実際に、年間で数万円通信費を抑えることができた人もいます。機種にこだわりのない方や、あまり電話やメッセージアプリ、その他の通信機能を利用していないという方は、ぜひ検討してみるとよいでしょう。
資産運用を行う
老後に向けて資産運用をする場合、手堅く運用することをおすすめします。投資は「長期」「積み立て」「分散」が基本となってきます。資産運用は長い時間をかけて運用することで、リスクを減らしてコツコツ資産を増やしていけるのです。
そのため、「老後の資産がない」とわかってからでは難しい場合もありますが、まだ老後に向けて資産運用を考えているという段階であれば始めどきといえます。時間をかけて取り組むことができますので、若い方がこれから資産を増やす方法としてはおすすめです。
資産運用は金融機関にお金を預ける形で行うことが多いため、貯金と勘違いをしてしまう方もいるかもしれませんが、全く違うものですので注意が必要です。特に、老後資金を準備しようと考えているのであれば、個人向け国債やつみたてNISAなどで手堅く投資していくのがよいでしょう。これらは投資の中では大きく稼ぎにくいといわれるものですが、大きく損失を出すことないのはメリットといえます。老後の資金形成には向いている方法ですので、自分に合っている投資方法を調べてみるとよいでしょう。
老後破産になる理由は?
老後破産とは、定年退職後の年金生活が破綻状態に陥って、生活が困窮してしまう状況のことをいいます。高齢化社会の現代においては、高齢者の老後破産は社会問題の1つに挙げられています。老後破産の特徴としては、老後の資金がないわけではなく、十分に蓄えがあったり退職金を十分に受け取ったりしていたにもかかわらず、破綻に陥ってしまっているというものが挙げられます。
老後の生活を安心して過ごすために、老後破産を他人事と受け取らず、原因を理解して対策をしていく必要があるでしょう。ここでは老後破産に陥る理由を解説します。
昔と同じ感覚で生活をしてしまう
しっかりと老後の資金を蓄えていたとしても、40~50代の支出のピーク時のような生活を継続していると、当然資金は底をついてしまいます。老後の生活は、いくら年金があるとはいえ、基本的には資金を切り崩しながら生活をしていくことになります。
自身が蓄えた老後の資金と年金の支給額のバランスを考えて、計画的に生活をしていく必要があるでしょう。
住宅ローンの支払いが続いている
最近では、60歳を過ぎても住宅ローンの支払いが残ってしまっている家庭は珍しくありません。また、給与が思うように増えない世の中で、住宅ローンを支払いながら老後の資金を貯めることができないという影響もあるようです。
ほかにも、ローンを完済していても住宅には修繕費やメンテナンス費が発生します。こういった住宅にかかわる費用が理由で、思うように資産を準備することができないということがあると考えられます。
子供の教育費が長引いている
晩婚が増えている昨今では、子供の教育費を負担することで手一杯となり、老後の資産形成ができず老後破産につながることがあります。定年後であっても大学の費用が必要な家庭も少なくなく、学費のために貯金や退職金を切り崩してしまうことも原因の1つといえるでしょう。
老後の資金がないときに利用できる制度
基本的には自力で何とかすることをおすすめしますが、どうしても生活が成り立たない場合には国の制度を利用するのもよいでしょう。ただし、子供をはじめ親族にもしっかりと相談をしてから話を進めることをおすすめします。
子供の扶養に入る
年金の収入が一定よりも少ない場合は、子供の扶養に入れてもらうのもよいでしょう。そうすることで健康保険料の負担が全額免除となったり、子供にも扶養控除が適用されたりといったメリットがあります。これは子供にもデメリットがありませんので、条件が揃っているのなら検討してみるとよいでしょう。
生活保護を受ける
生活保護は、日本国内で生活する全ての人が持っている「生存権」を守るために、国が最低限度の生活を保障し、不足する資金を支給してくれるというものです。しかし、この制度を利用すると生活に制限が生じてしまいますので、どのような対策もできない場合の最終手段といえます。
生活保護の申請が許可されるためには、原則として自身の預貯金や資産などを全て手放す必要があるほか、車の所有も仕事で使用することが証明できない限り認められなくなってしまいます。また、生活保護を受けることは親族にも通知がいくようになっています。ほかにも制限がありますので、どうしても利用しなければならない場合は子供や兄弟などの身内にしっかりと相談し、方法がない場合に限り利用することを決めましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
今回は、老後の資金がないと感じる方に向けて、制度や対処方法、可能であれば避けたい老後破産についても紹介しました。紹介した通り、定年前はある程度の水準で生活した家庭でも、老後の資金がない状態になってしまう可能性は十分にあることがわかっていただけたでしょう。
老後の資金がないのは生活にも影響を及ぼしますので、どうしたらいいかわからないという人は、可能な限り貯金を行い、早めにお金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談をして今後の対策をしていくとよいでしょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


湯灌は故人の体を洗って清める儀式のことです。ホゥ。