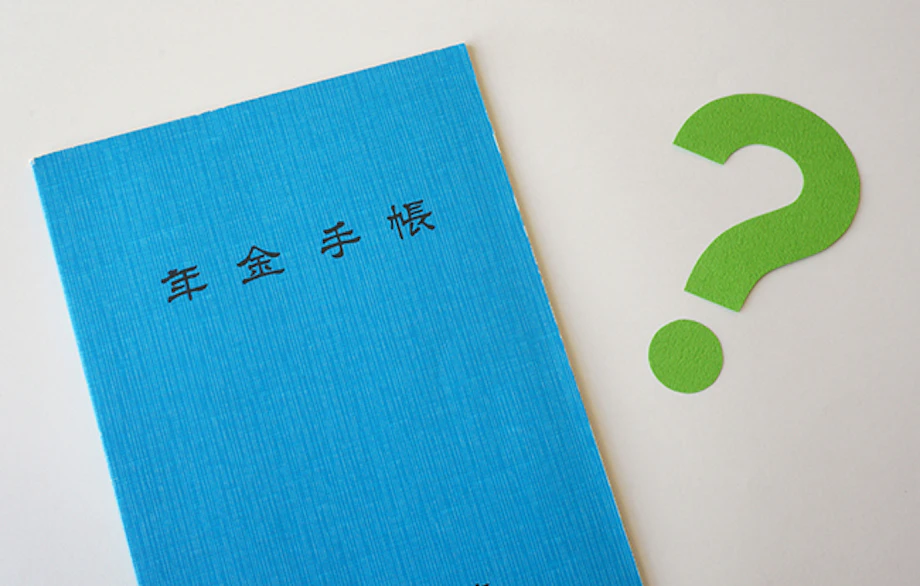「年金を払わないといけない?」「できれば納付したくない」と考える方がいるかもしれません。この記事では実際年金を払わないと将来受給できないのか、罰則を受けるのかといった疑問に答えます。
また収入や家庭内の事情により「どうしても年金の納付ができない」という方もいるでしょう。年金の免除・納付猶予制度についても解説しているので、あわせて読んでみてください。
<この記事の要点>
・年金の未払いは法律違反で、保険料の支払いが10年未満の場合は将来年金が受け取れない
・年間所得300万円以上で未納期間7か月以上続くと、財産の差し押さえを受けることがある
・経済的に困難な場合は、所得に応じて年金保険料の全額または一部免除される
こんな人におすすめ
年金を納付したくないと考えている人
どうしても年金の納付ができずに困っている人
年金の受給額が気になる人
年金を払わないとどうなる?違法?
年金の納付に対して「本当に払わないといけない?」「未払いだと将来どうなるのだろう……」といった、疑問を抱く方がいるかもしれません。ここでは年金の支払い義務について明らかにしつつ、未払いのリスクについて解説します。
年金を払うのは義務
日本国民は、国民年金への加入が義務付けられています。国民年金法第88条では、「被保険者は保険料を納付しなければならない」と定められており、年金の未払いは法律違反にあたるでしょう。
また会社員・公務員は、厚生年金に加入する必要があります。国民年金分の保険料も含まれており、給与から天引きされる仕組みです。
将来受け取れない可能性あり
将来年金を受け取るには、受給要件を満たしていなければなりません。受給要件のひとつには、10年以上の保険料の納付期間が必要です。もし数年間年金を納めた期間があっても、10年未満の場合は将来受け取れないと覚えておきましょう。
ただし経済的な理由により保険料を納付できない方、免除・猶予制度を利用した方は例外です。
参考:『日本年金機構』
差し押さえのリスクについて
年金の支払いを避けていると、最悪の場合は財産の差し押さえを受けることがあります。差し押さえの条件は、年間所得300万円以上で未納期間7か月以上のケースです。
ただし、すぐに差し押さえになるわけではありません。納付の催促から差し押さえまでの流れは、以下のとおりです。
1.電話や書面で納付の催促あり
2.特別催促状が届く
3.最終催促状が届く
4.催促状が届く(無視すると延滞金発生)
5.差押予告通知書が届く
6.財産の差し押さえ(強制徴収)を受ける
年金を払わなくていい方法|免除・猶予申請について
経済的な理由や家庭の諸事情により、年金を納められないケースもあるでしょう。ここでは、要件を満たす方を対象とした年金の免除・納付猶予制度の概要を紹介します。
年金の免除・納付猶予制度とは
収入が不安定な方や学生、諸事情により納付できない方は、年金の免除制度・納付猶予制度を利用できます。保険料納付猶予制度、学生納付特例制度、失業等による特例免除といった種類がいくつかあります。
それぞれ要件を満たすと、保険料の支払い免除もしくは、納付猶予期間が設けられる制度です。免除・納付猶予制度を利用する場合、申請書を提出し受理されると適用されます。
免除される保険料の範囲
年金の免除・納付猶予制度では、所得に応じて保険料の範囲が定められています。
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) (※)令和2年度以前は22万円 |
| 4分の3免除 | 88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は78万円 |
| 半額免除 | 128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は118万円 |
| 4分の1免除 | 168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は158万円 |
| 納付猶予制度 | 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) (※)令和2年度以前は22万円 |
引用:『日本年金機構』
年金を払わなくていい人|免除・猶予制度の一覧
年金の免除・納付猶予制度への申請を検討している方は、自身が対象になるのか気になるでしょう。「収入面で納付が難しい」「家庭の事情で支払う余裕がない」といった方は、どのような免除・納付猶予制度があるのか確認してみてください。
保険料納付猶予制度
保険料の納付猶予制度は、納付期限を延長できます。つまり「今は難しいが後々年金を納めたい」と考えている方が対象です。
【要件】
・20~50歳未満
・本人と配偶者の前年所得が一定額以下
納付猶予を受けられる所得の目安は、「(扶養親族の数+1)×35万円+32万円(※)」で計算します(※令和2年度以前まで22万円)。妻と一人の子を扶養している方は、「3×35万円+32万円=137万円」です。
納付猶予期間は「受給した期間」としてカウントされますが、年金額には加えられないため注意しましょう。
学生納付特例制度
一般的に十分な収入のない学生は、学生納付特例制度を利用するケースが多いでしょう。
【要件】
・学生(大学(大学院)/短期大学/高等学校/高等専門学校/特別支援学校/専修学校/一部の海外大学の日本分校/夜間・定時制課程や通信課程を受講している方)
・本人の所得が一定以下
[※128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等(2020年度の場合)]
(※)令和2年度以前は118万円
参考:『日本年金機構』
失業等による特例免除
失業により年金の支払いが難しい場合、保険料の免除や猶予を受けられます。免除・納付猶予の申請をする方は、申請書を提出しなければなりません。申請する際に、「雇用保険受給資格者証」や「個人事業の開廃業等届出書」といった必要書類を用意します。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
【要件】
・雇用保険の被保険者
・事業の廃止(廃業)または休止の届出をした方
参考:『日本年金機構』
産前産後期間の免除制度
産前産後期間は、所得の高さに関わらず受けられる保険料の免除期間が設けられています。
【要件】
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
※出産=妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産された方を含む)
・多胎妊娠の方は出産予定日または出産日が属する月の3~6か月間の納付免除を受けられる
ただし免除期間に、付加保険料(定額保険料に上乗せする)として年金を納めることも可能です。
参考:『日本年金機構』
配偶者からの暴力による特例免除制度
配偶者からの暴力(DV)により別居している場合は、配偶者の所得に関わらず保険料の全額もしくは一部が免除になります。ただし住居をともにしている父母等の第三者は、所得審査を受けるケースもあるため注意しましょう。
【要件】
・本人の前年所得が一定以下である
・配偶者の暴力が要因で別居している
参考:『日本年金機構』
新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除
新型コロナウイルス感染により、保険料の納付が難しい方は「臨時特例免除申請」を提出します。ほかの免除制度と同様に、免除期間中は「年金の支払いをした期間」としてカウントし、「追納」すると年金額を増やせる仕組みです。
【要件】
・令和2年2月以降、新型コロナウイルスに感染したことで収入が減った
・令和2年2月以降、所得の見込みが保険料免除の水準に達する
※令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請が可能
参考:『日本年金機構』
年金を払わないと損する?受給額をチェック
年金の受給額は、納付した期間に応じて決まります。また厚生年金は給与から天引きされるため、収入の高さに比例して受給額も増えるのが特徴です。年金の納付によって、実際いくら受給できるのか知りたい方も多いでしょう。
年金の平均月額と満額で受給した場合をまとめました。
【年金の平均月額】
・国民年金(自営業・専業主婦)/5万6,000円
新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)/5万4,000円
・厚生年金保険(会社員・公務員)/14万4,000円(老齢年金)
※基礎年金(国民年金)も含む
【満額で受給した場合の基礎年金】
・月額6万4,816円(20~60歳まで全期間、納付した方)
参考:『令和2年度・厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚労省』
『令和4年4月分からの年金額等について|日本年金機構』
年金を払いたい|未納期間の確認と追納方法
免除・納付猶予・特例制度を受けた方は、受け取る年金額が少なくなります。「将来少しでも多く年金を受け取りたい」「まったく受給できないのは困る」といった方は、免除や猶予期間分の追納を検討するとよいでしょう。
未納期間の確認方法
未納期間の主な確認方法は、2つあります。
1.年金定期便(ハガキ・封書)
誕生月に届く「ねんきんネット」のハガキで未納分が確認できます。納付状況の欄に「未納」と記載されているので、保険料の納付額をチェックしてみてください。
35歳・45歳・59歳の年には、封書で年金定期便が届きます。ハガキの定期便と同じように、納付状況の項目を読んで未納分を把握しましょう。
2.ねんきんネット
日本年金機構が運営している「ねんきんネット」というサイトでも、未納期間を確認できます。ねんきんネットに登録すると、パソコンやスマートフォンから自身の年金情報が閲覧可能です。
未納分の追納方法
未納分の追納方法は、2パターンあります。
【年金事務所に申請する方法】
申請書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。年金事務所の窓口から本人が申し込む場合は、マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類を提示しましょう。
1.年金事務所に申し込み
2.届いた納付書で追納する
【ねんきんネットから申請する方法】
1.ねんきんネットにログインし、「追納申込書」作成ページを開く
2.必要な情報を入力
3.書類をダウンロードして印刷する
4.年金事務所窓口に行くもしくは郵送する
参考:『日本年金機構』
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
年金は月々の支出になるため、「払わないといけないの?」と疑問に思うかもしれません。しかし未納は法律違反になり、最悪の場合は財産の差し押さえになるでしょう。経済的な理由や家庭の事情により納付できない方は、免除・納付猶予制度を利用します。
ただし免除や納付猶予を受けると、将来受け取る年金額が減ってしまうのが難点です。免除や猶予を受けた方も収入に余裕がある時期は、追納するとよいでしょう。
「小さなお葬式」では、低価格のお葬式プランを用意しています。老後の生活を考えるうえで、終活の一環としてお葬式プランを検討しましょう。葬儀に関する相談・疑問のある方は、気軽にお問合せください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。