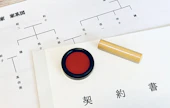生前贈与は、生きている間に他者に財産を譲り渡す方法です。基礎控除や非課税枠が設けられているものの、適用する際は一定の条件をクリアする必要があります。「非課税枠内で贈与したい」「現金を手渡しすれば非課税になるのでは」といった疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、生前贈与のやり方や注意点を紹介します。また、「現金でも適用できるのか」「贈与申告は必要なのか」という基本情報もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。基礎知識が深まることで、適切に財産を贈与できるようになるでしょう。
<この記事の要点>
・年間110万円以下の贈与財産の場合は非課税になる
・現金手渡しの生前贈与は税務調査によって認められなくなる場合があるため、避けた方がよい
・定額贈与は課税対象になるため現金の手渡しを避け、受贈者の銀行口座に振り込むのが得策
こんな人におすすめ
現金手渡しで生前贈与をしたい場合の対策を知りたい人
生前贈与を非課税にするための適用条件を知りたい人
生前贈与の現金手渡しで非課税となる条件
生前贈与は、自身が生きている間に、指定した人物に財産を譲り渡す行為です。現金の受け渡しも生前贈与と見なされ、財産の受け取り手に税金の支払い義務が発生します。
では、現金をいくら贈与すると税金が発生するのでしょうか。まずは、贈与税に関する基本情報を紹介します。
年間110万円以下の暦年贈与なら非課税
生前贈与の基礎控除は年間110万円です。基礎控除以下の財産を贈与することを暦年贈与といいます。暦年贈与では、110万円以下の贈与財産には税金が発生しません。直接現金を渡す際も同様です。
一方、110万円を超える金額を受贈する際には、超えた分の金額に対して贈与税が課されます。例えば、祖父が孫に210万円を贈与したとしましょう。この場合には、孫が受け取った財産のうち、100万円(210万円-110万円)が贈与税の対象となります。
相続時精算課税制度なら2,500万円まで非課税
暦年贈与以外の贈与方法として、「相続時精算課税制度」を選択することもあるでしょう。相続時精算課税制度とは、贈与時の税負担を軽減し、相続時に相続財産とまとめて税金を支払う制度です。
この制度では、2,500万円の控除が適用できます。2,500万円以下の財産贈与を受けた際には、贈与税がかかりません。一方、控除額以上の財産を受け取ったときには、2,500万円を超える金額に一律20%の贈与税が発生します。
生活費や養育費は非課税
親子間や夫婦間のように、扶養義務者から日々の暮らしの中で使用する生活費や教育費を受け取った際には、贈与税がかかりません。ただし、非課税の対象になるのは「通常必要とされるもの」の贈与時に限定されています。
そのため、扶養義務者からお金を受け取った場合でも、貯金や投資に使用するのであれば、贈与税の対象となるため注意しましょう。
現金手渡しの生前贈与は止めたほうがよい理由
「現金を手渡しすれば贈与税が発生しないのでは」と思う方もいるかもしれません。しかし、生前贈与をする際は、現金の受け渡しは避けた方がよいでしょう。ここからは、現金の手渡しをおすすめしない理由について詳しく解説します。
生前贈与が認められない可能性があるため
現金手渡しによる贈与が生前贈与に適さない主な理由は、税務調査によって生前贈与が認められなくなる場合があるためです。例えば、毎年100万円を10年間受け取っていたような場合では、定期贈与と見なされる可能性があります。
定期贈与とは、事前に決めた金額を計画的に贈与していく方法です。定期贈与では、贈与された合計金額に対して贈与税がかかります。しかし、現金による贈与では記録(証拠)を残せないため、「定期贈与ではなかった」と確実には証明できません。そうなると、必然的に納税の義務が発生します。
税務署に隠し通せないため
贈与や相続などお金が動く際は、税務署による税務調査の対象になる可能性があるため注意が必要です。税務署は、不動産の所有権移転や保険金の支払調書からお金の流れを確認し、場合によっては銀行口座の履歴や使用用途なども徹底調査されます。
対象となるのは、申告者だけではありません。無申告の場合にも税務調査は実施されます。「現金だからバレない」「申告する必要はない」などと考えるのは危険です。しっかりと申告し、納税をしましょう。
現金手渡しで贈与税申告をしないのはNG
年間110万円を超える生前贈与をしているにもかかわらず、贈与税の申告をしないでいると税務署によりペナルティが課される恐れがあります。期限内に贈与税申告や納税をしなかった際に起こり得るペナルティは以下の通りです。
・無申告加算税
・重加算税
・延滞税
悪意があると見なされると、最悪の場合は、刑事罰が与えられることもあります。現金手渡しの贈与でも、基礎控除を超える金額を譲り渡す場合はしっかりと申告しましょう。
現金手渡しで生前贈与をしたい場合の対策
生前贈与の際は、「贈与契約書」を作成するのが得策です。贈与契約書があれば、両社の合意の下に贈与があったことを証明できます。また、一度きりではなく、贈与をする度に作成するのがポイントです。そうすることで、定期贈与を疑われた際の証明として利用できます。
贈与契約書は自身で作成が可能です。テンプレートや形式の決まりは特にありませんが、以下の必要事項は記載しましょう。
・贈与日
・贈与条件
・贈与方法
・贈与財産の種類と金額
・贈与者と受贈者の名前
・押印欄 など
生前贈与を非課税にするために利用できる特例
生前贈与には、基礎控除以外にも複数の非課税制度があります。支払う税金を減らしたい方は、制度の内容を事前に確認しましょう。自身の場合に合った制度を適用することで、贈与税を上手に節税できます。
配偶者控除
配偶者控除の特例は、居住用の不動産、あるいは不動産の購入資金を夫婦間で贈与した際に利用できる制度です。贈与財産のうち2,000万円までは非課税の対象となります。基礎控除との併用も可能です。なお、以下のような適用条件に合致している方が利用できます。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること
・受贈者が、贈与があった年の翌年3月15日までに対象の不動産に居住しており、その後も継続して住む予定があること
・贈与税申告をすること
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、直系尊属から結婚や子育て資金を一括で贈与された際に適用できる制度です。子育て資金は1,000万円、結婚資金は300万円を限度に、非課税枠が設定されています。基礎控除との併用も可能です。適用条件は以下をご確認ください。
・受贈者が、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満であること
・直系尊属からの贈与であること
・受贈者の前年度所得が1,000万円以下であること
・国税庁が定める方法で贈与すること
住宅取得等資金の贈与
住宅取得等資金の贈与は、住宅を購入したり増改築したりする資金として直系尊属から贈与を受けたときに適用できる制度です。非課税限度額は住宅の種類や取得年度、消費税率により異なります。適用条件は以下の通りです。
・直系尊属からの贈与であること
・贈与年の1月1日時点で18歳以上であること
・受贈があった年の受贈者の合計所得が2,000万円以下であること
その他にも対象となる住宅の要件や、居住要件などが設定されています。詳しくは国税庁のホームページで確認しておきましょう。
(参考: 『国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』)
教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与の特例は、直系尊属から教育に関する資金の贈与を受けたときに適用できる制度です。贈与税の基礎控除に加え、最大1,500万円(塾や習い事などは500万円)までが非課税となります。特例制度の適用条件は以下の通りです。
・受贈者が平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満であること
・直系尊属からの贈与であること
・受贈者の前年度所得が1,000万円以下であること
・国税庁が定める方法で贈与すること
生前贈与をする際の注意点
生前贈与をする際には、注意したいポイントがいくつかあります。事前に注意点を確認し適切に対応しましょう。しっかりと知識を深めないまま贈与をすると、生前贈与と認められなくなる恐れがあります。
定期贈与にならないようにする
定期贈与とは、毎年一定額の贈与をすると定め、計画に基づいて贈与を進める方法です。暦年贈与だと思っていても、定期贈与とみなされることがあるため注意しましょう。
定期贈与では、毎年の贈与額が基礎控除以下であっても関係なく、贈与した合計額に対して税金が発生します。定期贈与とみなされないためには、現金の手渡しを避け、受贈者が普段使用している銀行口座に振り込みをするのが得策です。また、万が一に備えて贈与契約書も作成しましょう。
亡くなる3年以内の贈与は相続税の課税対象になる
贈与者が亡くなる3年以内(※)に生前贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。暦年贈与によって得た財産も同様です。相続時に受け取った財産と、3年以内の贈与で受け取った財産を合計して、相続税を支払います。
ただし、一部の特例制度を使用した場合は、相続財産に加算されません。また、贈与時に税金を支払っている場合は、その分を相続税から控除できます。
※被相続人の相続開始日が令和8年12月31日までの場合
(参考:『No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)』)
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
財産を贈与する際は、現金の手渡しを避けることが賢明です。贈与があったという証拠が残りにくく、税務調査によって贈与税の支払いを求められる可能性があるからです。現金を贈与する場合は、受贈者が利用している銀行口座に直接振り込みましょう。また、贈与契約書も作成しておけば安心です。
生前贈与を検討中の方は、贈与財産や特例制度など、贈与に関する知識を深めて自身に合った方法を選択しましょう。その際は、今回の記事もぜひ参考にしてみてください。相続と同時に葬儀をご検討中の方は、小さなお葬式にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


お付き合いのあるお寺がない場合、寺院手配サービスを利用する方法もあります。ホゥ。