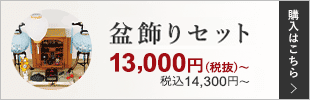お盆は先祖を迎えて祀る(まつる)行事です。普段とは違ったお盆飾りをする習わしがありますが、特に初盆を迎える方はどのような飾りを作れば良いかわからないことも多いのではないでしょうか。
盆行事はきちっと決まった形があるわけではなく、地域や宗派によっても違いが見られます。この記事では、日本のお盆についてや、一般的な盆棚の飾り方、お供え物についてご紹介します。
<この記事の要点>
・盆棚は帰ってきた先祖を家で祀る臨時壇のことである
・盆棚の飾り方は盆提灯、まこものゴザ、精霊馬などを用意するのが一般的
・お盆の期間の期間中は精霊への食事としてお供え物をするが地域や宗派によって異なる
こんな人におすすめ
お盆の概要を知りたい方
お盆に準備する「盆棚」の作り方を知りたい方
お盆のお供え物の種類を知りたい方
日本のお盆について
お盆は、亡き父母や祖父母、さらにはもっと昔に亡くした先祖をお迎えして祀る行事です。現在私たちが行っているお盆は、日本人がもともと持っている祖霊信仰が外来信仰の仏教と結びついた形となった、「日本仏教の行事」と言われています。
お盆の期間
盆行事の期間は地域によって統一されておらず、いつ始まっていつ終わるのかが明確には決まっていません。盆月の1日に灯篭を立てるところがあり、これがお盆の始まりと意識されています。「七日盆」という言葉もあり、7日頃がお盆の準備に入る時としているところもあります。盆行事の中心は、13~16日です。
お盆の時期
東京や一部の地域では7月(新のお盆)、そのほかの地域では8月(旧のお盆)にお盆を迎えることが多いようです。
また、8月24日が「地蔵盆」であり、13~15日が「表盆」であるのに対して、この日を「裏盆」と呼ぶところが全国にあります。15日を中心にして1日から24日頃までが一連の盆行事期間と捉えていることが多いようです。
初盆について
初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。逝去日から四十九日以内にお盆がくるのであれば、その翌年が初盆となります。
盆棚の飾り方
盆棚は、精霊棚(しょうりょうだな)とも言って、帰ってきた先祖を家で祀る臨時壇のことです。仏壇の前に机などを置いてお盆に飾るのが一般的ですが、家の庭や縁側あるいは仏壇脇に棚を別に作ることもあります。初盆の新仏の時だけ作るところもあります。
盆棚の作り方は地方によってさまざまですので、「正しい作り方」というものがあるわけではありません。
盆棚に飾るもの
盆棚の飾り方は地域や宗派によっても異なりますが、一般的には以下のような物を用意します。
| 盆提灯 | 盆提灯は、飾る場合と飾らない場合がありますが、初盆で飾る場合は白提灯になります。 |
| まこものゴザ | 盆飾りの下には、まこもで編んだゴザを敷きます。 |
| 精霊馬 | ナスとキュウリに麻がらまたは割りばしを刺して、馬と牛をかたどった物を供えます。 |
| 麻がら | 箸木(はしのき)とも言います。適度な長さに切り、ほうろくという素焼きの皿に乗せます。迎え火や送り火にも使用します。 |
| ほおずき | 箸木(はしのき)盆花のひとつで、盆飾りの上からつるす形で飾ることが多いです。 |
盆飾りの飾り方の例
盆飾りの飾り方は地域の風習によりさまざまですが、一般的には、まこものゴザの上に台を設置し、中央に位牌を置いて、その周りを飾っていきます。
ゴザを敷いた部分が、先祖の精霊を迎える霊座の結界であることを示すため、棚の四方に篠竹を柱として立てるところもあります。また、この柱に縄を張って、ほおずきやキキョウ、ミソハギなどの盆花で飾ることもあります。
提灯は2基用意した場合には、盆棚の両脇に1基ずつ置きましょう。
地域によっては盆棚の下などに皿を置き、供物をあげて餓鬼を祀るところがあります。餓鬼は祀り手のなくなった無縁霊で、先祖の霊にくっついてくるものだと言われています。「一切精霊様:いっさいしょうれいさま」と呼んでいる地域もあり、供え物はお盆の期間中下げてはいけないとされています。
さまざまなお盆のお供え物
お盆の期間には、訪れた精霊への食事としてさまざまなお供え物をしますが、これも宗派や地域によって異なります。
サトイモの葉の上に皮のままの青豆、洗米、きざんだナスを入れるところ、団子やオケソウと呼ばれる白餅や蓮菓子を供えるところなどがあります。
そうめん、おはぎ、高野豆腐、白蒸し(餅米を炊き、小豆を入れずに黒豆を入れたおこわ)、味噌汁、コイモ、トウモロコシ、ナスなどもお供え物としてよく見られます。
盆飾りを用意してご先祖様を迎えましょう
盆棚の飾りやお供え物については、地域や宗派によって違いがあるものの、それぞれに意味が込められているものです。地域の風習に従って、年配者やお寺さんに教えてもらいながら、神聖な気持ちでご先祖をお迎えしてみてはいかがでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
新盆・初盆に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。


相続人には、被相続人の遺産を一定割合受け取れる「遺留分侵害額請求権」があります。ホゥ。