日本の夏の風物詩ともいえるお盆ですが、時期や風習、呼び方も地域によって異なります。親族が亡くなり、施主として初盆や新盆の準備をしなければならない状況を迎えたとき、わからないことばかりで戸惑うことがあるかもしれません。
そこで今回は、初盆や新盆を迎えるにあたり、何をすれば良いのかについてご紹介します。また初盆を迎える時期や、親族の初盆に向けてのスケジュールを確認しましょう。
<この記事の要点>
・新盆とは、故人の四十九日法要以降に迎える初めてのお盆のこと
・四十九日と新盆の時期が重なる場合は、翌年が新盆となる
・新盆を迎える際は、法要の1か月前までにはお寺に連絡をする
こんな人におすすめ
新盆の意味を知りたい方
新盆の時期を知りたい方
宗派ごとの新盆の違いを知りたい方
新盆(初盆)とはいつのこと?
お盆は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、年に一度故人が家に戻ってくる期間と考えられています。それでは「新盆」には、どのような意味があるのでしょうか。ここからは、新盆の意味や時期について解説します。
新盆は故人の四十九日法要以降に迎える初めてのお盆
故人の死後初めて迎えるお盆は、「初盆(はつぼん・ういぼん)」や「新盆(にいぼん・あらぼん・しんぼん)」と呼ばれ、丁寧な供養が行われます。四十九日よりも前にお盆を迎える場合は、翌年が新盆となるのが一般的です。
四十九日と新盆の時期が重なる場合
お盆と四十九日が重なる場合もあるかもしれません。お盆の期間は地域によって異なりますが、ここでは新暦8月盆の始まり8月13日の場合で説明します。
6月25日~6月28日の間に亡くなった場合は、四十九日がお盆と重なります。四十九日法要は、亡くなった日から49日を越えないように日程を調整します。そのため、お盆よりも前に法要を実施できる場合は特に問題ありません。
ただし、お盆と四十九日の日程が近かったり重なったりする場合は、新盆を翌年に行うか、新盆と四十九日法要を同時に行うとよいでしょう。どちらがよいのかは、地域や家庭によって異なるので、家族で相談をしてきめるのがおすすめです。
四十九日法要は、故人が無事に極楽浄土にたどり着けるように祈る儀式です。一方で、お盆は故人が極楽浄土からこの世に帰ってくる期間と考えられています。そのため、新盆と四十九日法要を同時に行うことは極楽浄土に渡った故人をすぐに迎えることとなり、故人を疲れさせてしまうという考えもあります。

東京はいつお盆を迎える?新のお盆と旧のお盆
お盆には新盆と混同されがちな「7月盆」と呼ばれる新のお盆と、「8月盆」や「月遅れ盆」と呼ばれる旧のお盆の2種類があります。これは、明治時代に太陰暦から太陽暦に変更されたことに伴い生まれた慣習とされています。
現代では旧のお盆である8月盆が一般的で、7月盆を主流とする地域は、東京都や神奈川県、北海道の一部や石川県金沢市、静岡県の一部などに限られています。
改暦の布告からしてわずか23日後の施行で日本の各行事が1か月遅れることになり、8月盆が浸透しました。また、農家にとって7月は農繁期で忙しく、落ち着いて先祖をお迎えできないためにお盆を1か月遅らせたという説もあります。
2025年の新のお盆は7月13日(日)~7月16日(水)、旧のお盆は8月13日(水)~8月16日(土)です。地域によってはお盆の期間が4日間ではなく3日間のところもあります。
また、沖縄県や九州地方など、新暦が導入される前の旧暦盆を守り続けている地域もあります。旧暦盆の期間はその年によって変わるため、9月にずれ込むこともあります。たとえば、2025年の旧暦盆の地域でのお盆の期間は、9月4日(木)~9月6日(土)です。
新盆の準備とスケジュール
新盆を迎えたことがないと、わからないことも多いでしょう。ここからは、新盆を迎える際に施主が準備することと、新盆の流れを紹介します。
お寺への依頼
新盆では、菩提寺のお坊さんを呼んで読経をしてもらいます。お盆の期間はお坊さんにとってもっとも忙しい時期なので、法要の1か月前までには連絡してスケジュールを確認しておきましょう。
新盆では法要後に会食の席を設けることが多いため、お坊さんには読経のお願いと会食の案内をします。
法要の日取りがきまったら、招待する方に連絡をしましょう。会食の出欠確認をしておくと、その後の準備がスムーズに進みます。

仏具・盆棚・お供えなど必要なものを用意
新盆を迎えるにあたり、故人のために準備しておくべきものがいくつかあります。
まずは「迎え火」と「送り火」です。これは、故人の精霊が迷わず帰って来られるように焚く目印のことです。迎え火と送り火を行うには「おがら」が必要です。「おがら」とは、皮を剥いた麻のことで、お盆の時期になるとスーパーやホームセンターで販売されます。地域によっては、おがら以外に松明(たいまつ)やロウソク、藁を用いるところもあります。
新盆では、白木で作られた白提灯を飾ります。盆提灯は目印として、また故人が安らかに成仏できるように祈りを込めて飾ります。盆提灯は親族から贈られることもあるでしょう。
先祖を迎えるために必要な「盆棚」や「精霊棚」は、仏壇とは別に設ける特別な棚です。地域や宗派によって特徴がありますが、一般的にはお盆の月の12日の夕方、もしくは13日の朝に仏壇を清めてから飾ります。
ただし、浄土真宗では亡くなると故人はすぐに浄土へ往生するという考えのため、追善供養を行いません。そのため、追善供養にあたる盆棚や精霊棚は飾りません。
棚には以下のものを飾ることが一般的です。
・位牌
・精霊馬
・水の子
・盆花
・お膳(霊供膳)
・果物
・お供え菓子
・香炉
・リン
・ロウソク など
それぞれの仏具については以下で詳しく説明します。
位牌は仏壇に飾っているものを移動させて、精霊馬はナスとキュウリに割りばしを刺して、それぞれを牛と馬に見立てます。牛と馬である理由は、「帰ってくるときは足の速い馬に乗って早く帰ってきて、帰るときは足の遅い牛に乗ってゆっくりと帰ってほしい」という願いが込められているからといわれています。
水の子はすべての精霊に捧げるお供え物で、蓮の葉の上にナスとニンジン、キュウリをさいころ切りにしてお米と混ぜたものに水を含ませて盛りつけて飾ります。さいころ切りにするのは、多くの先祖や精霊に食べ物が行き渡るためと考えられています。
盆花はキキョウやミソハギ、ヤマユリなど夏の花が選ばれます。浄土宗や日蓮宗では、ほおずきを飾ります。
お膳は「霊供膳(りょうぐぜん・れいぐぜん)」や「御霊供膳(おりょうぐぜん・おりくぜん)」と呼ばれ、故人の精霊をお膳でもてなす意味があります。お盆期間中は、毎食自分たちの食事の前にお供えします。
霊供膳の内容は不殺生の教えに従い、肉や魚などの生き物の食材を使わない精進料理であることが一般的です。お膳の配置は、飯椀と汁椀の位置はどの宗派でも同じですが、高坏(たかつき)、平椀、壺椀は宗派によって配置が異なるため注意が必要です。
お膳に乗せる飯椀には白米を大盛にして丸く形を整えてお供えします。汁椀には、お味噌汁またはお吸い物を入れましょう。出汁は動物性のかつおだしは使わずに、昆布を使います。高坏にはお漬物を二切れ、平椀には昆布出汁煮物を3~4種類のせます。壺椀には、おひたしなどを小さな山になるように盛りつけます。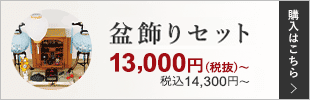
お墓の掃除をする
お墓の掃除を行う時期にきまりはありませんが、迎え火を焚く前日までに済ませるようにしましょう。新盆であれば、家族以外の人がお盆よりも前にお参りに来てくれることもあります。そのため、月の始めに掃除をして新盆に備えておくのもおすすめです。
お墓の掃除方法は、お墓の周りの落ち葉や雑草を除去して、墓石は水を含ませたスポンジで洗います。汚れがひどい場合は、石材用洗剤を使いましょう。花筒や線香皿などの小物は、中身を綺麗に取り出し洗って最後に乾いたタオルで拭きあげます。水気が残っているとコケがつきやすくなるので注意しましょう。
盆入りの夕方に迎え火を焚く
盆入りとなる月の13日の夕方に迎え火を焚きます。昔はお墓の前で迎え火を焚き、提灯の灯りで先導しながら家に帰るという風習がありましたが、防災の観点から現代で行われることは少ないでしょう。
盆の法要
新盆の法要では、親戚や知人などが集まりお坊さんに読経をしてもらいます。その後、参列者とともに会食をするのが一般的な流れです。
盆の最終日に送り火を焚く
盆の最終日にあたる16日(地域によっては15日)に、送り火を焚きます。浄土への道中の無事をお祈りしましょう。迎え火のときと同じように、お見送りとしてお墓参りをする地域もあります。
新盆はいつ・何をするのか
ここからは、お墓参りや新盆のお宅の訪問、お供え、灯篭流し、白提灯など、新盆ではいつ何を行うのかを紹介します。
新盆のお墓参りはいつするのか
新盆のお墓参りは、お盆の月の初めがよいでしょう。お盆の月に入ってから遺族がお墓掃除をすることが多いため、月の始めごろから13日の午前中が適しています。13日の夕方以降は精霊が自宅に帰るため、お墓参りはしません。
新盆を迎える遺族は、13日に「お迎えに行く」という意味でお墓参りをして、帰ってから玄関先や庭先で迎え火を焚きます。
新盆の訪問はいつするのか
新盆の訪問は、お盆の月の初めに遺族の都合を聞いたうえで伺います。法要当日の訪問は避けましょう。
新盆のお供え物はいつ手配するのか
新盆の法要に参加できず、お供えを送りたいと考える方もいるでしょう。その場合は、法要の一週間前から前日の間に届くように新盆のお供えを手配するのがおすすめです。
灯篭流しはいつするのか
死者の魂を弔い、火を灯した灯篭を川や海に流す「灯篭流し」は、送り火の一種としてお盆の最終日に行われます。地域によって慣習が異なるので、事前に確認しておきましょう。
白提灯はいつ飾るのか
盆提灯(白提灯)はお盆の月の初めから飾ります。白提灯は新盆にのみ使われるので、13日に飾り、新盆が終わった後は処分するのが通例です。

宗教による新盆の違い
宗教によって新盆の捉え方は異なります。ここからは、宗派別の新盆の概念について紹介します。
真言宗・浄土宗などの仏教系の場合
真言宗と浄土宗において、新盆は故人を初めてお迎えする日であることから、通常のお盆よりも盛大に供養をするのが一般的です。一方で浄土真宗では、故人はすぐに極楽浄土に往生すると考えられており、お盆の期間に霊として戻ってくるという概念がありません。追善供養が必要ないことから、お盆に特別なことは行いません。
神道の場合
神道では、「新盆祭」や「新御霊祭(あらみたままつり)」が仏教の初盆にあたります。神道において、お盆は先祖供養・祖先崇拝の行事のひとつとされているため、祖霊舎(それいしゃ)を掃除したり、季節の果物や酒をお供えしたりします。仏教と同様に、迎え火や送り火も行います。
宗教以上に地域色も豊かな盆行事
お盆の行事は宗教によってもさまざまですが、地域色も豊かです。
8月16日に行われる「京都五山の送り火」は、お盆の精霊を送る伝統行事です。東山に「大」の字が浮かびあがり、それに続いて松ケ崎に「妙」「法」、さらに西加賀に船形、大北山に左大文字、嵯峨に鳥居形が現れます。これらは京都市無形民俗文化財に登録されています。
8月15日に行われる「長崎の精霊流し」は、故人の霊を弔うために船を手づくりし、その船をひきながら街を練り歩き、故人を極楽浄土へと送り出す行事です。1メートル程度のものから何十メートルもある船まで大小はさまざまで、家紋や家名、町名が記されて、船の飾りつけには故人の趣味などが反映されています。
7月13日~7月16日の間に行われる靖国神社の「みたままつり」は、昭和22年に戦没者の霊を慰める行事として始まりました。3万個を超える提灯やぼんぼりが参道に並び、大道芸や神輿振りなどを見学できます。
8月12日~8月15日の間に行われる徳島の「阿波踊り」は、日本最大規模の盆踊りといわれています。江戸時代から続く歴史ある伝統芸能で、踊り手が一斉に踊り歩きます。
お盆行事とその由来|そもそもお盆とは?
盆行事は、さかのぼること飛鳥時代の606年、推古天皇が「推古天皇十四年七月十五日斎会」という行事をしたことが始まりといわれています。江戸時代以前までは貴族や武士、僧侶といった上流階級の方の行事でしたが、江戸時代からは庶民にもお盆の文化が広まりました。
宗派や地域によってお盆の時期や行事内容、風習は違いますが、先祖の霊を供養することが目的であることに変わりはありません。
お盆が終わった後の白提灯やお供えはどうする?
お盆が終わったら、盆棚やお供え物を片付けます。送り火をしたあとに、お供え物を棚から下ろしましょう。片付けのタイミングは宗派や地域によって異なります。
お供えしていたものは、基本的には無駄にならないように食べましょう。しかし、傷んでいて食べられない場合は、生ごみとして処分して問題ありません。その際は白い紙に包んで感謝の気持ちを示して処分しましょう。
白提灯は、昔はお焚き上げをしていました。しかし、現在の住宅事情では難しいことも多いため、地域のゴミの分別方法に従って処分しましょう。菩提寺に相談してみるのもおすすめです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
故人の死後初めて迎えるお盆は、「初盆(はつぼん・ういぼん)」や「新盆(にいぼん・あらぼん・しんぼん)」と呼ばれ、丁寧な供養が行われます。四十九日よりも前にお盆を迎える場合は、翌年が新盆となるのが一般的です。
お盆には新盆と混同されがちな「7月盆」と呼ばれる新のお盆と、「8月盆」や「月遅れ盆」と呼ばれる旧のお盆の2種類があります。現代では旧のお盆である8月盆が一般的で、7月盆を主流とする地域は、東京都や神奈川県、北海道の一部や石川県金沢市、静岡県の一部などに限られています。
また、沖縄県や九州地方など、新暦が導入される前の旧暦盆を守り続けている地域もあります。
法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


よくある質問
新盆はいつからいつまで?
新盆の準備はいつから始める?
新盆の飾りはいつまで飾る?
不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。


































