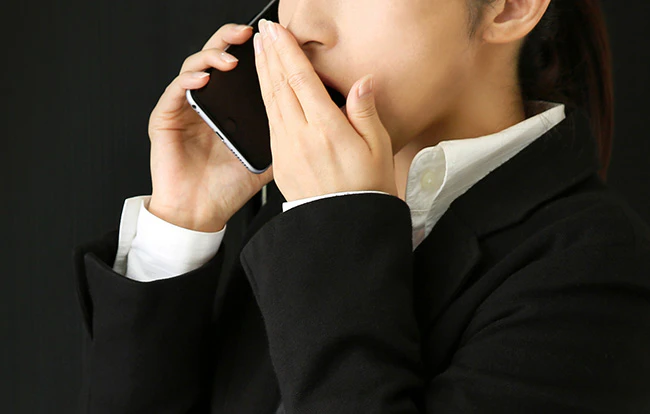危篤とは、いつ息を引き取るか分からない状態を指します。しかし、医師よって危篤と診断を受けてから、持ち直すことがあるのか気になるという方もいるのではないでしょうか。危篤の連絡があった場合、突然のことであれば冷静な判断でものごとを進めるのは難しいでしょう。
そこでこの記事では、危篤となっても持ち直すことがあるのかについてと危篤状態のときにしておくとよいことについてご紹介します。ここでまとめている内容を読めば、いざというときに慌てず、後悔のないようにやるべきことを選択できるようになるでしょう。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。
<この記事の要点>
・危篤状態は生命の危機が迫っている状態であり、回復の見込みは低いが持ち直すこともある
・家族は亡くなる可能性を受け入れ、冷静な判断と心の準備が必要
・危篤の場合、忌引休暇ではなく有給休暇を取得するのが一般的
こんな人におすすめ
危篤状態とは何かを知りたい方
危篤状態から持ち直すことはあるのかを知りたい方
危篤状態のときにしておくとよいことを知りたい方
危篤状態とは?
危篤とは、病気やケガなどにより身体状態が悪化し、「生命」に危機がせまっている状態を指します。病気で入院し、少しずつ容態が悪化する場合や不慮の事故で生命危機にいたるなど状況は複雑です。
危篤と診断した場合、回復する見込みは低く、息を引き取るまでそう長くないという判断にいたったといえます。家族はこのときに、希望を持ちながらも亡くなる可能性を受け入れます。
また、似た言葉に「重篤(じゅうとく)」があります。危篤は生命活動の停止を見越しているのに対し、重篤は重い病状のため、このままでは死にいたる状態です。重篤は、危篤と同じく生命に危険が迫っている状態ですが、その危険の意味合い・度合いが異なります。
<関連記事>
危篤とは?重篤との違いや家族が危篤となったときにすべきことも解説
危篤状態から持ち直すことはあるの?
医師から危篤と言われ、多くの方が最期のときを迎えます。しかし、すべての方が同様の経過にいたるのではなく、人によっては長く生き続けたり持ち直したりする場合もあります。常に症状は変化し、総合的な判断によって危篤とするため、正確な判断はできません。
それぞれに持ち直す状況や期間の目安を解説していきますので、以下よりぜひ参考にしてください。
危篤から持ち直すこともある
危篤の状態は、病状やバイタルサイン、そのときの状況を総合的に見て判断します。そのため、常に変化する状況を医師が正確に判断するのは困難です。
また、危篤状態になったからといって、必ず息を引き取るわけではなく、回復する可能性も残されています。危篤状態から回復したケースも少なくありません。
生命の危機が迫っている状態ですが、急な回復力を取り戻すなど目に見えない部分での身体状態は予測が大変困難です。危篤状態から持ち直すかどうかは、誰にもわかりません。
危篤からご臨終や持ち直す期間は人それぞれ
危篤状態と診断を受けてから臨終のときを迎えるまでの期間は、持ち直す可能性と同様に予測が困難です。短時間で息を引き取った例もあれば、数か月または数年と生き続ける例もあります。危篤の診断から持ち直し、回復にいたったケースも実在しています。
また、危篤状態と持ち直しを繰り返したケースもあり、状況の予測を正確に立てるのは困難です。どのような状況であっても「命に危険がある」状態は変わりません。そのため、希望をもつ反面、もしもの事態を予測して行動することが大切です。
危篤状態のときにしておくこと
危篤状態と連絡を受けた場合に備えて、何をするべきか前もって準備をしておくとよいでしょう。急に容態が悪化する場合や不慮の事故など、予測できない状況では冷静な判断をするのは容易ではありません。
それでは、危篤の連絡を受けたら何をしておくべきなのでしょうか。以下より項目に沿って解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
心の準備をしておく
危篤と診断するのは回復の見込みが難しく、処置の限界や身体的な状態など総合的な判断からです。持ち直す可能性も考えつつ、死期が迫っている覚悟をもつ必要があります。危篤者の状態次第では、決断を余儀なくされる場合も考えられます。
冷静な判断は難しい状況ですが、慌てずに対応することが望まれるでしょう。慌ててしまったことで、現地へ向かう際に事故を起こしたり、トラブルが起こってしまったりするケースも考えられます。そうなる可能性を予期し、心の準備をしておきましょう。
葬儀社などを決めておく
亡くなると決めつけるわけではなく、もしもの場合に備えて、葬儀社を決めておくと心の負担が軽くなります。臨終を迎えたあとは手続きや葬儀社との打ち合わせが必要です。前もって考えておかないと冷静な判断ができない状態で判断を迫られるのです。
具体的にどの葬儀社にお願いするか決めなくてもよいので、大まかにどこにお願いするか考えておくとよいでしょう。予測できない状況で判断を迫られるより、ある程度の流れを押さえているほうが冷静さを維持しやすくなります。
<関連記事>
危篤と言われたらどうする?親族や会社への連絡方法を紹介
近しい人に危篤状態であることを伝える
危篤と診断を受けてから連絡を入れる範囲は、一般的に3親等以内の親族が該当します。しかし、3親等以内の親族ではなくても親しい友人など、当人の関係性をもとに連絡を入れるとよいでしょう。
親族であっても普段付き合いがなかったり、疎遠だったりする場合は必ずしも連絡を入れる必要はありません。
本人の意識があったころの意思も踏まえ、連絡する相手を選別するといいでしょう。また、危篤の際は親族へ連絡する時間帯は考慮せず速やかに伝えるようにしましょう。
危篤のときに仕事は休める?
危篤は状況により、短時間で亡くなる可能性もあるため、連絡を受けたら速やかに駆けつける必要があります。しかし仕事をしていた場合、急な申し出でも休めるのでしょうか。忌引休暇もありますが、実際に直面しないと使うことはありません。
事前にこれらの内容を把握しておくことで、仕事への影響も同僚や会社への負担も抑えられます。
危篤の場合は忌引休暇とならない
危篤と診断された状態での休みですが、忌引休暇とはならないのが一般的です。理由としては、危篤の状態ではまだご家族が亡くなっていないためといえます。一般的に忌引休暇は、家族の葬儀に参列することを理由にした休みとして扱っています。
また、危篤状態であれば、回復の見込みがあることから従業員が不正に休みを取得することも考えられます。会社によっては危篤の際の決まりがある場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズに対応できます。
有給休暇を取得する
休みの理由が危篤となる場合は、有給休暇を取得して休むのが一般的です。危篤時に伝達を受けるタイミングは予測が難しいため、急な休みでも事後申請で通る可能性は高くなります。会社ごとの決まりもあり、危篤時は会社でどのような扱いをしているか事前に確認を行うようにしましょう。
もし有給休暇が残っていない場合は欠勤扱いになる可能性も高く、取得できないと給料が減ることは覚悟しなければなりません。意図がなければ、万が一に備えて有給休暇は残しておくのがベストです。
上司には事前に相談しておくのがよい
いずれの状態であっても、まずは上司へ相談しておくことが望ましいといえます。危篤の診断を受けると引き継ぎや手続きに使っている時間はなく、休みをどれくらい要するのかもその時点では判断がつきません。
急を要する場合、できるだけ速やかに連絡をしましょう。就業の時間外であればメールで伝え、反応を見ながら電話で伝えるといいでしょう。また、闘病中などで状況の変化が読めない容態が続いている場合も事前に伝えておいたほうがスムーズに対応してもらえます。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
危篤の連絡をするときの方法
危篤の診断を受けてから連絡をする際、具体的にどのような手段と優先順位で伝えるべきか悩んでしまう場合があります。このときに冷静さを欠いてしまうと判断がつかないため、できるだけ事前に備えておきましょう。
電話で伝える場合も、親族との関係性や時間帯など普段ではよくないとされる場合もあるため、押さえておく必要があります。
電話で伝えるのがよい
メールやSNSツールが発達し、伝達手段が多様化していても電話のスピーディーさと表現の伝わり方にはどれも劣ります。できるだけ速やかに正確に伝達するため、電話を使用するほうがよいでしょう。メールでは気付かない可能性もあり、ことの重大さも伝わりにくい場合があります。
日頃の関係性にもよりますが、親族へ電話をする際は深夜、または早朝でも電話で伝えるのは常識の範疇でしょう。その場合、「深夜(もしくは早朝)に申し訳ないです」と前置きがあるとよいです。文字だけで伝えるよりも、口頭でのやり取りは相手の反応を見ながらショックをやわらげる効果もあります。
職場にはなるべく早く伝える
職場へ連絡する際は、可能な限り早い方がよいです。勤務中であれば直接伝え、勤務時間外であればメールで概要を伝えた後、詳細を電話で伝えましょう。職場は休む可能性があるため、できる限り速やかに伝えるのがマナーです。
上司への電話連絡は早朝・深夜を避け、メールで連絡を入れておきましょう。電話に出られそうな時間帯を見計らい、電話をするとよいでしょう。休む期間が数日間以上に渡る場合、業務に支障をきたすことがあるため、定期的に連絡を取りながら相談をします。
宗教者への連絡は事前に伝えておくとよい
もしもの場合に備え、菩提寺に連絡をしておくとよいでしょう。菩提寺とは、先祖代々の墓があるお寺です。亡くなった場合は菩提寺で法事や葬式をお願いするため、遠方の場合は早めの連絡で初動が違います。
仏事に関する相談も受け付けており、事前に伝えられるよう連絡先を確認しておきましょう。危篤になれば、おおよその状況を踏まえて対応ができるため、もしもの場合も考えた上で現在どのような状況か合わせて伝えるとよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
危篤と診断され、連絡があった場合は想像以上に冷静さを欠いてしまうことがあります。冷静な判断ができないと伝えるべき情報が正確に伝わらなかったり、慌ててしまいケガや事故につながったりする恐れもあるでしょう。
事前に備えておくことで、いざというときに慌てず対応することが可能です。いざというときに困らないために、葬儀に関することは小さな疑問でも、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。
お客様満足度の高さと実績がある「小さなお葬式」では、お客様が抱える不安や悩みを全力でサポートいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
危篤になったり持ち直したりを繰り返すときに毎回仕事を休むべき?
危篤で会社を休むのは非常識?
危篤が長引いたときはどうすればいい?
危篤の連絡を受けたらまず何をすればいい?
危篤の連絡をするときに何を伝えればいい?
危篤からご臨終になったあとはどうすればいい?

墓じまいとは、先祖供養の続け方を考えた際の選択肢の一つです。ホゥ。