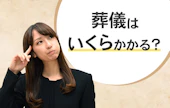超高齢社会を迎えた今、人生の終わりに向き合いよりよい人生を過ごす終活を行う人も増えてきました。終活サポートに力を入れている自治体もあり、身寄りのない人の終活支援を行う取り組みとして注目を集めています。しかし、終活サポートについて正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。
終活サポートを活用することで、葬儀関係の契約サポートや安否確認訪問を受けたりすることができます。この記事では、終活サポートの概要、目的、エンディングノートに記載する内容について紹介します。
<この記事の要点>
・終活サポートは、身寄りのない人に向けて行う終活支援のことを指す
・終活サポートでは葬儀業者を紹介し、葬儀・納骨の生前契約のサポートを行う
・終活サポートとしてエンディングノートを配布している自治体もある
こんな人におすすめ
自治体の終活サポートとはどのようなものかを知りたい方
自治体の終活サポートの目的を知りたい方
自治体の終活サポートで行われる内容を知りたい方
終活サポートは身寄りのない人のための終活支援
終活サポートは、ひとり暮らしをしている身寄りのない人に向けて行う、終活支援のことを指します。神奈川県横須賀市が先駆けて始めたことが有名で、それ以降ほかの自治体も独自の方法で終活サポートに取り組むようになりました。
ここからは終活サポートはどこの自治体で行われているのか、どのような人が受けることができるのかを紹介します。
横須賀市・大和市などで行われている
終活サポートは、各自治体に広まりつつある事業として注目されています。神奈川県横須賀市が終活サポートのパイオニアとして有名です。横須賀市に続いて、神奈川県大和市でも終活サポート事業への取り組みが開始されました。
ほかにも神奈川県綾瀬市、千葉県千葉市、愛知県北名古屋市、兵庫県高砂市などでも独自性のある内容の終活サポートが行われています。自治体の中には、終活サポート対象者の条件に「所得制限」を設けている場合もありますので確認しましょう。
終活サポートの対象となる人は?
終活サポートを使ってみたいと思っても、条件を満たしていなければ利用できないこともあります。対象となる人は、原則的にはひとり暮らしで身寄りがなく、高額の財産を有していない人です。
自治体によっては、終活サポートの対象になる条件を広げていることもあります。たとえば、生涯未婚の人、ガンで余命宣告を受けた人も自治体によってはサポートの対象です。終活サポートの利用を検討する前に、自分は対象者になるのか確認しておきましょう。
終活サポートの目的
終活サポートの目的は、 ひとり暮らしをする高齢者の孤独死を防ぎ、終末期の人生を有意義に過ごすことにあります。自治体の負担が大きい孤独死は深刻な問題です。包括的サービスの一面がある終活サポートは、地域の人が終活について考えるきっかけにもなるでしょう。ここからは、終活サポートの目的を解説します。
孤独死を防ぐ
終活サポートを利用することで、対象者が生前に葬儀や納骨の契約をすることができ、預金を利用して葬儀などを行うことが可能です。公費を利用して孤独死した高齢者の火葬を行うことは、自治体にも大きな負担になります。
横須賀市の場合は、孤独死の増加で公費による火葬が増えたため、終活サポートの導入に踏み切りました。もしものことがあったとき、ひとり暮らしの高齢者が「どのようなスタイルで葬儀や供養をして欲しいのか」を自治体が把握することができるのもポイントです。
残りの人生を有意義に過ごす
終活サポートを利用することで人生の最期について見つめ、残された時間を有意義に生きる努力をするきっかけになります。葬儀や納骨など、死後の問題について元気なうちに解決しておくことで心配事がひとつ減り、毎日を生き生きと過ごすことができるでしょう。
最期を誰かしらに見届けてもらえる安心感から、新しいことにチャレンジする人も出てくるかもしれません。しかし、終活サポートは自治体によって内容が異なります。住んでいる地域ではどんなプランなのか、役所に確認してみましょう。
終活サポートで行われる内容
終活サポートは死後のことを自分で決めたり、もしものことがあったら誰に連絡すればよいか伝えたりと、さまざまな角度から対象者をサポートすることができます。
最近ではエンディングノートを配布する自治体も増え、終活の一部として活用する人も増えてきました。終活サポートで行われることを具体的に確認し、利用するかどうか考えてみましょう。
葬儀・納骨の生前契約のサポート
終活サポートでは、自治体と提携している葬儀業者や事業に協力している葬儀業者を紹介し、相談するサービスを実施しています。低額で葬儀・納骨の生前契約ができるよう情報提供を行い、終活サポート利用者が自分の考えに近いプランを選択できるのが魅力です。
葬儀業者を決めたら、費用を預けそのときが来たら葬儀などを執り行ってもらうシステムになっています。身寄りはいないが、家族と同じお墓に入りたいという人にはうれしいサポートです。
安否の確認
自治体によっては終活サポートの一環として、対象者の「安否確認」として定期的に訪問を行うサービスを実施しています。このサポートは、自治体が行う地域包括システムのひとつで「見守り支援」と呼ばれるものです。
ひとり暮らしの高齢者は、地域とコミュニケーションをとる機会が少なく、孤独を感じやすい状況の中で生活しています。元気に暮らしているかどうか、職員が訪問するだけでもサポート対象者の安らぎになっています。
関係先への連絡
入院・死亡時などなにかあったときに、指定された連絡先に自治体が連絡を取るのも終活サポートです。元気なときに緊急連絡先を何かにまとめておいても、いざというときにどこにあるかわからないと困ってしまいます。
元気なときに連絡してほしい人を自治体に伝えておけば、職員が指定した関係先へ連絡してくれるので安心です。終活サポートを行っている自治体でも、このサポートを実施している場合としていない場合があるので事前に確認しましょう。
エンディングノートの配布
終活サポートをひとつの事業として本格的に取り組んでいる自治体はまだ少数です。しかし、エンディングノートを配布している自治体は増える傾向にあり、終活サポートへの動きも少しずつ広まってきています。
自治体によっては、エンディングノートを配布する数に限りがあるところもあります。エンディングノートが欲しい場合は、在庫状況を事前に電話で問い合わせてから行くようにするとよいでしょう。
エンディングノートに記載する内容は?
終末期になると、自分を見つめ直すという意味でエンディングノートを手に取る人も多くなります。自分のことはもちろん、遺産、遺品、お墓など死後どうするのかを記載するのが定番です。
自分以外の人が見ても、理解しやすいように心がけるとよいでしょう。エンディングノートには、どのような内容を記載するものなのか基本的なところを紹介します。
自分について
自分の人生を振り返りながら、自分史を書きます。まずは、これまでの人生はどのようなものだったかを書きましょう。続いて生年月日、本籍地、家系図、ライフイベントなど自分のことを書きます。
そして資産、Webサイトなどの個人アカウントのパスワードなど身の回りのことを記入し、分かりやすくまとめるとよいでしょう。次に延命治療を希望するか、入所希望施設など医療や介護についても記しておきます。最後に、葬儀や納骨はどのようにしてほしいか、宗教形態も含め書いておけば問題ありません。
ペット・友人について
ペットを飼っている場合は、世話を引き継ぐ人に向けてペットの基本的な情報を記載します。基本データである名前や種類、生年月日、好き嫌いなどを書き残しましょう。ほかにも、かかりつけの動物病院やアレルギーの有無などを書いておくと、世話を引き継ぐ人も困りません。
親しくしている友人の連絡先も書いておきましょう。入院したときや葬儀に来てほしい人を伝えます。事業を持っている人は、税理士や司法書士といった専門家を書いておくのもおすすめです。
葬儀やお墓について
葬儀や納骨はどうしてほしいのか、詳しく記載します。「葬儀を実施するか」「生前契約してあるか」「費用はどうするか」「葬儀の形式」などエンディングノートに希望を明記しておきましょう。訃報の連絡をしてほしい人のリストも、一緒に書いておくことをおすすめします。
お墓については、お墓がある場所やない場合の希望を記載しましょう。どのように供養してほしいのか、仏壇の希望、希望の年忌法要などもできるだけ詳しく書いておけば、希望に沿った対応をしてもらえる可能性が高くなります。
遺品について
遺品は形見分けをするかどうかを記載します。形見分けをする場合は、遺品をリスト化します。遺品の説明、受理する人の名前、保管場所、譲渡する理由などできるだけ詳しく書き残すことで、トラブルを回避できます。
形見分けは高額なものが多いと、受け取る人同士のトラブルに発展することもあるので慎重に行うようにしましょう。形見を受け取る人数が増えると、公平さを重視することが求められます。
お世話になった人や感謝の気持ちを伝えたい人に対しては、よい品物を分け与えるという人もいます。その場合は、遺品をリスト化するときにほかの人が納得できる理由を記載することが大切です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
終活サポートは、ひとり暮らしの高齢者がこれから増えてくる日本にますます必要となってくるものです。自治体によって取り組み方は異なるので、まずは住んでいる自治体が終活サポートに取り組んでいるかどうか、確認してみるとよいでしょう。葬儀の相談、安否確認を行っている自治体もいくつかあります。
元気なうちに死後の葬儀や納骨について決めておくことで、残された時間を有意義に過ごすことができます。葬儀のことで疑問や不安がありましたら、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
また、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
終活をしないとどうなるの?
身寄りがない場合遺産は誰が相続するの?
家族はいないなかで遺産を残したい人がいるときは?
遺産を寄付したいときはどうしたらいい?
ペットに遺産を残すには?
終活サポートの「死後事務委任」とは?
遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。