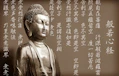「家族葬での供花にお返しは必要なのだろうか」「お返しに適切な品物はあるのだろうか」「お返しの品の相場はいくらなのか」このような疑問をお持ちではないでしょうか。
家族葬での供花のお返しは特に決まりがないため、どうすればいいのか分からない方も多いです。
そこで本記事では、家族葬における供花のお返しについて徹底解説しました。この記事を読むことで、お返しに関するあらゆる疑問が解決できるようになっています。ぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・供花のお返しは必須ではないが、感謝の気持ちとしてお礼状と共に品物を送るとよい
・供花のお返しで適切な品物は、消え物(お茶、コーヒー、お菓子など)がおすすめ
・相場は頂いた供花の3分の1から半額程度で、香典と供花を両方頂いた場合は合算した金額を基準にする
こんな人におすすめ
家族葬で供花を頂いた方
家族葬での供花にお返しが必要か悩まれている方
供花のお返しで適切な品物の例を知りたい方
家族葬での供花でお返しは必要?
家族葬での供花に対して、お返しは必要でしょうか。この点に関しては、いくつかの考え方があります。
・供花にお返しは不要で、お礼状をのみ送ればよい
・供花は香典とは違い、お供えの一種なのでお返しが不要
・余程高額でない限りはお返し不要
などです。
実は供花のお返しに関しては、明確な規定が存在しません。そのため、どのようにすべきか迷う方も多いところでしょう。
しかし、一部の説にある「何もお返しをしない」というのは、あまりおすすめしません。返礼不要の記載がない限りは、何かささいな品でもよいので、お礼状と合わせて送ると相手にお礼の気持ちがより一層伝わります。
また、葬儀に参列できない代わりとして、供花を送る方もいます。そのような心配りに対して「何か少しでもお返しを」と思う気持ちは自然なことです。
故人や遺族に対する心遣いに対しては、お礼状とちょっとしたものでよいので、感謝の気持ちとして品物をお送りするとよいでしょう。
供花のお返しで適切な品物とは
基本的に、供花のお返しの品は法事のお返しや香典返しと同様に考えて問題ありません。
一般的には「消え物」といい、消費できて形に残らない以下のようなものがおすすめです。
お茶
コーヒー
お菓子
海苔
そば
うどん
そうめん
入浴剤
洗剤
消え物が良いとされているのは「不祝儀を後に残さないように」という考え方や「悲しみや不幸を消す・洗い流す」などの考え方に基づくと言われているからです。
また、消え物ではありませんが、タオルもお返しの品物としてよく選ばれています。タオルには「不幸を拭い去る」「悲しみを覆い、包み込む」などの意味があると考えられているからです。
<関連記事>
葬儀での香典返しのマナーは?金額相場・品物・香典返しなしの場合などを解説
小さなお葬式で葬儀場をさがす
供花のお返しの相場はいくら?
供花のお返しの品を送る場合、いくらぐらいの品物をお返しすれば良いのでしょうか。こちらに関しては明確な定義は無く、地域や親族の慣習などによって様々です。
一つの目安としては、いただいた供花の3分の1から半額程度と考えておけばよいでしょう。一般的な香典返しと同様の金額です。
ちなみに、親族や身内からの供花へのお返しは、上記で挙げた相場より多少低くとも失礼にはあたりません。
また、香典と供花を両方いただくこともありますが、この場合は二つを合算した金額を基準にお返しの品物を選びます。それぞれに対して別々にお返しを用意する必要はないでしょう。
お返しの適切なタイミングは?
供花のお返しは、いつお渡しするのが適切なのでしょうか。
供花のお返しに適切な品物や価格の目安があるように、実は贈るのにも適切なタイミングが存在します。
知らずに贈ってしまうと、相手に失礼な印象を与えてしまい兼ねません。しっかりと事前に確認しておきましょう。ここからは2つのケース別に、お返しの適切なタイミングを紹介します。
1. 香典と供花の両方をいただいた場合
香典と一緒に供花もいただいた場合は、香典返しと同様のタイミングでお返しをするのが一般的です。香典返しに関しては、従来通り後日返す場合や、葬儀当日にお返しする場合があります。
いただいた香典・供花が高価であった場合や、参列せずに香典と供花をいただいた場合は、必ず後日お返しをする必要があります。
このような場合、香典返しは四十九日が明けてからお贈りします。そのタイミングで香典と供花を併せた分のお返しの品物と、お礼状を添えてお贈りすると良いでしょう。
2. 供花だけをいただいた場合
供花だけをいただいた際には、四十九日明けにお返しの品物と、お礼状を添えてお贈りするとよいでしょう。
ただし「返礼不要」と明確に伝えられていた場合は、お返しの品物をお贈りしません。この場合はお礼状をお送りしましょう。お礼状を送るタイミングは、四十九日前であっても問題はありません。
もし何の音沙汰もなく、お礼状も届かなければ、相手に対して失礼な印象を与えてしまいます。
また、葬儀に参列できずに供花だけ送って下さった方には「供花がきちんと届いているのだろうか」と心配をかけてしまうかもしれません。
感謝の気持ちを伝えるため、相手を不安にさせないためにも、お礼状はできる限り早めに送るのが賢明です。送るタイミングは、葬儀から1週間ほど経ってからが良いでしょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
適切なお返しの仕方とは
お返しの品は、ただ単に送ればいいというものではありません。品物の選び方や送るタイミング以外にも、気をつけるべき点がいくつかあります。
ここからは、適切なお返しの仕方について紹介します。供花は故人に対する弔慰が込められた、大切な贈り物です。お返しにあたっては、失礼のないようにマナーをしっかりと確認しておきましょう。
1. お返しは「のし」に包む
供花のお返しの品物は、必ずのしで包みましょう。のしには「外のし」と「内のし」があります。供花のお返しの場合は、弔事に関するものなので「控えめに」という意味で内のしをかけるのが一般的です。
また、四十九日明けに宅配で送ることを考えても、のし紙が破れたりしないという観点からも内のしが適切です。
のしの表書きは、一般的に「志」と書きます。ただし、地域や宗教・宗派によって違う場合もあるため、不安な場合は事前に確認しておき、適切な表記で記載するようにしましょう。
水引に関しては「黒白結びきり」を使うのが一般的です。また、関西地方や一部地域では「黄白結びきり」が使われることもあるようです。
2. 会社へお返しする場合の宛名は?
会社から供花をいただき、お返しをする場合の宛名は、会社名もしくは会社名と代表者名で記載しましょう。個別に分けてお返しする必要はありません。
また、故人が所属していた部署単位で供花をいただいた場合には、部署名を記載しましょう。故人が生前最も関わりの深かった方が多くいらっしゃる部署へのお礼は、丁寧に心を込めて行いましょう。
会社からの供花に関してはお返しが必要ないという考えもありますが、感謝の気持ちを示す上でも、お返しは用意した方がよいでしょう。
3. お返しにはお礼状を添える
供花のお返しの際には、お返しの品物だけではなく、お礼状も添えるとより丁寧です。また、お礼状を貰うことで、遺族が供花をきちんと受け取ったことや、葬儀が無事に終わったことの報告にもなります。
ただ単に品物を贈るだけでは、遺族の思いが伝わるとは限りません。感謝の思いを文章に記すことによって、遺族からの感謝の気持ちがより伝わります。
お礼状は忘れないように、お返しの品に添えて贈りましょう。
<関連記事>
葬儀後のお礼はどうしたらいいの?知っておきたいお礼のマナーを徹底解説
供花のお返しに添えるお礼状の適切な書き方とは
供花への感謝の気持ちを示すために送られるお礼状ですが、適切な書き方はあるのでしょうか。実は、お礼状にはいくつかの押さえておきたいポイントや、注意点があります。
ここからは、供花のお返しに添えるお礼状の適切な書き方を紹介します。葬儀における独特の注意点もありますので、しっかりと確認しておきましょう。
1. お礼状に書くべき内容
お礼状にはいくつか書くべき内容があります。代表的なものは以下のような内容です。
1. 供花をいただいたことに対しての感謝の意
2. 供花を受け取り、霊前に飾らせていただいたことの報告
3.「略儀ながら…」などの言葉と挨拶
お礼状は、遺族の感謝の意を伝えると同時に、供花を受け取り、滞りなく葬儀が終了したことを報告するものでもあります。伝えるべき内容を簡潔にまとめ、漏れのないように書きましょう。
また本来であれば、もっとも適切なお礼の伝え方は直接お会いして伝えることです。しかし、現実問題として葬儀後に一人一人と直接お会いし、お礼を伝えることは難しいでしょう。
そこで「本来であれば、直接お会いしてお礼を申し上げたいのですが」という気持ちを表すことが大切です。お礼状の最後にて「略儀にて失礼ながら謹んでご挨拶申し上げます」等の一文を添えるのと、気持ちをうまく伝えられます。
2. お礼状の例文
上記で紹介した、お礼状に書くべき内容を踏まえて、お礼状を送る場合には以下のような例文を参考にしてください。
拝啓
この度は故〇〇の葬儀に際しまして 立派なご供花を賜り 誠にありがとうございました
謹んでお受けし霊前に飾らせていただきました
故人もさぞ喜んでいるかと存じます
お蔭をもちまして 葬儀を無事終えることができました
本来であればお伺いして 直接お礼申し上げるところではございますが
略儀ながら書中をもちまして お礼のご挨拶を申し上げます
敬具
令和〇〇年◯月
喪主〇〇
上記の例文は一例です。お礼状を送る相手との関係性によって、挨拶の言葉などは様々に変化しますので「誰に対して送るのか」をしっかり意識した上で書き進めましょう。
3. お礼状を書く際の注意点
お礼状には以下のようなポイントや注意点があります。
1.「拝啓・敬具」を書く
2. 句読点をつけない
3. 縦書きで書く
4.「忌み言葉」を使わない
拝啓や敬具に関しては、供花のお礼状には不要という考え方もあるようですが、お礼状は相手を敬って出すものなので「拝啓・敬具」は書くことをおすすめします。
また、葬儀におけるお礼状の最も特徴的な点のひとつとして「句読点をつけない」ことが挙げられます。
この理由には諸説ありますが、一部を取り上げると「葬儀が滞りなく流れるように」もしくは「葬儀がつつがなく終わった」という意味から、文章の切れ目となる句読点を使用しなくなった、という説もあります。
横書きか縦書きかについては、気になるところではありますが、一般的には縦書きがよいと言われています。
最後に、葬儀における特徴的な注意点の一つ「忌み言葉」を使用しないように気をつけましょう。忌み言葉とは、葬儀の場においては相応しくなく避けた方が良いとされている言葉です。
例えば、死や苦痛を連想させる「4」や「9」などの数字、「重ね重ね」「たびたび」などの繰り返す重ね言葉があります。知らずに使ってしまった場合でも、後々トラブルになる可能性があるので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
<関連記事>
葬儀に出席する際に覚えておきたい忌み言葉の言い換え
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
家族葬での供花へのお返しは、故人に対する弔慰への感謝の気持ちとして、何かささいなものでもいいので用意するのがおすすめです。
贈る物は消費できる「消え物」が良いでしょう。相場は香典返しと同様に、いただいた供花の金額の3分の1~半額程で用意すれば問題ありません。
小さなお葬式では、家族葬に関する様々な知識やノウハウを備えたスタッフが在籍しております。24時間365日、ご質問にお答えできる体制を整えておりますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



香典の郵送は、現金を不祝儀袋に入れ、現金書留用の封筒でなるべく早く送ります。ホゥ。