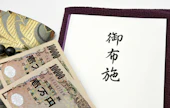無事に葬儀が終われば、ちょっと一息つきたいところです。ですが、会葬してくれた方や手伝ってくれた方への感謝の気持ちを表す「お礼状」の作成をしなければなりません。とはいっても、初めてのことでどのようにすれば良いのか分からないという人もいるかもしれません。
葬儀が終わった後のお礼には知っておくべきことがいくつかあり、それらをしっかりと把握しておく必要があります。そこで今回は、お礼のマナーについて徹底解説していきます。この記事を読めば、葬儀が終わった後のお礼に関する知識を身に付けることができます。
<この記事の要点>
・お礼状は手紙で送るのがもっとも丁寧
・お礼状は忌明けに送るのが一般的
・お礼状に時候の挨拶は不要で、忌み言葉や重ね言葉、句読点も使用しない
こんな人におすすめ
葬儀のお礼状の送り方を知りたい方
お礼状に書く内容を知りたい方
対象者別のお礼状の書き方が知りたい方
葬儀を終えたらお礼状を送ろう
そもそも、お礼とはどのような意味を持つものなのでしょうか。会葬者にはその場で返礼品とともに「会葬礼状」を手渡すのが一般的です。会葬礼状とは、葬儀(または通夜)の会葬者にお礼状としてお出しするものです。 葬儀当日に会葬者にお渡しするものであり、忌明けの頃に香典返しに添えて送る「忌明けの挨拶状」とは別ものとなります
高額の香典をいただいた人や葬儀でお世話になった人に対して、葬儀後にも「お礼状」を送るとより丁寧です。また、会葬していなくても香典や弔電、お供え物を送っていただいた場合に、お礼の気持ちを示すものでもあります。
葬儀のお礼状は、葬儀が終わった後にすぐ送るものではありません。少し落ち着いて、四十九日を過ぎてから送るのが良いとされています。葬儀後バタバタするのはあまり良いことではありませんので、一息ついてから改めて葬儀の際の感謝の気持ちを伝えるためにお礼状を送りましょう。
お礼状は手紙で送るのがベスト
葬儀が終わった後に送るお礼状に関しては、手紙にしたためて送るのがマナーです。メールやハガキのお礼状は略式にあたるため、失礼だと感じる人も少なくありません。そのため、本来であればNG行為にあたることは理解しておきましょう。
ただし、例外として親しい間柄の友人などであればメールやハガキでのお礼も認められつつあります。とはいっても、文面はくだけた口調にするのではなく、最低限のマナーを守りながらお礼状を作成することが大切です。
お礼状を送るタイミング
葬儀が終わり、急いでお礼状の作成に取り掛かる人もいるのではないでしょうか。たしかに参列された一人ひとりに対して丁寧に手書きで書こうとすれば、葬儀が終わったタイミングから書き始めた方が良いかもしれません。
しかし、葬儀後は時間的にも精神的にも遺族の負担が増える一方です。そのため、出す相手や数が多いときは印刷しても構いません。葬儀のお礼状に関しては、葬儀後すぐに送るのではなく、四十九日の忌明けに出すのが一般的です。
誰にお礼状を送るのかをリストアップしよう
いざお礼状を出そうと思っても、誰に出すべきなのかが分からななくなってしまうことも少なくありません。葬儀後は故人を失った悲しみに支配されてしまうため、どうしてもヌケ漏れがでてしまい、「〇〇さんが抜けている」と後になって気づくこともあります。
そのような送り忘れがないよう、参列者や僧侶・神主、葬儀社などお礼状を送る人をリストアップしておくことをおすすめします。葬儀の準備などを手伝ってもらった場合は、知人や友人、親類など、すべての人を書き留めておきましょう。
お礼状に書くべき内容とは
一口にお礼状といっても、何を書いたら良いのか全くわからないという人も多いでしょう。葬儀の喪主になる機会はそんなに多くありません。ですから、初めてお礼状を書く人がほとんどです。お礼状には長々とかしこまった文章を書く必要はありません。では、どのような書き方が正しいのかをご紹介します。
お礼の言葉
故人の会葬してくださった方々は、ご多忙の中で時間をつくってくれています。また、お供え物やご香典をいただくこともあるでしょう。このような気持ちに対するお礼の言葉を添えることが大切です。わざわざ遠くからからお越しいただいた方に関しては、直接お礼をお伝えすることが困難な場合もありますので、手書きで感謝の意を伝えると良いでしょう。
故人の名前・戒名(法名)
誰の葬儀に対するお礼状なのかが分かるようにしなければいけません。そのため、お礼状の最初には故人の名前を書いておくのが一般的です。俗名なので、「亡父」「亡母」「亡祖父」「亡祖母」「故 〇〇」といった書き方で構いません。また、戒名(法名)が付けられている場合は、故人の名前と合わせて戒名も記載しておくと良いでしょう。
書面での挨拶についてのお断り
本来であれば、会葬してくださった方や香典やお供え物をいただいた方に対して直接お礼を言うのがベストです。しかし、参列者が多いなど、書面での挨拶のみとなってしまうこともあるかもしれません。特に遠方からお越しいただいた方にはお礼状のみで済ませることがほとんどですので、その旨のお断りをしっかりと記載しておきましょう。
法要日
お礼状にはいつのものであるのかを記載する必要があります。ただし、法要日に関しては参列された誰もが認識していることでもあるため、省略することも少なくありません。どの内容についても共通して言えることですが、法要日などの間違いはマナーを逸脱しています。お礼状を送る前に書き間違いがないか、しっかりと確認しておきましょう。
その他(香典返しの品を送ることについてのお断りなど)
本来、香典返しは四十九日を過ぎた後に送るのが一般的です。そのため、現在ではお礼状と一緒に郵送することになります。また、最近では葬儀当日に持ち帰っていただくことも少なくありません。ただし、香典の金額に応じて後日改めて送ることも覚えておきましょう。お礼状には香典返しの品を送ることについてのお断りなども記載しておきます。
お礼状の文例とは
では、具体的にお礼状とはどのような文面で書けば良いのでしょうか。遺族が出すお礼状には、会葬くださった方だけでなく、故人が生前お世話になった方などへ送るものなど、いろいろな種類があります。それぞれどのような内容にするのがマナーとされているのか、文例をご紹介しながらポイントを解説します。
葬儀委員長をお願いした方へのお礼状
葬儀委員長とは、遺族以外で葬儀をサポートしてくださる葬儀委員をまとめる最高責任者のような役割を担います。近年の一般的な葬儀では、葬儀の進行などを葬儀社のスタッフが行うことがほとんどなため、葬儀委員長を選出する必要はありません。
しかし、場合によっては、葬儀委員長が必要になるケースもあります。ご多忙の中、葬儀委員長を引き受けてくださっているので、丁寧にお礼をしましょう。
<お礼状の記載例>
謹啓
先般 故〇〇〇〇の葬儀に際しましては 御多忙中にもかかわらず
葬儀委員長をお引き受けいただき 誠にありがとうございました
大切なお時間をお割きくださり 立派な葬儀を執り行っていただき
亡父もさぞかし喜んでいることと思います
遺族一同深く感謝申し上げます
今後も変わらぬご指導ご鞭撻ご厚誼を賜りますようお願い申し上げ
略儀ながら書中をもちまして御礼の御挨拶を申し上げます
敬白
令和〇年〇月〇日
〇〇市〇〇区
喪主 〇〇〇〇
親族一同
生前にお世話になった方へのお礼状
会葬してくださった方の中には、故人ととても親しくしてくれた方もいるでしょう。急な葬儀にも関わらず出席していただいたことに対するお礼はもちろんのこと、故人がお世話になったことに対してのお礼も伝えることが大切です。
また、葬儀当日も遺族に対して配慮をしてくださることもあります。遺族との面識があるなしに関係なく、故人が生前お世話になった方へのお礼状もしっかりと送りましょう。
<お礼状の記載例>
謹啓
先般 故〇〇〇〇の葬儀に際しましては
御多忙中にもかかわらず会葬をいただき 誠にありがとうございます
また生前父が何かとお世話になりましたこと 心から厚く御礼申し上げます
お陰様で父も心置きなく旅立つことができたと思います
貴兄におかれましてもくれぐれも御身大切になされ、末永くご健勝にお過ごしくださいますよう 心からお祈りいたしております
略儀ながら書中をもちまして御礼の御挨拶を申し上げます
敬白
令和〇年〇月〇日
〇〇市〇〇区
喪主 〇〇〇〇
親族一同
主治医や病院へのお礼状
最後まで病院や自宅療養にて懸命に生き続けたのかもしれません。そのためには、故人一人の力だけでなく、主治医や病院の関係者のサポートがあったからではないでしょうか。最後に自宅で息を引き取った場合でも、病院へのお礼状は欠かせません。
故人に対して決死のサポートをしてくださったことに対する感謝の気持ちを伝えることが大切です。また、現在の心境についても触れてみると良いでしょう。
<お礼状の記載例>
〇〇先生をはじめ病院の皆々様には 故〇〇〇〇の入院中 何かとお世話になりました
先般 亡父の葬儀も終わり 家族一同ようやく少しは落ち着きを取り戻したところです
亡き父入院中は いろいろと手を尽くしていいただいたにも関わらず
十分な御礼を申し上げる余裕もなく大変失礼いたしました
思えば亡父も先生の治療と皆様の看護を受けることができ幸いだったと存じます
本来ならお目にかかり御礼を申し上げるところではございますが
書中をもちまして御礼申し上げます 遺族一同
お礼状の注意点とは
お礼状には基本的に上記でご紹介した内容を文章にすれば問題ありません。しかし、ビジネス文書などと同様に、お礼状にもいくつかのマナーが存在します。それらを守っていなければ、相手にも失礼に当たることになるでしょう。間違ったお礼状を送ってしまわないようにするためにも、お礼状の注意点についてご紹介します。
時候の挨拶は不要
ビジネスレターを送る場合など、頭語の後に季節や天候に応じた心情や季節感を表す「時候の挨拶」を書くことがマナーとされています。また「拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。」といったように、安否を尋ねる挨拶とひとまとめにすることもあります。
しかし、葬儀後に送るお礼状において、時候の挨拶は不要です。一般的に手紙となると、頭語・結語である「拝啓」や「敬具」を書くことがあります。しかし、お礼状では書くこともありますが、両方書かずに略儀で済ませることも少なくありません。
忌み言葉・重ね言葉を使用しない
結婚式や出産祝いなどで忌み言葉・重ね言葉は「縁起が悪い」と理解している人もいるでしょう。しかし、葬儀が終わった後に出すお礼状にもそれらの言葉を添えることは相手の気持ちを害してしまうことになりますので、言葉選びには十分に注意してください。
死や不幸を連想させるような言葉や重ね言葉は避けるのが無難です。
死、死亡、四(=死)、九(=苦)、度々、ますます、重ねがさね、返す返す、次々、続いて、引き続き、近々、繰り返す、再び、追って、くれぐれも、まだまだ、いよいよ、ときどき、しばしば、さらに、生きる、生存
また、上記以外にも、楽しい、喜ぶ、嬉しいといったような、悲しみの場面には不適切とされる言葉も使わないようにするのがマナーとされています。
句読点を使用しない
結婚や出産などのお祝い事の手紙には「区切りや終わりがないよう」などの意味合いから、句読点を使用しないのが一般的です。このような慶事においては、幸せが切れないようにするためというのがひとつの大きな理由とされています。
また、葬儀が終わった後に出すお礼状や喪中はがきなど、弔事に関連する文書にも句読点を使用しないのが通例化しています。ただし、お礼状などに句読点を付けないことが正しいというわけではありませんので、句読点をつけていてもマナー違反ではありません。
葬儀を知らせていない人へは出さなくてよい
一般的に、故人と親しい間柄であった人には葬儀の案内をすることとなります。しかし、葬儀を知らせていない人もいるかもしれません。このような場合にお礼状を出すのは、相手に気を使わせてしまうだけなので、基本的には出さない方が無難です。
ただし、亡くなったことを葬儀が終わった後に知らせた方が良い場合もあります。参列されていないにも関わらずお礼状という形で出すのは失礼に当たりますので、葬儀の案内を出さなかった理由も添えると良いでしょう。
宗教・宗派に合った表現を使用する
お礼状では宗教・宗派に応じて正しい表現をしなければいけません。たとえば、「忌明法要」や「四十九日法要」といった言葉は、仏教で使用される言葉です。また、同じ仏教でも西日本の地域では「満中陰法要」などと呼ぶところもあります。
| 宗教 | 四十九日法要に相当する名称 |
| 仏教 | 四十九日法要、忌明法要、満中陰法要(西日本) |
| 神道・天理教 | 五十日祭 |
| キリスト教 | 追悼ミサ(カトリック)、記念式、記念集会(プロテスタント) |
葬儀後には挨拶回りも行うとベター
葬儀には、非常にたくさんの方に参列していただくことになります。その一人ひとりに対して直接お礼を伝えるのは難しいかもしれませんが、直接会うことが可能な人には葬儀が終わった後に挨拶回りも行っておくとより丁寧です。では、どのような人に「いつ」「どこで」挨拶回りを行えば良いのかについてご紹介します。
お寺・葬儀会社への挨拶
葬儀当日は、やるべきことがたくさんあるため、きちんとお礼ができないまま終わってしまうことも少なくありません。しかし、当日にお世話になったお寺や葬儀会社へは、後日改めて「挨拶」という名目で伺ってもいいでしょう。
近隣住民への挨拶
近隣に住んでいる方で会葬してくださったり、香典やお供え物をいただいたりした方に対しては簡単な挨拶回りをしておくと良いでしょう。葬儀を終えた翌日、もしくは遅くてもその週のうちには玄関先まで出向きます。
このような近隣住民への挨拶回りでは、難しい言葉や長々とした言葉を並べる必要はありません。玄関先に直接出向くことで相手の時間を奪っているということも考慮しながら、感謝の気持ちを簡潔に伝えることが大切です。
勤め先や故人の会社関係への挨拶
自分の勤務先や仕事関係の人の中に会葬者がいた場合の挨拶も忘れずに行いましょう。葬儀が一段落ついて出社したタイミングで伝えることが大切です。この場合も、難しい言葉を述べるのではなく、簡潔に感謝の気持ちを伝えます。
また、故人が勤めていた会社やその関係者への挨拶も行います。遺族で面識がないということもあるかもしれませんが、誰にお礼をすべきなのか確認しておくことも必要です。どのような関係性であるのかを調べた上で、お礼状も出しましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
いざ葬儀が終わった後にお礼状を送ろうと思っても、誰に出せば良いのか分からなくなることもあります。時間的にも精神的にも余裕がなくなっていますので、誰に贈るべきなのかをしっかりとリストアップするだけでなく、家族で話し合うことが大切です。
この記事を参考に、会葬してくださった方やお世話になった方にきちんとお礼の気持ちを伝えましょう。
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
会葬礼状とはなんのこと?
葬儀のお礼状はいつどうやって送ればいいの?
お礼状は誰に送ればいいの?
お礼状には何を書けばいいの?
お礼状を書く際の注意点は?
お礼状を送る以外にすべきことはあるの?

葬儀費用が捻出できないときは「葬祭扶助」を活用することで補助金が受け取れる場合があります。ホゥ。