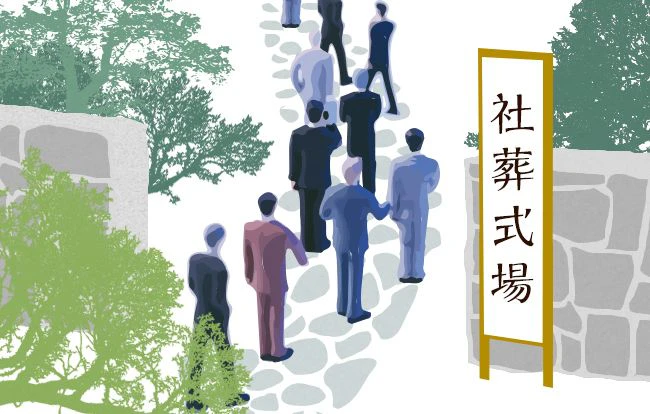葬儀の準備をしていて、祭壇選びに困った経験がある方もいるのではないでしょうか。通常、祭壇は亡くなってから葬儀までの間に決めなければなりません。種類が多く、故人の意向や宗教ごとの特性もあるため、短期間で選ぶのは難しいでしょう。
そこで今回は、祭壇の選び方や費用の目安といった基本情報を紹介します。特徴や重要なポイントを理解すれば、祭壇選びに困らずに済むでしょう。
<この記事の要点>
・祭壇とは故人のためのお供え物を置く台のことで、故人を弔うために使用する
・仏教では白木祭壇を使用するのが一般的
・祭壇は会場や葬儀の規模に合わせて選び、宗教や故人の好みを考慮する
こんな人におすすめ
祭壇とはどのようなものかを知りたい方
葬儀で使用する祭壇の種類を知りたい方
祭壇選びのポイントを知りたい方
祭壇とはどんなもの?
「祭壇」という言葉は、葬儀を執り行う際に見聞きしたことがある方も多いでしょう。ただし、意味や役割まで理解している方は少ないかもしれません。祭壇にはいくつか種類があり、葬儀で使用するもの以外にも祭壇と呼ぶものがあります。まずは祭壇に関する基礎知識への理解を深めましょう。
祭壇とは何?
祭壇と聞くと、葬儀会場に設置しているものをイメージする方が多いかもしれませんが、葬儀以外で使用する常設の祭壇もあります。それぞれの違いは以下の通りです。
・常設の祭壇:寺院にある御本尊を安置する壇、家庭に置いている仏壇
・仮設の祭壇:葬儀から四十九日まで遺骨を安置するもの
なお、この記事で紹介するのは、葬儀で使用する仮設の祭壇です。
本来の意味と現代の役割
祭壇は亡くなった方のためのお供え物を置く台です。土葬していた当時は埋葬の際に棺を置いて祀り、儀式で使用する物を並べていたといわれています。
現代では物を置くという役割だけでなく、故人を弔うために使用し、故人そのものを表すものにまで発展しました。故人が好むような装飾にしたり、会場の大きさに合わせて見栄えの良いものにしたりするといった個性豊かでオリジナリティあふれる祭壇を使用する方も少なくありません。
【宗教別】葬儀で使用する祭壇の種類
祭壇は葬儀の際に中央の一番目立つところに配置します。遺族が納得できるように、妥協せずしっかりと選びましょう。ただし、宗教による違いが大きいため、注意が必要です。ここでは、祭壇のバリエーションを宗教別に紹介します。
仏教の場合
仏教では白木祭壇を使用するのが一般的です。シンプルな見た目ですが、厳粛な雰囲気を感じられる美しさがあります。また、白木には「汚れがない」「新しい」というイメージがあるため、好まれるのでしょう。
遺影と白い生花がよく目立つ配置で、一番奥の上部の飾りは棺を入れていた輿(こし)をイメージしたデザインです。昔ながらの日本の慣習や伝統を感じられる祭壇といえます。
| 装飾品 | 輿、位牌台、遺影台、供物台、灯籠、生花、葬儀用品 |
神道の場合
神道でも仏教同様に、白木祭壇を使用します。ただし、装飾品には違いがあるため注意しましょう。例えば、鏡と剣、勾玉の3つをセットにした「三種の神器」を飾ります。神道の祭壇飾りの中で最も大きな特徴といえるでしょう。他にも、お供え物や遺影といった葬儀を執り行う際に必要なものは仏教と同じように飾ります。
| 装飾品 | 三種の神器、五色旗、三方、ぼんぼり、霊璽(れいじ)、しめ縄と紙垂 |
キリスト教の場合
キリスト教の場合、教会に常設している祭壇を使用します。遺族が祭壇を用意する必要はありません。祭壇の中央最上部に十字架を飾り、その周りに生花を供えます。両脇にろうそくをともすのもキリスト教式祭壇の特徴です。
ただし、キリスト教にはカトリックとプロテスタントという宗派があり、宗派による違いもあります。悩んだときは教会に相談するのが望ましいでしょう。
| 装飾品 | 十字架、ろうそく、白い花 |
その他の祭壇
宗教にこだわらない独自性にあふれた祭壇もあります。故人の好みや遺族の意向に合わせて選びましょう。
・花祭壇:祭壇にまんべんなく花を飾って彩る祭壇。造花と生花の2種類がある
・モダン祭壇:飾りが少なくシンプルで落ち着いた印象の祭壇
・オリジナル祭壇:故人の趣味や趣向に合わせたものを飾る祭壇
・日蓮正宗祭壇:花の代わりに枯れることのない樒(しきみ)を飾った祭壇
・折衷祭壇:白木祭壇に花祭壇の要素を盛り込んだ飾り付けをした祭壇
・キャンドル祭壇:キャンドルを飾り幻想的な雰囲気を味わえる祭壇
祭壇には厳格な決まりはないため、自由に選べます。また、祭壇を設置しないシンプルな葬儀を執り行うことも可能です。
<関連記事>
花祭壇の花の種類や定番のお花をご紹介! 選び方についても解説
小さなお葬式で葬儀場をさがす
祭壇の費用の目安はいくら?
祭壇を設置する場合、いくらくらいかかるのか気になる方もいるでしょう。祭壇の費用は葬儀の規模によって変わります。故人を供養し表現する祭壇は、費用やデザインに納得できるものを選びましょう。ここでは、3つの葬儀のタイプに分けて、祭壇の費用の目安を紹介します。
一般葬:30万円~80万円
一般的な葬儀の場合、祭壇の費用は30万円~80万円程度が目安で、どのタイプの祭壇でもほぼ同じ金額です。祭壇自体は20万円~30万円ほどですが、人件費や生花料、デザイン料といった費用に数万円から数十万円かかります。
また、葬儀を執り行う際は、祭壇だけでなく式場の利用料や火葬の費用も必要です。小さなお葬式が行った調査では、一般葬にかかる費用総額の全国平均は約191万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)
家族葬:20万円~50万円
気心の知れた家族だけで小規模に執り行うのであれば、祭壇設置にかかる費用の目安は20万円~50万円程度です。一般的な葬儀には100人程度が参列しますが、家族葬は10人~50人程度と少ないため、大きな祭壇にする必要はありません。
家族葬のようなシンプルな葬儀は近年人気が高まっています。小さなお葬式が行った調査では、家族葬にかかる費用総額の全国平均は約110万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)一般葬より費用が抑えられる分、お墓や仏壇に費用をかけてもよいでしょう。
大規模な葬儀:100万円以上
たくさんの人を呼んで盛大な葬儀を執り行う場合、100万円以上かかると考えられます。遠くからでもしっかりと見えるように祭壇が大きくなり、その分飾りも増えるためです。祭壇は30万円~50万円程度ですが、生花をたくさん用意するため、生花料に30万円~100万円程度の費用がかかります。
ただし、費用はあくまで目安です。祭壇は葬儀の顔であると同時に、故人を表すものでもあるため、飾り方や生花の量は遺族の気持ち次第で異なります。祭壇の規模に合わせて金額も変化すると考えましょう。
<関連記事>
最適な祭壇を選ぶために知る、費用内訳と規模に合った選び方
祭壇選びのポイントは2つ
葬儀のとき、一番目立つ場所に設置する祭壇は、飾り方次第で印象を大きく左右します。故人が亡くなってから葬儀まで時間はあまりありません。しかし、葬儀は一度しかできないため、「こうしておけばよかった」と後悔することがないように心を込めて選びましょう。ここでは、祭壇選びのポイントを2つ紹介します。
葬儀の規模を確認する
葬儀の規模が大きい場合、遠くからでも見えるように大きな祭壇を選ぶとよいでしょう。広い会場に小さな祭壇だと寂しい印象になります。大きな祭壇にたくさんの花を飾れば、故人の存在の大きさを表現できるでしょう。また、生前故人が好きだった趣味に合わせたオリジナル祭壇もおすすめです。
一方、家族や限られた友人のみで執り行う葬儀には、大きな祭壇はバランスがよくありません。会場や葬儀の規模に合わせた祭壇を選ぶのがベストです。
宗教や故人の好みを考慮する
祭壇の大きさが決まったら、宗教を重んじるか、故人の意向を尊重するか考えましょう。何を重視するかによって、祭壇の種類や飾り付けは大きく異なります。信仰する宗教で飾り方が決まっていれば問題ありませんが、オリジナル祭壇を用意する場合は遺族が飾りを用意しなければなりません。
また、葬儀社によって用意できる祭壇の種類が異なるため、個性豊かな祭壇にする予定がある方は事前に伝えておく必要があります。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
祭壇にお供えできるものは?
祭壇にはさまざまな飾り付けをしますが、お供え物にも一定のルールやマナーがあります。祭壇を用意するときに必要な知識であるため、まとめて確認しましょう。ここでは、宗教ごとの違いの他、祭壇に飾る遺影について解説します。
仏教の場合
仏教では、五供(ごくう)をお供えします。五供とは、「花」「灯明」「水」「飲食」「香(お線香)」の5つです。飲食は日持ちする食べ物が基本ですが、季節の果物も好まれます。また、故人が好きだったお菓子を供えても問題ありません。一方、生の食べ物や肉・魚といった殺生を連想するものは避けたほうがよいでしょう。
花は四十九日までは白い花を基本とする傾向があります。また、バラのようにとげがある花もお供えしないのが一般的です。
神道の場合
神道の場合、神饌(しんせん)と幣帛(へいはく)をお供えするのがマナーです。神饌とは食べ物で、お菓子、果物、野菜、米、餅、酒、塩、魚、水といったものを指します。また、仏教とは異なり、魚を供えてもマナー違反ではありません。
幣帛とはもともと神饌以外のお供え物を指していましたが、現在はくすんだ赤地の織物のことです。神饌や幣帛を乗せる土台には、白木でできた案を使用します。案の上に三方を置き、最後に神饌と幣帛を飾りましょう。
キリスト教の場合
キリスト教の場合、「供養」という概念がありません。故人の魂は亡くなったら神の元に帰ると考えられています。したがって、お供えについても特に指定はありません。
キリスト教の葬儀にあたる儀式では、親族から贈られた花を祭壇に飾る慣習があります。花の種類は白い百合がほとんどです。百合は聖母マリアの象徴であるためでしょう。また、白いカーネーションや胡蝶蘭も祭壇に飾ることがあります。
祭壇に飾る遺影も用意する
最も目立つ場所に設置する祭壇ですが、その中でも遺影は祭壇の顔で、生前の故人の姿を思い出せる大切なものです。たくさんの参列者が目にするため、慎重に選びましょう。
できるだけ近い日に撮影した写真の中から、故人の人柄が伝わるような写真を選ぶのがポイントです。顔が正面から写っていて、生き生きとした表情のものが望ましいでしょう。写真を引き伸ばし過ぎるとぼやけてしまうため、故人の顔が大きく写っている写真を選ぶのも重要です。
葬儀後に使用する後飾り祭壇とは?
葬儀を終えた後も祭壇は使用します。火葬後に自宅に戻ってきた故人の遺骨を安置するためです。一般的に「後飾り祭壇」と呼びますが、宗教や地域によって呼び方が異なる場合もあるため注意しましょう。ここでは、後飾り祭壇について解説します。
後飾り祭壇とは?
後飾り祭壇は自宅で火葬後の遺骨を安置するための祭壇で、仏教や神道では白木を使用します。葬儀社が用意することがほとんどですが、素材に厳密な決まりはなく、段ボールでも代用可能です。
仏教の場合、二段もしくは三段で、遺影や線香、白木位牌、ろうそくを置きます。神道では「八足の祭壇」を使用するのが基本です。キリスト教は特別な決まりはありませんが、小さな机に白い布をかぶせて、後飾り祭壇の代用とします。
置く向きに注意
後飾り祭壇は簡易的ではありますが、遺骨を安置したり親族や友人がお参りしたりする大切なものです。後飾り祭壇を置くときには、向きに十分注意しましょう。遺族やお参りに来た方が北か西に向かって手を合わせられるように設置します。すでに仏壇がある場合、仏壇のそばに置くとよいでしょう。
飾る期間は四十九日まで
後飾り祭壇を設置する期間は、火葬後から四十九日までです。四十九日の法要で納骨することが多いため、四十九日を過ぎると後飾り祭壇は必要ありません。処分する際にお清めは必要なく、ゴミに出すか、自宅に保管するとよいでしょう。残しておけば、お盆や法要の際に再利用できます。
お供えは何がよい?
後飾り祭壇にお供えするものは、宗教によって異なります。主なお供え物は以下の通りです。
・仏教:ご飯、水、御膳、花、お茶、お菓子
・神道:お神酒、水、洗米
・キリスト教:決まりなし
仏教でお供えするご飯や水、御膳は毎日交換します。花やお菓子は頃合いを見て変えましょう。ただし、同じ仏教でも浄土真宗は水やお茶、御膳をお供えしません。宗派による違いが気になる方は親族や寺院に相談すると安心です。
<関連記事>
【マナー】後飾り祭壇の意味から飾り方や処分方法まで徹底解説
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
祭壇は葬儀用品を置くための台であると同時に故人を表すものであり、大切な意味を持つものです。祭壇の種類は多く、宗教や故人の意向によって飾り方は異なります。選ぶ際は葬儀の規模や費用の目安を参考にしましょう。
葬儀や祭壇についてお困りのことがあれば、小さなお葬式に何でもご相談ください。24時間365日、電話による問い合わせも可能です。知識や経験豊富なスタッフがサポートします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



遺産相続が発生した場合、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ホゥ。