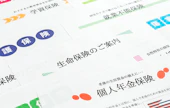20歳の誕生日を迎えると同時に毎月支払う義務が生じるのが、国民年金の保険料です。その後何十年も払い続けるからこそ、年金を受給できる年齢になったら満額を受け取り、余裕のある年金生活を送りたいと思う方も多いのではないでしょうか。
年金を受給する年齢になるまでの間は年金制度の変更点などを定期的に把握し、自分の保険料納付状況も確認しておきましょう。この記事では、年金は満額でどの程度もらえるのか、どうすれば満額を受け取れるのかについて詳しく解説します。
<この記事の要点>
・2024年の国民年金の満額は年間81万6000円、厚生年金は年間276万5796円
・年金を満額受給するためには、20歳から60歳までの40年間の支払期間が必要
・65歳まで国民年金に任意加入することで年金の受給額を増やすことができる
こんな人におすすめ
年金の受給額が気になる方
年金受給額を満額にする、近づけるための対策を知りたい方
年金が受け取れる時期について知りたい方
年金の満額はいくら?平均受給額は?
日本に住む満20歳から満60歳までの成人は、毎月の国民年金保険料を支払う義務があります。2020年4月から2021年3月の保険料は月額1万6,540円です。老後の生活を支える国民年金は、40年間欠かさず払い込むことで満額を受給できます。
自分が将来受け取れる年金額を把握するため、まずは2つの視点に基づいて年金制度の中身を確認しましょう。
満額で受け取れる受給額
日本の公的年金制度は、国民年金(老齢基礎年金)と、これに上乗せする老齢厚生年金の「二階建て」となっています。
2024年の満額は、国民年金が年間81万6000円です。2023年度よりも2万1000円の増額に、厚生年金は276万5796円で2023年度より7万2012円の増額になっています。
会社員、公務員が加入する厚生年金には満額の考え方がなく、受給額は加入期間の長さと賞与を含む月給の平均額(控除前)で決まります。厚生年金のモデル世帯は平均月収43万9,000円で40年間加入した夫婦2人のケースで、満額の国民年金(月額6万5,141円)とあわせた毎月の受給額は22万724円です。
これらを補完する公的年金制度には、満額で月額5,030円の老齢年金生活者支援給付金、1級認定は月額6,275円、2級が月額5,020円の障害年金生活者支援給付金、月額5,020円の遺族年金生活者支援給付金があります。
参考:『日本年金機構』
年金の平均受給額
実際の年金の平均支給額を改めて確認しましょう。厚生労働省がまとめた2018年度の年金事業年報概要によると、厚生年金の平均受給額は月額14万5,865円、国民年金は月額5万5,809円です。
これは受給資格期間が25年以上の平均額です。25年未満の場合、厚生年金は月額6万687円、国民年金は月額1万9,064円となっています。
公的年金への理解をさらに深めるうえで、次の2点について留意しましょう。ひとつは、厚生年金は国民年金も含んでいるため受給額が大きいということ、もうひとつは保険料を払い込んだ月数が多いほど、もらえる年金額も増えるということです。
参考:『厚生労働省 厚生年金保険・国民年金事業年報概要』
年金受給額が満額もらえない理由
国民年金を満額受給するためには、満20歳から満60歳まで40年間、決まった保険料を毎月支払い続けなければなりません。つまり、満額もらえないという事態は未納が発生していた期間があったということです。
保険料支払いの空白期間が生まれやすい状況には「20歳のときはまだ学生で、国民年金の加入手続きをしていなかった」「会社を辞めて厚生年金を脱退した後、国民年金に移行する手続きが遅れた」、あるいは「会社員または公務員の夫(妻)が退職したとき、扶養している60歳未満の妻(夫)が国民年金に移る手続きを忘れた」といったことがあります。
ちなみに、サラリーマンの被扶養配偶者は年金保険料を支払わなくても国民年金を受給できる国民年金の第3号被保険者です。しかし、その夫や妻が厚生年金を脱退したときは、国民年金に第1号被保険者として加入して保険料を納める必要があります。
年金受給額を満額にする、近づけるための対策とは?
国民年金は10年以上の保険料支払いで受給資格を得ることができますが、払い込んだ額に比例した年金額しか受給できません。10年程度の納付期間では、老後の暮らしに最低限必要な年金額さえも受け取るのは難しいでしょう。
しかし、できるだけ満額に近づける方法があります。4つの方法をご紹介するので、保険料の納付に空白期間がある人は、ぜひ参考にしてください。
65歳まで国民年金に任意加入する
保険料支払いの条件を満たさなければ、国民年金の受給額は減ってしまいます。しかし、60歳から65歳の間に「任意加入制度」を利用すれば、年金の受給額を増やすことが可能です。
この制度のメリットは、65歳からの年金受給額が増えることだけではありません。任意加入期間中に障害の原因となるけがや病気をした場合は障害基礎年金を、生計を維持していた加入者が亡くなった場合は遺族基礎年金を受け取ることができます。さらに、納入した保険料はすべて社会保険料控除の対象になるので節税が可能です。
参考:『日本年金機構 あなたも国民年金を増やしませんか?』
保険料の追納をする
国民年金保険料の「全額免除」「一部免除」「猶予」を申請し、承認を受けると保険料の支払いは免除か猶予になりますが、承認期間をすぎてもそのままにしておくと、受け取れる年金額は全額納付した場合より少なくなってしまいます。
しかし「追納」制度を利用すれば、国民年金の受取額を取り戻すことが可能です。追納は年金保険料の支払い免除分を後から納付できる制度で、過去10年間までさかのぼって古い順に納付できます。
この制度も任意加入制度と同じく社会保険料控除で節税できるので、しっかりチェックしておきましょう。
参考:『日本年金機構 国民年金保険料の追納制度』
付加年金の保険料(付加保険料)の支払いをする
国民年金の付加保険料とは、決められた保険料に月400円を上乗せして納める保険料を指します。比較的簡単に年金受給額を増やせる方法です。
受け取れる付加年金は「200円×付加保険料を納付した月数」で計算します。付加保険料を1年間納めた場合、保険料は400円×12か月で4,800円です。1年4,800円の付加保険料支払いで年金受給を受ける際には毎年2,400円が上乗せされます。ただし、対象は国民年金第1号被保険者か任意加入被保険者(65歳以上は対象外)です。
参考:『日本年金機構 付加保険料の納付のご案内』
滞納している保険料の支払いをする
滞納した国民年金保険料を後で支払うことができるのは、過去2年間までです。この期間に正当な理由なく支払っていない保険料があれば、期限が過ぎてしまわないうちに納付しておくのが賢明でしょう。
数年前までは特例で「10年後納制度」「5年後納制度」がありましたが、それぞれ2015年9月30日と2018年9月30日に終了しました。2020年時点では、過去2年以上前の滞納分は支払えないことになっています。
参考:『日本年金機構 国民年金保険料の後納制度(平成30年9月30日をもって終了しました。)』
年金が受け取れる時期
年金を受け取れる時期は、国が数年ごとに行う年金制度の見直しで変わることがあります。高齢者数が増え続けている中、受給開始年齢が上がることはあっても下がることはないでしょう。
過去には、国民年金と厚生年金の受給開始年齢が異なることもありました。ここでは2020年現在の年金を受給できる時期を詳しく確認します。
国民年金の場合
国民年金の保険料を納めると、老齢基礎年金が受け取れます。支給が始まるのは原則65歳です。年金の繰り上げ受給は60歳から始めることができますが、毎月の受取額は減るので注意しましょう。
年金受給額の全部を繰り上げた場合、請求月から65歳になる前月までの月数×0.5%の減額が適用となります。たとえば64歳のときに全額繰り上げを申請すると、12か月×0.5%となるので、受給できるのは本来もらえる額から6%分を差し引いた額ということになります。
反対に、受給開始年齢を66歳から70歳までの間で選ぶこともできます。年金の受け取り開始を遅らせた分、支給額が増える制度で、1か月遅らせるごとに0.7%ずつプラスとなる計算です。
参考:『日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額』
厚生年金の場合
厚生年金の老齢厚生年金は、以前は60歳からの受給でした。2020年時点では、国民年金と同じく原則65歳からとなっています。
国は受給開始年齢の引き上げをスムーズにしようと、60歳から65歳までの移行を段階的に進めてきました。男性は1941年4月2日生まれから1961年4月1日生まれまで、女性は1946年4月2日生まれから1966年4月1日生まれまでが受給開始年齢の移行世代にあたります。
移行世代から完全に外れるのは1961年4月2日生まれ以降の男性と、1966年4月2日生まれ以降の女性のため、2020年時点はまだ移行期間中です。
移行期間中は「特別支給」の制度があります。国民年金の受給資格期間(10年間)を満たした上で厚生年金の加入期間が1年以上あれば、対象者は段階的に60歳から厚生年金の特別支給を受け取ることができる制度です。
参考:『日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額』
『日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金について』
公的年金が満額でなくても補える年金がある?
満額、もしくは満額に近い公的年金をもらえたとしても、公的年金だけでは安心できないと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは、公的年金とは別に老後の生活資金を確保するのに役立つ、任意加入の年金システムを2種類紹介します。
個人年金保険に加入する
個人年金保険は、民間の保険会社による年金システムです。主な加入目的は、公的年金とは別の年金を受け取ることで、老後の生活費などを補うということにあります。
個人年金保険のメリットは、条件を満たせば所得控除を受けることができること、利息が少ない預貯金よりも老後資金を増やせることです。注意する点としては、途中解約すると元本割れすること、インフレになると価値が下がってしまうことがあります。リスクも考慮し、無理のない範囲で掛け金を収めるのがよいでしょう。
個人年金には大きく分けて、「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3つがあり、主に被保険者が死亡した場合の条件によって保険受取内容が異なっています。自分の生活環境にあったサービスを選ぶようにしましょう。
iDeCoで資産運用する
iDeCoは「イデコ」と読み、個人型の確定拠出年金を意味します。確定拠出年金法に基づいて運用する私的年金で、2020年現在で約160の金融機関が商品を提供しています。
月1回ずつ掛け金を拠出し、自分で資産を運用する年金です。主に預貯金や保険商品などの「元本確保型商品」と、投資信託の「元本変動型商品」から選べます。「元本変動型商品」は市場の状況に左右されるので、元本割れの恐れがあることも理解しておきましょう。
基本的には、60歳まで掛け金を拠出して運用を続けます。60歳をすぎれば年金として資産を引き出せますが、その額は運用成績によるので、1人ずつ受取額が異なるのが特徴です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
少子高齢化が進み、年金受給額が少なくなる見通しの中、十分な年金を受け取るためには保険料払い込みの空白期間をなくしておくことが大切です。満額か、それに近い金額を手にできなければ、老後の暮らしが不安定になりかねません。
任意加入制度を利用するなどの公的年金の受給額を増やす方法でも足りなければ、保険会社の年金保険の利用も検討してみましょう。自分ができそうなことを調べ、将来のために少しずつでも準備しておけると安心です。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
年金の満額はいくら?
年金受給額が満額もらえない場合はある?
年金受給額を満額にする、近づけるための対策はある?
年金を受け取れる時期は?
御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。