故人が所有していた土地を相続する際には、税金など複数の手続きを進める必要があります。法律の専門的な規定が関わる部分でもあるため、土地の相続について不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続が決定してから実践したい手続きの種類について詳しく解説します。特例もあわせて理解しておくと、臨機応変に対応できるでしょう。相続税の計算方法や売却方法などもご紹介します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・土地相続の手続きは、相続人同士の話し合い後に相続登記の書類や費用を用意する必要がある
・相続税は財産から基礎控除を差し引いた額に相続税率をかけて算出する
・固定資産税の納税義務は、相続が発生した翌年から開始される
こんな人におすすめ
土地の相続手続きについて知りたい方
土地の相続税について知りたい方
相続した土地の売却や分割について知りたい方
土地を相続するにはどんな手続きが必要?
土地の相続が決まった後は、相続人と十分に話し合って適切な手続きを進めましょう。評価額を調べる方法や、相続登記の手続きに関する知識も必要です。手続きが滞ると税金面の問題も発生する可能性があるため、事前知識として蓄えておきましょう。2つの項目に分けて、相続に関する基本的な手続きをご紹介します。
まずは相続人同士で話し合い
初期段階で明確にしておきたいのは、「誰が土地を相続するのか」という内容です。遺産分割協議を実施し、故人から特定の相続人に名義を変更します。協議の形式にルールはないため、親族間で電話やメールを交わすかたちでも問題ありません。
話し合いが成立した後は、「遺産分割協議書」を作成して署名を行います。相続人全員が内容に合意している事実を、法的に証明するための書類です。協議書には、「登記事項証明書」の内容も反映する必要があります。
相続する土地の評価額を調べる際は、路線価が公開されている「地下マップ」を活用するといいでしょう。
相続登記の必要書類や費用を用意
相続登記の手続きを始める際には、申請書をはじめ複数の書類が必要です。以下の項目を参考に、用意する書類を押さえておきましょう。
・相続登記の申請書
・相続人・被相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑登録証明書
・相続人の住民票抄本
・相続人の住民票謄本
・被相続人の住民票除票
・固定資産評価証明書
・全部事項証明書
準備した書類は、手続き時に法務局へ提出します。登記申請書には課税価格や登録免許税といった記入欄も設けられているため、間違いが内容確認しながら反映できると安心です。書類に問題がなければ、1週間~2週間を目安に権利証が発行されます。
土地の相続税はやっぱり心配。計算方法は?
相続税は普段触れ合う機会が少ないため、どのくらい課税されるのか気になる方もいるでしょう。財産全体の金額が明確であれば、課税される相続税の金額も把握できます。金銭的負担を和らげるための特例を適用されるケースもあるため、制度に関する知識を深めておきましょう。計算方法と特例2つの観点から詳しく解説します。
財産から基礎控除を差し引いた額に相続税率をかける
相続税額を算出するためには、土地だけでなく他の財産を含む総合的な金額の反映が必要です。基礎控除額も明確にした上で、以下の計算式に当てはめてみましょう。
相続税額=(全ての財産を含む総額-基礎控除額)×相続税率
基礎控除額や相続税率は、国税庁によって定められています。財産の金額が変わると相続税額も異なるため、以下を参考に適切な数字を把握しておきましょう。
| 財産の総額 | 相続税率 | 基礎控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円 | 40% | 1,700万円 |
相続税を引き下げる特例もある
財産の金額が高いほど税金も高額になり、遺族の金銭的負担を増幅させる可能性があります。このような場合には、「小規模宅地等の特例」を活用することで減税が可能です。以下のいずれかに該当する土地において、特例が適用されます。
・特定事業用宅地等
・特定居住用宅地等
・貸付事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
土地に関する条件の他、故人との関係性によって適用可否が異なる点にも注意しましょう。配偶者の場合は要件を設けていませんが、その他の親族は居住状況の条件を満たす必要があります。相続税の申告期限と、所有期間の情報も重要な要素です。
相続した土地を売る場合はどうするの?
土地を所有している方の中には、「相続直後に売却したい」と考えるケースもあるでしょう。適切に売却するためには、相続登記や価額の決定といった過程も重要といえます。名義変更の必要性を理解した上で、売却までの全体的な流れを把握しておくと安心です。3つのステップに分けて、相続から納税までの手続きを解説します。
名義換えをする
故人の土地を売却する場合、事前に名義変更を行う必要はありません。ただし、多くの所有者が手続きを済ませてから買い手を探します。故人の名義を反映したままでは、買い手が不安を感じることで希望者を探しにくいためです。
一度相続人の名義へ変更するために、相続登記の手続きを進めましょう。複雑な工程を完了させる自信がない方は、司法書士に代行を依頼する選択肢もあります。司法書士報酬(依頼料)は内容や依頼先によって異なりますが、10万円~30万円が目安です。
相続に関して親族間でトラブルが発生している場合、個人的な手続きは困難に感じるかもしれません。客観的な意見を求めるためにも、専門家に任せられると安心です。
不動産会社に売却の依頼をする
相続登記が完了し、名義を変更した後は売却手続きに移ります。不動産会社に、物件の売却を希望する旨を伝えましょう。特定の不動産会社が決まっていない段階であれば、複数の無料相談を受けて絞り込むのもおすすめです。
買い手が見つかって売買契約が成立すると、不動産会社には仲介手数料を支払います。金額には上限があるため、適切な数字であるか確認しておきましょう。目安となるのは、取引額の3%程度です。
譲渡所得課税を支払う
無事に売買取引が成立した後は、取得金額にかかる税金を支払います。土地の売買は「譲渡」の扱いになる点も理解が必要です。
課税譲渡所得金額=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額(該当する場合)
上記の計算式を基に、納税する金額が算出できます。土地の所有期間によって税率が異なるため、以下の条件も押さえておきましょう。
| 期間 | 税率 | |
| 長期譲渡所得 | 1月1日時点で所有期間が5年以上 | 15% |
| 短期譲渡所得 | 1月1日時点で所有期間が5年以下 | 30% |
相続した土地を分けたい!どうすればいい?
現金で遺された財産と同様、土地の相続時にも分割は可能です。複数の相続人と分ける際には、現物分割や代償分割などからひとつの方法を決める必要があります。それぞれメリットとデメリットがあるため、相続人と相談しながら最適な選択肢を見極めましょう。4パターンの分割方法について、特徴を踏まえながら詳しく解説します。
遺産をそのまま分ける方法
分割方法の中でも、比較的多く選択されるのが「現物分割」です。故人の預金・土地・車など各項目の相続人を決定します。例えば「土地は配偶者に、預金は長男に」といったかたちです。
| メリット | デメリット |
| ・分割方法がシンプルで、明確に分けやすい | ・財産の内容によって、価値の差が開きやすい |
分割作業がシンプルである一方、相続人の間に金銭的な不公平が生じるリスクも考えられます。場合によってはトラブルのきっかけにもなるため、十分な話し合いが必要な分割方法ともいえるでしょう。特性上、価値が高いものほど関係性の深い方に相続される傾向があります。
売却後、お金で分ける方法
相続する財産をお金に換え、現金を分割する方法が「換価分割」です。土地のように、価値が見えにくい財産を平等に分けられるメリットがあります。
| メリット | デメリット |
| ・相続人間で金額差が生じにくい | ・売却や処分の際に税金が発生する ・売却できない財産を分割しにくい |
金銭的なデメリットは、売却または処分のタイミングで発生する税金です。財産の金額が大きいほど、納税の負担を感じるリスクも高まります。相続したい土地を利用中の親族がいる場合、売却も困難になるでしょう。相続人が公平な分割を希望する状況であれば、メリットの方が大きい手段といえます。
不足分をお金で支払う方法
特定の親族が財産を相続し、他の相続人に不足分を支払う方法が「代償分割」です。土地や車などを相続した上で、金銭的価値を基に支払額を決定します。
| メリット | デメリット |
| ・現金化できない財産を公平に分割できる ・複数の財産をまとめて算出できる |
・代償金の用意が必要 |
財産を相続する方は、他の相続人に対して支払うお金の用意が必要です。保有している資金が少ない場合、代償金が足りず実現できないケースもあります。財産が多いほど代償の金額も高額になるため、金銭的な負担を増幅させるリスクに注意しましょう。
分けずに相続人で共有する方法
特定の相続人を決定せず、複数人で相続する方法が「共有分割」です。土地を分けたり現金化したりすることなく、合同で所有するかたちになります。
| メリット | デメリット |
| ・共有財産となるため、公平に相続できる | ・後にトラブルへ発展する可能性がある |
共有分割は、各相続人が受け取れる土地や金額を明確化するものではありません。売却の決定権もあいまいになるため、後にトラブルを引き起こす可能性があります。全員が納得できる状況であれば安心ですが、他の方法に比べてリスクが高い方法ともいえるでしょう。将来的な相続も含めて検討することが大切です。
土地相続のよくある疑問
故人から財産を相続する場合、原則的に取捨選択はできません。相続を放棄する際は、全てを相続できなくなるルールも理解しておきましょう。名義変更の期限や、固定資産税などの規定も重要なポイントです。ここからは、土地の相続に関して抱きやすい疑問と質問を3つご紹介します。
売却が期待できない土地は相続放棄できる?
複数の土地を相続するとき、「資産価値がある土地のみを相続したい」と考える方もいるでしょう。金銭的に考えると魅力的な手段ですが、法律の観点では実行できません。原則として、相続する財産の内容は自由に決められないためです。
例えば「2つのうちひとつは価値がないから」と相続放棄を選んだ場合、残りのひとつも放棄することになります。売却しにくい土地の相続を予定している方は、他の財産も考慮しながら選択肢を見極めましょう。将来的に使う予定がなく、売却もできない土地は放棄した方が負担の軽減につながるケースもあります。
相続した土地の名義変更に期限はあるの?
相続後の名義変更(相続登記)手続きに、明確な有効期限はありません。ただし、可能な限り早い段階で済ませた方がいいでしょう。手続きまでの期間が長くなると、以下のようなデメリットが生じるためです。
・土地を売却しにくい(買い手が見つかりにくい)
・長期間経過すると、登記費用が高額になる
・名義変更前に処分される可能性がある
・処分の実行後は相続登記が認められない
他の相続人が処分を決断し、手続きを進めるかもしれません。この後は相続登記も認められないため、相続が決定した時点で実行に移すと安心です。
土地を相続したら、いつから固定資産税を払うの?
固定資産税の納税義務は、相続が発生した翌年から開始されます。「1月1日時点に誰が所有しているか」を明確にしておきましょう。名義変更を完了しておらず故人が所有者となっている場合は、相続人が納税者です。
故人が生前納税していなかった場合、相続人に債務が引き継がれます。相続放棄を選んだ場合は支払いも不要ですが、生前の納税状況も確認した方がいいでしょう。
また、1月1日時点で新しい所有者に名義が変更されている状態であれば、固定資産税も変更先の名義が対象となります。名義変更が反映されたタイミングが重要となるため、手続きの時期にも注意しましょう。
家族信託という選択肢もある
相続について詳しく知りたい際に、認知症についても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。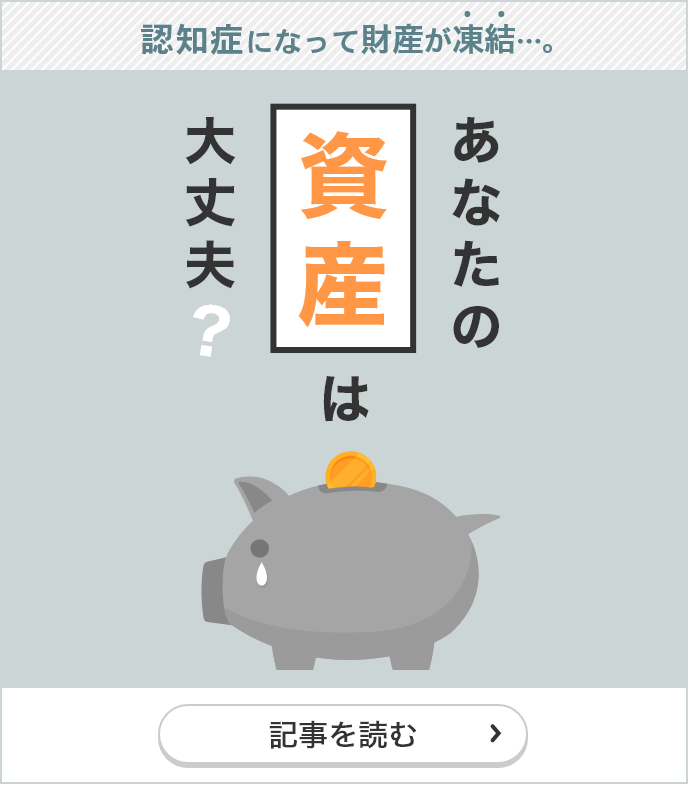
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
土地の相続が決定した後は、名義変更や相続税関係の手続きが必要です。複数の書類提出を求められるため、不足がないようしっかりチェックしましょう。財産全体の金額が分かると、納める相続税も算出できます。
土地のように複数人で分けにくい財産においては、分割方法の選択も重要です。相続放棄に関する規定も、今後の生活に大切な要素といえます。手続きの完了まで問題なく進められるよう、相続人の話し合いも重ねておきましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
土地の相続に必要な手続きは?
相続した土地の名義変更に期限はあるの?
土地の相続税の計算方法は?
相続した土地を分ける方法は?
お付き合いのあるお寺がない場合、寺院手配サービスを利用する方法もあります。ホゥ。































