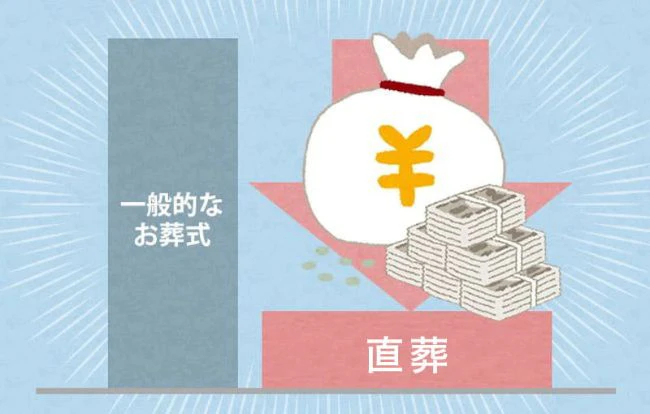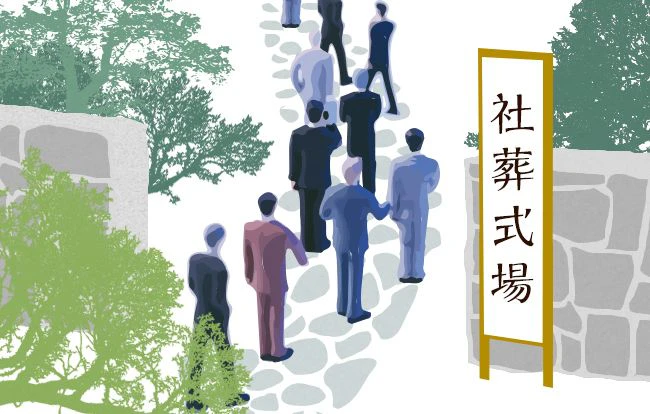葬儀では、特有の道具を使って故人を供養します。葬儀は基本的に宗教行事であり、それぞれの宗教に由来する道具を使うケースがほとんどです。それらを葬具と呼びますが、いくつか種類があり、一つひとつに意味があります。
この記事では、葬具の種類や意味を解説します。葬具について知ることで、葬儀の流れが掴みやすくなり、故人への供養も心の込もったものになるでしょう。
<この記事の要点>
・松明は野道具に由来する道具で、魔除けとして使用される
・位牌は仏具由来の葬具で代表的なもので、故人の魂を宿すための道具である
・お香を焚く入れ物を香炉と呼び、焼香の際に使用する
こんな人におすすめ
葬儀で使う道具について知りたい方
野辺の送りについて知りたい方
野道具に由来する葬儀の道具について知りたい方
葬儀で使う道具について
葬儀で使われる道具を葬具と呼びます。葬具の由来は、昭和初期頃まで行われていた「野辺の送り」の「野道具(のどうぐ)」や、仏教の儀式で用いられる仏具であると言われています。また、これらが葬儀の形態に沿って変化し、現代の葬具となったとされています。葬具では、基本的に金具は使用しません。白木や紙を使用するのが通例です。
葬具には、故人を見守り極楽浄土へ旅立つのを願う意味があります。
野辺の送りについて
ここからは、葬具の由来の一つである「野辺の送り」について解説します。野辺の送りとは、葬送の儀式を指します。近親者たちが列を成し、故人を火葬場や墓地へと見送る儀式です。「野辺」には、埋葬という意味があります。かつては自宅で執り行うのが通例でした。
また、昔の日本は土葬が一般的で、葬儀が終わると棺を担いで墓地まで運び埋葬したことから「野辺の送り」と呼ばれています。宗教上の区別はほとんどなく、地域の風習に合わせて葬送は行われていました。
野辺の送りにおける葬列について
葬列の組み方は地域によって異なるため一概には言えませんが、松明や行灯を掲げながら歩くのが通例です。葬列では、故人との間柄で役割が決められます。例えば、喪主には位牌を持つ役目があり、喪主の妻が飯碗を運ぶのが一般的でした。
野辺の送りは年を追うごとに大きくなり、特に故人が社会的地域のある人物だった場合は、葬列のために人を雇用するほどだったと言います。
しかし、野辺の送りは廃れ、現代ではほとんど見られません。理由としては、遺族の経済面に負担がかかったことや、都市部で車や市電が発達したために、長い葬列を組むと交通を妨げてしまうといったことが挙げられます。現代の葬儀では、葬列の代わりに霊柩車を導入するのが通例です。
<関連記事>
あなたの知らない霊柩車の知識
野辺の送りにまつわる儀式
野辺の送りでは、穢れを現世に残さないための習わしがあります。例えば、出棺や土葬をする際には、三度周りと呼ばれる儀式を行いました。棺を横に三回転することで、故人の方向感覚を狂わせ、現世に戻らないようにする意味があります。
また、仮の門を作り遠回りして運ぶことも故人が現世に戻らないための作法です。現代でも、霊柩車が斎場から火葬場に向かう際に、遠回りして向かうケースがあります。
野辺の送りが終わった後、参列者はまずお風呂に入り穢れを落とすのが通例でした。また、味噌や塩を口にして清めてから食事についたと言います。現代の葬儀でも塩が配られるのは、こうした儀式の名残です。
野道具に由来する葬儀の道具
野辺の送りを執り行う上で使用した道具を野道具と言います。野道具は、野辺の送りが廃れた現代でも葬儀の際に使われる葬具です。現代は、斎場から火葬場へ出棺する際に祭壇を飾ることを目的として使用されることが多いでしょう。ここからは、野道具に由来する葬具について解説します。
松明
野辺の送りでは、先頭に立人が松明を持って進み、道を清めていました。また、現世と来世の架け橋になるという意味や煩悩を消し去るといった謂れもあります。魔除けとしても重宝され、故人を極楽浄土へと送り出す大切な道具です。そのため、昼間の葬儀においても松明が灯されていました。
魔除けという目的では、米や紙吹雪、小銭を撒く役割の人がいました。棺の中に刃物を納める地域も存在したようです。
現代の葬儀では、こうした葬列を組まない代わりに、イグサや藁を束ねたものを松明に見立てるのが通例です。この束ねたものは投げる、手に持って回す、と宗派によって使い方は異なります。例えば、浄土宗では「引導下炬(いんどうあこ)」という大切な儀式の際に松明が使用されるのが通例です。
<関連記事>
浄土宗の葬儀・法要の特徴やマナー
四本幡
野辺の送りでは、仏教の教えが書かれた旗を棺の周りや墓の四隅それぞれに立てていました。これを四本幡(しほんはた)と言います。
四本幡には、それぞれ「諸行無常」「是生滅法」「生滅滅巳」「寂滅為楽」と書くのが通例です。この世の全ては移り変わるものであり、いつか必ず死が訪れることや、生滅(生きて死ぬこと)に執着しないといった意味があります。
現代でも四本幡の使用方法は当時と変わらず、葬儀会館で導入されるケースが多いです。安置した棺の上に乗せたり前に並べたりするパターンも見られます。墓の四隅に立てる場合は、結界を張り故人の滅罪にも効果があるそうです。
四華花
白い紙を竹串に巻きつけて、横に細かい切れ目を入れた葬具を四華花と言います。白い紙だけではなく、金や銀の紙を使うケースもあります。野辺の送りでは、親族が手に持ち、墓地の四隅に立てるのが通例でした。
四華花の由来は、お釈迦様が涅槃に入るシーンです。お釈迦様の入滅により悲しんだ沙羅双樹の四本の花が白く変わったことから、まるで白いツルが並んでいるようだという故事「涅槃経(ねはんぎょう)」を表していると言われています。
かつては、四華花を立てなければ故人が極楽浄土へ行けないと言われるほど大切な道具でした。現代では、祭壇や経机の周りに設置するのが通例です。また、葬儀の後に火葬場へ移動する様子を野辺の送りと見立て、親族が四華花を持つケースも見られます。
六道
篠竹に小さい蝋燭を6本立てたものを六道と言います。地域によっては、8本のところもあり、そのうち2本は葬列に先行して辻に立てたようです。松明と同様に、葬列の案内役とされました。
また、故人は生前の行いに合わせて、「天道」「人間道」「修羅道」「畜生道」「餓鬼道」「地獄道」といった六道のいずれかに行くという考え方が地蔵信仰にはあり、六地蔵に助けてもらう意味も込めて六道が誕生したという謂れもあります。現代も、祭壇上部の両側に6本の灯明が飾られることがありますが、これらは六道の名残です。
仏具を由来とした葬儀の道具
葬具には野道具が由来となったものだけではなく、仏具が変化したものもあります。どれも葬儀で欠かせない道具であり、目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。続いては、仏具由来の葬具について解説します。
位牌
仏具由来の葬具として代表的な道具は、位牌です。仏壇にもあるため馴染みが深い道具ですが、葬儀においても非常に大切な役割を果たしています。
そもそも位牌とは、故人の魂を宿すための道具です。かつての葬儀では、葬列の際に喪主が位牌を持ち、火葬場や墓地へ故人の魂を運びました。現代でも、故人が乗る霊柩車に、位牌を持った喪主が同乗します。ただし、地域によっては野辺の送りのしきたりを重んじ、喪主が霊柩車に乗ることを避ける場合もあるので注意が必要です。
位牌は、臨終後すぐに作られます。葬具としての位牌は、簡素な白木素材を使った、「内位牌」と呼ばれるものです。表側に戒名を書き、裏には生前の名前と死亡年月日、享年を書くのが通例です。基本的には、葬儀会場の祭壇や葬儀が終わったのちの自宅に祀ります。内位牌に書く内容を紙に書いて貼るケースもあります。葬具である「内位牌」は、忌引明けまで使います。
四十九日以降、仏壇に飾る位牌は「本位牌」です。ほとんどが木製で、漆塗りに金箔や蒔絵が施されています。宗派によっては、位牌を使用しないパターンもあるので、わからないときは確認しましょう。
<関連記事>
位牌は必要?作る時期は?位牌作成時のよくある疑問に答えます
香炉
お香を焚く入れ物を香炉と言います。野辺の送りでは、参列者が運びました。いわゆる仏具の三具足や五具足の一つで、燭台や花立と並び現代でも使われる道具です。
香炉には2パターンあり、香炉と香合がひとまとまりになったものと、別れたタイプのものがあります。日常的な供養では線香に火を灯し、香炉に刺すのが通例です。しかし、葬儀や法要の折には、細かくしたお香を香炉の火種に落とす焼香という作法を行います。また香炉は、金属や真鍮で作られた金香炉と、陶磁器である土香炉の2種類があるのも特徴です。
焼香は、参列者の心を清め整える大切な儀式です。また、極楽浄土はよい香りに満ちていると言われており、焼香の香りと煙で、故人を極楽浄土へ導くとされています。さらに、焼香の香りが隅々まで広がる様子から、仏の慈悲が隅々まで平等に行き渡ることをイメージしているというのも一つの謂れです。
提灯
照明器具として使用される提灯も、葬具の一つです。室町時代の終わりには、葬儀の場で仏具の役割を担っていたようです。葬儀で使う提灯は、「門前提灯」という名称で、門の前に一対掲げるのが通例です。
また、祭壇の両脇に飾るケースもあります。御霊に火を捧げるといった意味が込められており、「御霊燈」や「忌中」といった文字が書かれます。
元来、提灯は近所の人に葬儀を執り行う旨を知らせるために用いられていました。しかし最近は、近所に知らせないケースも増えており、提灯を使う家庭は少なくなっています。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀に使う道具は、古き良き日本の風習や思いが込められています。野辺の送りが一般的に行われなくなった現代においても、葬具は変わらず大切なものです。それぞれの意味を大切にすることで、現代の葬儀も故人への思いが詰まった素晴らしいものになるでしょう。
ただし、地域や宗派によって葬儀の道具は異なります。葬儀を執り行うにあたって、葬具に関する疑問がある場合は、小さなお葬式にご相談ください。葬具をはじめとする葬儀についてのご質問に、専門知識を持った経験豊富なスタッフが親身になってお答えいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



家族葬とは、家族や親族を中心に、小規模に行う葬儀形式のことです。ホゥ。