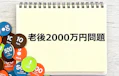パートが加入条件を満たせば加入できる社会保険とは、健康保険と厚生年金の2種類です。それぞれ加入することで、現在よりも手厚い保証を受けられるようになります。
ただし、自身が国民年金の第3号被保険者で社会保険料を負担していない場合は、社会保険に加入することで負担額が増加するリスクもあります。また、社会保険に加入しない場合は年収の壁を意識することが重要です。
この記事では社会保険料の計算方法と、パートが社会保険に加入する条件、メリット、注意点について解説します。
<この記事の要点>
・パートが社会保険に加入するためには正社員の4分の3以上の勤務日数と勤務時間が必要
・週の労働時間が20時間以上30時間未満であれば社会保険に加入できる
・社会保険料は、報標準報酬月額をもとに健康保険料と厚生年金保険料を足す
こんな人におすすめ
現在パートをしていて社会保険料について気になっている人
パートを始めた際の社会保険料について知りたい人
社会保険料の計算方法について知りたい人
パートが社会保険に加入するメリット
パートの方が社会保険に加入するメリットは3つあります。社会保障が手厚くなり、場合によっては保険料の負担の軽減にもつながるので、把握しておきましょう。
厚生年金への加入で年金額が増える
現在、国民年金に加入しているパートの方は厚生年金に加入することで年金の受給額が増額します。国民年金の被保険者区分は第2号被保険者となり、厚生年金に加入すると共に継続して国民年金の加入者としても扱われる仕組みです。
厚生年金の加入者は国民年金の支給額と厚生年金の支給額の両方が貰えることになります。厚生労働省が発表した日本年金機構の令和6年4月分からの年金額によると、国民年金と厚生年金を受け取る場合、合計金額が298,483円(老齢基礎年金68,000円、老齢厚生年金230,483円)です。
上記はあくまで平均値を目安にした計算であり、実際の支給額は厚生年金の被保険者期間や支払った保険料に依存します。
(参考:『令和6年4月分からの年金額等について』日本年金機構)※2024年11月時点
社会保険料の自己負担額が減少する
現在、社会保険料を自身で負担している場合は、自己負担額が現在よりも減少します。厚生年金保険料と協会けんぽ等の健康保険料は労働者と雇用者が原則として折半するのが基本です。国民年金保険料と国民健康保険料は全額を自己負担する必要があるので、社会保険に加入したほうが自己負担額は減少する可能性があります。
支払うべき保険料をパート先の企業が負担してくれるので、社会保険に加入することで支出を減らすことにもつながります。後ほど詳しく解説しますが、加入するすべての人の社会保険料の負担額が減少するわけではないため気をつけましょう。
傷病手当金や出産手当金の対象になる
勤務先の健康保険に加入していると、傷病手当金や出産手当金の対象となります。傷病手当金は業務外の自由により病気や怪我で休業をした場合に支給される手当であり、入院だけでなく自宅での療養も対象になります。連続して3日以上休み、4日目以降から支給が開始される仕組みです。
傷病手当金は平均給与の3分の2の額が支給されます。また、受け取るためには休業した期間に給与の支払いがないことも条件です。
また、出産を理由に会社を休み、その間に給与の支払いがなかった場合は、出産日も含む出産日以前の42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日から56日目の範囲内で出産手当金が支給されます。支給額は傷病手当金同様に平均給与の3分の2の額です。
参考:
病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) 全国健康保険協会(協会けんぽ)
出産で会社を休んだとき 全国健康保険協会(協会けんぽ)
パートの社会保険の加入条件
社会保険が完備された会社は、短期間契約に該当する労働者以外で、条件を満たす従業員を社会保険に加入させる義務を負います。
健康保険・厚生年金に加入するために従業員が手続きをする必要はありません。すべて、勤務先の企業が手続きをおこないます。ただし、社会保険に加入する際に、現在加入している国民年金や国民健康保険から外れる場合は、資格喪失届の提出が必要になるので、自身で手続きをするようにしましょう。
正社員に限らずパートの方でも次の条件を満たす場合は社会保険の対象になるので確認しましょう。
勤務日数と勤務時間が正社員の4分の3以上
パートやアルバイトが正社員と同様に社会保険に加入対象になるためには、正社員の月の労働日数と1日の勤務時間が4分の3以上であることが条件です。
例えば、正社員の1日の勤務時間が8時間と仮定すると、1日の勤務時間は6時間以上で正社員の勤務日数が20日と仮定すると15日以上勤務していることが条件になります。
短時間労働者で4つの条件に該当する
上記の勤務日数や勤務時間の条件を満たさない場合でも、短時間労働者で4つの条件に該当する場合は社会保険の加入対象になります。条件は下記の通りです。
1.週の労働時間が20時間以上30時間未満
2.賃金の月額が8.8万円以上
3.2ヵ月以上の雇用の見込みがある
4.学生でないこと(夜間や定時制の学校を除く)
毎月の賃金の月額が8.8万円以上という条件は年収に換算すると106万円であり、短期労働者の条件に該当する年収として重要な数字になります。後ほど106万円の壁について解説するので、この数字は覚えておきましょう。
また、見込み雇用期間が1年以上という条件は法律の改正に伴い、2022年10月から2ヶ月に変更されました。
(参考:『社会保険適用拡大 対象となる事業所・従業員について』厚生労働省)※2024年11月時点
パートが社会保険に加入する際の注意点
パートが社会保険に加入するメリットと条件について解説しましたが、社会保険に加入することで損をしてしまうケースもあります。メリットだけでなく加入する際の注意点についても確認しましょう。
国民年金の第3号被保険者は社会保険料の負担が増加
配偶者が国民年金の第2号被保険者で、自身が第3号被保険者である場合は配偶者の勤務先が保険料を負担しているので保険料を折半しても負担が増加します。
第3号被保険者が加入する年金は第1号被保険者と同様に国民年金であるため、厚生年金に加入するほうが受給できる年金額は増加するメリットはあります。しかし、社会保険に加入することで社会保険料の負担額が減少するメリットはありません。
現在、国民年金の被保険者区分が第3号被保険者である場合は、社会保険の加入に関しては慎重になるほうがよいでしょう。
年収の壁で収入が減少する可能性がある
短時間労働者の社会保険の加入条件の106万円を含む、社会保険にまつわる年収の条件は年収の壁とも呼ばれる重要な数字になります。例えば、年収130万円未満は国民年金の第3号被保険者になるための条件です。
仮に年収130万円で社会保険に加入し、第2号被保険者になるケースと年収129万円以下で第3号被保険者になるケースでは、社会保険料を支払うことで年収が減少し、手取りが逆転する可能性があります。
パートかつ第3号被保険者で年収が106万円~129万円の方は収入を増やす目的で労働時間を増やして、基準となる条件を満たしてしまうと、手取りが減少してしまうリスクがあることに注意が必要です。
社会保険料の計算方法
それでは、具体的な社会保険料の計算方法について解説します。まずはひと月あたりの平均収入を求める必要があり、年収130万円であれば「130万円÷12=10万8,000円」になります。この平均収入を協会けんぽが公開している健康保険・厚生年金保険の保険料額表を参考に該当する保険料を足し合わせます。
報酬月額の平均が10万8,000円の場合は「10万7,000円~11万4,000円」に該当するので、折半額を合計して「5,412円(健康保険料)+1万65円(厚生年金保険料)=1万5,477円」が社会保険料の自己負担額になります。
パートが知っておきたい社会保険料の目安
パートの方が負担する社会保険料の目安について、106万円~200万円までの自己負担額について下記にまとめました。(東京都の場合)
| 年収 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 合計 |
| 106万円 | 4,391円 | 8,052円 | 1,2443円 |
| 110万円 | 4,391円 | 8,052円 | 12,443円 |
| 120万円 | 4,890円 | 8,967円 | 13,857円 |
| 130万円 | 5,489円 | 10,065円 | 15,554円 |
| 140万円 | 5,888円 | 10,797円 | 16,685円 |
| 150万円 | 6,287円 | 11,529円 | 17,816円 |
| 160万円 | 6,687円 | 12,261円 | 18,947円 |
| 170万円 | 7,086円 | 12,993円 | 20,078円 |
| 180万円 | 7,485円 | 13,725円 | 21,210円 |
| 190万円 | 7,984円 | 14,640円 | 22,624円 |
| 200万円 | 8,483円 | 15,555円 | 24,038円 |
130万円の壁以外にも120万円から130万円に年収が上昇する場合は、保険料が増加する境目の年収であることも理解しておきましょう。
また、社会保険には直接関係はありませんが、年収150万円は配偶者特別控除を全額(38万円)受けられる基準となっており、年収が150万円を超えると控除額が減額するため世帯収入が減少するリスクがあります。年収が201万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。
パートで社会保険への加入を考える年収の方の中には、年収の壁の影響で収入を調節するために、年収が一定以上にならない働き方を意識する必要があるかもしれません。
(参考:『令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 全国健康保険協会)
パートで社会保険に加入しないための働き方
社会保険料と年収の壁の都合上、社会保険に加入しないほうがメリットは大きいこともあります。しかし、従業員を社会保険に加入させるのは企業の義務であるため、従業員の意思で加入を決めることはできません。そのため、社会保険に加入することにデメリットがある方は社会保険に加入しないための働き方を考える必要があります。
年収106万円の壁を意識する
勤務時間と勤務日数が正社員の4分の3未満で、月額の給与が8.8万円(年収106万円)未満の方は社会保険に加入する条件を満たしません。よって、勤務時間と勤務日数を減らして、年収を調整しましょう。
ただし、1つの勤務先で基準を満たすことが社会保険の加入義務が発生する条件であるため、社会保険に加入せず年収を増やすなら勤務先を掛け持ちする選択肢もあります。
また、106万円の壁の下には100万円の壁と103万円の壁があり103万円以下の給与収入では所得税が発生せず、自治体によって基準は異なりますが100万円以下の場合は住民税が発生しません。
106万円以下に年収を調節することに問題がない方は、税金が発生する年収の壁も意識して年収を調節するとよいでしょう。
勤務先に相談する
社会保険に加入したくない理由がある場合は、自身の状況や、働き方について勤務先に相談することも重要です。社会保険に加入しないために年収106万円や130万円という壁を意識していることを伝えることで、勤務先が勤務日数と時間を調整することが期待できます。
また、条件を満たした従業員に対して社会保険に加入させる義務を負う企業は従業員数が501名以上であることが条件です。これを特定適用事業者と呼びます。特定適用事業者でない企業は条件を満たした従業員を社会保険に加入させる義務はありません。
ただし、従業員数において特定適用事業者の条件を満たしていない場合でも、勤務している人の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することを同意している事業所や地方公共団体に属する事業所も要件を満たします。
事業所によっては必ずしも適用要件を満たしているわけではないので、勤務先に相談することで、企業側が社会保険に加入させる義務を負っているかを把握できます。
また、令和6年10月から短時間労働者の加入要件が拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
(参考:『社会保険適用拡大 対象となる事業所・従業員について』厚生労働省)※2024年11月時点
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
社会保険への加入は基本的には年金の支給額が増加し、保証も手厚くなるのでパートにとってもメリットがあることは間違いありません。
特定適当事業者の要件拡大や、見込み勤務期間の条件が短くなることも含めて社会保険に加入しやすい環境が法律の改正により整っていることは従業員にとって有利です。
ただし、パートで第3号被保険者の方は社会保険に加入する注意点を理解した上で、家族や勤務先と相談しながら社会保険に加入するかどうかを考えましょう。加入しないのであれば働き方を意識することをおすすめします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。