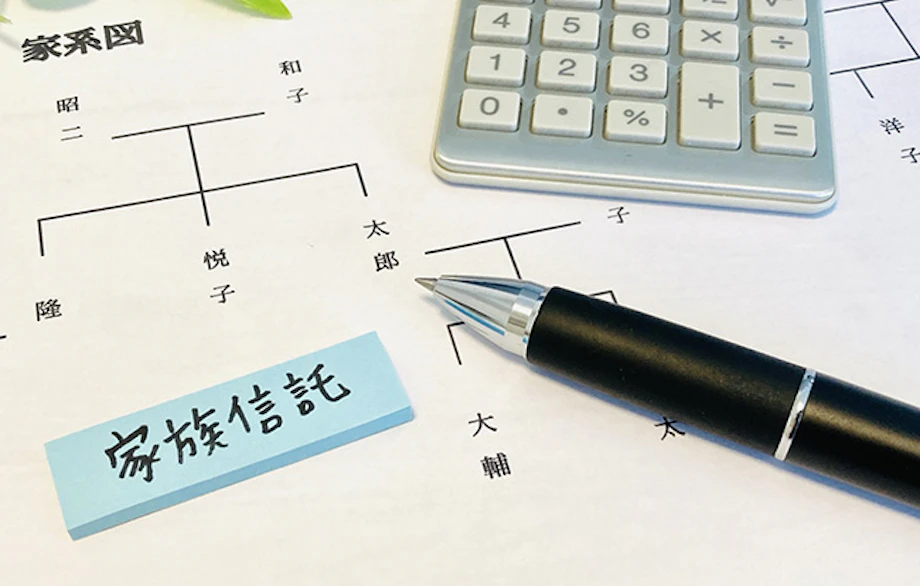老後の財産管理や相続方法の1つに「家族信託」があります。この記事では、家族信託とはどのようなものなのかをわかりやすく解説します。その特徴やメリットを知り、老後に備えて家族信託を選ぶ際の検討材料としましょう。
<この記事の要点>
・家族信託とは、家族に財産の管理権を託すための制度を指す
・家族信託は所有者の状況に関わらず財産管理ができるのがメリット
・家族信託適用後は、受益者が課税対象となるため注意が必要
こんな人におすすめ
財産管理を信用できる人に任せたい人
家族信託のメリットを知りたい人
家族信託の手続きの流れを知りたい人
家族信託とは何か
ここでは家族信託がどのようなものなのか、特徴や仕組みを解説します。家族信託の概要を押さえ、大まかな使い方を理解しましょう。
家族信託の特徴とは?
家族信託とは、その名前のとおり家族に財産の管理権を託すための制度です。年を重ねて、財産の管理が難しくなってきた場合に備えて活用することを想定しています。
なお、家族信託は正式名称ではありません。本来は「民事信託」といいますが、制度を利用するケースの多くが家族間であるため、通称として家族信託という言葉が用いられています。
家族信託の仕組みとは?
財産には所有権が付随しますが、本来であれば所有権は、管理権と受益権の2つから成り立ちます。このうち管理権だけを家族に受け渡すのが、一般的な家族信託の方法です。
つまり、受益権は財産所有者に残るため、財産の運用により発生する収入などは、すべて所有者のものになります。
家族信託が必要となるケース
ここでは、家族信託がおすすめとされる一般的なケースを紹介します。自身の状況と照らし合わせることで、検討材料としてください。
認知症に備えたい場合
認知症になると、正常な判断が難しいといった観点から財産の所有権を移すことができなくなります。その結果、銀行口座の凍結や、不動産の運用・売却ができなくなるといった状況につながります。
家族信託を事前に済ませておくことは、財産が無駄になり得る状況の回避に活用できます。
障がいのある子どもに財産を残したい場合
障がいを持つお子さんをお持ちの場合をはじめ、財産管理が難しい家族のためにも家族信託は活用可能です。このケースでは一般的な家族信託とは異なり、受益権はお子さんに渡し、管理権は親族をはじめとした信頼のおける人物に委託する形になります。
なお、子どもだけでなく、孫世代に財産を引き継がせるための指定も家族信託では可能です。
成年後見人制度以外の方法で対策したい場合
財産の管理権を委託する方法としては、家族信託だけではなく「成年後見人制度」という方法も検討できます。しかし、成年後見人制度は、家族信託に比べて相続対策の方向性が限られているのが特徴です。財産所有者の意向よりも裁判所の意向が優先される傾向もあります。
そのため、事前に自分の意思で相続対策をしておきたいという場合には、家族信託が有効でしょう。
家族信託で得られるメリット
家族信託で得られるメリットは主に5つあります。これらのメリットに強い魅力を感じる場合は家族信託を積極的に検討することをおすすめします。
柔軟な財産管理ができる
家族信託は成年後見制度と異なり、家庭裁判所が関与しません。そのため、委託者の専任条件から委託内容まで柔軟に決めやすいのは大きなメリットです。管理権を移すタイミングも委託者が自由に決められます。
(※成年後見制度の場合、財産の管理権が移るタイミングは、委託者の判断能力が低下したと認められた時点に限られます。)
財産管理が容易にできる
家族信託を利用して管理権を移せば、管理権を持つ家族は所有者の状況に関わらず財産管理ができるようになります。成年後見制度のように、管理が難しいと考えられる状況であっても判断能力がないとは見なされません。
倒産隔離機能を利用できる
家族信託には、倒産隔離機能が付与されます。倒産隔離機能とは、信託後の財産名義が受託者になることから、「財産の運用により負債が発生しても財産が差し押さえられることはない」というものです。
(※ただし、受益権には倒産隔離機能が反映されず、受益者が破産した場合には、財産の差し押さえが起こります。委託者と受益者が同一の場合には注意が必要です。)
財産継承の順位付けを行える
家族信託では、財産の継承先についても柔軟性が高く、財産継承の順位付けまで取り決めることができます。ほかの財産継承の方法としては遺言書や生前贈与などがありますが、これらで指定できるのは自分の次の相続人までです。次世代の相続先まで指定できるのは、家族信託のメリットだといえるでしょう。
遺言書の代わりになる
家族信託は、遺言書としても活用できます。遺言書との大きな違いとして挙げられるのは、その仕組みによって生まれる内容の変更しやすさがあります。
遺言書は、本人の意思により作成され、いつでも本人の意思に基づいて内容を変更できます。これに対して、家族信託の場合は信託契約として締結するため、内容の変更には委託者と受託者の合意が必要となります。家族信託のほうが、双方が納得のいく内容になりやすいといえます。
家族信託の注意点とは?
家族信託にはメリットも多くありますが、注意点もあります。メリットだけでなく、注意点も押さえてトラブルを回避しましょう。
受託者を決める際にトラブルになる
家族信託は遺言書とは異なり、委託者と受託者で話し合って契約を進めます。家族全員で話し合いのうえで契約することがおすすめですが、その際に権利を巡ってトラブルに発展する恐れは十分あるでしょう。契約締結後に不平不満が表面化するケースもあります。
受託者が使い込むリスクがある
管理権を委託された受託者には、本来であれば委託者の意思に沿って財産を管理する義務があります。しかし、実際の管理については個人の裁量に任される部分が大きいため、受託者の私利私欲により財産が使い込まれるリスクは避けられません。
このようなリスク対策に関しては、身上監護権が適用される「成年後見制度」のほうが安心感を得やすいでしょう。
相続税の軽減にはならない
家族信託の趣旨は、財産所有者の意思を最優先した財産の移転を行うことであり、相続税の軽減ではありません。不動産の売却など、ケースによっては結果として節税できることもありますが、家族信託そのものには基本的に節税効果はないと思っておくのが賢明です。
受益者が課税対象となる
家族信託の適用後は、受益権を持つ者に財産運用による収入が入ります。そのため、所得税は受益者に課税されるほか、受益者が委託者でない場合には贈与税も課税されるため、注意が必要です。さらに、財産の内容によっては受益者が不利益を被る恐れもあります。
家族信託の専門家が少ない
家族信託は比較的最近になって生まれた制度であることから、認知度が低く、対応可能な専門家も少ない傾向にあります。お住まいの場所によっては、なかなか信頼できる専門家を見つけられず、手続きを進められないということもあり得るでしょう。
家族信託のやり方や手続きの流れ
ここでは、家族信託のやり方や手続きの流れを紹介します。実際に家族信託制度を利用しようと考えた際に参考にしてください。
1.信託契約書の作成と公証
まずは、家族信託における契約書の内容を家族で取り決め、信託契約書を作成しましょう。信託契約書は個人でも作成可能ですが、専門家に依頼すると安心です。
完成した信託契約書は公証役場に提出し、公証人の認証を受ける必要があります。
2.専用口座の開設
受託者は自身の財産と委託財産を分けて管理しなくてはいけない「分別管理義務」を負うため、新たに家族信託専用の講座を開設するのがおすすめです。銀行によっては、家族信託向けの口座として「信託口口座」が用意されています。
3.運用の開始
信託契約書と口座の用意ができたら、家族信託の手続きを進めます。信託財産が不動産であれば、登記申請をおこない名義変更も済ませておきましょう。
以上の流れで、家族信託の契約がすべて完了すれば、管理権を持つ受託者によって財産の運用が可能になります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
家族信託とは、家族に財産管理を委託する制度のことです。その名前のとおり信用に基づいた契約となるため、制度を活用する際には、あらかじめ家族と話し合いを重ねて決めることが大切です。家族信託のメリットと注意点をよく考えて検討しましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。家族信託をはじめ、老後の準備に悩みや不安を抱えている方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
老後の準備以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


自身が亡くなったときのために、エンディングノートを書いておくのもおすすめです。ホゥ。