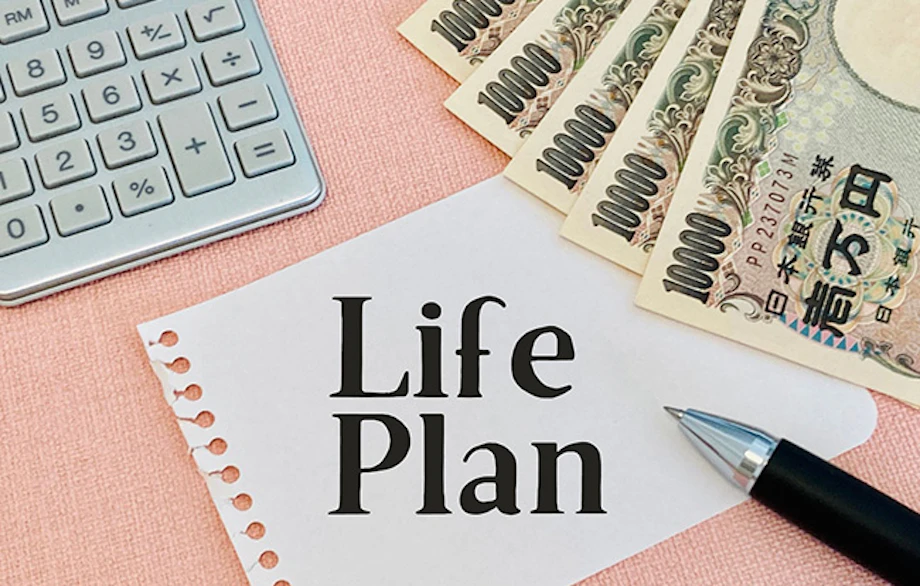老後にもらえる公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。自分がもらえる年金の計算方法や確認方法を知って、老後に必要な生活資金を把握しましょう。
この記事では、年金の計算方法や受け取れる年金が少ない場合にできる対策について紹介します。
<この記事の要点>
・国民年金の計算方法は「年金額 × (保険料の納付月数 ÷ 480ヶ月)」となる
・年金受給額は「ねんきんネット」「ねんきん定期便」の2つから確認することができる
・年金増額の対策として年金加入月数を増やす方法と、年金繰り下げ制度を活用する方法がある
こんな人におすすめ
年金の計算方法を知りたい方
「国民年金」と「厚生年金」の違いを知りたい方
将来受け取れる年金額の計算方法を知りたい方
種類別│年金の計算方法
公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類あり、それぞれ計算方法が異なります。ここからは、国民年金と厚生年金の計算方法を紹介します。
国民年金の場合
国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満の人全員が加入する年金のことです。「基礎年金」とも呼ばれます。国民年金の年間受給額の計算式は以下のとおりです。
年金額 × (保険料の納付月数 ÷ 480ヶ月)
令和6年度の国民年金の月額は1人6万8,000円です。(昭和31年4月1日以前生まれの方は月額67,808円)
厚生年金の場合
厚生年金とは、会社に所属し、かつ要件を満たしている人が必ず加入する年金のことです。厚生年金保険料は、毎月の給料やボーナスから一定額天引きされます。厚生年金の計算額は以下のとおりです。
報酬比例年金額 + 経過的加算 + 加給年金額
老齢厚生年金は「報酬比例年金額」「経過的加算」「加給年金額」を割り出す必要があり、自身ですべてを計算するのは難しいでしょう。
(参考:『令和6年4月分からの年金額等について』日本年金機構)
パターン別│年金の計算方法シミュレーション
自分は年金をいくらもらえるのか気になる人も多いでしょう。ここでは、年金の計算方法を働き方や家族構成別にシミュレーションしました。厚生年金の保険料の大部分は標準報酬月額によってきまるため、算出金額は人それぞれ異なります。
単身者の場合
ここでは、年収400万の会社で働いている単身者が受給できる金額を計算します。会社員であるため、国民年金と厚生年金の2つを年金として受け取ることが可能です。年収400万円の厚生年金を月額6万円と仮定し、国民年金を月額6万5,000円とします。
厚生年金6万円 + 国民年金6万5,000円 = 12万5,000円
このケースの単身者が毎月受け取れる金額は、12万5,000円です。
会社員と専業主婦の場合
ここでは、年収600万円の会社員と専業主婦が受給できる金額を計算します。会社員は国民年金と厚生年金、専業主婦は国民年金を受け取ることが可能です。年収600万円の厚生年金を月額9万7,000円と仮定し、国民年金を月額6万5,000円とします。
16万2,000円(会社員の年金受給額) + 6万5,000円(専業主婦)=22万7,000円
このケースの夫婦が毎月受け取れる金額は、22万7,000円です。
会社で働いている夫婦の場合
ここでは、年収600万円の会社員と年収300万円の会社員の夫婦が受給できる金額を計算します。夫婦共に会社員であるため、国民年金と厚生年金の2つを年金として受け取ることが可能です。
年収600万円の厚生年金を月額9万7,000円、年収300万円の会社員の厚生年金を月額6万円と仮定し、国民年金を月額6万5,000円とします。
16万2,000円(年収600万円の会社員の年金受給額) + 12万5,000円(年収300万円の会社員の年金受給額) = 28万7,000円
このケースの夫婦が毎月受け取れる金額は、28万7,000円です。
自営業をしている夫婦の場合
ここでは、自営業の夫婦の年金受給額を計算します。夫婦共に自営業であるため、国民年金のみ受け取ることが可能です。国民年金を月額6万5,000円とします。
6万5,000円(国民年金) + 6万5,000円(国民年金) = 13万円
このケースの夫婦が毎月受け取れる金額は、13万円です。
年金支給額の確認方法
年金受給額は「ねんきんネット」「ねんきん定期便」の2つから確認することができます。ここからは、それぞれの確認方法について解説します。
ねんきんネットでの確認
ねんきんネットとは、インターネットを通じて自身の年金を確認できるサービスです。24時間いつでも、パソコンやスマートフォンから年金情報を確認できます。ねんきんネットで自身の年金を確認するには、マイナポータルとの連携やユーザーIDの取得が必要です。
ねんきん定期便での確認
ねんきん定期便とは、保険料の納付実績や将来の年金給付に関する情報を知らせてくれる通知書です。国民年金および厚生年金の被保険者を対象に、毎年誕生月になるとハガキや封書で送られてきます。
ねんきん定期便は、50歳未満でも年金の加入実績を確認することが可能です。50歳以上の場合は、60歳まで加入した場合の年金額の目安が分かります。
受け取れる年金の平均支給額や推移は?
年金の受給額は、働き方や年収によって異なります。ここからは、会社員が受け取れる年金の支給額や、年金支給額の推移を紹介します。
会社員が受け取れる年金の平均支給額
令和3年に厚生労働省が公表した『厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、厚生年金保険(第1号)受給者の平均年金月額は、令和4年度時点で14万4,982円で、支給額は減少傾向にあります。
ただし、厚生年金は人によっても異なるため、あくまでも参考程度にとどめてください。
(参考:『厚生年金保険・国民年金事業の概況』厚生労働省)
受け取れる年金が少ない場合にできる対策
「国民年金の未納があった」「将来受け取れる年金が少なく不安」という方もいるでしょう。国の制度の利用だけでなく、自身の力で老後に備えることも大切です。ここからは、受け取れる年金が少ない場合にできる対策を4つ紹介します。
年金増額の対策をする
年金を増額するための方法は主に2種類あります。ひとつは年金加入月数を増やす方法です。納付月数は480ヶ月が上限ですが、保険料の未納があった場合は65歳まで任意加入ができて、基礎年金を増額できます。
もうひとつは、年金繰り下げ制度を活用する方法です。年金の受け取り開始年齢を70歳まで繰り下げることで、最大で42%増額できます。
定期預金をする
定期預金をして老後に備える方法もあります。銀行預金は流動性が高いため、急にお金が必要になったときでも簡単に引き出すことが可能です。また元本が保証されているため、安全性も高いといえます。
しかし、銀行の定期預金は金利が低いため、債券や株式投資などと比べると資産は増やせません。
資産形成をする
NISAやiDeCoといった非課税制度を利用して資産形成をするのもよいでしょう。NISAは、NISA口座内で購入した金融商品に対して税金がかからないという制度です。ただし、限度額や期間などの条件があります。
iDeCoは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度です。掛金が全額所得控除されたり、運用益が非課税になったりします。
民間の保険に加入する
終身保険・養老保険・個人年金など、民間の保険を利用して老後に備えるのもおすすめです。投資よりもリスクが低く、預金よりも高利率の成果に期待できます。
終身保険や養老保険は死亡保障があるため、万が一に備えながらコツコツと積み立てていくとよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。会社員なのか自営業なのかで加入する年金の種類が異なり、年収によっても厚生年金の受給額は変わってくる点に注意しましょう。
老後に備えるためにも、将来受け取れる年金の目安を知り、少ないと感じれば資産運用をするなどして対策するとよいでしょう。
また老後の備え以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


お通夜とは、家族や友人たちが集まり、故人と最後の夜を過ごす儀式のことです。ホゥ。