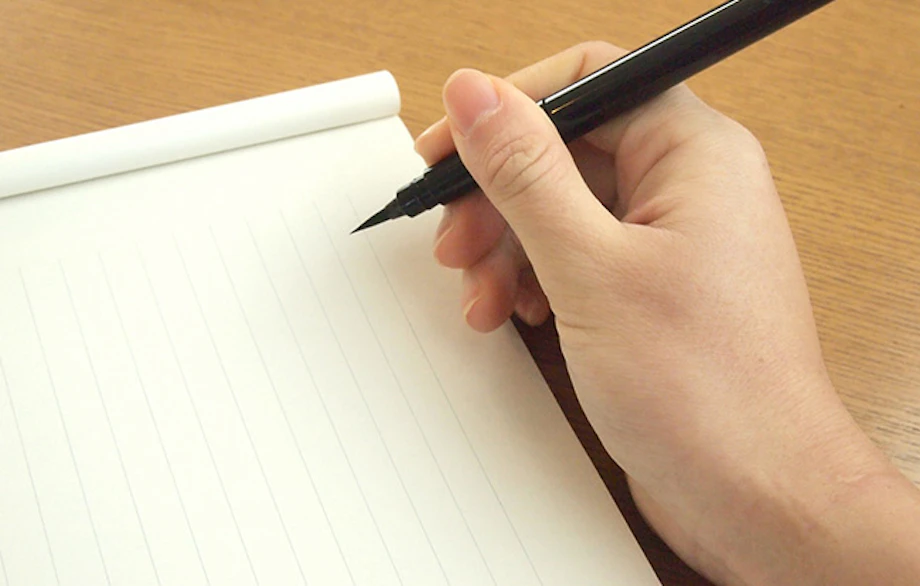一周忌のときは何をするのか、どんなマナーがあるのが知りたいという方もいるのではないでしょうか。一周忌の内容やマナーなどを知識として身に着けておけば、急な訃報を受けたときでも役立てることができます。
そこでこの記事では一周忌のマナーについてご紹介します。法要に参加できないときの対応、お悔やみの手紙の書き方についてもお伝えしますので、今後の参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・欠席する場合は、電話か返信ハガキで早めに連絡をする
・欠席連絡とは別に、故人の思い出や冥福を祈るお悔みの手紙を送る
・「ご冥福」とは、死後の幸せという意味の故人へ向けた言葉
こんな人におすすめ
一周忌について知りたい方
一周忌を欠席する際の注意点が知りたい方
お悔やみの手紙の書き方を知りたい方
一周忌とは?何をする?
「一周忌」といわれると故人の死を弔うというイメージはつかめるものの、詳しい内容はわからないという方も多いと思います。ここでは一周忌の内容、法要に参加できないときの対応について詳しくご紹介します。
亡くなって一年目の命日
亡くなった日からちょうど一年目の命日に行う法要を一周忌といいます。そのほかにも初七日、四十九日法要などさまざまな節目があります。初七日は葬儀とともに行う場合もありますが、四十九日法要と一周忌は葬儀のあとにそれぞれ行います。
遺族が節目に法要を行うことで、仏様によって故人が生まれ変わるとされていることから、法要を行うことが一般的となっています。
「一周忌法要」を行う
当日は僧侶に読経をしてもらい、焼香をします。そのあと法話を聞いて、一周忌法要は終了です。
法要のあとは食事の席を設けている場合が多くあります。特別な理由がない限りは出席しましょう。親戚が多く集まることが多いので、思い出話をしながら故人をしのぶことができます。
参列できないときには手紙でお悔やみの言葉を
一周忌法要の知らせを受けたものの、なんらかの事情があって参列できないということもあるでしょう。法要を執り行う遺族は会場と人数分の食事の手配があるため、欠席の連絡は早めにすることが大切です。
はがきで欠席を連絡したあと、それとは別にお悔やみの手紙を送りましょう。手紙の書き方や内容については後ほど詳しく解説します。
一周忌を欠席する際の注意点とは?
一周忌法要は亡くなってから一年の節目の日に行われるものなので、とても重要な意味をもちます。そのためできる限り参列することが望ましいのですが、どうしても参加できない場合はどのようなことに気をつけるべきなのでしょうか。ここでは一周忌法要を欠席するときの注意点をご紹介します。
早めに連絡する
法要の手配は遺族が行うことが多いです。出席する人数に合わせた会場を決めたり、法要後の食事を手配したりとやるべきことがたくさんあります。連絡が遅れると準備が進まないため、できるだけ早く連絡することを心がけましょう。
欠席の連絡は電話か返信ハガキで
一周忌法要の案内状は往復はがき、または返信用はがき付きで送られてきます。出席・欠席のどちらかに○をつけて返信します。出席するのであれば○のみでも構いませんが、欠席の場合は空白部分に一筆添えておきましょう。
「このたびは○○様の一周忌法要にお招きいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、やむをえない事情により欠席させていただきたく存じます」
などと書くのがよいでしょう。欠席の理由についてくわしく書く必要はありませんが、相手に誠意が伝わるような文章にすることが大切です。
また、法要まで時間がない場合は、はがきの返信とともに電話での連絡をしておくことがおすすめです。できるだけ早く、先方に欠席の旨を伝えておきましょう。
お悔やみの手紙の書き方を知ろう
法要に欠席するときは、別途手紙を送ることが大切です。一周忌法要を迎えるときの手紙にはなにを書くべきか、書き出しはどうするかなどわからない点も多いでしょう。ここではお悔やみの手紙の書き方について詳しくご紹介します。
書き出し
お悔やみの手紙の場合、時候の挨拶は不要です。「○○(故人の名前)様の一周忌法要にお招きいただきありがとうございました」と法要の知らせをくれたことへの感謝を書き出しとしましょう。
「○○(故人の名前)様の一周忌を迎えられ、悲しみを新たにしていることと思います」など、遺族に寄り添う言葉も一緒に書いておくとなお気持ちが伝わります。
お悔やみの言葉
続いてお悔やみの言葉を書き、故人の法要に参加できないことを残念に思う言葉を書きます。
・「生前お世話になった○○様のご法要には、ぜひともお参りさせていただくつもりでおりましたが、やむを得ぬ事情によりお伺いできませんことをお許しください」
・「本来であればお伺いすべきところですが、やむを得ぬ事情により参列できず誠に申し訳ございません」
お悔やみの言葉は、相手が親族であっても礼節をわきまえた文章とする必要があります。砕けた文章にならないよう注意しましょう。
故人の人柄や思い出など
次に自分が思う故人の人柄や思い出について触れましょう。「今もなお○○様のお優しい笑顔が色鮮やかに思い出されます」など、故人はどんな人であったかを記します。
故人といくつもの思い出がある場合は、記憶に残っているエピソードを書くのもよいでしょう。幼いころにたくさん遊んでもらった、悩みがあるときに相談に乗ってもらったなど思い出話を入れることで、自分だけの心がこもった温かな手紙となります。
故人の冥福を祈る・ご遺族を気遣う
ここでもう一度故人の冥福を祈る言葉を書きましょう。「あらためて故人のご冥福をお祈りいたします」「ご生前の面影をしのび、あらためてご冥福をお祈りします」など、故人の幸福を祈るという文章を入れます。
そして、遺族を気遣う言葉として「ご家族皆さまのご健康をお祈り申し上げます」「どうか無理をされませんよう、お身体ご自愛ください」などと書きましょう。「故人の冥福と、ご家族皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げます」と、故人と遺族への気持ちをひとつの文章にしても構いません。
結び
お悔やみの手紙の結びは、故人と遺族への配慮の気持ちとしてもマナー違反にあたりません。故人が仏教徒だった場合は結びの言葉として「合掌」を入れますが、省略も可能です。仏教以外の宗派であれば気にする必要はありません。
最後に後付けとして、手紙を書いた日付と施主の名前、左下に自分の名前を記しておきましょう。
「ご冥福をお祈りします」とはどんな言葉?
通夜や葬儀のときに使われる定型句にはさまざまなものがあり、「ご冥福をお祈りします」もそのひとつです。よく使われる言葉ではあるものの、どんなシーンで使われるのか、どんな意味があるのかを知らないこともあるでしょう。ここでは「ご冥福をお祈りします」という言葉を使うシーンとその意味について解説します。
主に弔電や弔辞に使われる
「ご冥福をお祈りします」という言葉は主に弔電・弔事のときに使われます。弔電とは、故人と親交のあった人物が葬儀に参列できなかったときに送る電報のことです。弔事とは、故人と親しかった人物が葬儀の場で述べる言葉のことです。
遺族と対面したときにお悔やみの言葉として使う人もいますが、宗派によってはこの言い回しが適さないこともあります。口頭で伝える場合は「ご愁傷様でございます」「お悔やみ申し上げます」といった言葉を選ぶとよいでしょう。
「ご冥福」の意味
「冥福」の冥は冥土、福は幸福という意味をもちます。つまり「ご冥福をお祈りします」とは「故人が冥土で幸福になることを祈っています」ということです。
お悔やみの言葉の多くは遺族に向けた言葉ですが、この言葉は故人に向けた言葉です。「○○様のご冥福をお祈りいたします」というふうに、故人の名前を入れて用いるとよいでしょう。
お悔やみの手紙を書くときのマナーとは?
お悔やみの手紙を書くときは、気をつけておくべきポイントがあります。マナー違反にならないようにくわしく知っておきましょう。
繰り返し表現は避ける
「さまざま」「いろいろ」などの繰り返し表現は避けましょう。同じ文字を繰り返し使う言葉は、不幸が繰り返されることを連想させます。弔事の言葉としては不適切であるため、文章を書き終えたら繰り返し表現がないかをチェックしましょう。
また、忌み言葉にも気をつける必要があります。死を連想させる「四」、苦を連想させる「九」や直接的な表現である「死亡」や「死去」もお悔やみの手紙にふさわしい言葉とはいえません。言葉に気をつけながら手紙を書きましょう。
はがきは使わない
法要の出欠確認ははがきにて行いますが、別途送るお悔やみの手紙にははがきは使わないようにしましょう。一般的にはがきは誰に見られても構わない内容、簡潔に用件を伝えるときに用いられるものです。
お悔やみの手紙は故人と遺族への気持ちを記したものなので、はがきでは失礼になります。白無地の用紙に手紙を書き、白い封筒に入れて郵送しましょう。用紙は縦書きのものをおすすめします。
和封筒は一重のものを使う
和封筒には二重・一重のものがありますが、一重のものを選びましょう。二重のものが正式な封筒だとされていますが、お悔やみの言葉を述べる手紙を入れるときは二重だと失礼になります。二重のものは不幸が重なるという意味合いがあることから、祝いごとなどに適しているとされています。
封筒は白無地、住所や宛て名が縦書きできるものを使いましょう。柄付きの封筒や色がついた封筒は弔事には不向きであるため注意が必要です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
亡くなってからちょうど一年目にあたる命日に行われる一周忌は、節目の法要として大切な行事です。どうしても都合がつかない場合を除き、極力参加することが望ましいでしょう。参加が難しい場合は、お悔やみの手紙を書いて施主に郵送するのがマナーです。
一周忌法要に関するマナーや知識は、ほかにもさまざまなものがあります。法要・法事に関するお困りごとや葬儀全般に関する疑問がある場合は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


葬儀の挨拶では、不幸を連想させてしまう忌み言葉と重ね言葉には気をつけましょう。ホゥ。