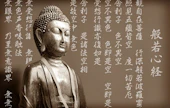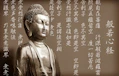「般若心経」はお経の中でも知名度が高く、耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、名前は知っていてもどのようなお経なのか意味を知らない方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、般若心経の具体的な意味や宗派による違いなどを解説します。知らなかった般若心経の全体像がわかれば、法要だけでなく日常生活にも役立つでしょう。
<この記事の要点>
・浄土真宗、日蓮宗では般若心経を唱えない
・般若心経の中心には「空」と「色」があり、宇宙全体における形のあるものを意味する
・般若心経の「色即是空」は形あるものは変わり、時代の変化を象徴すると解釈できる
こんな人におすすめ
般若心経とは何かを知りたい方
般若心経はどの宗派で唱えられているかを知りたい方
般若心経が説いている内容と意味を理解したい方
般若心経とは?
般若心経の大まかな内容や歴史的な意味を知ることで、どれだけの歴史があるお経なのかイメージできるでしょう。
ここからは、般若心経の意味や歴史的背景を紹介します。
宗派を超えた短いお経
般若心経は複数の宗派で読まれているお経で、262字と短い内容です。正式名称は「般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」「摩訶般若波羅蜜多心経(まかはんにゃはらみったしんぎょう)」です。
日本でもっとも知名度の高いお経であることから、仏教系の学校で生徒が唱えることもあります。短いお経ですが、各文には人生に通じる深い意味があり、研究対象としても人気なのが特徴です。
般若心経の由来
般若心経はインドをルーツとする仏教の経典です。インドの経典や仏具が日本に伝わり、日本の仏教において翻訳されたものと考えられています。
般若心経の原題はサンスクリット語です。仏教にはインドがルーツとされる教えや経典が複数あり、それらが日本に定着していることも知られています。般若心経もまた、インドの宗教に由来した経典のひとつだといえるでしょう。
誰が作ったのか?
日本のお経としての般若心経を完成させたのは、玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)です。5世紀に活躍した中国の僧侶であり、ドラマ『西遊記』のキャラクター「三蔵法師」のモデルにもなりました。
玄奘三蔵は13歳で僧侶になり、26歳でインドに渡ります。約16年間インドを旅した末に、日本の仏教のもとになる経典などの仏教道具を持ち帰っています。帰国後に翻訳したお経のひとつが般若心経でした。
般若心経はどの宗派で唱えられている?
日本には多くの宗派が存在しており、般若心経の扱われ方も異なります。そのため、般若心経を唱えない宗派も少なくありません。
ここからは、般若心経と宗派の関係性を踏まえつつ、各宗派の特徴と般若心経の扱われ方を解説します。宗派別の教えやお経について理解を深めていきましょう。
天台宗・真言宗
天台宗は比叡山延暦寺が総本山の宗派です。天台宗では「妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)」というお経が有名で、「すべての人に悟りの世界を与えること」を教えの中心としています。葬儀や法要では使わず、勤行儀(ごんぎょうぎ)という修行で使われるのが特徴です。
真言宗には50に及ぶ宗派があります。高野山真言宗が最大の宗派で、般若心経は信者の修行で唱えるほかに、葬儀でも使われています。
臨済宗・曹洞宗
臨済宗は鎌倉仏教のひとつとしてはじまりました。本尊がなく、宗派が複数に分かれています。禅宗の一つで、座禅により心身の調和を図ります。宗派ごとに細かい作法が異なりますが、勤行・葬儀でも般若心経を使うのが特徴です。
曹洞宗も禅宗で、ひたすら座禅を組みます。ほかの宗派と同じく、勤行・葬儀で般若心経が使われています。
浄土宗
浄土宗は鎌倉にルーツがある仏教のひとつで、「鎮西派」と「西山派」という2つの宗派に分かれています。
歴史的に宗派が分かれる機会が多く、それらをまとめるために「宗教法人浄土宗」が生まれました。しかし、現在の宗教法人浄土宗に西山派は入っておらず、違いが明確になっています。
「南無阿弥陀仏」という念仏を唱え、平穏な毎日や極楽往生を望むのが主な教えです。無量寿経や阿弥陀経などを主に唱えますが、祈願や食作法時に般若心経を唱えることもあります。
浄土真宗
浄土真宗には2つの宗派があります。西本願寺に本山がある本願寺派と東本願寺を本山とする大谷派です。
本願寺派は「臨終後すぐに極楽浄土に向かう」という考えで、故人を北枕に寝かせます。お経は浄土三部経で、般若心経は唱えません。大谷派は「南無阿弥陀仏」と唱えることで極楽浄土へ導くという教えです。こちらも般若心経は唱えません。
日蓮宗
日蓮宗は「南無妙法蓮華経」という漢字7文字による題目を唱える修行で有名です。何周にもわたり唱え続けることで、即身成仏ができるという言い伝えがあります。
釈迦が伝えた法華経の教えを主としており、「一人一人が仏で常に命に感謝しよう」という考え方です。お経は法華経からの内容に特化しているため、般若心経は唱えません。
般若心経が説いている内容と意味とは
般若心経を唱える目的や、お経の意味を知りたい方もいるでしょう。お経に出てくる「空」や「色」などには特有の意味があります。ここからは、般若心経の内容について解説します。
中心にあるのは「空」と「色」
般若心経で特に重要な言葉に「空」と「色」があります。ここでの「色」は、宇宙全体における形のあるものを意味します。宇宙の星から始まり、目の前にある一つ一つの物体すべてが形とともに「色」をもっています。赤・青・黄色・白・黒など、周囲にあるものを見渡せば、ほとんどに色がついていることがわかるでしょう。
一方で「空」は般若心経における色が示すもので、無心を意味します。「すべての形のあるものの中に、形のない無心がある」というのが般若心経の教えです。すなわち「空」は天にあるものではなく、物の奥に潜む形のない概念を示しています。
「色即是空」をどう理解する?
般若心経には「色即是空(しきそくぜくう)」という表現があります。「色はすなわち空を意味する」という意味です。
「この世の万物は形のある『色』として表現でき、それ自体が『空』にもなりうる」というのが般若心経の教えです。物事の本質には「空」という無心がありながら「色」を表しているといいます。「時が経てば形があるものは変わり、時代の変化を象徴する」と解釈できるでしょう。
「般若心経」は何を唱えている?
般若心経は「空」の思想を説いた経典という説が有力です。人によっては解釈が違ったり、有力な説をもとに新しい考えを発見したりすることもあるでしょう。しかし般若心経はあくまでも「空」という形のない概念を主役にしています。
般若が開く悟りをテーマとしていますが、色や空のあり方をとらえることも悟りのうちであると示しています。以上から般若心経は「空」を中心としながら、物事の奥深さを悟る経典ともいえるでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
般若心経は複数の宗派で読まれているお経で、262字と短い内容です。日本でもっとも親しみのあるお経ですが、般若心経を唱えない宗派も少なくありません。浄土真宗では「臨終後すぐに極楽浄土に向かう」と考えられているので、般若心経は唱えません。
小さなお葬式には、豊富な葬儀実績で培ったノウハウがあります。葬儀につきものの宗教や宗派についてお困りの方はぜひ「小さなお葬式」までご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
般若心経を素人が唱えるといけない?
般若心経を唱える効果は?
宗派に関係なく般若心経をあげてもいいの?
般若心経の「無眼耳鼻舌身意」の意味は?
般若心経と龍樹との関係?
祝詞と般若心経はどちらが除霊向きですか?

包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。