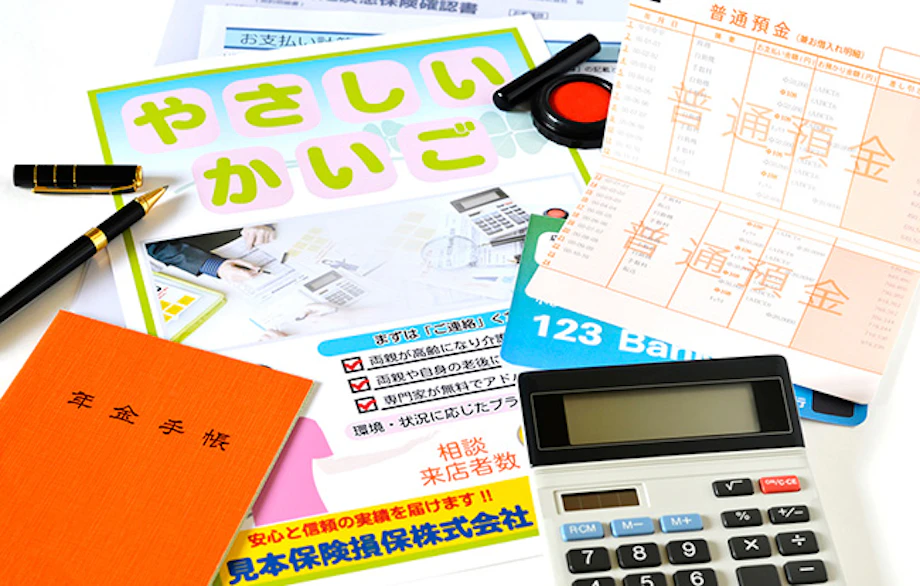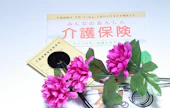40歳になると誰もが加入する介護保険ですが、制度を活用するには手続きが必要です。手続きをしたくても申請の方法がわからずにお困りの方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、介護保険の手続き方法を紹介します。手続きに必要な書類やサービスを受け始めるまでの手順を確認しておくことで、介護保険をスムーズに利用し始めることができるでしょう。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・介護保険の手続きは自治体の窓口で行い、必要書類を提出する
・書類提出後に訪問調査などが行われ、介護認定が算出される
・介護保険申請に必要な書類は申請書、介護保険被保険者証、身分証明書
こんな人におすすめ
介護保険の手続き方法を知りたい方
介護保険の手続きに必要なものを知りたい方
要介護認定のルールを知りたい方
介護保険の手続き方法
介護保険を利用して介護サービスを受けるには書類を提出するだけでなく、訪問調査を受けて対象者の状態を伝える必要があります。ここでは必要な手続きと認定を受けるまでの流れを見ていきましょう。どのような準備が必要なのかをしっかり把握すれば、戸惑わずに対応できます。
1.必要書類の用意・申請
介護保険の手続きは自治体の窓口で行います。申請を受け付けている窓口の名称は「高齢者支援課」や「介護保険課」など、自治体によって異なるので事前に調べておきましょう。
申請するには、申請書に記入して必要書類を揃えて窓口に提出します。本人以外が代理で申請を行うことも可能です。代理申請は家族に行ってもらうのが一般的ですが、諸事情により家族の手助けがえられない場合は地域包括支援センターや支援事業者のスタッフに頼むこともできます。
2.訪問調査
申請を行うと、後日自治体の担当者から訪問調査を行う旨の通達があります。訪問調査はケアマネージャーなどの担当者が対象者のもとに訪問して、聞き取りで対象者の状態を確認するものです。
調査は「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活の適応」などの基本調査74項目、概況調査、特記事項について行われます。生活に必要な基本的な動作ができるかといったことや普段の生活の様子を聞かれるので、スムーズに受け答えできるように日頃の様子をメモに取っておくとよいでしょう。
3.1次判定
訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、コンピューターで分析を行って出されるのが1次判定です。要介護認定等基準時間(介護にかかる推定所要時間)が算出され、7段階にレベル分けされます。
1次判定には、意見書を提出するための、かかりつけ医による診断が必要です。かかりつけ医がいない場合は自治体が紹介した医師の診断を受けることになります。
4.2次判定
1次判定の結果を受けて、専門家から成る介護認定審査会が2次判定を出します。この2次判定で対象者の介護の必要性が正式に決定されるシステムです。介護認定審査会は5名ほどの医療・保健・福祉の学識経験者で構成される合議体で、各分野の見地から対象者が必要な介護を受けられるように審査を行います。
5.認定結果の通知
申請から訪問調査や判定を経て、原則30日以内に自治体から認定結果が通知されます。30日経っても通知が到着しない場合は、自治体に進捗を問い合わせてみましょう。地域によっては2か月ほどかかる場合もあります。
その後は通知された要介護度に沿ったサービスの利用が可能です。希望するサービスを選んでケアマネージャーや家族と相談しながらケアプランを作成しましょう。
介護保険の手続きに必要なもの
介護保険の申請には下記の書類が必要です。すべて揃えて自治体の窓口に提出しましょう。ただし、自治体によっては必要な書類が異なることもあります。
申請書
自治体の窓口で配布されている書類です。インターネットから入手できる自治体も増えており、ファイルをダウンロードして印刷すれば使用できます。
申請書に記入する内容は、対象者本人の氏名・生年月日・住所・電話番号といった個人情報や、介護保険被保険者証に記載されている被保険者番号などです。訪問調査に立ち会う立会人の情報も必要なので、申請の段階で誰が立ち会うかを考える必要があります。
介護保険被保険者証
65歳の誕生日を迎えて、第1号被保険者となるときに自治体から送付されたものです。40歳~64歳の第2号被保険者の場合は、代わりに健康保険被保険者証を提出しましょう。
身分証明書
対象者ではなく申請する方の身分証明書が必要です。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの身分証明証を用意しましょう。
要介護認定のルール
認定を受ければ介護保険のサービスを利用できますが、すべてのサービスを受けられるわけではありません。介護保険にはルールがあり、ルールの範囲内で利用することになります。どのサービスを受けられるのか把握するためにも、しっかりと確認しましょう。
要介護認定には要介護レベルがある
要介護認定にはレベルが設定されており、レベルによって利用できるサービスが異なります。レベルの種類は、要支援1・2と要介護1~5の7つです。介護にかかる推定所要時間が多いほど高いレベルに認定されます。要支援1<要支援2<要介護1<要介護2<要介護<要介護4<要介護5の順にレベルが上がっていくことを覚えておきましょう。
要支援はほぼ自力で生活可能な状態ですが、要介護は日常生活の動作になんらかの介護が必要と判断されるレベルです。要介護3は日常生活においてほぼ全面的な介護が必要となり、要介護5は介護なしに日常生活をおくることがほぼ不可能な状態になります。
支給限度額は要介護認定区分による
支給限度額とは、認定を受けた方が介護サービスに利用可能な月ごとの限度額です。支給限度額は要介護度によって違いがあり、レベルが高いほど支給限度額も高くなります。要介護度別の支給限度額は下記のとおりです。
| 要介護度 | 支給限度額 |
| 要支援1 | 5万320円 |
| 要支援2 | 10万5,310円 |
| 要介護1 | 16万7,650円 |
| 要介護2 | 19万7,050円 |
| 要介護3 | 27万480円 |
| 要介護4 | 30万9,380円 |
| 要介護5 | 36万2,170円 |
支給限度額の範囲内で利用したサービスの自己負担率は1割~3割です。支給限度額を超えて利用する場合の超過分はすべて自己負担となります。
(参考:『2019年度介護報酬改定について』)
要介護認定には有効期間がある
要介護認定は1度受ければ永続的に有効というわけではありません。新規に認定された有効期間は基本的に6か月と定められています。自治体が必要と認めれば、3か月~12か月の範囲で自治体が月単位の設定をすることも可能です。新規認定でない場合の有効期間は12か月で、自治体が設定可能な範囲は3か月~36か月となります。
有効期間が過ぎると認定の効力がなくなってしまうので、期間後も引き続き介護保険の利用を希望する場合は更新手続きを行いましょう。
(参考:『厚生労働省 要介護認定の有効期間について』)
要介護認定に納得できない場合の対策
申請を行って認定通知が届いても、その結果が腑に落ちないことがあるかもしれません。そのようなときの対処方法として、不服申し立てと区分変更を行うための手続き方法を解説します。
認定結果によって介護者の負担が大きく変わることもありますから、納得できない場合に対応できるようにしておきましょう。
介護保険審査会に不服申し立てを行う
認定結果に疑問がある場合、中立的な第三者機関である介護保険審査会に不服申し立てができます。不服申し立ての受付期限は3か月です。期限を過ぎると受け付けられないので注意しましょう。
申し立て方法は各自治体によって異なります。書面を提出するのが一般的ですが、一部では口頭での申し立ても可能です。口頭での申し立てを受け付けている自治体では、職員が聞き取りを行い「審査請求録取書」を作成します。居住する自治体の申し立て方法は問い合わせて確認しましょう
区分変更申請を行う
区分変更申請は認定を受けている方の状態が大きく変化した場合に要介護度の変更を申し込むものですが、認定結果に不服がある場合に利用する方もいます。区分変更申請には受付期限が設けられていないため、必要と感じたときにいつでも申請可能です。
区分変更申請を行う際は、新規で申請したときと同様に自治体の窓口で手続きを行います。区分変更用の申請書に記入し、介護保険被保険者証・本人確認書類などと一緒に提出しましょう。
要介護認定後に受けられる介護サービス
要介護度が認定されれば、さまざまな介護サービスを利用できます。利用できる内容は要介護度によって異なるため、対象者の区分とその区分で受けられるサービス内容を把握しておくことが重要です。ここでは、要介護と要支援に分けてサービス内容を紹介します。
要介護1~5で受けられる介護サービス
要介護1~5と認定された場合、介護を目的としたサービスを受けられます。食事・排泄・入浴などの介護を自宅で通いのホームヘルパーからを受ける「訪問タイプ」や、介護施設や老人ホームへ入居する「入所タイプ」、デイサービスやリハビリなどが必要なときに施設へ足を運ぶ「通所タイプ」などが利用可能です。
普段は自宅で生活して、体調が悪いときは一時的に施設に入所するなどいくつかのタイプを組み合わせることもできます。
要支援1~2で受けられる介護サービス
要支援の認定を受けた方は、介護予防サービスを利用できます。介護予防サービスは、できる限り介護を必要とせずに生活していくために提供されるものです。
自宅にホームヘルパーが訪問して行う訪問入浴や訪問看護、施設に通って行うリハビリなどが対象になります。対象者への支援だけでなく、家族の負担の軽減も目的としたショートステイも利用可能です。
(参考:『公表されている介護サービスについて』)
介護保険・介護予防サービスを利用する手順
同じ要介護度でも、症状や環境はさまざまです。必要なサービスも人によって異なります。そのため実際に利用するには、個人に合ったサービスを受けるための手続きを行わなければなりません。認定後からサービスを受けるまでの流れを解説します。
介護保険サービスの場合
まずは知事の指定を受けたケアマネージャーがいる居宅介護支援事業者に連絡し、ケアプランを作成したいと伝えましょう。居宅介護支援事業者は自治体のホームページなどでも調べられますが、地域包括支援センターでも紹介してもらえます。
担当のケアマネージャーが決まったらどのようなサービスを受けたいかなどを伝え、ケアプランの作成を依頼しましょう。完成したら、そのブランにもとづいて、サービスを提供している事業者を探し契約をします。自宅を出て介護施設や老人ホームに入る場合、ケアプランの作成は入居する施設に所属するケアマネージャーが担当するのが一般的です。
介護予防サービスの場合
介護予防サービスを希望する場合、地域包括支援センターに連絡が必要です。センターのスタッフにどのようなサービスを受けたいのか要望を伝え、ケアプランの作成を依頼しましょう。介護サービスは、ケアプランの作成依頼先が異なるので注意してください。以降は作成したケアプランの内容に沿って、必要な介護予防サービスを利用できます。
介護保険の更新手続きをする方法
介護保険を継続して利用するためには、更新手続きを行う必要があります。有効期間が過ぎるとサービスを受けられないため、更新時期をきちんと把握して事前に備えておくことが大切です。ここでは更新に必要なものと申請方法を確認しましょう。
必要なもの
更新の申請に必要なものは下記のとおりです。基本的には新規で申請を行う際と変わりません。
・更新申請書:自治体の窓口のほか、インターネットからのダウンロードでも入手できます。
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証:40歳~64歳の方のみ
・本人確認書類:マイナンバーカードや運転免許証など
自治体によっては印鑑や、本人確認書類とは別にマイナンバーカードなどが必要なこともあるので、疑問があれば問い合わせてみましょう。調査が進む段階でかかりつけ医の意見書が必要になるのも、新規申請のときと同じです。
申請の流れ
更新申請後は、基本的に新規のときと同じ流れで調査をしてあらためて判定を行います。ただし、更新時の1次判定の結果と前回の1次判定の結果が同じなどの条件を満たせば、2次審査の簡素化が認められています。
更新申請を行ってから認定されるまでの期間は30日以内が原則です。それを超える場合は自治体からその旨が通知されます。30日を過ぎても何の連絡もない場合は問い合わせをしましょう。
家族信託という選択肢もある
ご自身やご両親の方に介護が必要になったときの心配ごととして、介護保険の他に、認知症のことがあるのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。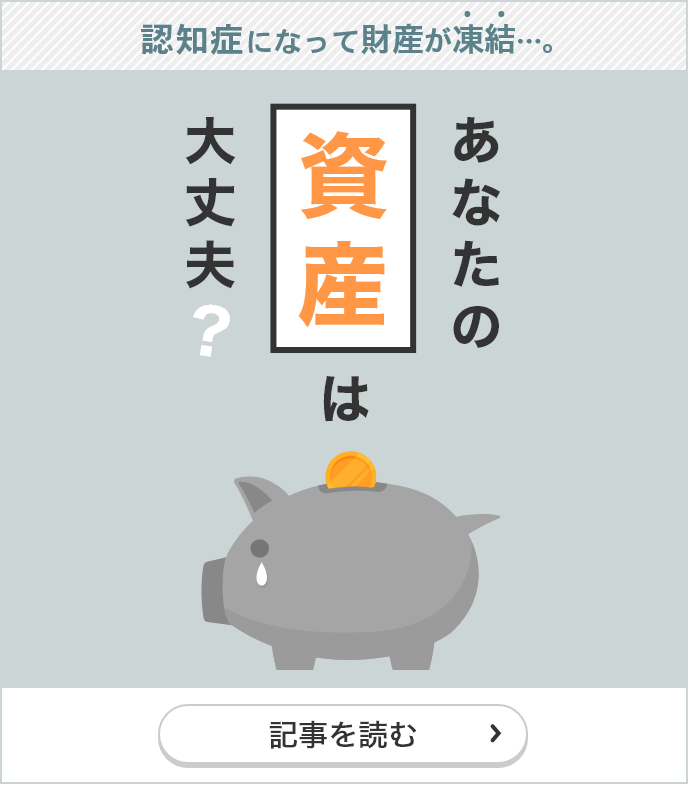
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
介護保険は必要書類を揃えて申請を行い、訪問調査、1次・2次判定を経て要介護度を決めます。その後ケアプランを立て、要介護度に合わせたサービスを受けるというものです。更新時期が近づくと自治体から通知が届くので、更新申請も忘れずに行いましょう。
介護保険のサービスを考えるころは、人生の終末期に向けて考える時期としてもふさわしいタイミングです。健康なうちに、家族に自分の思いや希望を伝える準備をしましょう。小さなお葬式では、葬儀プランや相続に関するご相談を承っています。この機会にぜひお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618へお電話ください。


訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。