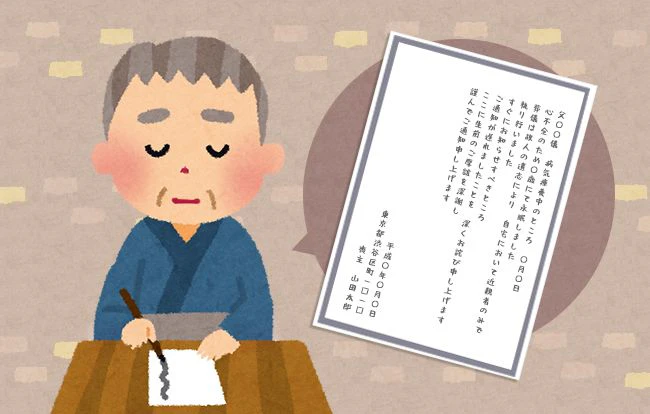近親者が亡くなったことを法的に証明するために役所へ提出する書類が「死亡届」です。死亡届を提出しないと、あらゆる手続きが滞ります。しかし、故人の口座からお金を引き出したい場合は、口座の凍結が心配で提出に踏み切れないこともあるでしょう。
この記事では、銀行口座凍結後の引き出しや相続手続きの方法を解説します。凍結されるタイミングを知れば、必要な手続きを円滑に進めることができます。亡くなった後の流れに沿って順に確認していきましょう。
<この記事の要点>
・死亡届を提出しても金融機関が口座名義人の死亡を把握しない限り、口座は凍結されない
・口座の凍結を解除するには相続手続きが必要
・2019年の民法改正により、凍結された口座から一定額の預貯金を引き出すことが可能
こんな人におすすめ
身内が亡くなった方
亡くなった後の必要な手続きを知りたい方
死亡後の銀行口座の取り扱いについて知りたい方
死亡届を提出したら銀行口座は凍結される?
人が亡くなると、その方が所持していた銀行口座は凍結されます。銀行口座の預貯金は故人の遺産です。ここからは、銀行口座がどのような手順で凍結されるか解説します。
死亡届で銀行口座は凍結しない
居住地の役所へ死亡届を提出すると、役所から各金融機関へ通達されて銀行口座が凍結すると考えている方もいるようです。しかし、役所から各金融機関に死亡が通達がされることはありません。口座は、凍結手続きをして初めて凍結されます。
銀行口座が凍結されるタイミング
銀行口座が凍結されるタイミングは、名義人が亡くなった事実を金融機関が把握した時点です。多くの場合は、遺族が金融機関へ連絡したタイミングで凍結されます。一般的に申請を行わない限り口座は凍結されません。
ただし、金融機関の職員が新聞のお悔やみ欄や葬儀の看板を見て、口座を凍結する可能性はあります。他にも、残高証明書の取得申請から名義人が亡くなった事実を把握することができます。
凍結申請は簡単だが解除は大変
故人の口座の凍結申請は、不要なトラブルを避けるためにもしておいた方がよいでしょう。故人の口座がある金融機関へ届出をすれば、銀行口座は凍結します。
その際は、口座名義人である故人の氏名や口座番号が必要になります。口座の凍結は簡単にできますが、凍結の解除には時間がかかります。凍結を解除するには、相続手続きが必要になるためです。
遺言書の有無や遺産分割協議書の有無によって、凍結解除するのに必要な書類は異なります。事前に必要な書類を調べておけば、スムーズに手続きができるでしょう。
口座を凍結する理由
金融機関が故人の口座を凍結する理由は、大きく分けて2つあります。ひとつは相続財産を死亡日時で確定させるためです。誰でも口座からお金を引き出せる状態だと、相続財産が不明瞭になり相続人の権利侵害につながります。
もうひとつは、相続時のトラブルを防止するためです。相続前に誰かが財産を引き出して使用すると、遺産分割を正しく行えません。金融機関の口座凍結は、故人の預貯金を守り、正確な相続を行うための重要な手続きです。
口座が凍結される前に!葬儀費用を準備するための対策
名義人が亡くなったことを金融機関が知らなければ、口座が凍結されることはありません。しかし、突然ふとしたことで凍結される可能性もあります。ここからは、口座の預貯金が必要な場合に備えて、凍結される前にできる対策を紹介します。
亡くなる前に必要な費用を借りておく
名義人が亡くなる前に必要な費用を引き出しておくことで、口座凍結による最悪の事態を避けられます。生活費をはじめ、介護費用や医療費、葬儀費用など引き出しておくとよいでしょう。相続時に精算を行う場合は、領収書が必要です。
不要なトラブルを避けるために一定の金額を生前から誰かに託す場合は、相続人や他の親族の合意を得ておきましょう。
生命保険を利用する
生命保険に加入するのも有効な対策です。生命保険は指定した受取人が保険金を受け取る仕組みなので、確実に費用を確保できます。預貯金のように口座の凍結を気にする必要がありません。
ただし、死亡保険金には相続税が課されます。ほとんどの場合、非課税枠が設けられているので、契約時に金額が枠内に収まっているか注意しましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
口座が凍結しても引き出しはできる?
2019年7月1日に民法が改正され、凍結口座から一定額の預貯金を引き出せるようになりました。今までより簡単に預貯金の引き出しができますが、遺産相続人と指定されている方のみ凍結した口座から預貯金を引き出せます。
また、預貯金を引き出す際は、1金融機関につき150万円と限度額が決まっています。それ以上の金額は引き出せません。凍結した口座から預貯金を引き出す場合は、事前に手続きが必要になります。
(参考:『遺産分割前の相続預金の払戻し制度』)
凍結した銀行口座の引き出し手続き
故人の凍結した銀行口座から預貯金を引き出すには、所定の手続きが必要になります。前もって必要な書類を用意しておくことで、スムーズに預貯金を引き出せるでしょう。ここからは、凍結した口座から預貯金を引き出す方法を紹介します。
引き出し可能な預貯金の金額
凍結した故人の口座から引き出せる金額は、計算式によって定められています。計算式は以下のとおりです。
単独で引き出せる総額=凍結している口座の残高 × 3分の1 × 自分に法定相続される金額
たとえば、凍結された口座の残高が900万円である場合を式にあてはめて計算してみましょう。口座の持ち主である父親が亡くなり、母親は存命です。凍結した口座から預貯金を引き出すのは、2人姉妹の長女です。
900万円 × 3分の1 × 3分の1=100万円
長女が引き出せる総額は100万円です。葬儀費用などを故人の預貯金から工面する場合もあるでしょう。引き出せる金額に上限はありますが、口座の凍結解除の手続きは不要なので、遺族の金銭的負担を減らせます。
引き出しに必要な書類
故人の凍結した口座から現金を引き出す際は、以下の書類が必要です。忘れずに準備しましょう。
・故人の除籍謄本か戸籍謄本、もしくは出生から死亡まで連続した「全部事項証明書」
・相続人全員分の戸籍謄本、もしくは出生から死亡まで連続した「全部事項証明書」
・預貯金を引き出す方の印鑑証明
金融機関によって必要書類は異なるので、故人の凍結した口座がある金融機関へ確認するとよいでしょう。
引き出す前にほかの相続人に連絡を!
凍結した口座から現金を引き出す際は、相続人全員分の戸籍謄本もしくは、全部事項証明書が必要です。そのため自分以外の法定相続人に、預貯金を引き出すことを連絡する必要があります。
説明もなく現金を引き出す事実だけを告げても、相続人の中には納得できない方がいるかもしれません。トラブルを避けるためにも、現金を引き出す理由や引き出した現金の用途を相続人全員に説明しましょう。
<関連記事>
死亡手続き後に知っておきたい戸籍謄本が必要なケースと取り寄せ方
小さなお葬式で葬儀場をさがす
凍結した銀行口座の相続手続き
凍結した口座の凍結解除を行う際には、遺言書の有無で必要になる書類や手続きは異なります。また必要書類や手続きは金融機関によっても異なるので、事前に確認しておくとよいでしょう。ここでは、凍結した銀行口座の相続手続きについてご紹介します。
遺言書がある場合
遺言書がある場合、相続人は凍結している口座のある銀行で手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類は以下のとおりです。
・被相続人が死亡していることを確認できる戸籍謄本
・遺言書
・検認済証明書(自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言の場合)
・遺言執行者の選任審判書謄本(相続人が裁判所によって選ばれた場合)
・相続人の印鑑証明書
・相続人の実印
・依頼書(銀行によって名称が異なるので確認しましょう)
・印鑑届(口座の名義を変更する場合のみ)
・通帳
・銀行証書
・キャッシュカード
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、遺産を分割する協議を行います。相続人が決定し、凍結した口座の解除をする場合、遺産分割協議書の有無で必要書類に大きな違いはありません。
| 遺産分割協議書がある場合 | 遺産分割協議書がない場合 |
| 遺産分割協議書 | なし |
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)か、除籍謄本、全部事項証明書 | |
| 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 | |
| 相続人全員分の印鑑証明書(未成年の場合は、法定代理人のもの) | |
| 手続きをする方の実印 | |
| 依頼書(銀行ごとに異なるので、銀行に準備されているものに記載する) | |
| 印鑑届(口座の名義を変更する場合のみ) | |
| 通帳 | |
| 銀行証書 | |
| キャッシュカード | |
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
死亡届を役所に提出しても、銀行口座は凍結されません。故人の口座が凍結されるタイミングは、金融機関が名義人の死亡を確認した時です。死亡届の提出後も利用できますが、金融機関が亡くなったことを把握すれば凍結されてしまいます。
故人の預貯金や相続人の権利を守るためにも口座の凍結は重要です。凍結後も手続きを行えば、故人の口座を利用することはできます。手続きが面倒に感じる方は、口座が凍結されても問題ないように、対策を取ってから金融機関へ連絡しましょう。
口座の凍結解除は必要書類が多く、手続きに不安がある方も少なくありません。金融機関の口座凍結でお困りの際は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
口座が凍結しても引き落としはできる?
口座が凍結したら他の銀行も引き出せなくなる?
凍結した口座を放置するとどうなる?

不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。