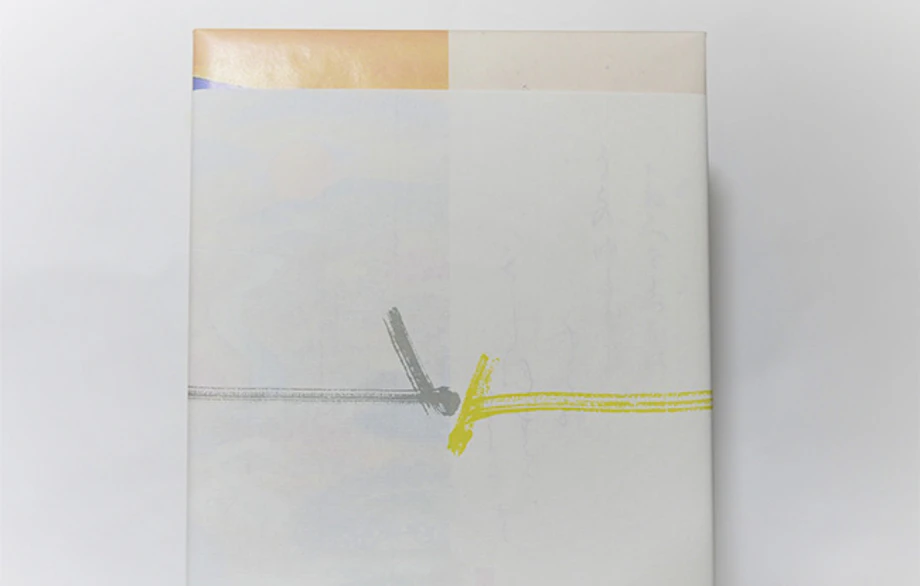一周忌に列席していただいた方へのお礼として、引き出物(お返し)を準備することが一般的です。ただし、引き出物(お返し)にもマナーがあり、控えた方がよい品物もあります。
また、引き出物(お返し)には「のし」をつけますが、この書き方にも作法があります。この記事では、一周忌の引き出物(お返し)の選び方とのしの書き方を紹介します。
<この記事の要点>
・一周忌の引き出物はのりやお茶、砂糖などの食品や菓子折りがおすすめ
・一周忌以降の法要の場合、濃い墨や筆ペンでのしの表書きを書くのがマナー
・一周忌のお返しの表書きには「志」や「粗供養」と書くことが一般的
こんな人におすすめ
引き出物(お返し)とは何かを知りたい方
一周忌の引き出物(お返し)の選び方を知りたい方
一周忌の引き出物の「のし」の書き方を知りたい方
引き出物とは
一周忌のお返しとして用意する引き出物は、参列者を交えて行う場合には欠かせません。一周忌では、法要後の会食で渡すのが一般的です。引き出物は法要を執り行う遺族が事前に手配しておく必要があるため、しっかりと準備を行いましょう。
一周忌の引き出物(お返し)|選び方について
一周忌の引き出物(お返し)は、法要に参列していただいた方に対する感謝の気持ちを表す品物です。ではどのような品物が、一周忌の引き出物(お返し)にふさわしいのでしょうか。
法要の参列者に対する感謝の気持ちは、直接言葉で表すのが大切です。ただし、縁起が悪い物として受け取られるケースがあるため、引き出物(お返し)は何でもよいというわけではありません。引き出物(お返し)をもらう側の身になって、貰って嬉しい品物・ギフトを選びましょう。
一周忌の引き出物はどんなものがいいの?
ここでは一回忌の引き出物(お返し)としておすすめのものを紹介します。参列者に喜んでもらえるよう、最適なものを選ぶ参考にしてください。
食品
のりやお茶、砂糖、調理油などの食品や菓子折りが引き出物としておすすめです。
法要はお祝いではありません。そのため、いつまでも不幸が残らないように「残るもの」は避けることが一般的です。
また、菓子折りは持ち運びに便利な引き出物です。洋菓子、和菓子問わず選んで構いません。故人を偲ぶという意味で、故人にちなんだお菓子がふさわしいかもしれません。遠方の方がいれば、地元の銘菓を贈ると手土産としても喜ばれるでしょう。
生活用品
キッチンで使う洗剤、洗濯洗剤やせっけん、入浴剤、タオルなどの生活関連用品も引き出物(お返し)としておすすめです。特に洗剤やせっけんは「洗い流す」というイメージがあり、不幸を洗い流すという意味を込めて贈ることがあります。
ただし、生活関連の引き出物は重量があるものが多く、荷物が増えることになるため、遠方の方にとっては好ましくありません。重いものは郵送にするといった配慮ができるとよいでしょう。
カタログギフト
引き出物を用意する遺族の負担と、引き出物を贈られる参列者双方の負担を軽減できるのがカタログギフトです。準備で忙しい遺族にとって、買い出しの手間も省けるため、負担を減らすことができます。
贈られる側としては、必要なときに好きなものを選び、好きなタイミングで利用することができます。生もの、レジャーや旅行関連のアイテムも選べるので、選択の幅が広いのもカタログギフトのよいところです。
一周忌の引き出物(お返し)|のしについて
一周忌のお返しにつけるのし紙ですが、のしの選び方、つけ方、書き方にそれぞれ作法があります。
弔事(葬儀・法要)の「のし紙」
弔事(葬儀・法要)の「のし紙」を整理しておきましょう。
葬儀/通夜
表書き:御供/御仏前/御霊前
水引:黒白結び切り
のしあわびはつけない
葬儀お返し
表書き:志/粗供養
水引:黒白結び切り
どの宗教にも通用
法要
表書き:御供/御仏前/御霊前
水引:黒白結び切りもしくは黄白の結び切り
のしあわびはつけない
法要お返し
表書き:志/粗品/粗供養
水引:黒白結び切りもしくは黄白の結び切り
香典返しののし
通夜・葬儀・告別式などでいただいたご香典(ご霊前)を忌明けとなる「四十九日(又は三十五日)」後に、 お返しするのが香典返しです。
この香典返しには通例のし紙をつけます。のし紙のおもて書きは、「志」が一般的ですが、地域、宗教により変わります。西日本の多くの地域で四十九日後の香典返しは「満中陰志」、神式では「偲び草」などが使われる場合があります。
のし紙の種類は告別式前後の御霊前や御供に「黒白結び切り」、関西地方では「黄白結び切り」があります。場面によって相応しい「のし」を選ぶようにしましょう。
「外のし」「内のし」について
「外のし」とは、引き出物を包装してから、「のし紙」をつける形です。 のし紙は包装の上となるため、これを「外のし」と呼びます。 お返しは法要に出席された方への、感謝の気持ちとして渡します。多くの場合、手渡しが多いことから表書きが見えるよう「外のし」が一般的です。
「内のし」は品物を包装する前に、「のし紙」をつけて、それから包装します。 のし紙は包装された内側にくるため、これを「内のし」といいます。
香典返しは、故人が亡くなった際にいただいたお返しとなり、一般的に、控えめな気持ちを表す「内のし」とされます。
遠方の方は葬儀のために来ることが多く、香典返しの場合は法事のお返しと異なり、相手方に宅配便などで直接送るケースが多くなります。輸送中に表書きが汚れないようにする意味も含め、内のしにする場合もあるようです。
のしの書き方
薄墨を使用するのは四十九日までです。それ以降は濃い黒を使います。なぜ薄い黒を使うかというと、四十九日のような忌日法要では、「亡くなってしまい悲嘆に暮れ流す涙で墨が薄くなった」という意味が込められるからです。
そのため一周忌以降年忌法要の場合は、そうした意味合いを込めずに通常の濃い墨や筆ペンでのしのおもて書きを書くのがマナーです。
表書きの正しい書き方
表書きには「志」や「粗供養」と書くことが一般的です。「志」の意味は「気持ち」という意味になり、「心ばかりのものですが、どうぞお受け取りください」という意味が込められています。
のしに名前は書く?書かない?
のしには表書きの下に名前を記載します。通常は苗字のみ、もしくは○○家とします。施主名は名字だけでなくフルネームで記載します。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
一周忌のお返しの品の選び方や「のし」のつけ方・書き方について紹介しました。引き出物の選び方や「のし」のつけ方にはマナーがあり、場合によっては失礼にあたる場合もあるため注意が必要です。
引き出物(お返し)はかさばらない消えものを選ぶようにしましょう。のしは地域や宗派によって選び方や書き方が変わるため、事前に確認できるとよいでしょう。
葬儀関係のことでわからないことがある場合は、「小さなお葬式」へご相談ください。24時間365日、専門知識をもったスタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。