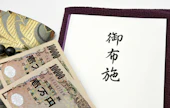法事の参列者から香典をいただいた場合、お返しとして引き出物を渡します。この記事では、法事の引き出物の相場と選び方、渡すタイミングやマナーについてご紹介します。
<この記事の要点>
・法事の引き出物は香典の半分から3分の1程度の金額で、タオルや洗剤、海苔、お菓子などから選びます
・会食がある場合は会食終了直前、会食がない場合は法要終了後に引き出物を渡しましょう
・引き出物の「のし」は黒白の結び切りの水引で、表書きは「志」または「粗供養」とします
こんな人におすすめ
法事のお返しにお悩みの方
法事を予定している方
法事の引き出物を渡すタイミングやマナーを知りたい方
引き出物の相場と選び方
法事の際に渡す引き出物の金額の相場としては、香典の半分~1/3程度がよいとされています。実際には香典をいただく前に手配をするので、2,000~5,000円程度の品を選びます。渡される側の事情を考えて、適切な品を用意しましょう。
引き出物を選ぶ基準は...
①かさばらないもの(持って帰る必要があるため)
②実用性のあるもの(受け取る側に立って考える)
③手元に残らないもの(不幸が残らないとして縁起が良い)
などがあげられます。石鹸や洗剤などの実用品、お茶やお菓子といった食品が贈られることが多いようです。
具体的には、次のようなものが選ばれています。
法事の引き出物の例
石鹸・洗剤
日常的に使うもので、消えもの(消耗品)のなかでも実用性の高いものです。また、汚れを落とすことから、不幸を洗い流すとも言われています。
海苔・お菓子・お茶
消えものであるため、不幸が消滅するとして選ばれるようです。また、いずれも重たいものではないので持ち運びもしやすい点が向いています。
タオル
消えものではありませんが、死後の世界へは白装束を着て旅立つことから、同じく白いタオルを法事のお返しにすることが多いです。
これら以外では、受け取った側が自由に品物を選ぶことができる「カタログギフト」も近年ではよく選ばれています。
引き出物を渡すタイミング
会食がある場合
会食がお開きになる直前のタイミングに渡します。施主自らが各テーブルを回り、一言声をかけながら渡します。このとき、僧侶が同席している場合は最初に渡します。
会食の参加者が多い場合は時間がかかりますし、長々と席の間を動くのも良くないので、予め各席に置いておくのもよいでしょう。
会食がない場合
会食がない場合、あるいは会食の前に帰る人に対しては、法要が終わってお開きになるタイミングで引き出物を配ります。折り詰めの弁当と小瓶に入ったお酒を用意するのもよいでしょう。
引き出物のマナー
引き出物の「のし」
引き出物ののしは、仏式の場合黒白(または銀)の結び切りの水引で、「志」もしくは「粗供養(そくよう)」と表書きをします。
引き出物が混ざらないようにする
参列者全員に同じ引き出物を渡すのであれば問題ありませんが、相手との関係によって引き出物が異なる場合もあります。特別にお世話になった方や関係が深い方に、他の方よりも少し高価な引き出物を渡すことも珍しくありません。その場合は、それらが混ざらないよう印を付けておきましょう。
引き出物の保管と引き渡し
法事のあと、そのまま同じ会場で会食を行うなら問題はありませんが、近年は場所を変えてホテルなどで会食を行うことも増えています。引き出物の渡し方や保管について、ホテルのスタッフと打ち合わせしておくのがよいでしょう。
生鮮食品などは選ばない
お菓子や海苔など食べ物を贈ることも多い引き出物ですが、賞味期限が長いものを選ぶようにしましょう。贈られた側がすぐに食べるとは限らないため、期限が短いと急かすことにもなってしまいます。生菓子や生鮮食品などは選ばないようにしましょう。
相手のことを考えて品物を選ぶことが大切
法事に参列していただいたことや香典に対するお礼として、引き出物は欠かせないものです。身内などでは双方合意の上で用意しないということもありますが、そうでなければ用意するようにしましょう。
法事のお返しに適した品をいくつかご紹介しましたが、その通りにする必要はなく、相手が何を貰ったら嬉しいのかを考えながら選ぶと、きっと良い物が見つかることでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。


御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。