「檀家」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。檀家とは、お寺と深いつながりをもつ家のことです。経済的なサポートを行うかわりに、供養やお墓の管理などをお寺に依頼できるのが特徴です。
この記事では、檀家になるメリットや発生する費用について解説します。これから檀家について詳しく知りたい方の参考になる情報をまとめました。
<この記事の要点>
・檀家になると、手厚い供養を受けられ、お盆などの繁忙期でも仏事に関する幅広い相談が可能
・檀家のデメリットは、入檀料や寄付などの費用が発生し、葬儀や法要を他のお寺に依頼できない点
・離檀する際はトラブルになりやすく、お寺によっては離檀届が必要
こんな人におすすめ
檀家の概要を知りたい方
檀家になるメリットとデメリットを知りたい方
入檀後に必要な費用について知りたい方
檀家とは寺院の運営を支える存在
檀家とは、特定の寺院に所属している家のことを指します。檀家は、個人ではなく「家単位」でなるのが特徴です。自身が知らないだけで、特定のお寺の檀家であることも少なくありません。家の墓がお寺にある場合は、そのお寺の檀家である可能性が高いでしょう。
檀家になると、墓の管理や供養などをそのお寺にお願いできます。その代わりとして、お布施で経済的な支援を行います。
昔はお寺の新築・改築の費用や本山への上納金など、檀家に期待される経済的負担は大きく、経済的な支援は必須ともいえるものでした。しかし、現在では檀家にならなくても供養をしてもらえるようになりつつあり、あまり無理な金銭的支援はしない風潮にあるようです。
檀家になる3つのメリットとは
檀家になると、仏事に関してさまざまな部分で質問ができたり、対応を任せたりできるのが大きなメリットです。ここからは、檀家になる3つのメリットを紹介します。
手厚い供養を受けられる
檀家になれば、お寺から手厚い供養を受けられます。家族が亡くなったときの通夜や葬儀、四十九日法要や納骨などの際に、読経によって手厚く供養してもらえるでしょう。また、戒名の相談もできます。
お寺との関係が代々続いていくと、信頼関係も深まります。回忌法要など継続的に供養を受けることで、安心感や心の平穏を得られるでしょう。
お盆などの繁忙期でも優先してもらえる
お盆の時期は法要を執り行う家が多く、お寺は混雑しています。しかし、檀家であれば、繁忙期であっても優先してもらえることがあります。法要の日時を指定したい時も、お寺と相談をすることで調整可能な場合も多いでしょう。
葬儀や法事など仏事に関することを相談できる
檀家であれば、葬儀や法事など仏事に関することを幅広く相談できます。戒名付けや葬儀に関すること、納骨についてなど、お寺は親身になって相談に乗ってくれるため、辛いときでも心強く感じるでしょう。
いざという時にお寺からアドバイスをもらえるのは、檀家になるメリットのひとつといえます。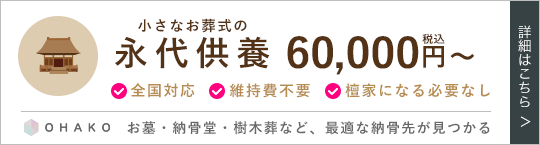
檀家になる3つのデメリットとは
檀家になると手厚い供養が受けられる反面、いくつかのデメリットも発生します。檀家になった際に発生する費用や注意点も正しく理解しましょう。ここからは、檀家になる3つのデメリットを紹介します。
費用が発生する
檀家になるには入檀料などの費用が発生します。お寺の修繕・改修のために寄付を募ることもあり、少なからず金銭的な負担が予想されます。資産状況や家計への支障などを考慮してから、入檀するかどうか判断しましょう。
葬儀や法要をほかのお寺に依頼できない
檀家になると葬儀や法要をそのお寺に依頼するのが一般的です。さまざまな相談をしやすくなる一方で、ほかのお寺への依頼が難しくなる点に注意しましょう。
例えば、希望した葬儀形式や法要の実施が難しい場合もあります。事前にお寺と打ち合わせを重ねて、トラブルがないように話し合いを進めましょう。
お寺ごとに決められたルールがある
葬儀のやり方や戒名の付け方は、お寺によってルールがあります。檀家になった場合、各お寺のやり方にならった葬儀や法要をすることになると把握しましょう。希望の葬儀や付けたい戒名があっても、自由度が下がる点に理解が必要です。
檀家になると発生する費用とその目安
檀家になると、継続的な管理費用が発生する可能性があります。知らずに入檀してしまうと、あとで予想外の出費に驚くこともあるかもしれません。トラブルを避けるためにも、檀家に必要な費用やその目安を事前に知っておきましょう。
入檀料や志納金
新しく檀家になる際には、「入檀料」と呼ばれるお寺の入会金が必要な場合があります。また、「志納金(しのうきん)」という会費のようなものを払うこともあるでしょう。
入檀料の目安は10万円~30万円程度といわれています。ただし、宗派やお寺によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
管理費や修繕時の寄付金
お寺から管理費や修繕のための寄付を求められることもあります。管理費は年間5,000円~2万円程度が目安です。
寄付金は強制ではありませんが、金額の目安が設定されていることもあります。状況によっては、金額を選べるケースもあります。大きな修繕が必要な場合や、修繕頻度が高い場合は求められる費用も高くなる可能性があるでしょう。
葬儀や法要の際のお布施
葬儀や法要の際は、檀家になっているお寺にお布施を渡します。葬儀・法要の内容や規模、地域、故人との関係性によってお布施の目安は異なります。お布施は地域差が大きい部分なので、迷ったらお寺に確認するか、葬儀・法要の経験がある周囲の方に相談するとよいでしょう。
法要や故人との関係性ごとの香典の相場は以下の記事を参考にしてください。
檀家をやめる方法(離檀)と注意点
檀家をやめることを「離檀」といいます。お墓の後継者がいなかったり、引っ越しに伴い改葬したりするために離檀を決断する方もいるでしょう。
ここからは、檀家をやめる方法と注意点を紹介します。離檀時はトラブルになりやすいため、注意点を守り丁寧な対応をしましょう。
離檀する方法
離檀する方法はお寺によって異なります。離檀したい旨を伝えるだけでよいお寺もあれば、「離檀届」を用意するケースもあります。
離檀について考えはじめたら、まずは入壇時の契約書を確認しましょう。必要なものがあればそろえて、疑問点があれば直接お寺に問い合わせるのがおすすめです。
離檀する場合は、閉墓または改葬が必要です。閉墓はお墓を引き上げる(閉める)こと、改葬はお墓を別の場所に移すことです。どちらの場合も、さまざまな供養が必要となるため、離断の相談はできるだけ早くから行いましょう。
離檀にかかる費用
檀家をやめる際は、これまでのお礼として「離檀料」を渡すのが一般的です。離檀料は5万円~20万円程度、または法要一回分が目安と考えられています。
離壇料に疑問がある場合は、周囲や弁護士などに相談しましょう。地域やお寺によって差があることも踏まえて、必要に応じて専門家の意見を取り入れるのがおすすめです。
離檀する際の注意点
お寺ごとの細かいきまりは、入壇時の契約書に記載されています。契約書は家族にもわかる場所に保管しておきましょう。
離壇の方法や費用などは、お寺や地域ごとの差が大きい部分です。不明点があれば、なるべく早くお寺に問い合わせましょう。離壇時はトラブルになりやすいため、しっかりと手続きをする時間を確保するのが重要です。
宗派による檀家の違い
どの宗派の檀家になっても、香典の目安に大きな違いはありません。しかし、同じ仏教でも、宗派によってマナーやルールが異なります。ここからは、真言宗と日蓮宗に注目して、宗派による檀家の違いを解説します。
真言宗の檀家とは
真言宗の檀家になった場合、焼香の回数に注意しましょう。一般的に焼香の回数は1回、または2回ですが、真言宗では焼香を3回します。
数珠の持ち方にもきまりがあります。真言宗の数珠は、数珠同士を擦り合わせて音を立てるのが特徴です。両手の中指に数珠をかけて、玉の部分が手のひらにくるように持つのが正しい持ち方と考えられています。
日蓮宗の檀家とは
日蓮宗の焼香も、ほかの宗派とは違う特徴があります。焼香の回数は1回ですが、抹香をつまんだあとは、額に掲げずそのまま香炉に持っていきます。
日蓮宗の数珠は、2本の房と3本の房がひとつずつ付いた独特な形をしています。2本の房がある方を右手の指にかけて、3本の房がある方を左手の指にかけると覚えましょう。日蓮宗は「南無妙法蓮華経」を唱えることが重要なため、参列者全員で読経します。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
檀家とは、特定の寺院に所属している家のことを指します。檀家になると手厚い供養を受けられる一方で、お寺のルールやしきたりに従う制約も発生します。一定の費用も発生するため、経済的な負担を考慮して入檀するかどうか判断しましょう。
小さなお葬式では、宗派別に適した葬儀や法要をご提案しています。現在檀家に興味を持っている方は、ぜひ小さなお葬式までご相談ください。
法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


湯灌は故人の体を洗って清める儀式のことです。ホゥ。

































