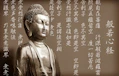離婚や再婚が決してめずらしいことではなくなっている昨今、再婚相手の連れ子と暮らしている方もいるのではないでしょうか。
しかし、連れ子がいる場合の相続については、誤解をしている方も少なくありません。そこでこの記事では、連れ子に相続権はあるのかといったことや、連れ子に財産を渡す場合の注意点などについて詳しく解説します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・再婚相手の連れ子は原則として相続人ではない
・連れ子と養子縁組をすることで、連れ子に財産を渡すことができる
・連れ子に財産を渡す場合、他の相続人の遺留分に注意が必要
こんな人におすすめ
再婚相手の連れ子は相続人になるのかを知りたい方
連れ子に相続で財産を渡す方法を知りたい方
連れ子に遺言で財産を渡す場合の注意点を知りたい方
再婚相手の連れ子は相続人?
誰が相続人になるのかは、民法で明確に定められています。しかし、実際の状況に当てはめて判断することは難しい点も多く、誤解をしている方も少なくありません。
はじめに、再婚相手の連れ子が相続人になるのかどうか確認しておきましょう。
再婚相手の連れ子は原則として相続人ではない
結論をお伝えすれば、再婚相手の連れ子は原則として相続人ではありません。
たとえ連れ子が幼い頃から実の親子同然に暮らしてきたとしても、それのみを理由に相続人になるわけではないので、注意しましょう。
連れ子と養子縁組をしていれば相続人
連れ子と養子縁組をしていれば相続人になります。養子である場合における連れ子の相続の権利は、実子となんら変わりはありません。
なお、連れ子の親と婚姻届を出したからといって自動的に連れ子と養子縁組がされるわけではないため、誤解しないようにしましょう。養子にしたいのであれば、連れ子の親との婚姻届とは別に養子縁組の手続きをすることが必要です。
相続人になる子、相続人にならない子
亡くなった人(「被相続人」といいます)に子がいれば、子は原則として相続人です。しかし、なかには連れ子のように判断に迷うケースもあるでしょう。
子が相続人になる場合とならない場合は、それぞれ次のとおりです。
相続人になる子
次の子は、原則として相続人になります。
【離婚をした前妻との間に生まれた子で、前妻が養育している子】
たとえ親権を前妻が持ったとしても、実子である以上は相続人です。
【認知をした子】
たとえ一度も会ったことがなくても、認知をしていれば相続人です。なお、認知をした子と婚姻関係にある相手との間で生まれた子に、相続での取り分に差はありません。
【結婚をして他家に嫁いだ子】
結婚をして名字が変わったからといって、相続権が失われるわけではありません。
【他家の養子になった子(特別養子の場合は除く)】
特別養子以外の養子の場合には、実の親からの相続権も失われません。たとえ他家の養子になったとしても、実の親子関係が終了するわけではないためです。つまり、養子は実の親からも養親からも相続を受ける権利を持ちます。
【疎遠となり長年会っていない子】
疎遠となっていても、それを理由に相続人から外れるわけではありません。
【養子】
養子縁組をしていれば、実子と同様に相続の権利を持ちます。なお、実子と養子で相続での取り分に差はありません。
相続人にならない子
一方で、次の子は相続人とはなりません。
【配偶者の連れ子】
上で解説をしたとおり、連れ子は原則として相続人ではありません。ただし、養子縁組をしていれば相続人になります。
【特別養子に出した子】
他家の特別養子となった子は相続人ではありません。特別養子とは、実の親が養育できないなどの事情で幼い頃に行う養子をいいます。特別養子の場合には、戸籍に「養子」の記載はありません。
連れ子に相続で財産を渡す方法とは
連れ子は、たとえ長年実子同様に暮らしてきたとしても、養子縁組をしていない限りは相続人ではありません。相続人ではない以上、何ら対策しなければ相続に際して財産を渡すことはできないということです。
では、養子に財産を渡すにはどうすればよいのでしょうか。
養子縁組をする
連れ子に相続で財産を渡す方法の1つ目は、連れ子と養子縁組をすることです。連れ子と養子縁組をすれば、実子と同様に相続の権利が発生します。
なお、養子は未成年のうちしかできないなどと誤解をしている方もいますが、連れ子がすでに成人をしていたり婚姻をしていたりしても養子にすることは可能です。養子に特に年齢制限はないため、何歳であっても養子縁組をすることができます。
ただし、連れ子が養親よりも年上である場合には、養子にすることができません。民法の規定により、年長者を養子にすることはできないとされているためです。
遺言書を作成する
連れ子に相続で財産を渡す方法の2つ目は、遺言書を作成しておくことです。遺言書で財産を渡す相手には特に制限はありません。そのため、相続人ではない連れ子に対して財産を渡す内容の遺言書を作成することも可能です。
生前贈与をする
相続ではありませんが、連れ子に財産を渡す方法で言えば生前贈与も考えられます。生前贈与はお互いの「あげます」「もらいます」という意思の合致さえあれば成立し、特に相手に制限はありません。
ただし、生前贈与には高額な贈与税がかかる可能性があるため、事前に贈与税を試算してから行うようにしましょう。
連れ子に遺言で財産を渡す場合の注意点
遺言書があれば、養子ではない連れ子に財産を渡すことが可能です。しかし、相続人ではない人に財産を渡す場合には、いくつか特別な注意が必要となります。
養子ではない連れ子に遺言で財産を渡す場合には、特に下記の点に注意しましょう。
「相続」ではなく「遺贈」になる
厳密にお伝えすれば、養子ではない連れ子に財産を「相続」させることはできません。相続させることができるのは、相続人のみであるためです。
しかし、上でもお伝えをしたとおり、相続人ではない人に遺言で財産を渡すこと自体は可能です。ただし言葉が異なり、相続人ではない人に遺言で財産を渡すことを「遺贈」といいます。
つまり、養子ではない連れ子に財産を渡す内容の遺言をつくる場合には、その語尾は「遺贈する」が正解です。
連れ子に財産を渡す内容の遺言書は、たとえば次のように記載しましょう。
遺言書
第1条 次に記載の財産を、私の妻の長女である 相続花子(昭和60年1月1日生・住所は大阪府大阪市○○区1丁目1番地 大阪マンション101号室)に遺贈する。
法定相続人の遺留分に注意する
連れ子に財産を遺贈する内容の遺言書をつくる場合には、他の相続人の遺留分に注意が必要です。遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人の保証されている相続での最低限の取り分のことを指します。
たとえば実子である長男がいるにも関わらず、配偶者の連れ子に全財産を遺贈するような内容の遺言書をつくった場合を考えてみましょう。
この遺言は、長男の遺留分を侵害しています。遺留分を侵害した内容の遺言書も作成することはでき、遺留分を侵害したからといって無効になるわけではありません。しかし、相続が起きた後で遺留分を侵害された長男から多くの財産を受け取った連れ子に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、自分の遺留分を侵害した分を金銭で支払ってくださいという請求のことです。この請求がされると、連れ子は長男に対し、侵害した遺留分に相当する額の金銭を実際に支払わなければなりません。
相続財産が金融資産ばかりであればその金融資産から遺留分侵害額相当分を支払えば良いので、それほど大きな問題にはならないこともあるでしょう。一方で、財産の大半が自宅不動産など簡単に売却できないものである場合には、連れ子が遺留分の支払いに困ってしまうかもしれません。
一括で支払えない場合は分割での支払いを検討することになりますが、それでも遺留分の額が多額であれば大変な思いをしてしまう可能性があります。
こうした事態を避けるため、遺言書を作成する際には遺留分について知り、必要な対策をおこなっておくことが重要です。
遺言書を作成するにあたっての遺留分についての考え方として、大きく分けて次の2つのパターンが検討できます。
1.遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成する
長男にも遺留分相当分程度の財産は渡す内容で遺言書の内容を検討する方法です。
2.遺留分侵害額請求に備えてお金を準備する
遺言書の内容は遺留分を侵害した内容としたままで、もし遺留分侵害額請求がされた場合にもその支払いに苦慮することのないよう、金銭を準備しておく方法です。代表的な方法としては、連れ子を受取人、遺言者を被保険者とした生命保険契約への加入が考えられます。
遺留分をまったく考慮せずに遺言書を作成すると、のちのトラブルの原因となる場合があるので、遺留分についても知ったうえで対策を検討しておきましょう。
なお、遺留分の割合は原則として2分の1です。個々の遺留分は、これに法定相続分を乗じて算定します。たとえば法定相続人が配偶者と長男のみである場合には、長男の遺留分は遺産全体の4分の1(遺留分2分の1×法定相続分2分の1)です。
遺言執行者を定めておく
遺言が相続人に対して財産を渡す内容であれば、名義変更などの手続きは、原則として財産を受け取る人が単独で行うことが可能です。
一方で、養子となっていない連れ子に財産を渡すなど「遺贈」に該当する場合には、財産の受取人だけで名義変更などの手続きをすることができません。遺贈の場合には、相続人全員か遺言執行者のいずれかの協力が必須となります。
相続人全員の協力が必要となれば、仮に相続人の中に連れ子が財産を受け取ることに納得しない人がいる場合には、手続きが停滞してしまいます。そのため、相続人に協力を求める必要がないよう、遺言執行者を定めておくとよいでしょう。
遺言執行者を決める方法には、次の2つがあります。
1.あらかじめ遺言で定めておく
2.相続が起きてから家庭裁判所で選任してもらう
相続が起きてから家庭裁判所で選んでもらってもよいですが、手続きの手間などを考慮すればあらかじめ遺言書内で定めておく方がスムーズです。
遺言執行者は遺言書の作成のサポートを受けた専門家などに依頼をする方法のほか、遺言書で財産を受け取る人などご家族を指定する場合の2つのパターンが存在します。
たとえば、連れ子自身を遺言執行者として指定をする場合には、次のように記載をします。
第○条 本遺言の執行者として、前記 相続花子(昭和60年1月1日生・住所は大阪府大阪市○○区1丁目1番地 大阪マンション101号室)を指定する。
2 遺言執行者は、不動産の名義変更、預貯金の解約、名義変更、払い戻しなど本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。なお、遺言執行者が本遺言を執行するに際し、法定相続人の協力は必要としない。
なお、これはあくまでも一例です。実際に遺言書を作成する際には、財産の内容などと矛盾のない内容で記載をしましょう。
相続税が2割増しとなる
相続税は、遺産総額が次の式で算定される相続税の基礎控除額を超える場合にかかります。
相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
遺産総額が基礎控除額を超える場合に相続税を支払う義務のある人は、相続や遺贈で財産をもらった人です。したがって、連れ子が遺言で財産を受け取った場合には、連れ子も相続税を支払わなければなりません。
このとき、連れ子が受け取った財産にかかる相続税は、通常の2割増しになることを知っておきましょう。
相続税法の規定により、次の人「以外」が受け取った財産にかかる相続税は2割加算がされると定められているためです。
・被相続人の一親等の血族
・代襲相続人となった孫
・配偶者
連れ子はこれらに該当しないため、2割加算の対象となります。
参考:『No.4157 相続税額の2割加算 国税庁』
登録免許税が高くなる
連れ子が受け取った財産に不動産が含まれる場合には、その不動産の名義変更にかかる登録免許税が高くなることにも注意しましょう。
登録免許税とは、不動産の名義を変える際にかかる税金です。相続や遺贈により不動産を名義変更する際の登録免許税は、次のように定められています。
相続や相続人に対する遺贈:固定資産税評価額の1,000分の4
相続人以外に対する遺贈:固定資産税評価額の1,000分の20
養子縁組をしていない連れ子は相続人ではないため、不動産の名義変更をする際にはこの高い方の登録免許税が課税されます。
参考:『No.7191 登録免許税の税額表 国税庁』
農地を渡す場合には許可が必要となる
農地は、日本の食料を支えるための大切な資源です。農地が勝手に宅地にされてしまえば、農地が減少して食料の自給率が下がってしまうかもしれません。そのため、農地については農地法という法律で権利の移転や転用などについて特別なルールが定められています。
相続人が農地を取得した場合や包括遺贈で農地を取得した場合
農地を相続で取得した人が相続人の場合や、相続人以外であっても「包括遺贈」で農地を取得した場合には、特に難しいことはありません。特別な要件などはなく、単に農地を取得した旨を農業委員会に届け出るだけです。
包括遺贈とは、たとえば次のような遺言で財産を渡すことを指します。個別の財産を指定するのではなく、全財産をひっくるめて割合で遺贈をするイメージです。
遺言書
第1条 私の財産のうち3分の1は、私の妻の長女である 相続花子(昭和60年1月1日生・住所は大阪府大阪市○○区1丁目1番地 大阪マンション101号室)に包括して遺贈する。
ただし、包括遺贈の場合には原則として他の相続人や包括受遺者と遺産分割協議をしなければならない点に注意しましょう。そのため、財産を渡したい相手間の関係性が良くない場合には、包括遺贈はおすすめできません。
特定遺贈で農地を取得した場合
一方で、「特定遺贈」の場合には原則として農地法の許可を得なければなりません。
許可には要件があり、たとえば農業に従事して農地を耕作することなどが必要です。仮に要件を満たせず許可が得られなければ、せっかく農地を遺贈する旨の遺言があったとしても法務局での名義変更をすることができません。
特定遺贈とは次のような遺言で財産を渡すことをいいます。個別の財産ごとに渡す相手を決める内容だとイメージすれば良いでしょう。
遺言書
第1条 次の財産は、私の妻の長女である 相続花子(昭和60年1月1日生・住所は大阪府大阪市○○区1丁目1番地 大阪マンション101号室)に遺贈する。(1)農地
所在 大阪府○○町○○
地番 100番
地積 1,000平方メートル
特定遺贈の場合には、他の相続人などとの遺産分割協議をする必要はありません。相続争いを防ぐ目的や遺産分割協議の手間をかけさせない目的などで遺言書をつくる場合には、特定遺贈で記載するようにしましょう。
ただし、相続人ではない連れ子に農地を特定遺贈で渡す場合には許可が必要となることを知った上で、許可要件を満たすのかあらかじめ農業委員会などに確認をしておくことをおすすめします。
家族信託という選択肢もある
連れ子の相続権について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。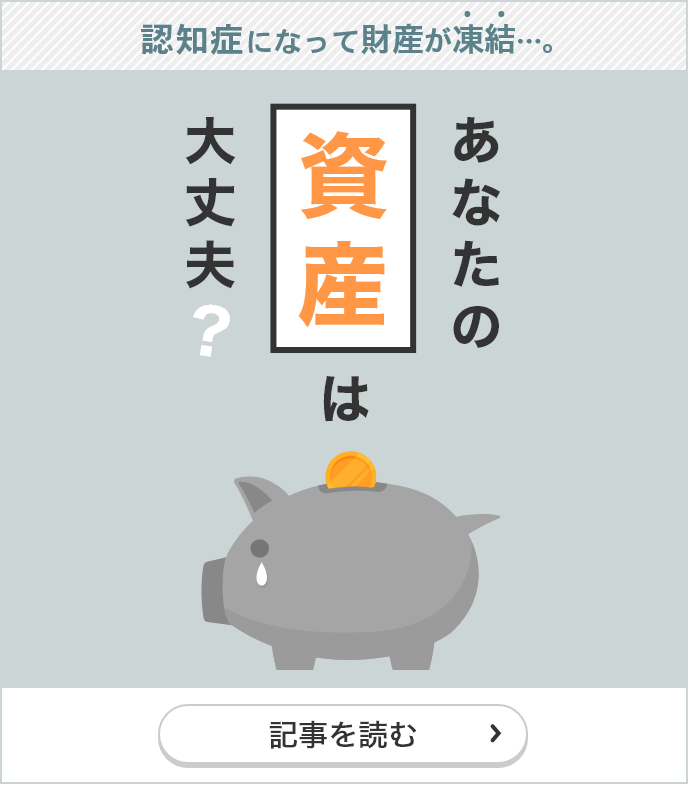
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
連れ子は原則として相続人ではありません。
しかし、遺言書を作成しておけば連れ子に財産を渡すことが可能です。連れ子に財産を渡す内容の遺言書をつくる際には、ここで記載をした内容にも注意をして作成するようにしましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。