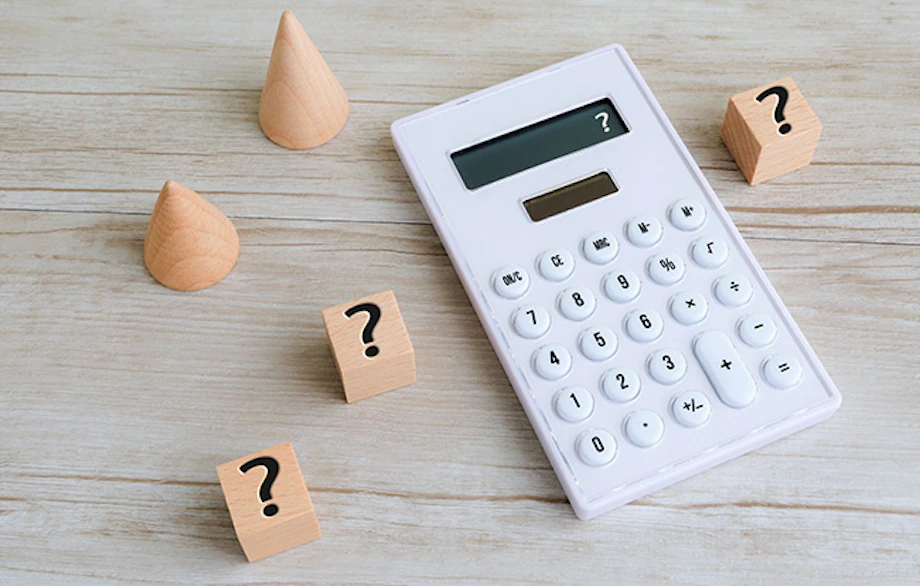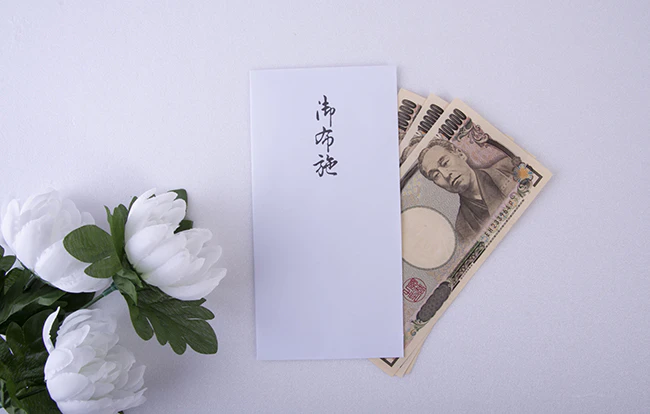何らかの事情でお墓を移動、引越ししたい場合、費用の目安や引越し方法はどうしたらよいのでしょうか。お墓の移動には手続きがあるため、下調べしておくことでトラブルなく円滑に行うことができます。
この記事では、お墓の移動や引越しの費用の目安、大まかな流れなど移動する際の注意点について解説します。
<この記事の要点>
・お墓の移動は、遺骨の量によって移送方法が変わる
・移動は、改葬先へ相談・必要書類を用意・抜魂供養・改葬先へ納骨の流れとなる
・墓じまいの費用は、必要書類の準備や墓石の撤去工事も含めると総額100万円~300万円が目安
こんな人におすすめ
お墓の移動・移転にかかる費用の目安を知りたい方
お墓を移動する際の大まかな流れについて知りたい方
お墓を移動する際の注意点を知りたい方
最近増えているお墓の移動
近年、核家族化の加速により、お墓の扱いについて話題にあがることが増えました。
一般的に、お墓には先祖代々の遺骨が納められており、ご先祖様を同じくする家族や親戚が管理や手入れをすることで、次の代へと引き継がれていきます。しかし近年では、地元を離れ都心で生活を続ける方も多く、地元にあるお墓の定期的な手入れや管理ができない方も増えています。
その場合は、お墓を移動させることが1つの手段といえます。お墓を移動させることは「墓じまい」と呼ばれ、今住んでいる場所の近くにお墓を移すことで、手入れや管理がしやすくなります。また、法要でお墓参りに行く際に、遠方まで足を運ばずに済むでしょう。
お墓は管理も含めて、将来的に子どもや孫に受け継がれていくことが一般的です。そのため、次世代への負担を減らしたいと考える方にもお墓の移動が検討されているようです。
墓じまいは、単に墓石を移動させるだけではありません。永代供養とよばれる、屋内に小規模で遺骨を収められる施設などへ遺骨を移動させる場合もあります。遺骨を移動し、別の場所で供養することを「改葬」と呼びます。
家族や将来のことを考えて、お墓を移動したり遺骨を移したりする方法を知っておくことは、これからの時代にとても重要なことだといえるでしょう。
お墓をどうやって移動させるか
お墓の移動と聞くと、大掛かりなものを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、一般的には遺骨だけを移動させる方がよいとされています。遺骨を移送した後は、解体か撤去されることが多いようです。石碑をそのまま運ぶことは負担が大きく、移動先で受け入れられない等の問題が多いことが理由のようです。
ここからは、より具体的な移動手段について解説します。
移動させる遺骨の量によって手段が変わる
一番重要なのは、移動させる遺骨の量です。お墓の中には、先祖代々の遺骨が納められていることが一般的です。そのため、墓じまいをしてお墓を撤去する場合は、中にある遺骨の量も移送方法に関係してきます。
遺骨の移送方法には、以下のようにさまざまな種類があります。
・すべての遺骨を移送する
・移送する遺骨を選ぶ
・分骨する
ただし、遺骨の移送やお墓の移動には、さまざまな手続きや家族や親族からの同意が必要になります。自分だけの意志で勝手に行わず、事前準備をしたうえで正しい手順で行いましょう。
業者に依頼する
お墓の移動は、改葬を手伝ってくれる業者に相談することをおすすめします。書類の手続きや移送方法などは複雑ですが、業者にお願いするとスムーズに進められます。もし個人で遺骨を移動させるとしても、適切な方法や手順を理解してから行いましょう。
お墓を移動する際に必要な書類
改葬の手続きには、必要な書類がさまざまあります。必要な書類や手続きをしっかりと確認しておきましょう。まずは、必要な書類を不備なくそろえることが大切です。
・埋葬証明書
・改葬許可申請書
・改葬許可証明書
・改葬承諾書
・永代使用許可書
・受入証明書
上記の書類の詳細は、市町村の役所や墓地霊園の管理者に確認することをおすすめします。また、改葬先(受け入れ先)からも事前に許可書を発行してもらう必要があります。
移動するにあたってトラブルが発生した場合に柔軟に対応できるように、市町村や霊園、墓地などを管理する方にあらかじめコンタクトをとっておくことも大切です。
お墓を移動する際の大まかな流れ
ここでは改葬の大まかな流れを解説します。流れを事前に頭に入れておくとスムーズに進められるでしょう。
1. 改葬元に相談し、許可を得る
まずは、改葬元となる管理人に「お墓の移動を検討している」と相談するのが先決です。相談なしで改葬をするとトラブルに発展する可能性があるため注意しましょう。事前に相談・報告を行い、許可を得ることが重要です。
2.必要書類を用意し、お墓移動の手続きをする
改葬元から移動の許可を得た後は、改葬先の管理者に連絡を入れることで「受入証明書」とよばれる書類が発行されます。改葬先となる霊園は、あらかじめ決めておきましょう。
その後、現在お墓がある市町村から「改葬許可申請書」を発行してもらいます。記載は役場でもできますが、改葬許可申請書は市町村のホームページからもダウンロード可能です。そのため、事前に記入して準備しておくのもよいでしょう。
改葬許可申請書が受理されると「改葬許可書」が発行されるので、元の管理者に提出しましょう。
不明な点があれば、事前に役場に問い合わせておくのがおすすめです。改葬の手続きをしたい旨を伝えると、必要記載事項や注意点を教えてもらえます。
3.抜魂供養や遷仏法要を行う
書類手続き後は、抜魂供養や遷仏法要を行うのが一般的です。その後、墓地を更地にして管理者へ返還手続きが完了します。
4.改葬先に納骨する
改葬のために墓じまいを済ませた後は、改葬先である管理者に改葬許可書を提出し、納骨しましょう。その後、納骨の法要をしなおすことでお墓の移動は完了します。
お墓を移動する際の費用
墓じまいのかかる費用は総額でいくらほど必要になるのか気になる方もいるでしょう。墓じまいはそれぞれの状況によってかかる費用の総額が変わってきます。ここでは、墓じまいの費用のある程度の目安と、別途生じる可能性のある費用についてご紹介します。
費用総額の目安
墓じまいや各種書類を整え、工事や移動にかかる費用は、墓石の撤去工事なども含めるとおよそ100万円~300万円といわれています。
ただし、お墓の大きさをはじめ、中に納骨されている遺骨の状態や量、供養のために発生するお布施などによって、費用は異なります。加えて、運搬費や設置などの工費、各種手数料が別途発生する可能性があるため注意が必要です。
別途費用
墓じまいの過程において、それぞれに別途費用が発生する可能性があります。
例えば、管理元から離れるための費用である「離檀料」が必要になったり、墓の大きさに合わせて解体にかかる費用が変動したりします。金額にすると1万円~10万円、さらには50万円ほどになることもあります。
また、改葬の際には、遺骨1体につき費用がかかる場合があるので、そのような点も細かく確認しておく必要があります。一度見積もりや相談をするとよいでしょう。
お墓を移動する際の注意点
改葬する際は、遺骨を長距離移動させるケースもあります。特に電車などの交通機関で移動する場合は、持ち忘れやトラブルに巻き込まれる可能性もあるため、可能な限り車で移動することをおすすめします。
遺骨を移動させた後は、速やかに納骨するのが一般的ですが、改葬先の予定によっては、スムーズに納骨できないケースもあるでしょう。双方のスケジュールが合わない場合は、当日まで自宅で保管しておくのが一般的です。
自宅での保管が難しい場合は、管理者となる改葬先に依頼をすることで一時的に預かってもらうことが可能な場合もあります。その場合は、事前に保管してもらえるのか尋ねておき、可能であれば依頼しておくとよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
時代の変化により、墓じまいを検討する方は増えています。さまざまな事情により、地元を離れる人が近年増加傾向にあることが理由の1つでしょう。墓じまいをすることで、自分が住んでいる地域に遺骨を移動させることが可能です。
墓じまいの費用は、総額100万円~300万円が目安です。必要な手続きは多いですが、あらかじめ手続きの内容や書類を知っておくことで、円滑に行えます。また、墓じまいを検討している場合は、市町村に事前に相談しておくのもよいでしょう。
墓じまいや遺骨の供養について疑問をお持ちの方は、お気軽に小さなお葬式にご相談ください。
納骨先探しをお手伝いするサービス「OHAKO(おはこ)」では、永代供養をはじめさまざまな納骨先をご提案します。墓じまいで納骨先をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
納骨先探しのお手伝いをするサービス「OHAKO-おはこ-」
・土地、墓石など必要な費用を全て含んだ明瞭価格
・お墓、納骨堂、樹木葬、永代供養、海洋散骨、自宅供養など様々な納骨方法から簡単に比較、検索できる
・全国の霊園、寺院、墓地の豊富な情報を集約
あなたに最適な納骨先が見つかる「OHAKO」 詳しくはこちら
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


葬儀の挨拶では、不幸を連想させてしまう忌み言葉と重ね言葉には気をつけましょう。ホゥ。