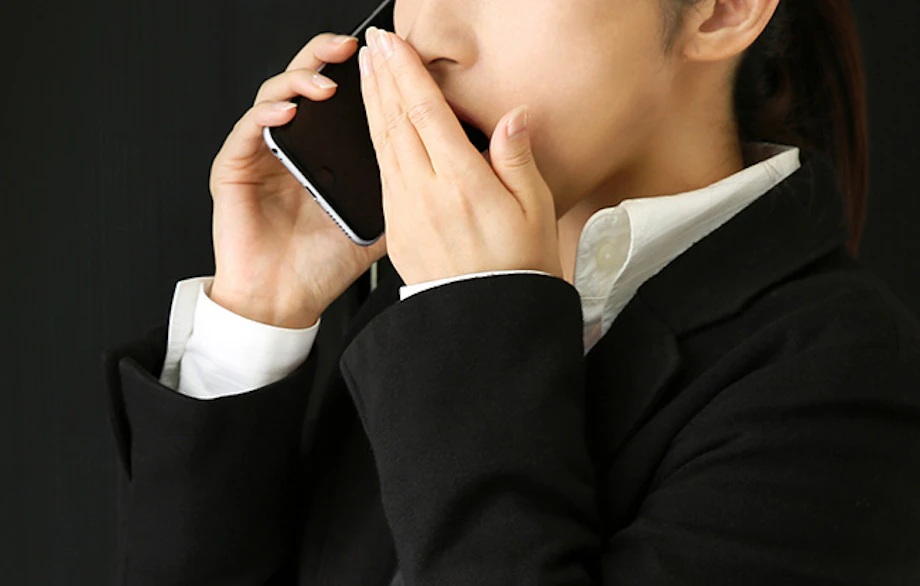人が亡くなったお知らせのことを「訃報(ふほう)」といいます。訃報を伝える際は、間違いがないように細心の注意を払う必要があります。
この記事では、訃報の意味や伝え方を解説します。実際に訃報を伝える際の例文も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・「訃報」とは、人が亡くなった知らせのこと
・身内が亡くなった場合、まずは三親等以内の親族に訃報を伝える
・連絡手段は電話が基本だが、場合によってはメールやSNSも活用するとよい
こんな人におすすめ
「訃報」の意味を知りたい方
訃報をつたえるタイミングを知りたい方
訃報の連絡手段を知りたい方
訃報とは?
訃報とは、どのような意味の言葉なのでしょうか。ここでは訃報の意味について解説します。よく似た言葉として、訃報や悲報、凶報などがありますが、それぞれの違いも明確に押さえておきましょう。
訃報の意味
「訃報」とは、人が亡くなった知らせのことです。故人の名前や亡くなった日時、通夜・葬儀・告別式の日程・会場などを関係者に伝えます。葬儀に参列したい方にとっては、名前や葬儀に関する情報が重要になります。
悲報との違い
「悲報」とは、悲しい知らせという意味です。面識のある方以外に関する知らせでも使われます。
悲報は、不慮の事故や自然災害で被災した場合にも使われます。訃報は人の死に限定した知らせですが、悲報は悲しい知らせ全般を指す点が異なります。
凶報との違い
「凶報」とは、悪い知らせやよくないことに関する知らせという意味です。聞いた瞬間に、悪い知らせだと感じてしまうような強烈な出来事に対して使われます。凶報は人の死も含んだ悪い知らせ全般を指します。
訃報を伝えるタイミング
訃報は伝えるタイミングが重要です。あらかじめ伝える人の優先順位をはっきりさせておきましょう。また、どの範囲までの関係者に連絡をするべきかも明確にしておくこと大切です。
家族や親族の場合
身内が亡くなったら、まずは家族や親族に連絡しましょう。連絡する範囲の目安は、三親等までの親族です。連絡するべき親族がほかにもいれば、家族で手分けをして訃報を知らせましょう。
亡くなった直後は葬儀の段取りが決まっていないので、亡くなったことだけを早急に伝えます。葬儀の日程等の情報は、きまり次第改めて連絡しましょう。
故人の友人や知人の場合
故人の友人や知人、仕事関係者にも早めに連絡を入れましょう。葬儀の日程や会場がきまった後すぐに連絡を入れるのがおすすめです。また故人が会社員や学生であった場合は、会社や学校にもすぐに連絡しましょう。
遺族の勤務先の場合
遺族は、自身の勤務先にも連絡する必要があります。葬儀を執り行う際には、休暇の取得や業務の引き継ぎが必要になるためです。まずは、上司に訃報を伝えましょう。葬儀の日程や会場がきまったら改めて連絡します。
地域の関係者の場合
近所の方や町内会など、地域の関係者にも訃報を伝えます。故人と特別親しかった方がいる場合には、すぐに伝えましょう。
地域の方には、葬儀の日程や会場がきまってから連絡します。特に町内会などの関係が強い地域では、早めの連絡が大切です。
訃報の伝える4つの手段
訃報を伝える方法は主に4つあります。相手に応じて連絡手段を使い分けるとよいでしょう。ここからは、電話やメール、SNSなど、訃報を伝える方法を紹介します。
電話
電話による連絡は、迅速かつ正確に必要な情報を知らせたい場合に便利です。
ただし、すべての関係者に電話をかけるのには時間と手間がかかります。自分だけで連絡をするのが難しい場合は、電話で訃報を伝えた相手から別の関係者に連絡してもらうように頼む方法を検討してもよいでしょう。
メールやSNS
メールやSNSであれば、多方面に連絡ができます。また、葬儀の日程や会場などを文字で送れるので、情報に間違いがありません。
一方で、メールやSNSは読んでもらえない可能性があることに注意が必要です。開封されていないと思われる場合には、追って電話をかけましょう。
手紙
訃報を手紙で伝えるメリットは、紙媒体で多方面に連絡できることです。葬儀後に死亡通知として故人が亡くなったことを伝えたいときに、手紙やはがきが役立ちます。
しかし、郵送の準備に一定の時間がかかる点に注意しましょう。葬儀前に訃報を伝えたい場合には、不向きな方法です。
広告媒体
新聞やニュースを通じて、訃報を伝える方法もあります。著名人が亡くなったことを発表するのと同様に、地域の新聞や回覧板などで知らせるほうが分かりやすい場合もあります。
お世話になった方が多い場合や、故人が生前に影響力を持った人物であった場合に役立ちます。
訃報を伝える際の例文
訃報をお知らせする際は、どのような文面で伝えればよいのでしょうか。ここからは、社内通知で伝える場合と、訃報広告で伝える場合に分けて例文を紹介します。
社内通知で伝える場合
社員の家族や親族の訃報を、社内メールなどで通知することがあります。文例は以下のとおりです。
各位
◯◯部の ◯◯様のご尊父様がご病気のため〇月〇日に逝去されました
通夜および告別式につきましては以下の日程で仏式にて行われますので謹んでお知らせいたします
日時:令和◯年◯月◯日 午後◯◯時から
場所: ◯◯市◯町◯丁目◯番地
電話:◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯
喪主:◯◯◯◯様
訃報広告で伝える場合
訃報広告とは、新聞の広告として訃報や葬儀に関する情報を伝えることです。故人の訃報を多くの人に知らせたい場合に使用します。文例は以下のとおりです。
父 ◯◯◯◯儀
かねてより闘病中のところ◯月◯日◯時に◯◯歳をもって永眠いたしましたのでご報告申し上げます
生前は多大なご厚情を賜り誠にありがとうございました
通夜および告別式につきましては仏式にて執り行います
日時:令和◯年◯月◯日 午後◯◯時から
場所:◯◯市◯町◯丁目◯番地
喪主:◯◯(故人との続柄) ◯◯◯◯(名前)
訃報を受けた際の対処法
訃報を受けた際は、何をすればよいのでしょうか。ここからは、訃報を受けた際の対応方法を紹介します。メールの返信の仕方や、弔問する際の注意点などを確認しておきましょう。
簡潔な内容にまとめて返信する
訃報の連絡を電話で受けた場合は、まずお悔やみの言葉を述べましょう。「御愁傷様です」というお悔みの言葉とともに、早々に訃報を知らせてくれたことに対する感謝の気持ちも伝えましょう。
メールの場合は、簡潔でわかりやすい文章で返信します。時候の挨拶や前置きは省き、お悔やみの言葉と遺族を気遣う言葉を添えましょう。訃報に返事をする際は、相手の連絡手段に合わせるのがマナーです。
近親者の場合は弔問する
近親者や親しい友人の訃報を受けた場合は、なるべく早く弔問しましょう。服装は派手なものでなければ、平服でかまいません。
香典なども通夜や葬儀の際に持参すればよいため、まずは向かうことを優先しましょう。遺族と対面した際は、お悔やみの言葉を短く伝えます。
故人との関係性によっては告別式のみに参列する
故人とあまり親しい間柄ではなかった場合や、遺族と会ったことがない場合は、告別式に参列するだけで問題ありません。弔問するのであれば、訃報を聞いてすぐに行くのではなく、通夜の準備ができた段階で弔問するのがよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
「訃報」とは、人が亡くなった知らせのことです。訃報は家族や親族、故人の友人や遺族の勤務先に伝える必要があります。相手に応じて、電話やメール、SNS、手紙やはがきで訃報を伝えます。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話料無料でご連絡をお待ちしております。訃報について知りたい方や、葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。