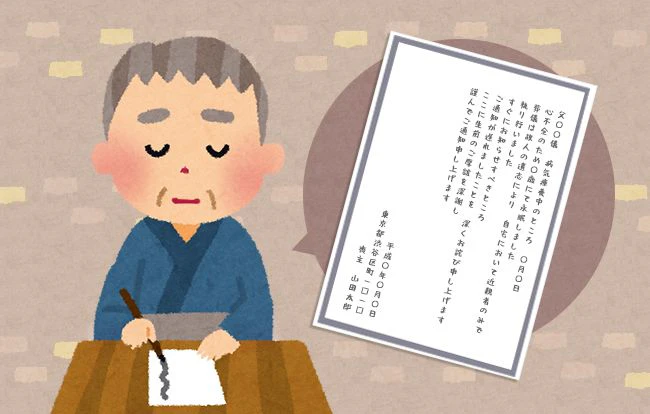身近な方が亡くなった場合、故人や自身の会社へ訃報を伝えます。しかし、最近は家族葬を選択する方も増えて、何をどこまで伝えればよいのかわからない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、会社への訃報連絡の方法や伝える内容を解説します。想定されるケースに応じた伝え方をまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・訃報は電話で伝えるのがマナーだが、つながらない場合はメールなどを利用してもよい
・家族葬でも故人・遺族双方の会社へ訃報の連絡は必要で葬儀の案内は不要
・故人の勤務先へは、故人の氏名や関係性、亡くなった日時、葬儀情報などを伝える
こんな人におすすめ
家族葬の訃報連絡について知りたい方
会社への訃報連絡について知りたい方
訃報の連絡で伝える内容を知りたい方
会社に訃報連絡をする2つのパターン
葬儀の規模や形式に関わらず、会社への訃報連絡は必要です。故人が生前に勤めていた場合は故人の会社に、また、遺族が会社を休む必要がある場合は自身の勤務先に訃報を伝えます。
故人の勤務先に訃報を伝える
故人が現役で働いていた場合は、勤務先に訃報を伝える必要があります。可能であれば、所属部署の上長に連絡するとよいでしょう。部署がわからない場合は、人事部や総務部などに連絡します。
故人の所属していた部署とは、手続きなどでしばらくやり取りする可能性があります。連絡先などをメモしておくと安心です。
遺族の勤務先に訃報を伝える
身内が亡くなり会社を休む場合は、勤務先への連絡が必要です。具体的には、以下の内容を伝えておきましょう。
・故人との関係性
・葬儀の予定
・休む期間
・業務の引き継ぎ など
忌引きの手続きは、所属の部署内で完結できない可能性があるので、必要に応じて人事部や総務部にも連絡しましょう。
会社への訃報連絡の方法
身内が亡くなった際は、会社に訃報を伝えて忌引き休暇を取ります。急な不幸で落ち着かない状況でも、マナーを守って会社に連絡を入れましょう。
連絡方法は「電話」が基本
訃報の連絡手段は電話が基本です。つながらない場合は、メールやSNSなどで連絡してもよいでしょう。相手から返答があれば問題ありませんが、連絡が来なければ見落としている可能性もあるため、時間をおいて改めてかけ直す必要があります。
会社に限らず、訃報は電話で伝えるのがマナーです。特に高齢層の方は、メールやSNSでの連絡よく思わない場合もありますので、注意しましょう。
訃報連絡は誰にする?
会社に訃報を伝える際は、所属部署の直属の上司に連絡します。休暇に伴う手続きや引き継ぎなどが必要なケースも多いため、部署内や社内の状況を把握している方に連絡をしましょう。
忌引き休暇申請に必要な手続きが部署内で完結しない場合は、人事部や総務部にも連絡します。引き継ぎが必要な同僚や部下、チームのメンバーなどにも連絡をし、忌引き休暇中も業務が滞りなく進むような体制を整えることも大切です。
忌引き休暇は会社により日数が異なることもあるため、訃報を連絡した際に確認しましょう。一般的な忌引日数の目安は以下のとおりです。
| 【故人との関係性】 | 【忌引の日数】 |
| 配偶者(妻・夫) | 10日 |
| 両親(母・父) | 7日 |
| 実子(娘・息子) | 5日 |
| 兄弟、姉妹(実兄・実弟・実姉・実妹) | 3日 |
| 祖父母(祖母・祖父) | 3日 |
| 配偶者の両親(義母・義父) | 3日 |
| 配偶者の祖父母(義祖母・義祖父) | 1日 |
| 配偶者の兄弟、姉妹(義兄・義弟・義姉・義妹) | 1日 |
故人との関係性だけでなく、葬儀が行われる場所などによっても、忌引きの日数は変わることがあります。
家族葬でも会社への連絡は必要?
一般的な葬儀を行う場合は、故人と関わりのあった方を多く招きます。しかし、家族葬の参列者は、家族や親族など故人とごく近しい方々のみであるため、それほど縁の深くない方には訃報を伝えないのが一般的です。
そのため会社への連絡も迷ってしまうかもしれませんが、家族葬でも故人・遺族双方の会社へ訃報の連絡は必要です。葬儀の案内は不要ですが、規模や形式に関わらず、会社側ではさまざまな手続きが必要です。会社に迷惑をかけないように、速やかに訃報を伝えましょう。
故人の勤務先に伝える訃報の内容は?
身内が亡くなって間もないと、訃報連絡をするときに落ち着いて話せないこともあるかもしれません。あらかじめ伝える内容をまとめておくと、慌てずに対応できるでしょう。ここからは、故人の勤務先に伝える訃報の内容を紹介します。
故人の氏名や故人との関係
故人の生前の勤務先に訃報を知らせる際は、故人の氏名と故人と電話主との関係性を伝えます。手続きなどについて会社から電話がくることもあるので、連絡先を伝えることも忘れないようにしましょう。
亡くなった日時
故人が亡くなった日時は、細かく伝える必要はありません。「昨日深夜」「○月○日早朝」のように伝えましょう。死因を伝えることも多いですが、詳細までは不要です。「病気により」「不慮の事故で」など、可能な範囲で問題ないでしょう。
葬儀に関する情報
家族葬の場合は、身内だけで葬儀を執り行う旨を会社に連絡しておきましょう。伝えていないと、「通常規模の葬儀をする」と思われる可能性があります。行き違いを防ぐためにも、訃報連絡をする際に「家族葬を行う」と明確に伝えることが大切です。
香典や弔電などを受け付けているかどうか
基本的に、会社の関係者が家族葬に参列することはないため、香典や弔電を受け取らないことも多いでしょう。訃報を連絡する際は、家族葬であることと、香典や弔電辞退の旨も伝えておくと不要なトラブルを防げます。
ただし、ご厚意で香典や弔電をいただくことがあるかもしれません。会社関係者ということもあり固辞するのが難しいと感じることもあるでしょう。
香典や弔電を受け取るか否かは、遺族間でも意見が分かれることがあります。訃報を伝える前に、香典や弔電への対応について家族で話し合っておくと安心です。
身内の不幸で会社を休む場合の連絡内容
身内に不幸があり忌引き休暇を取得したいときは、早めに会社に連絡する必要があります。しかし、近しい方が亡くなって間もないタイミングに、通夜・葬儀やさまざまな手続きが重なると、何を伝えればよいかわからなくなることもあるかもしれません。ここからは、自身の勤め先に訃報連絡をする際に伝える内容を紹介します。
故人に関する情報
まずは、誰が亡くなったのか、自分とどのような関係なのかを伝えます。故人の名前は弔電や供花を出す際に必要です。また、続柄によって忌引き休暇の日数が異なるため、この2点は忘れずに伝えましょう。
葬儀に関する情報
会社の方が葬儀に参列する場合は、葬儀に関する情報を伝えましょう。葬儀の会場や日時をはじめ、家族葬か通常規模の葬儀か、通常規模の場合は仏式・神式・キリスト教式など宗派も知らせると親切です。
忌引き期間
忌引き期間は故人との続柄により異なります。一般的な期間は配偶者や両親が亡くなった場合は7日~10日、実子や兄弟姉妹、祖父母などが亡くなった場合は3日~5日ほどといわれています。
連絡の前にどれくらい休暇を取りたいかを決めておくとよいでしょう。取得可能な期間がわからない場合は、一般的な忌引き日数を参考に希望を伝えて人事部や総務部に確認しましょう。
緊急連絡先や引き継ぎ事項
忌引き休暇中も会社は通常通り稼働しているため、仕事に関する連絡が入る可能性があります。スムーズに連絡が取れるように、緊急連絡先も伝えておきましょう。
会社以外に訃報を伝える方法
訃報は電話で伝えるのが一般的ですが、昨今はさまざまな方法で連絡が取れます。ここからは、会社以外の方に訃報を伝える際の内容や注意事項を紹介します。
関係性に関わらず「電話」が賢明
訃報の連絡手段に悩んだ際は、電話連絡をすることをおすすめします。関係性ごとの連絡事項は以下のとおりです。
親族
親族への訃報連絡は、亡くなった事実、日時、自身の連絡先などを伝えます。近しい親族には速やかに訃報を伝えて、その後改めて葬儀に関する連絡をすることも多い傾向にあります。遠縁の親戚には、葬儀の詳細が決まってから訃報と葬儀の案内を伝えてもよいでしょう。
友人・知人
友人や知人には、亡くなった事実、日時、葬儀の方針をまとめて伝えましょう。葬儀を一般的な規模で執り行う場合は葬儀の場所や日時を案内します。連絡先のわからない友人や知人への伝達を依頼しても構いません。家族葬を執り行う際は、その旨を明確に伝えましょう。
メールを使ってもよい
訃報を伝える際は、メールやSNSなどを使ってもよいといわれています。相手によっては電話での連絡が取りにくかったり、電話番号が分からなかったりすることもあるからです。また、文字にして伝えることで、あとから確認しやすいという利点もあります。
しかし、なかにはメールで訃報を受けることに違和感を持つ方もいます。状況に応じた使い分けが必要な手段であることを、忘れないようにしましょう。
手紙は事後通知状として送る
手紙やハガキは、葬儀を執り行った報告として送る「事後通知状」として送れます。家族葬や密葬の場合に多く用いられる連絡手段です。
事後通知状には亡くなった事実と葬儀を済ませたこと、生前の親交のお礼などを記載します。弔問や香典などを辞退する場合は、その旨も事後通知状を通じて伝えられます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀の規模にかかわらず、会社への訃報連絡は速やかに行いましょう。故人が生前勤務していた会社へ連絡する際は直属の部署へ、自身が会社を休む際は直属の上司に連絡します。
家族葬の場合は、会社にその旨を伝えておくことも大切です。香典や弔電の対応の仕方についても家族間で話し合い、方針を決めておきましょう。訃報を連絡する手段は電話が一般的ですが、状況によってはメールでも構いません。
会社に訃報を連絡するときや対応の仕方など、葬儀に関するお悩みは小さなお葬式にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフが、お悩みに合わせて丁寧にアドバイスいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。