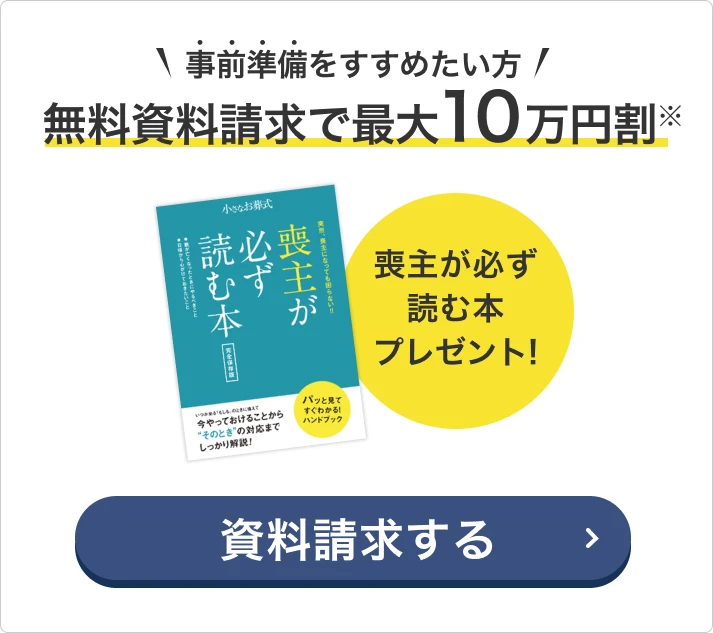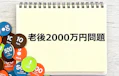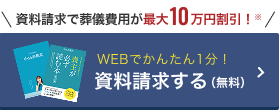金融庁が発表した、95歳まで夫婦で生きるには2,000万円が必要だという報告書は、メディアや世間を大きく騒がせました。「このまま貯蓄をしていても2,000万円をためることができない、どうしたらいいのだろう」「いくら必要なのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
2,000万円という大きい数字を前にして気後れしそうになりますが、今から私たちにできる「お金をふやす方法」の具体的な対策を知ることによって、改善できることがたくさんあります。今回は「老後のために貯金を増やす方法」についてまとめましたので参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・老後は一般的に2,000万円~3,000万円必要とされている
・生活費のほかに、特別支出や介護費用も念頭においておく
・老後の貯金を増やす方法として財形貯蓄、iDeCo、つみたてNISAなどが挙げられる
こんな人におすすめ
老後のお金事情について調べている方
老後のための貯蓄方法について気になる方
終活をはじめた方
老後は一般的に2,000万円~3,000万円必要とされている
老後の貯金で2,000万円が必要とされている理由は、2019年に金融庁が発表した資産形成の報告書が発端となっています。そこには男性65歳以上、女性60歳以上の夫婦(無職世帯)が年金だけで生活をすると、1ヶ月あたり5万円の赤字が出ると報告されました。
それではなぜ2,000万円~3,000万円という金額が必要なのでしょうか。また老後にいくら必要なのか以下から確認しましょう。
なぜ2,000万円~3,000万円なのか
老後の貯金で2,000万円が必要とされている理由は、無職世帯が1ヶ月で得られる収入の割合と消費支出では支出が赤字になり、赤字を補うために算出された金額が2,000万円~3,000万円ということです。詳しく見てみると男性65歳以上、女性60歳以上が年金で得られる収入は約21万円、消費支出は約26万円になると計算されています。
ここで毎月約5万円の赤字になることから、5万円×12=60万円、60万円×30年間(男性95歳、女性90歳)=1,800万円、つまり約2,000万円が赤字になる、よってこの2,000万円は貯蓄などから補填する必要があると報告書にまとめられていました。
上記の計算は、男性95歳、女性90歳で生きることを前提として計算されていますので、「そこまで長生きしないと思うから私たちには関係ないだろう」と考える人も多いでしょう。しかし、「人生100年時代」と言われている現代は、どのように資産をたくわえていくのか考える必要があります。
夫婦二人の年金が今後の収入となる
まず基本的な知識としておさえておきたいのが、会社員で勤めに出ている方や公務員が加入する「厚生年金」、個人事業主や専業主婦の方は「国民年金」の受給対象であるということです。厚生年金に加入している場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けとることができます。
反対に、国民年金に加入している場合は、老年厚生年金はなく老齢基礎年金のみです。しかし、夫婦共働きの場合老齢基礎年金と老齢厚生年金をダブルで受けとることができるので、老後の蓄えとしては有利と言えます。
厚生労働省が発表した日本年金機構の令和6年4月分からの年金額によると、国民年金と厚生年金を受け取る場合、合計金額が298,483円(老齢基礎年金68,000円、老齢厚生年金230,483円)です。
あくまで上記の厚生年金の230,483円は、40年間就業した場合に受け取れる年金の給付水準となるので、この限りではありません。しかし、妻が働くことで老後の受給額にも大きな差が出ることは確かです。
(参考:『令和6年4月分からの年金額等について』日本年金機構)※2024年11月時点
老後の生活資金の平均的な目安は?
総務省が発表した「2023年(令和5年)家計の概要」によると、二人以上世帯で世帯主が60歳~69歳の世帯の消費支出は月額平均306,476円、70歳以上の世帯の月額平均は249,177円です。また65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は月額平均244,580円、消費支出の月額平均は250,959円となっています。
(参考:『2023年(令和5年) 家計の概要』総務省統計局)※2024年11月時点
特別支出や介護費用も念頭に入れておく
特別支出や介護費用はこの内訳に含まれていません。特別支出とは、固定資産税や自動車税などの税金、結婚式やお葬式などの冠婚葬祭、家電や車の買い替えなどを指した支出です。
全ての人に関係しないように感じますが、実は多くの世帯で年間に数十万円の単位で特別支出があると考えられています。老後はこの特別支出を貯金からまかなうことが予想されるので、知っておいた方が良いでしょう。
介護費用は、医療費や介護費用を含めて約300万円〜500万円プラスアルファが必要とされています。在宅介護の場合は必要な福祉用具や設備の手配、老人ホーム利用の場合は施設利用料など、大きな金額を要する項目です。
介護が必要になってから慌てるのではなく、必要になる前に自治体で提供しているサービスや助成、自分が住んでいる市区町村の窓口などで調べておくと安心です。
老後のための貯金を増やす方法
ここで紹介する老後の貯金を増やす方法は「財形貯蓄」「企業年金」「iDeCo」「つみたてNISA」「小規模企業共済」です。
これらは、サービス内容や特徴が様々です。ご自身に合った貯蓄方法があるか参考にしてみてください。
財形貯蓄
財形貯蓄とは、企業側が従業員の資産形成を支援する制度で、毎月の給料やボーナスから決められた金額を天引きにします。会社勤めの方なら一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄額の3種を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
一般財形貯蓄は他2つの財形貯蓄とは異なり、結婚や出産、けがや病気などの出費がかさむ際にも利用でき幅広い目的で活用することができます。積立期間は原則3年以上で、引き出しを希望する場合は開始より1年後です。
財形住宅貯蓄は家を建てる時や、住宅の購入、リフォームなどで利用できます。積立期間は5年以上で、財形年金貯蓄と合わせて貯蓄残高550万円まで利子などに税金がかからないことがメリットです。
財形年金貯蓄は、60歳以降に年金として受け取るための貯蓄方法で、財形住宅貯蓄同様に貯蓄残高550万円まで利子などに税金がかかりません。積立期間は5年以上で年金以外の払い出しを行った場合、さまざまな制限が加えられますので注意が必要です。
企業年金
企業年金には、将来従業員が受け取る金額が決まっている「確定給付企業年金」と、掛け金が決まっている「企業型確定拠出年金」の2つの種類があります。「確定給付企業年金」は企業側が一括で年金資産を運用しますが、転職を希望する際には脱退一時金相当額を得ることができる制度です。
「企業型確定拠出年金」は確定給付企業年金とは違い、運用は従業員自らが行います。掛け金の拠出は企業側ですが、将来受け取れる金額が運用成績によって変わることが特徴です。運用を従業員が行うので、年金資産の残高確認、転職時には iDeCo( 個人型確定拠出年金)などに変更することも可能です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeco(個人型確定拠出年金)は、個人で掛け金を拠出して運用を行う私的年金の制度です。基本的に20歳以上60歳未満の全ての方が対象で、職業関係なく個人事業主以外にも学生、会社員や公務員の方も加入することができます。
iDeCoは個人事業主が掛け金を拠出する場合、上限が月額6万8,000円(年額81万6,000円)と他の職業より設定が大きいです。老齢給付金として60歳から受け取ることができ、一時金として一括で受け取る方法や年金として受け取る方法、一時金と年金を組み合わせて受け取る方法を選ぶことができます。
iDeCoの運用先や商品を自ら決めていきますので、将来受け取れる金額が運用成績によって変化するのが特徴です。また、税制優遇もされているため、積立と運用期間が長ければ長いほど節税効果も大きいです。
個人年金
個人年金の特徴は、契約者が死亡した場合遺族に対しての保証が手厚くサポートされていることです。個人年金は契約時に決められた年齢から年金を一生涯、または一定期間受け取れるタイプがあります。
貯蓄方保険の他にも変額個人年金、外貨建個人年金などもあり、様々なサービスから選べるのも個人年金の特徴です。
つみたてNISA
つみたてNISAとは、毎年の非課税枠までの購入した株や投資信託の利益(年間40万円が上限金額)が最長20年間非課税になる制度です。つみたてNISAは安定して長期にわたって資産をつくれるようにできた制度ですので、老後の資金作りにはおすすめと言えます。
なお、金融庁で一定基準をパスした商品をつみたてNISAで購入することができるので、投資初心者にとっては運用がしやすいでしょう。
自営業の方は小規模企業共済
小規模企業共済とは、積み立て式の小規模企業の経営者や役員、自営業の方向けの退職金制度です。掛金が全額控除の対象となるので節税効果が期待できます。積立の掛金は自分で1,000円~70,000円までで決めることが可能で、加入後に設定した金額の変更も可能です。
小規模企業共済金は退職時や廃業の際に受け取ることが可能で、受け取り方も「一括」「分割」「一括と分割の併用」と選ぶことができます。他には一般貸付、傷病災害時貸付などさまざまな貸付制度がありますので、自営業の方にとってはメリットが多い制度です。
知識があるなら投資に挑戦
投資への知識があるなら、老後の蓄えのために挑戦してみるのもおすすめです。投資には金投資や債券などのローリスクローリターンのものから、株式投資、不動産投資などのミドルリスクミドルターン、FXや仮想通貨などのハイリスクハイリターンのものがあります。
資産運用の方法もインターネットの普及によって変化し、種類も増えているのでご自身の環境にあった投資に挑戦してみるのはいかがでしょうか。
ファイナンシャルプランナーへ相談する
老後への資金に不安がある方や、理想とする生活にいくら必要なのかなどの悩みがつきない方は、一度ファイナンシャルプランナーへ相談してみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーは「お金のプロ」です。退職後の年金などの収入と、老後のライフデザインの作成、老後の対策方法をサポート、提案してくれます。また、定期預金や資産運用などについても相談することができるので、安心した老後を暮らすために早い段階から検討してみてはいかがでしょうか。
家計を見直すことも大事
安心した老後生活を過ごすには、収入と支出のバランスがポイントです。収入があまり多くないが、支出が多いとなると貯蓄が減るばかりか気持ちにも余裕がなくなります。
そういったことにならないためにも、普段消費しているものの中で節約できる項目はないか確認してみましょう。例えば、インターネットなどで自分の家計支出が他の一般家庭と比べて多いか、少ないかが分かるとさまざまな気付きが得られます。これらは今後の家計に役立てることができますので、ぜひ参考にしてみましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。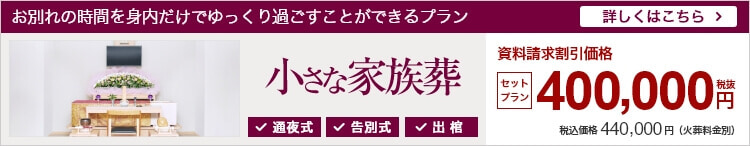

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
老後は年金だけの収入でまかなうことは難しく、自分の世帯に合った老後資金の準備を行わなければいけません。昔と比べて老後のために資金を増やす方法や種類は増えていますので、今からできることを少しずつ実行していくだけでも将来は変わってきます。
充実した老後生活を築くためにも、貯蓄や投資に目を向け増やしていくことが大切です。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。