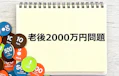老後の資金をいくら用意すればよいのか、お悩みの方もいるのではないでしょうか。年金や退職金は、老後に使える資金の代表ですが、それだけではありません。必要な金額は人それぞれであり、用意する方法も様々です。
老後の資金作りには、あなたに合った方法を選ぶことが大切です。そこでこの記事では夫婦で必要な老後の資金の額と準備する方法、押さえておきたいポイントについてご紹介します。
<この記事の要点>
・夫婦の場合、老後資金は25万円以上が必要
・老後資金は労働や年金収入、金融商品の活用などで準備できる
・老後資金確保の際、受給できる年金の種類と金額を確認しておくことがポイント
こんな人におすすめ
老後の資金は夫婦でいくら必要か知りたい人
老後の資金の準備方法について知りたい人
老後の資金を確保するためのポイントが知りたい人
老後の資金は、夫婦でいくら必要?
老後の日々を過ごすためにどのくらいの資金が必要なのでしょうか。まずはこの点について、確認していきます。
老後に必要な支出
老後の生活に必要な支出にはさまざまな項目があります。総務省統計局が公表した調査結果では、以下の11項目が挙げられています。生活の中ではこれらの支出に対応していかなければなりません。
| 項目 | 備考 |
| 食料 | いわゆる「食費」。外食も該当する |
| 住居 | 持ち家なら修繕費、賃貸なら家賃が該当する |
| 光熱・水道 | 電気・ガス・上下水道が代表的 |
| 家具・家事用品 | せっけんや家電、寝具など。家事サービスも含まれる |
| 被服及び履物 | 洋服や靴など |
| 保健医療 | 医療費や医薬品の購入費など |
| 交通・通信 | 公共交通機関の運賃や車に関する費用、スマホ代など |
| 教育 | 通信講座など、学びにかかる費用 |
| 教養娯楽 | 書籍代や定額制動画配信サービスなど |
| その他の消費支出 | 交際費や小遣い、仕送り金など |
| 非消費支出 | 税金や社会保険料 |
(参考:『2023年(令和5年) 家計の概要』総務省統計局)※2024年11月時点
最低限の生活には月25万円が必要
総務省が発表した「2023年(令和5年)家計の概要」によると、世帯主が60歳~69歳の世帯の消費支出は月額平均306,476円、70歳以上の世帯の月額平均は249,177円です。また65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は月額平均244,580円、消費支出の月額平均は250,959円となっています。
(参考:『2023年(令和5年) 家計の概要』総務省統計局)※2024年11月時点
ゆとりを持った生活を送りたいならば月38万円は欲しい
生命保険文化センターの調査では生活に必要な費用と別に、ゆとりを持った老後生活を送るためには旅行やレジャー、趣味や教養などをはじめとした以下の用途にお金を使うと回答した方が約半数、またはそれ以上にのぼっています。
| 項目 | 回答者の割合 |
| 旅行やレジャー | 60.0% |
| 趣味や教養 | 48.3% |
| 日常生活費の充実 | 48.6% |
| 身内とのつきあい | 46.2% |
上記の目的をかなえるために必要な金額は、平均で月額14万8,000円です。この結果から、ゆとりを持った老後を送りたいならば、老後の最低日常生活費とあわせて月37万9,000円は必要ということになります。
(参考:『2022(令和4)年度 生活保障に関する調査』生命保険文化センター)
老後に向けて全員が2,000万円貯めなければいけないとは限らない
2019年に話題となったキーワードの1つに、「老後2,000万円問題」が挙げられます。「2,000万円の貯蓄がなければ老後を過ごせない」という解釈も広まりましたが、もちろん全員がこれにあてはまるわけではありません。
たとえば夫婦の年金額が月38万円を超えているならば、それだけで余裕のある生活を送れる方もいるでしょう。この場合の貯蓄は夫婦の葬儀やお墓の費用だけでよく、貯蓄の代わりに保険でまかなうこともできます。
一方で夫婦ともに国民年金しかない場合、2人合わせた支給額は満額でも月13万6,000円(令和6年4月以降)に過ぎません。つつましい生活でも不足分が発生するため、もし免除を受けた期間がある方は年金の支給額も減額となり、さらに多くの金額を用意しなければなりません。
老後の資金はさまざまな方法で準備できる
「私が加入している年金では、夫婦あわせても月22万円は得られない。どうしよう」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。しかし、老後で必要なお金を準備する方法は年金だけではありません。働いて稼ぐ、金融商品を活用するなど、さまざまな方法が活用できます。
ここでは大きく4つの項目に分けて、老後の資金を準備する方法を考えていきましょう。
定期的に得られる収入を活用する
老後を迎えても、定期的に収入を得る方法はあります。ここでは代表的なものとして、働いて稼ぐ方法と年金収入を得る方法を解説していきます。
働いて稼ぐ
働いて稼ぐ方法は、老後の資金を得る代表的な方法の1つです。得たお金は貯蓄など、自由に活用できるのは大きなメリットです。多額の資産を得ることができれば、早いうちから充実した老後を満喫することも可能です。
一方で高い収入に縁がなく、老後資金が足りない高齢者の場合でも、働いて稼ぐ方法は重要です。最低賃金(令和6年から適用)が最も低い地域は時給952円ですが、それでも1日8時間、月15日間の労働で約11万円を得られます。
年をとって働き続けることに抵抗を覚える方もいるかもしれませんが、多くの高齢者が働いていることは知っておきたいポイントです。
(参考:『地域別最低賃金の全国一覧』厚生労働省)※2024年11月時点
年金収入で生活する
年金収入は、老後を支える基本的な収入として重要です。10年以上保険料を支払っていれば受け取れる国民年金や、会社員経験のある方が受け取れる厚生年金は代表的です。このほかにも以下の通り、さまざまな年金があります。
・国民年金基金
・厚生年金基金
・企業型確定拠出年金(DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)
・小規模企業共済
・財形年金貯蓄
・個人年金保険
複数の年金を組み合わせて、老後の資金を充実させることも可能です。
貯金や退職金の取り崩しや保険から受け取れるお金
貯金や退職金を取り崩すことも、老後の資金を用意する代表的な方法の1つです。ただし、この方法で月々10万円程度取り崩すとしても、年月を重ねると多額になることには十分注意しておきましょう。
たとえばゆとりのある老後を満喫するため毎月14万円を取り崩すと、その合計額は10年間で1,680万円におよびます。現時点で多額の資金があるからといって無駄遣いをすることは避け、計画を立てて使うとよいでしょう。
また保険に加入している方は、満期保険金や祝い金などを受け取れる場合や、解約による返戻金が得られる場合もあります。該当する保険をお持ちの場合は、資産に加えておきましょう。
金融商品を活用する
金融商品の活用も、老後の資金を確保する代表的な方法の1つです。ここではどのような金融商品が活用できるか、商品選びのポイントを説明します。
金融商品の種類
老後の資金調達には、以下に挙げる様々な金融商品を活用できます。
・株式投資
・投資信託
・外貨預金
毎年120万円まで株式や投資信託に非課税で投資できるNISAも、この種類に含まれます。また確定拠出年金はご自身で運用する必要がありますが、そのメニューに投資信託が含まれていることは押さえておきたいポイントです。
金融商品選びのポイント
現在発売されている金融商品には、「元本保証で高い収益が見込める」というものがありません。そのため老後の資金作りに活用する場合は、以下のどちらかを選ぶことが求められます。
1.ある程度の収益を狙うため、元本割れも許容する
2.元本が保証される代わりに金利がほぼ0%など、収益性の低い商品
リスクを取る場合は1番、ローリターンを取るなら2番となります。日本円での定期預金は、ローリターンの代表的な商品です。ローリターンを選ぶと資産が減ることはない一方、インフレなど物価の値上がりにより資産の相対的な価値が下がることはデメリットに挙げられます。
一方で株式投資や投資信託、外貨預金は、高い収益を得る可能性がある一方で値下がりのリスクもあります。但し投資先や商品を組み合わせることにより、リスクを下げることは可能です。
持ち家など不動産を活用する
老後の資金を得る方法には、不動産の活用も挙げられます。主な方法には以下の3つが挙げられますが、それぞれ一長一短があることに留意しましょう。
| 方法 | メリット | デメリット |
| 売却する | ・まとまった収入が得られる ・固定資産税などの負担から解放される |
・購入時と同じ価格で売れるとは限らない ・自宅を売る場合は、住む場所を確保しておく必要がある |
| 他の人に貸す | ・定期的な賃料が得られる | ・いったん貸してしまうと、自分が必要なタイミングに利用できない制約がかかる |
| リバースモーゲージを利用する | ・売却よりは少ないものの、まとまったお金が得られる ・今の家に住み続けることが可能 |
・家主が亡くなると、出ていかなければならない |
なお、リバースモーゲージとは「自宅を担保にして金融機関から融資を受け、亡くなった後に自宅を売却するなどの方法で一括返済する」金融商品です。上記の表を参考にして、あなたにとって最も良い方法を選ぶことをおすすめします。
老後の資金を確保するために押さえておきたい6つのポイント
老後の資金を確保するためには、知っておきたいポイントが6つあります。それぞれどのような点に注意しておくとよいか、1つずつ確認していきましょう。
1.老後にもらえる年金の種類と金額を確認する
まずはあなたがどのような種類の年金に加入しているか、確認しましょう。国民年金や厚生年金は代表的ですが、それだけとは限りません。勤務先によっては、厚生年金基金や企業型確定拠出年金に加入している場合もあります。
そのほかにもiDeCoや個人年金保険など、ご自身で加入した年金も受け取れます。この機会に加入している年金の種類と、老後にもらえる金額を確認しておくとよいでしょう。
終身年金と定期年金の違いをチェックする
老後を考える際に、終身年金と定期年金の違いをチェックすることは重要です。終身年金は文字通り、生きている限りずっと受け取れる年金を指します。一方で定期年金は確定年金とも呼ばれており、健康であっても一定期間支払われると支払が終了することが特徴です。
国民年金や厚生年金、厚生年金基金は終身年金です。国民年金基金の場合は、一部を確定年金にできます。一方で個人年金保険では定期年金だけの商品もあるため、契約時によく確認しておくことをおすすめします。
公的年金額が少ない方は繰り下げ受給も検討する
国民年金や厚生年金には、繰り下げにより年金支給額を増やせる制度が用意されています。70歳まで繰り下げた場合、1月当たりの支給額は42%も上昇します。この制度を活用することで、年金額が少ない方でも多くの年金を受け取ることが可能です。
たとえば国民年金の場合、1人当たりの年金額は満額でも月6万5,075円です。この金額は65歳から受給開始した場合という点に注目しましょう。70歳になった後に支給申請すると42%アップされ、1月当たり9万2,406円を受け取れます。
参考:日本年金機構「老齢基礎年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)」
iDeCoや企業型確定拠出年金の場合は運用成績を手堅く見積もる
iDeCoなどの確定拠出年金は、運用成績により受け取れる年金額が変動する特徴を持っています。いくら年金を受け取れるかは、受給する時点まで正確な金額はわかりません。確実を期すためには、運用成績を手堅く見積もることをおすすめします。
1つの目安として、千葉銀行が2019年7月に公表した「アセットクラス別の平均利回り」が挙げられます。リーマンショックを挟んだ20年間で最も低い運用成績となったのは国内株式ですが、それでも税引き前の平均利回りは年1.43%でした。年1.5%で運用成績を見積っておくことにより、思った額の年金を受け取れないリスクは少なくなるでしょう。
参考:千葉銀行「つみたてNISAの平均利回りは?ファンド選びで重要な3つのポイント」
https://www.chibabank.co.jp/blog/tsumitate-nisa-average-yield.html
2.会社に勤務している方は、退職金がいくらもらえるかをチェック
会社に勤務している方は、定年まで勤めた際の退職金がいくらもらえるか社内規定を改めて確認しておくとよいでしょう。
ただし退職金は見込みの金額であり、必ずもらえるとは限らない点に注意が必要です。途中で社内規定が変われば、受け取れる額も下がる可能性があります。また中途退職した場合は退職金が減るほか、懲戒処分を受けた場合は退職金を受け取れない場合があることにも注意しましょう。
3.入院・手術や介護費用には保険の活用も有効
長い人生では、ご自身の入院や手術、介護されるといったことが起きる場合もあります。これらは全員が経験することではない一方で、もし起きた場合は多額の支出を伴います。老後の備えには、保険の活用も有効です。
保険は安価な費用で、いざという時に備えられる点が強みです。多くの保険は、若いほど入りやすく保険料も安い特徴があります。老後に備える意味でも、早めの加入がおすすめです。もし必要な保障が変わった場合は、その時点で乗り換えをすればよいでしょう。
4.リスクの高い金融商品は極力避ける
資産運用をする方のなかには一発逆転を狙うなど、高い収益を目指してハイリターンの商品を選ぶ方もいます。しかしこのような商品は値動きが激しく、多額の財産を失うおそれがあります。商品の仕組みとリスクを熟知しているプロの方は別として、一般の方はこのようなハイリスクの商品は避けるとよいでしょう。
一例として先物取引やFX、バイナリーオプション、暗号資産(仮想通貨)などが挙げられます。悪徳商法の被害も出ていますので、業者やSNSなどによる甘い言葉には十分注意しましょう。
5.リバースモーゲージの場合は、配偶者が亡くなると転居を余儀なくされ、コスト増となる場合がある
リバースモーゲージとは「自宅を担保にして金融機関から融資を受け、亡くなった後に自宅を売却するなどの方法で一括返済する」金融商品です。リバースモーゲージを利用して資金を得た場合は、注意しておきたい点があります。それは持ち家の所有者が亡くなった場合、配偶者は新たな家を探さなければならないという点です。
たとえば「夫の持ち家で、先に夫が亡くなった場合」が該当します。夫の死後は家を売り、残された妻は新しい住まい探しを強いられるかもしれません。もし賃貸物件に住む場合は家賃がかかり、家計を圧迫することになります。このような事態を防ぐには「リ・バース60」など、夫妻が両方亡くなったときまで家の売却を待てる商品の活用も有効です。
もちろん返済できる余裕のある方は、これまで借りた額を返せば引き続き住み続けることができます。しかしリバースモーゲージは老後の不足分を補うために利用するわけですから、全額返済できるほど余裕のある方は少ないでしょう。
6.ご自身の葬儀など、亡くなった後のことも準備しておく
亡くなった後には葬儀やお墓など、まとまった費用がかかります。
| 項目 | 費用 |
| 葬儀(家族葬の場合) | 80万円~150万円 |
| 墓石の費用 | 100万円~200万円 |
| 永代供養 | 10万円~150万円 |
これらの費用は、終身保険や死亡保険で一部まかなうことができます。高額な保険ではないため、準備しておくことをおすすめします。
なお、亡くなった際の用途に特化した掛け捨て型の保険も用意されています。しかしこれらの保険のなかには、以下のように年齢が上がると保険料が大幅にアップする商品もあります。このため、契約前に保険料についてよくチェックしておくことをおすすめします。
・契約を更新するごとに、更新時の満年齢に応じて保険料がアップする
・保険料が5歳刻みで変更される
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
老後に必要な資金は、決して少額ではありませんが、用意する方法はさまざまです。まずは将来受け取れる収入や資産、保険などを把握することから始めましょう。そのうえで、あなたの状況に応じたプランを考えることをおすすめします。
迷った場合は、ファイナンシャルプランナーに相談するとよいでしょう。豊富な知識をもとに、あなたが思ってもみなかった方法を提案してもらえるかもしれません。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
老後の資金は最低限いくら必要?
ゆとりを持った生活をしたい場合の老後の資金はいくら?
老後の資金を準備する方法は?
老後の資金を準備する際に気を付けるべきことは?
遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。