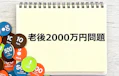2019年に金融庁が公表した、老後に2000万円不足するという報告が話題となりました。老後に必要となる金額は人によって違うため一概には言えませんが、退職後は収入が減ることから貯蓄額が多いことに越したことはありません。
老後2000万円問題の言葉を聞いたことはあるけれど、知らないという方もいるのではないでしょうか。詳しく解説していきます。
<この記事の要点>
・2000万円問題とは、老後生きるためには2000万円が必要になることを指す
・老後に必要な費用は約25万円~30万円
・生活費以外に子供に関するイベント費用が必要
こんな人におすすめ
老後の資金について気になっている人
老後2000万問題について知りたい人
老後の資金を貯める方法を考えている人
老後2000万円問題とは
2019年に金融庁が発表した老後2000万円問題が話題となりました。金融審議会の市場ワーキング・グループ報告書によると、老後生きるためには2000万円が必要になるというものです。日本人の平均寿命は世界の中でもトップクラスにあたり、男性が81歳、女性が87歳となっています。
健康寿命とは、医療や介護に頼らずに生活することができる期間のことで、関心が高まっている話題の1つです。健康寿命は平均で男性が72歳、女性が74歳です。
平均寿命と健康寿命は異なり、自分1人で生活していくためにも健康に過ごせるよう生活習慣を大切にしなければなりません。今後も平均寿命や健康寿命は延びると予想されるため、老後の必要な費用について検討していく必要があります。
金融庁の報告書の内容
金融庁の報告書は、単身世帯が増えているなどの人口に関することや、収入や資産などの金融についてまとめられています。高齢化社会が進んでいるため、老後の生活の心構えも記載されており、老後を迎えることに不安を抱えている人は老後2000万円問題について正しい知識を身に付けられます。
老後に必要な資金は人によって異なるため、2000万円問題と共に学んでいきましょう。
参考:金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」
老後2000万円問題の背景
老後2000万円問題の2000万円とは、男性が65歳、女性が60歳で無職の状態で、30年後に健在の場合にかかると予想される費用のことです。人によって差はありますが、収入が年金へと移行し、毎月の食費や娯楽費などを引くと毎月5万円ほど年金では足りない状態になります。5万円が12か月続き、30年生きるとすると1800万円になり、約2000万円足りない計算となります。
このような背景から老後2000万円問題と呼ばれ、話題となりました。しかし、人によって生活の仕方や生きる年数などライフスタイルが大きく異なるため、一概には言えません。そこで、平均年齢から計算し、必要な費用を見ていきましょう。
60歳から80歳まで生きる場合に必要な費用は?
生きるために必要な費用は人によって異なるため、例を出して紹介していきます。
・60歳から80歳まで健在
・会社員退職後、独身1人暮らし
60歳から80歳まで20年間生きるとすると、老後に年金のみの収入が老後2000万円同様毎月5万円ほど足りないため1200万円必要になる計算となります。
しかし、この金額は夫婦での問題となるため1人暮らしの場合は異なります。老後の生活費は、平均で16万円といわれています。公的年金は今までに支払ってきた税金の金額によっても異なりますが、厚生年金の平均月額は約14万円、国民年金では平均月額で約64,000円といわれています。男女でも変わってきますので、今のうちに計算しておくことをおすすめします。
(参考:『令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』厚生労働省)
老後の日常に必要になる費用を知り生活設計を立てる
老後の日常生活で必要になる費用は、食費や日用品など一般的な生活費に加え、イベント費用がかかります。イベント費用の内容としては、子供に関することです。子供が結婚することになればお祝い金が必要ですし、出産や孫が入学となれば教育費も必要になります。
老後に必ず必要になる食費などの費用をまとめることで、老後にかかる費用と共に年金だけで足りるのか足りないのかを把握することができます。老後の資金にかかる目安について見ていきましょう。
必要な老後資金の目安をノートに書き出す
必要な老後資金を食費や日用品などの生活費、車両費、居住費、娯楽費、保険料を自分に置き換えて書き出すことで目安がわかります。
退職後の収入と共に、税金なども一緒に記入するとさらに信憑性が増します。老後に必要な生活費は人によって異なるため、独自でノートを作成するとより具体的な生活費を知ることができます。具体的な生活費をノートに記載するためには1ヶ月どれくらい食費がかかるかなどを知っていく必要があるため解説していきます。
老後 1ヶ月にかかる生活費
総務省が発表した「2023年(令和5年)家計の概要」によると、世帯主が60歳~69歳の世帯の消費支出は月額平均306,476円、70歳以上の世帯の月額平均は249,177円です。また65歳以上の夫婦のみの無職世帯の消費支出の月額平均は250,959円となっています。
(参考:『2023年(令和5年) 家計の概要』総務省統計局)※2024年11月時点
生活費以外
生活費以外に必要な費用は、子供に関するイベント費用です。子供が学生の人は仕送りで毎月費用が必要となってきますし、結婚や出産などお祝いのイベントには出費が重なります。イベント費用以外にも、自分たちの家のリフォームや車の買い替えなど必要な費用が高額な傾向にあります。生活費以外の節約を検討している方は、車のランクを下げる、仕送り金額を見直すことをおすすめします。
固定費の見直し
賃貸や保険を見直すことで固定費が抑えられます。賃貸は家賃の見直しを行い、可能であれば今住んでいるところよりも家賃が低いところに住み替えることで節約になります。保険は現在加入している保険が自分に合っているか、ライフスタイルが変わると同時に保険の専門の人に相談してみましょう。
負債を抱えているものを老後までに返済しておく
老後になると現役の頃と比較して収入が減ることが多いため、負債は早めになくすようにしましょう。負債で多いものは、住宅のローンです。住宅ローンを繰り上げ返済することで利息の金額が減り、老後の負担を減らすことに繋がります。
ライフプランシミュレーションに挑戦
ライフプランシュミレーションを行うことで将来設計の参考になります。年齢や年収などを入力することで簡単に結果が出ます。将来の資産の予想がグラフで出てきて、どのように将来に向けて過ごすべきかアドバイスを見ることができます。
参考:ライフプランシミュレーション 金融庁
老後の資金は年金だけで足りる?
老後に必要な資金は人によって異なるため一概には言えませんが、老後2000万円問題もあり一般的には年金だけでは足りない傾向にあります。
年金の金額は、会社員と自営業などでもらえる金額が違うため、自分がいくらもらえるのかを確認していきましょう。
年金はいくらもらえる?
年金には種類があり、もらえる額によって将来設計を立てる必要があります。また、年金がもらえる年齢も年金の種類によって異なります。
国民年金
国民年金は、日本の公的年金で20歳から60歳のすべての人が原則加入しており、一律の保険料を納めます。第一号被保険者(学生や自営業)、第二号被保険者(会社員)、第三号被保険者(専業主婦)と分類され、年金の受取額も異なります。満額で月々68,000円もらえます。基本的には65歳以降に年金を受け取ることができます。
厚生年金
厚生年金は、会社員の人が加入する年金制度です。支払額は収入によって一人一人異なるため、一律ではありません。厚生年金は収入によって異なるため人によって違いがありますが、夫婦2人分の標準の金額は230,483円です。
(参考:『令和6年4月分からの年金額等について』日本年金機構)
個人年金保険の加入も検討する
老後2000万円問題のこともあり、公的年金制度だけでは不安視されています。そこで国の年金制度とは別に、独自で加入する年金保険を検討することをおすすめします。
定額年金保険は、保険料を保険会社が契約時の固定された利率で運用するものです。物価が上がることで資産の価値が下がるためインフレリスクに注意が必要です。株や投資と比較しても元本割れするリスクが少ない点がメリットのため、安定して資産を増やしたい人に向いています。
老後2000万円問題に備えた長期的な資産形成の方法
老後に備えて資産形成をおこなうためには早い段階から計画を立てることが大切です。時間に余裕をもって資産の貯蓄をしておかないと、無理して節約することになりかねません。会社員で働いている人は、給料以外の収入源があると貯蓄額が増えやすい状況になります。
収入の軸を増やす
収入の軸があればあるほど貯蓄額も増えやすくなります。現代は新型コロナウイルスの影響から職を失う人も増えているため、もし本業を失ったとしてもほかで収入を得ることができれば、すぐに困る状態に陥らずに済みます。
副業
副業が禁止されていない会社であれば、収入の軸を増やすためにも積極的に取り組んでいきましょう。副業はさまざまな種類がありますが、在宅で自由時間に取り組めるものを選ぶと本業と両立しやすいです。
趣味を活かして収入アップを目指す
趣味を持っている人は活かして副業としてもよいでしょう。老後の趣味ランキングでは1位は旅行、2位は家庭菜園、3位はボランティアです。旅行であれば、ブログで収入を得ることが可能ですし、家庭菜園は食費節約になります。直接収入に繋がらなかったとしても別の形でブログで投稿する、余った野菜を売るなど意外と副業になることもあります。
参考:シニアの趣味ランキング|老後にオススメの趣味50選【決定版】
資産運用
資産運用はリスクを伴うものであるため、確実に金額が増えるとは限りません。しかし、資産運用にも種類があるためリスクが低いものを選択することがおすすめです。リスクが低いものは金額が増えるのも長期的なものが多いため、自分の資産を金融機関に任せてしまうのではなく、自分でも勉強してみましょう。
定年後も働く
老後に資産を減らさないようにするためには、収入を増やすことが必須となります。定年後も働くことで安定して収入を得られるため、資産を増やしたいと考えている人は検討してみてはいかがでしょうか。
定年後も働いている人の割合
定年後に働き続けることで資産を増やすことに期待することができます。定年後も働いている人の割合は、60~79歳の3700人を調査したところ6割以上の人が働いているという状況になっています。
参考:【ミドル・シニア 8,000人調査】 5割以上が「定年後、働きたかった」と回答、そのうち6割強が現在も就業
雇用形態について
60歳から64歳で一番多い雇用形態は正社員で、続いて契約社員となっています。年齢によって雇用形態に差があります。
不動産の活用
空き地や空き家を所有している人は、有効活用することで資金を増やすことができます。
空き地の土地活用方法としては、駐車場や農園などが上げられます。安定した収入を得たい人におすすめです。土地を維持するためにはコストがかかりますが、その費用や手間を省きたい人は売却することも検討してみてください。
空き家の活用方法としては、賃貸が上げられます。空き家の期間が長くなればなるほど、家が傷んでしまうため、家を維持したい人に向いています。終活の対策としても空き家の売却は資産となるため、現金化する方法として選択する人もいます。
空き地も空き家も売却する場合の金額と、有効活用して収入を得る場合の費用を比較して決めることがおすすめです。維持するためには費用も手間もかかるため比較することで決定しましょう。
保険の活用
保険を活用することでも資産運用ができます。養老保険のような貯蓄型の保険に加入すると満期保険金を受け取れて貯蓄することができます。銀行の定期預金よりも利率が高いため、運用に期待ができるでしょう。
また、保険会社が運用してくれるため初心者でも取り組みやすいメリットがあります。デメリットは、保険料が高いことがあり、元本割れの可能性もあることを知っておきましょう。加入しすぎによって保険料が払えなくなり解約する事態に陥らないよう、加入する場合は慎重に決めましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
老後2000万円問題で、老後の資金を心配に思った人もいるでしょう。貯蓄をおこなうにしても必要経費で急な出費などは避けられないため、自分ができる範囲の節約から取り組むことをおすすめします。
お金の不安はついてきますが、資産形成や運用などもやっていくと不安が解消される可能性が高くなります。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
老後2000万円問題とは?
老後の資金はいくら必要?
公的年金はいくらもらえる?
老後2000万円問題に備える方法は?
一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。