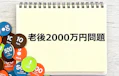退職して安定した老後を送りたいと考えるなら、毎月の生活費を把握する必要があります。食費、住居費、光熱・水道費などの具体的に生活に必要な費用だけでなく、医療費などの老後に発生することが予想される費用も含めて資金準備をしましょう。
また、年金だけでは生活費を十分に用意できない場合は、年金以外に資金を準備する方法が必要です。
この記事では、老後の生活費の目安と生活費以外にかかることが予想される費用を紹介します。具体的に、生活費となる資金を準備するための方法も解説します。
<この記事の要点>
・65歳以上夫婦世帯の生活費は約25万円、単身者世帯は約14万5,000円
・生活費の内訳では食費、交通・通信費などの割合が多い
・財形貯蓄やiDeCoなどを活用することで年金以外でも老後資金を準備できる
こんな人におすすめ
老後の生活費が気になる人
老後の生活費以外にかかる費用を知りたい人
老後の資金を準備する方法を探している人
老後の生活費の平均はいくら
まずは、老後における毎月の生活費の平均を夫婦世帯と単身世帯に分けて見ていきましょう。
65歳以上夫婦世帯の生活費の内訳
総務省統計局の2023年調査によると、65歳以上夫婦世帯の生活費の内訳の平均値は下記の通りです。
| 支出の内訳 | 金額 |
| 食費 | 7万2,930円 |
| 住居費 | 1万6,827円 |
| 光熱・水道費 | 2万2,422円 |
| 家具・家事用品 | 1万477円 |
| 被服及び履物 | 5,159円 |
| 保健医療費 | 1万6,879円 |
| 交通・通信費 | 3万729円 |
| 教育費 | 5円 |
| 教養娯楽費 | 2万4,690円 |
| その他の消費支出 | 5万839円 |
| 合計 | 25万959円 |
生活費で最も割合が大きいのは食費であり29.1%を占めています。続いて交通・通信費が12.2%です。その他の消費支出には交際費や家族への仕送り金などが含まれます。
住居費は人によって変化するため上記の平均を参考にするのは難しいですが、その他の費用に関しては平均的な老後の生活費として目安にできる金額といえるでしょう。
(参考:『家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要』 総務省統計局)
65歳以上単身世帯の生活費の内訳
次に、総務省統計局の調査を参考に単身世帯の生活費の内訳も確認していきます。
| 支出の内訳 | 金額 |
| 食費 | 4万103円 |
| 住居費 | 1万2,564円 |
| 光熱・水道費 | 1万4,436円 |
| 家具・家事用品 | 5,923円 |
| 被服及び履物 | 3,241円 |
| 保健医療費 | 7,981円 |
| 交通・通信費 | 1万5,086円 |
| 教育費 | 0円 |
| 教養娯楽費 | 1万5,277円 |
| その他の消費支出 | 3万821円 |
| 合計 | 14万5,430円 |
食費の割合が27.6%と高い割合を占めるのは夫婦世帯と変わりませんが、次に教養娯楽費が10.5%、交通・通信費で10.4%で高い結果となりました。
(参考:『家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要』 総務省統計局)
持ち家の場合は生活費が減少
上記の結果は平均であるため、持ち家のある方とない方の住居費が集計に含まれています。老後を賃貸で生活するなら家賃の額だけ生活費は上昇しますが、持ち家がある場合は住居費を支払う必要がないので生活費は減少します。
ただし、持ち家がある場合は家の老朽化によるメンテナンス費用を負担するリスクがあります。毎月の支出は減らせますが、持ち家の築年数が高いほど老朽化が進むため、特定のタイミングで大きな支出が発生しやすくなるため注意が必要です。
持ち家がある場合は、メンテナンス費用がかかることも考慮して貯蓄などの備えを万全にする必要があります。老後の生活において、持ち家を選択する場合と賃貸を選択する場合で発生する費用にどのような差が生まれるのか理解しておきましょう。
老後の生活費以外にかかる費用
老後を過ごすためには生活費以外に負担する必要がある費用が存在します。生活費以外に必要になることが考えられる費用を紹介します。
医療費
現役と老後の決定的な違いの1つは、健康上のリスクが老後のほうが高まるということです。国民医療費の平均は65歳未満では年間18万8,300円ですが、65歳以上では年間73万8,700円に跳ね上がります。
生活費だけでなく、治療や、入院にかかる費用を負担できるように医療保険への加入や、貯蓄を準備しておく必要があるといえるでしょう。
また、生活費の平均において食費の割合が最も高いことから、食費を削ることで節約を考える方もいるかもしれません。過度な節約は現役世代であれば問題がなかったとしても、老後においては病気になりやすくなり、医療費が増加する原因になることも考えられます。
介護費
老後の生活において、自立して日常生活を送ることが困難になった場合は、介護が必要になります。家族に介護してもらうことが難しい場合は、ホームヘルパーから介護を受けるための費用が必要になります。
また、持ち家がある場合は高齢者に適したバリアフリー住宅に改築することも選択肢にあげられるので、自立して生活することが難しくなった場合に備えておくとよいでしょう。
葬儀費
葬儀の規模によってかかる費用は異なりますが、家族が死亡した際には負担が必要です。現在では葬式の形式も多様化しており、通夜をおこなわない形式や、火葬のみをおこなう形式があります。
自身や配偶者が死亡した場合に葬式をどのようにおこなうのか事前に相談しておくと、必要な費用が分かりやすくなります。
その他の費用
最低限必要な費用以外にも旅行や趣味などに使う費用や、住宅に関係する費用があれば老後になる前に想定して用意しておきたいところです。また、余裕があれば子世代の住宅購入の援助や、孫の進学費用を負担したいと考える方もいるでしょう。
余裕資産の範囲内で負担をするのは問題ありませんが、生活費などの必要な費用を考えて出費するようにしましょう。
年金の平均受給額はいくら
退職後して労働収入がなくなった後に、老後の生活費を賄う収入は主に年金収入になります。厚生労働省が発表した日本年金機構の令和6年4月分からの年金額によると、国民年金と厚生年金を受け取る場合、合計金額が298,483円(老齢基礎年金68,000円、老齢厚生年金230,483円)です。
あくまで上記の厚生年金の298,483円は、40年間就業した場合に受け取れる年金の給付水準となるので、この限りではありません。しかし、妻が働くことで老後の受給額にも大きな差が出ることは確かです。
また老後の生活費以外にもかかる費用があるため、年金以外で生活費を準備する方法を考えることが老後を安心して生活していくためには必要です。
(参考:『令和6年4月分からの年金額等について』日本年金機構)※2024年11月時点
年金以外で老後の生活費を準備する方法
それでは、年金以外に老後の生活費を準備する方法を5つ紹介します。現役世代である今だからこそ取り組めることがあるので、どのような選択肢があるのか確認しましょう。
財形貯蓄
財形貯蓄とは勤労者財産形成促進制度の1つであり、会社に属している方が受けられる従業員の資産作りを支援する制度です。会社の給料から天引きされる形で貯蓄されるので、上手く貯金ができない方におすすめの制度になります。
財形貯蓄には貯蓄の目的を定めずに利用できる一般財形貯蓄と、住宅の購入資金を用意する目的で利用する財形住宅貯蓄がありますが、老後の資金準備に利用するなら財形年金貯蓄がおすすめです。
財形年金貯蓄で貯めた資金からは利息が発生しますが、550万円までの貯蓄から発生した利息であれば非課税になります。ただし、財形年金貯蓄を利用して保険商品を購入する場合は非課税枠が385万円に変動するので気をつけましょう。
(参考:『財形貯蓄制度』 厚生労働省)
終身保険
保険は万が一の保証だけではなく、老後の資金を準備する手段として利用できます。その中でも終身保険は貯蓄性の高い保険です。終身保険は加入者が死亡した際に死亡保険金を受け取れる保険ですが、保険料の払い込み方式が掛け捨て型と貯蓄型があります。
貯蓄型の終身保険は解約払戻金や満期保険金を受け取ることが可能です。途中解約で解約払戻金を受け取る場合は払い込み金額より保険金が下回る可能性がありますが、満期保険金は払い込み金額よりも上回ることが期待できます。
ただし、貯蓄型終身保険は掛け捨て型と比較して保険料が高い傾向にあります。貯蓄型の終身保険で保険料を安くしたい場合は、低解約返戻金型終身保険に加入すれば、途中解約による解約払戻金が通常の終身保険よりも安くなる代わりに保険料が安くなります。
個人年金保険
現在の年金の不足金額を年金の収入を増やす形で解消したい場合は、個人年金保険に加入する方法があります。保険料を積み立て、契約時に決めた年齢になった後に保険金を年金形式で受け取ることが可能です。
個人年金保険には確定年金、有期年金、終身年金の3つの種類があります。確定年金と有期年金はどちらも保険金の支払期間が決まっていますが、加入者が死亡した場合に支払い期間が終了するまでの保険金を確定年金は受け取れますが、有期年金は受け取れません。終身年金は加入者が死亡するまで期間を定めず保険金が受け取れる仕組みです。
また、夫婦世帯では夫婦年金を利用する選択肢もあります。夫婦年金は夫婦のどちらかが生存している限り年金を受け取れるので、配偶者が死亡した場合でも保険を利用して生活費を賄うことが可能です。
個人型確定拠出年金iDeCo
資産運用には元本割れのリスクもありますが、老後を見据えた長期間の運用を前提とする場合は資金を積極的に用意する一つの方法になります。個人型確定拠出年金iDeCoは資産運用を利用して老後の資金を用意する制度です。
60歳以上かつ、加入から10年経過で年金を受け取れるようになります。毎月保険料の積立をおこない、保険料を利用して投資商品を購入します。保険料は5,000円以上、1,000円単位で決められます。
投資できる商品は投資信託が代表的ですが、保険商品や、定期預金に積み立てることもできます。投資信託は運用をプロに任せられる投資商品であり、資産運用に関する知識がなくても投資しやすい商品です。
また、保険料を申告すると保険料控除を受けられ、受取時には公的年金等控除、または退職所得控除の対象になります。自身の許容できるリスクに合わせて商品を選択して、iDeCoを生活費の準備に役立てましょう。
(参考:『iDeCo(イデコ)をはじめるまでの5つのポイント』国民年金基金連合会)
資産運用
iDeCo以外にも積極的な資産運用をおこなうことで資金準備が可能です。株・債券・不動産など、長期的に利益を生み出すことが期待されるものに投資することで、現在の貯蓄を増やす形で資金準備ができます。
老後の資産運用を考える上で重要なのはリスクのバランスを考えることです。例えば、50代以上の方であれば老後が近いため、十分な運用期間が取れないことを考えると債券のようなリスクの低い資産をメインに保有することが適切になります。
一方で、40代以下は老後までの運用期間を20年以上取れる世代です。株式などのハイリスクハイリターンの資産を保有しても、長期的には利益を生み出すことが期待できるなら、短期的に資産が目減りするリスクを取っても、リスクの高い資産を保有するほうが資金効率は良くなります。
投資商品のリスクとリターンを知るだけでなく、自身の年齢から老後までの運用期間を計算し、余裕があるかどうかで資産運用に利用する商品を選択するとよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
老後の生活費の目安となる平均値を紹介しました。自身が過ごす老後を想像しながら平均値や現在の出費なども参考に世帯全体の生活費を計算し、生活費以外にかかる費用も考慮しながらどのように資金を準備するのかを考えることが重要です。
年金が老後の生活における主な資金になることは間違いありません。しかし、年金だけで生活費を賄うのは難しいです。そのため、保険や資産運用などの方法によって資金を準備することが重要になります。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


墓じまいとは、先祖供養の続け方を考えた際の選択肢の一つです。ホゥ。