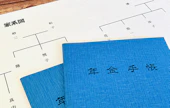初めて遺族年金を受給するとき、どのくらい受け取れるのか気になるかもしれません。また家計を支えていた方が亡くなった場合は、悲しみのなかでも金銭的な不安を感じるでしょう。
本記事では、遺族年金の受給額をシミュレーションできます。加入していた年金保険、加入状況、遺族の年齢といった条件に合わせて受け取れる金額を確認しましょう。
<この記事の要点>
・遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある
・遺族厚生年金は、条件によって子のある配偶者や父母、孫などが受給できる
・遺族基礎年金の受給額は「81万6,000円+子の加算額」で計算する
こんな人におすすめ
自分の遺族年金の受給額を知りたい人
初めて遺族年金を受給する人
遺族年金のシミュレーション|受給の条件
遺族年金でいくらもらえるかシミュレーションする前に、受給の条件をクリアしているか確認しましょう。年金保険は、自営業者が加入する「国民年金」と会社員・公務員が加入する「厚生年金」に分かれます。ここでは、死亡者の加入していた年金制度の受給条件をご覧ください。
国民年金加入者の場合(死亡者が自営業の方)
国民年金加入者は、条件に当てはまると「遺族基礎年金」を受給できます。
| 死亡者の条件 | 下記のうち、ひとつでも条件に当てはまる ・国民年金の加入期間に死亡した ・日本在住の60歳~64歳の方 ※上記は死亡日の前日までに、保険料納付期間が3分の2以上ある。もしくは死亡日の2か月前までの1年間に保険料の未納がない(令和8年3月31日以前に死亡日がある方) ・老齢基礎年金の受給権があり、受給資格を満たしていた ※ただし保険料を納めたとされる期間が25年以上ある方 |
| 残された配偶者の条件 | ・子を持つ夫もしくは妻 |
| 残された子の条件 | ・婚姻していない ・18歳になる年度の3月31日を迎えていない (20歳未満でも、障害年金の障害等級が1級・2級は対象) |
(参考:『遺族基礎年金の受給要件|日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html)
遺族基礎年金・遺族厚生年金の条件
【厚生年金加入者が遺族年金を受け取る条件】会社員・公務員の方
条件に当てはまる方は、遺族厚生年金を受給できます。
| 死亡者の条件 | 下記のうち、ひとつでも条件に当てはまる ・厚生年金の加入期間に死亡した ・加入期間に傷病が原因で、初診日~5年以内に亡くなった(加入期間に初診を受けている) ※上記は死亡日の前日までに、保険料納付期間が国民年金の3分の2以上ある。もしくは死亡日の2か月前までの1年間に保険料の未納がない(令和8年3月31日以前に死亡日がある方) ・老齢厚生年金の受給権があり、受給資格を満たしていた ※ただし保険料を納めたとされる期間が25年以上ある方 |
| 残された遺族の条件 | ・妻(子のいない30歳未満の妻は5年間受給できる) ・子、孫 (18歳になる年度の3月31日を迎えていない。20歳未満でも障害年金の障害等級が1級・2級は対象) ・夫、父母、祖父母 (加入者が死亡したとき55歳以上の方) |
| 夫、父母、祖父母の受給開始 | ・60歳から遺族年金を受け取れる ・遺族基礎年金と両方受け取れる方は、55歳~60歳でも遺族厚生年金の受給対象になる |
(参考:『遺族厚生年金の受給要件|日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html)
受給できない条件とは
ここでは遺族年金を受け取れないケースについて、簡単にまとめました。
遺族基礎年金が受け取れないケース
・保険料の未払い期間がある
・死亡者は60歳未満だった
・子どもがいない
・遺族である子は結婚した、または19歳以上である
遺族厚生年金が受け取れないケース
・保険料の未払い期間がある
・遺族は子どものいない夫、かつ65歳未満
遺族年金シミュレーション|計算方法をチェック!
計算方法は、加入している保険により異なります。それぞれの計算方法は、以下のとおりです。
遺族基礎年金の計算方法
子どもの人数に応じて、加算額が決まります。
計算式:81万6,000円+子の加算額
第1子・第2子:23万4,800(1人)
第3子以降:7万8,300円(1人)
※令和6年4月からの年金額。昭和31年4月2日以後生まれの方は上記の金額に、
昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円 + 子の加算額となります
参考:『厚生労働省』
遺族厚生年金の計算方法
死亡者の老齢厚生年金の4分の3で計算します。
計算式:A+B
A:平均標準報酬月額×(7.125÷1,000)×平成15年3月までの加入月数
B:平均標準報酬月額×(5.481÷1,000)×平成15年4月以降の加入月数
※条件を満たしているが加入月数25年(300月)未満の場合は、25年(300月)として計算する
(参考:『遺族年金ガイド|日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf)
(参考:『遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html)
遺族年金シミュレーション|夫婦の場合
夫婦のうち、どちらかが亡くなった場合の受給額をシミュレーションしましょう。加入している保険や子どもの有無、年齢によっても異なるので自身の状況に照らし合わせみてください。ここでは子を持つ夫婦の世帯と、子どものいない夫婦の世帯で分けて紹介しています。
夫婦と子どもの世帯の月額シミュレーション
夫と妻それぞれが死亡したケース、自営業・会社員(または公務員)だったケースをまとめました。
【故人が自営業の場合】
| 遺族基礎年金(月額) | |
| 子ども3人 | 約10万8,000円 |
| 子ども2人 | 約10万2,000円 |
| 子ども1人 | 約8万3,000円 |
【故人が会社員・公務員の場合】
| 平均標準報酬月額 25万円 |
平均標準報酬月額 35万円 |
平均標準報酬月額 45万円 |
|
| 遺族基礎年金+遺族厚生年金(月額) | |||
| 子ども3人 | 約14万1,000円 | 約15万5,000円 | 約16万8,000円 |
| 子ども2人 | 約13万5,000円 | 約14万8,000円 | 約16万2,000円 |
| 子ども1人 | 約11万6,000円 | 約13万円 | 約14万3,000円 |
夫婦のみ世帯の月額シミュレーション
子どものいない夫婦は、年齢や加入している保険によって受給の可否や金額が違います。下記では夫と妻それぞれが死亡したケース、自営業・会社員(または公務員)だったケースをまとめました。※子が18歳になる年度末日を過ぎた場合、子のいない妻と同じ条件になります。
夫が死亡した場合
【夫が自営業の場合】
| 遺族基礎年金(月額) | |
| 妻が40歳未満 | 支給されない |
| 妻が40歳~64歳 | 支給されない |
| 妻が65歳以降 | 妻の老齢基礎年金(月額) |
| 約6万4,000円 |
【夫が会社員・公務員の場合】
| 平均標準報酬月額 25万円 |
平均標準報酬月額 35万円 |
平均標準報酬月額 45万円 |
|
| 妻が40歳未満 | 遺族厚生年金(月額) | ||
| 約3万3,000円 | 約4万6,000円 | 約6万円 | |
| 妻が40歳~64歳 | 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(月額) | ||
| 約8万2,000円 | 約9万5,000円 | 約10万8,000円 | |
| 妻が65歳以降 | 遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金(月額) | ||
| 約9万8,000円 | 約11万1,000円 | 約12万4,000円 | |
妻が死亡した場合
【妻が自営業の場合】
| 遺族基礎年金(月額) | |
| 夫が65歳未満 | 支給されない |
| 夫が65歳以降 | 夫の老齢基礎年金(月額) |
| 約6万4,000円 |
【妻が会社員・公務員の場合】
| 平均標準報酬月額 25万円 |
平均標準報酬月額 35万円 |
平均標準報酬月額 45万円 |
|
| 夫が65歳未満 | 遺族厚生年金(月額) | ||
| 支給されない | |||
| 夫が65歳以降 | 遺族厚生年金+夫の老齢基礎年金(月額) | ||
| 約6万4,000円 | |||
遺族年金シミュレーション|妻の加算制度について
妻の年齢に応じた加算制度があります。以下2つの制度を確認し、当てはまる方は請求手続きをしましょう。
【中高齢寡婦加算】
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受け取れない40歳~64歳の妻が対象です。子どものいない夫婦もしくは、18歳年度末日に達した子どものいる夫婦も受給できます。加算額は、58万3,400円です。
【経過的寡婦加算】
上記の中高年齢寡婦加算の対象者が65歳になったとき、または昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳になったとき支給されます。
(参考:『日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms04)
遺族年金シミュレーション|いつまで受給できる?
遺族年金の受給期間は、加入している保険によって違います。
【死亡者が自営業者で国民年金に加入していた】
国民年金の場合は、子どもの年齢が基準となります。18歳を迎える年度の末日までが子どもの条件なので、その日に到達した時点で受給対象から外れるのが基本です。ただし障害等級1級・2級の子の場合は、20歳を迎えるまで受給可能だと覚えておきましょう。
【死亡者が会社員・公務員だった場合】
厚生年金は遺族の年齢や子どもの有無によって、受給期間が決まります。
・妻(子どものいない+30歳未満):5年間
・妻(30歳以上):一生涯
・子ども、孫:18歳になる年度の末日、
※ただし障害等級1級・2級の子は20歳を超えるまで
遺族年金に関するよくある質問
遺族年金をもらう方は、いくつかの疑問を抱くかもしれません。ここではよくある質問の「共働きでももらえるのか」「独身だと年金はどうなるのか」「併給は可能か」に、答えました。
共働きでも遺族年金をもらえる?
条件を満たすと、共働きでも遺族年金を受け取れます。遺族厚生年金の場合は「生計を同じくしていた」に加えて「残された配偶者の年収850万円未満」または「所得655万円5000円未満」に当てはまる方が対象です。
ただし遺族基礎年金の場合、子どものいない家庭は支給されません。
独身者が亡くなったら年金はどうなる?
生計を同じくしていた父母・孫・祖父母・兄弟がいるケースだと、独身であっても遺族厚生年金もしくは死亡一時金を受け取ることができます。
【死亡一時金の条件】
・死亡したのは国民年金加入者
・死亡者は年金を受け取っていなかった
・保険料の納付期間が合計で36か月以上ある
遺族年金の併給はできる?
年金の種類によっては、併給も可能です。
・遺族基礎年金+遺族厚生年金
・遺族厚生年金+死亡一時金
ただし寡婦年金は、併給不可なので注意しましょう。
【寡婦年金とは】
死亡者が年金を受けずに死亡しており、妻は60~65歳であるとき、寡婦年金を受給できます。受給条件は、夫の保険料納付済期間が10年以上あることです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
遺族年金の受給額をシミュレーションするにあたって、死亡者の保険加入状況や子どもの有無、遺族の年齢が基準です。また妻の年齢によっては、中高年齢寡婦加算や経過的寡婦加算の対象になります。受給額で損をしないためにも、確認しておきましょう。
身近な方が亡くなると、葬儀の手配も必要になります。「小さなお葬式」では、最後のお別れをサポートするために5つの葬儀プランをご用意しています。火葬のみや小規模での葬儀も取り扱っておりますので、故人やご遺族の意向に沿ってお選びください。
お客さまサポートダイヤルは、24時間365日対応しています。お急ぎの方も、ぜひお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


自筆証書遺言は押印がなければ無効だと判断されてしまうので注意しましょう。ホゥ。