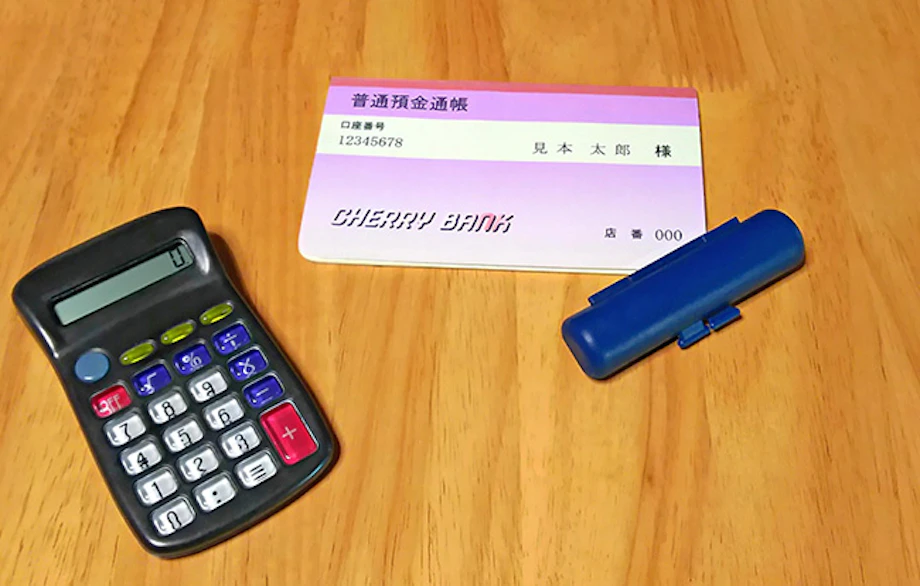少子高齢化の進展を背景にして、年金制度に関するさまざまな問題が起こりつつあります。老後の人生をいかに安定的に送れるかは、多くの人にとって重要な問題でしょう。
そこでこの記事では、年金問題とは何か、備えるための対策、今後の年金制度などについて解説します。
<この記事の要点>
・年金問題とは、公的年金の運用が悪化していることを指す
・年金制度が抱える問題として少子高齢化問題、年金額の目減り、世代間格差などが挙げられる
・年金問題対策として、付加年金制度やiDeCo(個人型確定拠出年金)など私的年金を活用する方法がある
こんな人におすすめ
年金問題とは何かを知りたい方
公的年金が行う財政の取り組みを知りたい方
年金問題に備えて今から対策をしたい方
年金問題とは一体?
年金問題とは、公的年金の運用が悪化していることを指します。この原因には、現役世代の負担の増加や、年金積立金の運用利回りの低下などがあります。
また「老後2,000万円問題」と呼ばれる、老後の生活に必要な資金をどうまかなうかという問題があります。これは、年金のみの収入で生活する無職の夫婦が、退職後の20年~30年間に必要な資金が年金以外に2,000万円であるという報告に基づいています。
年金制度が抱えるさまざまな問題
年金制度は、具体的にどのような問題を抱えているのでしょうか。ここからは、少子高齢化問題、年金額の目減り、世代間の格差、外国人が抱える問題という4種類の問題について解説します。
1.少子高齢化問題
公的年金の財政方式は、「賦課(ふか)方式」を採用しています。賦課方式とは、現在の年金支給に必要な財源を、現在働いている世代が支払う保険料収入から用意する方式のことです。少子高齢化が進むにつれて、現役世代の負担が増していくことになるといわれています。
2.年金額の目減り
厚生労働省の予想によると、将来、少子高齢化によって、賦課方式の均衡崩壊が発生するとされています。その結果、受け取れる年金額が目減します。
また「在職老齢年金制度」により、高齢者が就労する場合には、厚生年金の受取額が減額されることになるという問題もあります。
3.世代間の格差
公的年金の場合、世代間の格差があります。受け取れる年金給付の総額と、支払った年金保険料の総額を比べると、1955年以降に生まれた人は支払った額のほうが大きく、収支としてはマイナスになります。現在の高齢者のほうが、年金を多く受け取れる仕組みになっているのです。
4.外国人が抱える問題
年金に関して外国人が抱える問題もあります。在日外国人の場合も年金保険料の支払い義務が原則としてあります。ただし、10年以上支払わないと支給対象にはなりません。
そのため、義務として支払っていたのにも関わらず、年金を受け取れない外国人が多くいるということが問題になっています。「脱退一時金」という制度を利用すれば、一時金を受け取ることができますが、制度があまり知られていないというのが実情です。また、保険料が未納となっているケースもあります。
公的年金がおこなっている財政の取り組み
少子高齢化に対応して年金制度を維持していくために、公的年金がおこなっている財政の取り組みがあります。どのような仕組みで年金制度を安定化させようとしているのかについて解説します。
保険料の引き上げ
上限を固定した上で、年金保険料の引き上げをしてきました。上限を固定したのは、現役世代への負担が増えることに歯止めをかけるためです。
少子高齢化の進展を見据えて、年金の財源となる保険料を引き上げて収入を増やそうという取り組みです。
基礎年金国庫負担の引き上げ
老齢基礎年金などの基礎年金給付費に対して、国庫負担割合は3分の1でしたが、平成21年度以降は2分の1へと引き上げられました。そのため、少子高齢化が進展しても、年金制度がより安定的に運営されることになります。
財政均衡期間終了時に積立金の活用
財政均衡期間とは、公的年金の財政において、収入と支出のバランスをとる期間のことです。現在の財政検証においては、およそ100年間で財政均衡を図るとしています。
財政均衡期間の終了時すなわち100年後に、給付費1年分程度の積立金を保有・活用し、後世代の給付に充てるという取り組みがあります。
給付水準を自動調整できる仕組みの導入
現役世代の人口減少や平均余命の伸びなどの社会情勢に合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みである「マクロ経済スライド」を導入しています。
この仕組みによって、今後少子高齢化が進展しても現役世代の負担を抑えることができるとされています。
年金制度が今後破綻することはある?
将来、年金制度が破綻する可能性があるのではないかという心配を持っている人がいるかもしれません。
政府はマクロ経済スライドを導入し、社会情勢に応じて年金の給付水準を調整しているため、理論上は破綻を防げるとされています。
また、年金積立金を運用したり税金を活用したりして国が年金制度を維持しているため、破綻する可能性は低いといえるでしょう。
ただし、年金制度が維持されたとしても、老後2,000万円問題があることには変わりありません。そのため、昔のように年金さえ払っていれば老後は安心して暮らせるという認識では対応できない可能性が高いでしょう。何らかの対策を講じていく必要があります。
年金制度の今後はどうなっていくのか
年金制度が破綻しないとしても、変化が起こる可能性は十分にあります。年金制度は今後どうなっていくのか、気になるところでしょう。ここからは、支給額と増税についての見通しを解説します。
支給額が減る可能性はある
マクロ経済スライドにより、社会・経済情勢に応じて年金額が調整されるため、今後の支給額が減額となる可能性が考えられます。
もちろん未来のことはわかりませんが、受け取れる年金額が減額されることを想定して、老後の準備を進めていくことが重要です。
増税の可能性がある
年金制度を維持するために必要な財源を確保するために、今後、増税となる可能性が考えられます。すでに日本では年金に税金が使われています。
今後、少子高齢化が加速するなかで、消費税などがさらに増税される可能性があることを認識しておきましょう。
年金問題に備えてできる対策
年金制度が維持されるとしても、受け取れる年金額が減額される可能性や、老後2,000万円問題があります。そのため、自分で年金問題に備えてできる対策を講じることも必要です。では、どのような対策が考えられるのかを紹介します。
付加年金制度の活用
「付加年金制度」とは、毎月の国民年金保険料に400円を加えて支払うことによって、将来受け取れる年金額を増やせる制度です。
付加年金額(年額)は、「200円×納付済期間の月数」で計算し、2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の年金を受け取ることができます。
高齢任意加入の活用
国民年金の加入義務は60歳に達するまでの期間ですが、「高齢任意加入」は、60歳以降も任意で加入できる制度です。
年金を満額支払えず、満額の老齢基礎年金を受給できない人は、高齢任意加入の申し出をすれば受給額を満額に近づけることができます。
私的年金の活用
公的年金だけでは不安がある場合は、私的年金を活用しすることも考えられます。私的年金とは、公的年金の上乗せの給付を保障する制度であり、企業や団体が運営するものです。
自営業者向けの任意で加入できる「国民年金基金」や、個人で掛金を設定し、運用商品を決める「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などがあります。
貯蓄
老後に備えて貯蓄をして補う方法があります。例えば、20年分の老後資金を貯蓄すると想定します。老後の生活で必要な支出を算定し、自分が退職するまでに、毎月いくら貯蓄すればまかなえるのかを計算してみましょう。
もちろん、老後資金の全てを貯蓄でまかなう必要はないので、他の方法と組み合わせて考えるとよいでしょう。
資産運用
資産運用によって利益を得て、老後に備える方法があります。マンションなどの物件を購入して賃貸したり売却したりする「不動産投資」、投資家から集めたお金を運用の専門家が投資・運用する「投資信託」、株を購入して配当金を得たり売却益を得たりする「株式投資」など、さまざまな方法があります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
この記事では、年金問題とは何か、今後の年金制度の動向、年金問題に備える対策などについて説明しました。年金制度が今後破綻する可能性は低いですが、受け取れる年金額が少なくなることを考慮に入れて、将来の老後の生活に備えましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。 年金問題について知りたい方や、葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。